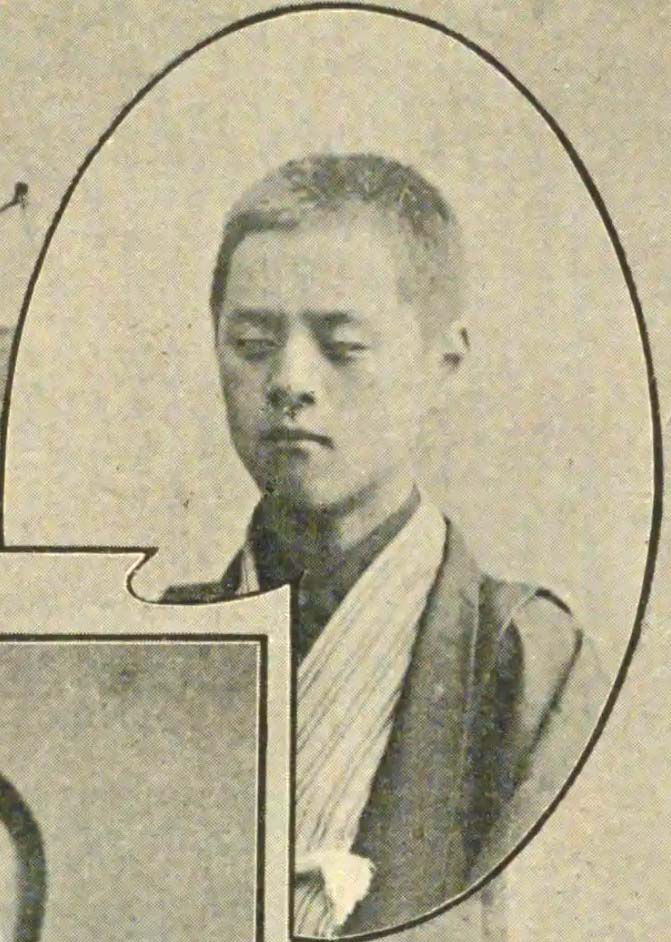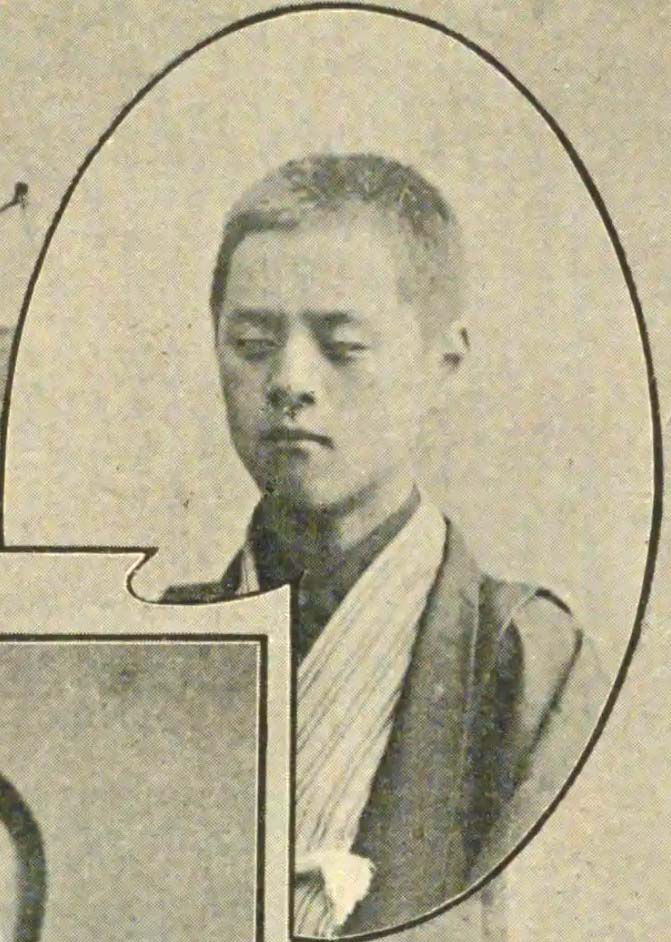豊竹小富太夫
駒太夫と小富太夫
二竹道人
現今東京義太夫節の副頭取を勤め居る六代日豊竹駒太夫は初め広見太夫と呼ばれ、次で富太夫と名乗り、其後五代目駒太夫に従ひ去る明治二十五年六代目を継ぎて今の名の駒太夫とは成りたるなり其子弟を薫陶[おしふ]るに於て懇切厳正克く其面倒を見る、宜なり数十百人の子弟を有し斯道後進の指南車と仰がる誠や弟子を視ること師匠に如かずと、其門中一頭地を抽んで今や都下客席に尠なからぬ好人気を博しつゝある豊竹小富太夫は是ぞ即ち駒太夫が秘蔵の門人にして在阪の頃より其薫陶に従ひ居るものなり、小富太夫は年歯僅に三五、その坂地に生るゝや病の爲め襁褓中既に両眼明を失ひたるを以て其親これを検校になさんとの心なりしも小富は之を嫌ひ常に義太夫浄瑠璃を好むこと甚だしく遂に五歳の時より駒太夫の門に投して斯道を修む、後ち駒太夫は其身上京するに際して小富の将来大いに見所あるを予知し之を豊沢松太郎に托しぬ斯くて後は小富は松太郎に就て倍々励み居たりしが松太郎も次で上京したるを以て駒太夫は之と図りて小富を坂地より上京を促したるを以て昨二十九年十一月を以て出京し鶴仙亭に初お目見得の看牌を掲げぬ、爾来到る所の各席何れも好評を以て迎へらる、其語り物中尤も得意と聞ゆるは堀川猿廻し、合邦、柳等にして壷坂は其身の盲目に嵌りてや殊に聴客[きゝて]の感を動かすものありとぞ、齢まだ若うして一意専念技芸に熱注せるは頗る感ずべきもの、この徳果して孤ならず共同新聞舖の小西氏の之を輔くる所となりて目下同氏の宅に引取られて庇護せられ居るは小富丈の爲め幸福の次第といふべきなり
古来盲人にして斯道の名手稀に之れあるを見る、総て盲目の人、その技を練り、芸を修むるの点に於てや熱注励精、大いに常人に超絶するものあり、是れその名人巧手の輩出する所以なる歟、噫々小富丈や前途尚ほ遙に遠し、愈々倍々斯芸に黽[つと]め天晴れ名太夫の花を咲せんことを望むと倶に其師駒太夫丈に向つて尚その薫陶注意を併せて希ふものなり』【義太夫雑誌19:15-16評判】
豊竹小富太夫 昨年中出京して好評を博したる盲人豊竹小富太夫は、その当時目貫の場所の寄席のみにかゝり常に大入を占めたるにも拘はらずその道の習慣に制せられ、爾来多くは場末に出席し居たるが、別項の如く今度神田表神保町新声館の操人形に出勤 【東京朝日新聞1897.2.28(東京の人形浄瑠璃p283による】
偖大切の卅三間堂平太郎住家の段は大坂新登り十四才にて頃日評判の高き(豊竹小富太夫)と古きお馴染にて我輩最愛の(豊沢兵吉)語り口小供らしくなく巧者に沈着たる芸節はあざやかにして声に艶あり此語り物は適当ならんまづは無難の出来兵吉丈の糸に助けらるゝは幾許の仕合か知れずいつもなから終尾の音頭になりて調子を上げて弾く時の音の艶というものは鶯の初音といはんか迦陵頻伽の妙音ともたゝへんか聴て心地の清々しく帰宅ても猶耳に残りし程なりしき【義太夫雑誌16:20 三月狂言新声館略評 島の屋千鳥】
小富太夫文楽座に出勤す 先頃帰坂せし豊竹小富太夫は本年より文楽座に出席し曩に下阪せし祖の太夫と俱に大序を勤め居れり【義太夫雑誌26:38 1898.1】
参考 明治15年2月20日大阪生。2才脳膜炎で失明。始め富崎検校につき地唄。明治20年3代富太夫入門。初名小富太夫。翌年師上京、野沢太八につき稽古。9才巡業、帰阪後松太郎の薫陶。17才初代呂太夫、更に2代津太夫預りで31年出座。明治35年4代富太夫襲名。大正3年7代駒太夫襲名。【義太夫年表大正篇】