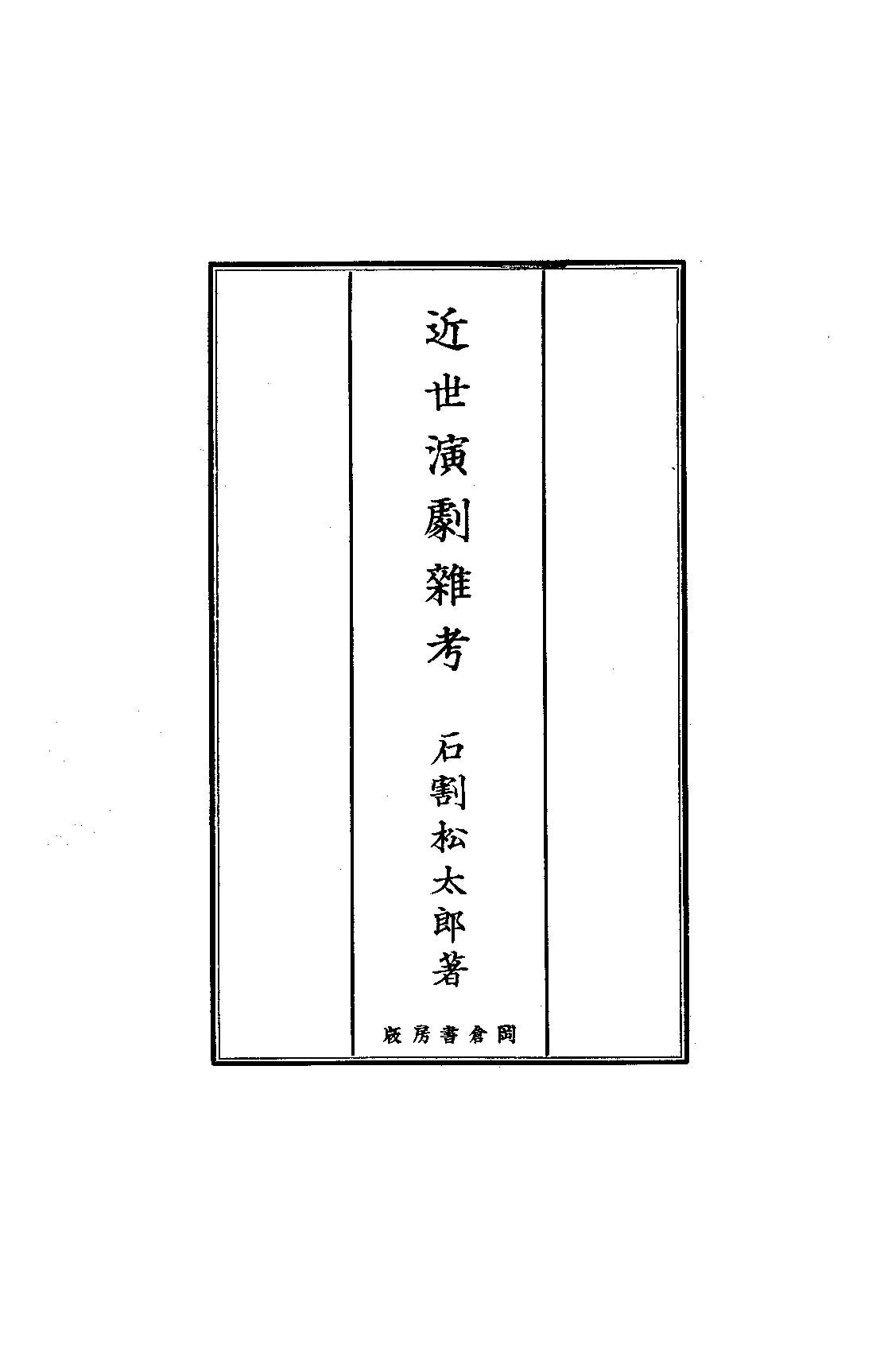 |
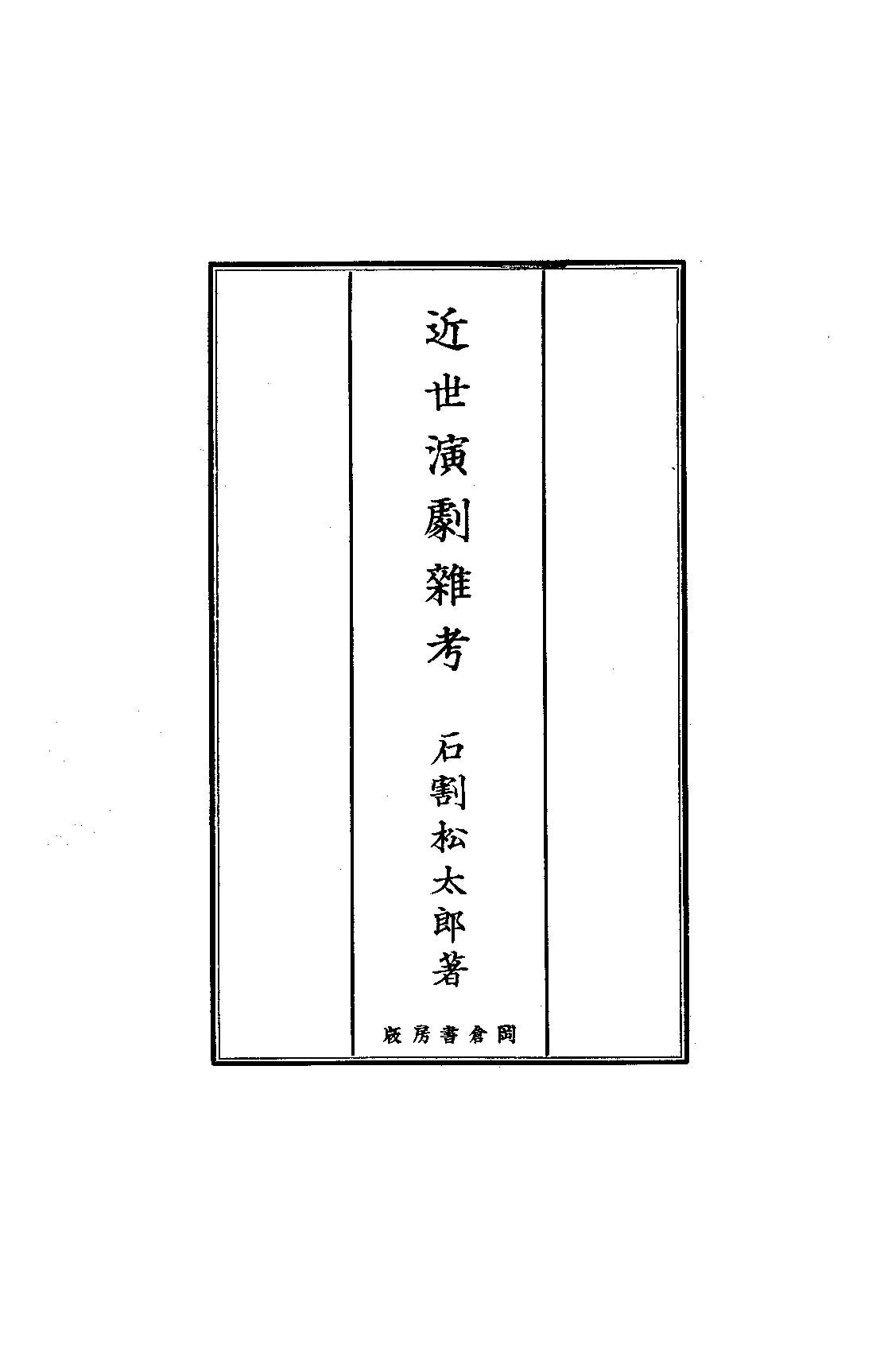 |
| はしがき | ||
| 目次 | ||
| 001 | 浄るりの「形式」と浄るりの「風」 |
一、形式と「風」との意味-「風」が操全体を支配し-技巧が操の総てゞある-風は操の生命線 二、浄るり五段組織が提唱された径路-十二段から六段が最初の形式-次が五段組織一古浄るりと当流-謡曲と浄るりの関係-加賀の正本と謡曲のゴマ-五段と西洋劇詩の関係-『竹豊故事』の記載-『雲錦随筆』の記載-千賀太夫の謂ふ「語りやうの心得」-能の五段組織説 三、序破急の本来の面目-言葉の意味-『学習条々』 四、机上の空論としての『忠臣藏』の五段組織-黒木氏の誤れる五段還元法 五、正しく実際の舞台に即した『忠臣藏』の五段組織への還元-書卸し当時の分割-後世の分割 六、「段」と「場」との 浄るりの位と「立端場」の意義-テクニックの説明-術語に内在する芸術的の根本義 七、各段の趣向とその語り口-各段の目安-その語り口-『音声巨細秘抄』から 八、五段組織の原則が確立するまで-浄るりの本体は時代物-一線を画する『出世景清』-「風」の発生-西風東風-政太夫節の大成は『国姓爺合戦』-その五段組織-立端場の存在 九、『夏祭浪花鑑』の一例-その五段組織-玉島の段の異例 十、浄るりの「風」といふ事-「風」は各段各場の格式也-「播磨地」-「駒太夫風」-「宮守酒」の一例-「沼津」の一例-端場と小揚-浄るりの芸術価値-浄るり批判の客観性 |
| 049 | 人形三人遣ひの源流研究 | 人形の遣ひ方-突込遣ひ-三人懸りの始-その記録-山本飛騨掾-飛騨は何人-『棠大門屋敷』の記載-人形遣ひの受領-片手人形の様式の発見-古評判記の記載-飛騨の系列-吉田三郎兵衛-吉田文三郎-『例[倒]冠雑誌』の記載-片手人形の様式を認めて三人懸りの記載の再吟味-『北条時頼記』の画証-『愛染明王影向松』の再吟味-人形の大さ |
| 069 | 「操」における「人形」の研究 |
一、人形の種類と、こゝでの研究する範囲-操の古い意味-人形の種類-その特質-人形の分類 二、「突込」と「片手」との人形二様式-二つの様式の特質-突込人形と人形舞台の構造-片手人形と飛騨掾-人形細工人として-人形遣として-浄るり作者として-その様式-「片手人形」といふ言葉の変遷-片手人形-手妻人形、碁盤人形の意味-「人形に足を付けた」といふ意味とその解釈 三、人形の二様式は胎生期の昔から-『雍州府志』の記載と「人倫訓蒙図彙」の異つた二つの画証-『好色一代男』の上幕つらかくしの意味 四、「三人遣」の源流は「片手人形」-三人遣ひで記憶すべき近本九八郎の『時頼記』出演 五、「三人遣」の工夫者は桐竹門左衛門と近本九八郎-偶然の機会の工夫-丸胴から助手へ 六、人形機構の工夫と肩板の発生-記載のない肩板に注意を向けよ 七、吉田文三郎その他名人芸-現在の舞台に残る片手人形の余蘖-それは「ツメ」の人形 |
| 097 | 吉田文三郎の初代と二代 | 人形の大成者-『人倫重宝記』の記載-その画証-文三郎の生立-文三郎五度の反逆-座本竹田近江の弱腰-文三郎の一生涯の生活の目安-文三郎の給金に近松の給金を加算-文三郎の死期死因の疑問-二代の文吾-その墓碑-名誉の景事-伝統の便りなさ |
| 117 | 人形遣ひが台詞を言うた時代 | チョボの嚆矢-人形遣のひ辞-角太夫の『大念仏七万日詣』 |
| 123 | 浄瑠璃雑話 | 故なき古格の破潰-「酒屋」のアトの問題-サハリとクドキ-その正しき意味-その実例 床本の質入-織太夫の「牢屋」-入質の証文-その床本-左官の綱太夫-街に起つた逸話 -綱太夫目の上のコブ-『佐倉曙』の価値-新作と作曲の問題-綱太夫の土佐の「牢屋」の人気 |
| 139 | 勾欄雑話 | 文楽を見に行く-その言葉の意味と時代の変遷-大衆は耳よりも目-竹本座更生の宝永二年の事実-突込人形と片手人形-「ツメ」の人形-三昧線の発達-糸の目方-三絃工石村東助の工夫-鉛ゴメの駒-撥皮-団平の前後の二期-改革と保守-境目は明治十四年十一月-越前風と駒太夫風-羨しい大衆の耳-越路と団平の分離 |
| 163 | 文楽夜話 | 博識的の団平の芸-家庭人としての団平-経済的に見た団平-団平後妻ちか女との馴れ染め-太夫と人形遣の見解の相違-津太夫の帯屋と玉造時代-名人辰五郎-その芸幅-紋十郎の出世芸-文五郎の『太十』の型-名人喜十郎-と、その槍-吉田錦糸の『古八』-人形部屋の符牒-ゲンマの仕掛物 |
| 183 | 勾欄雑考 | 浄るりと劇場の構造-東京人と浄るり-義太夫はヤボ-五代目春太夫の話-大隅太夫の非常識-摂津の土佐興行-江戸庄の割腹-その追善興行-鶴澤重造の先代-文楽座の玉筋の系圖-初代玉造の狐 |
| 201 | 豊澤団平の研究 | 浄るりの研究は近松ばかりでは分らぬ-『壼坂』の出来るまで-その原作と第一回の原作-この作の枕の作者-団平の古い浄るりに対する対度-風の発生と推移-団平越路分離の奥に潜める事情-その記録の語るところ |
| 229 | 浄るり「曲風」の発生と、今日批判の標準 | 古典の繰返へし反復-「標準の耳」-風の成立から観て-竹澤権右衛門の晩年からの推考-「沼津」の作曲の実例-この作曲の歴史を知らずして批判がなるか |
| 243 | 『久右衛門日記』に読む操史の貴重資料 | 尾戸焼の陶工久右衛門の日記の発見-御振舞、酒奉行の記事-太夫の連名-伊勢大掾の通称-「さつま」と「江戸さつま」-「小平太」とは?-「熊野」は紀州でなく堺の熊野町-島津侯と甥の関係-島津と薩摩太夫の関係-人形品目の不審-浄るりの立て方-狂言の配置 |
| 257 | 院本『八百屋お七江戸紫の存在』 | 大阪図書館の『江戸紫』-紀海音の『八百屋お七』の再吟味-『恋緋桜』と同一?別の丸本?-竹本喜太夫の検討-竹澤権右衛門-『江戸紫』の刊記と太夫連名の教ゆる事実-辰松八郎兵衛座の興行-二代の八郎兵衛-『音曲猿轡』の記載-手妻太夫の意義 |
| 277 | 「揚巻助六」心中の系統 | 『大阪助六心中物語』の存在-この書の特異の五点-この書の形式-「揚巻助六」と呼ぶ物語の従来に知られたる十点-『千日寺心中』の存在-『蝉のぬけがら』との相違点-『大阪助六』の心中みちゆきの全文-『千日寺心中』の竹本内匠利太夫とは?-「揚巻助六」心中系統一覧 |
| 293 | 「天和三年」と刊記せる脚本『浮かれ狂言』の存在 | 守随氏のいふ『好色伝授』-『浮かれ狂言』の体裁-この書の口上-作者山本遊学-場割-役人付-「読む脚本」?-『好色伝授』との比較-筋-ト書形態-チヨボの嚆矢?-その説経節の本文 |
| 317 | 異本『傾城仏の原』 | 内田魯庵氏の愛蔵本-近松の『仏の原』-異本との比較-俳優替名-水島四郎兵衛とは何者?-『役者略請状』の記載 |
| 329 | 「鳥熊」の春木座興行の記録 | 鳥熊の素性-東京春木座の新興行法の実施-その興行月表-「春木座の規則」-再度の興行月表-役者の出入-鳥熊の没落理由 |
| 347 | 舞台照明に電光を用ゐた始 | 明治十七年五月道頓堀の中の劇場-発動機は千日前の竹林寺に-その宣伝文-『艶競華咲方』の歌詞-囃子の発達 |
| 357 | 日本最初の沙翁劇の番付について | 明治十八年五月の道噸堀戎座の『ベニスの商人』の翻案『何櫻彼櫻銭世中』-シヤイロックは中村珀琥郎 |
| 361 | 都萬太夫その他 | 都萬太夫の素性-『可盃』の記載-萬太夫の口宣案-『道成寺』の道行-佛の原の後日 |
| 奥付 |