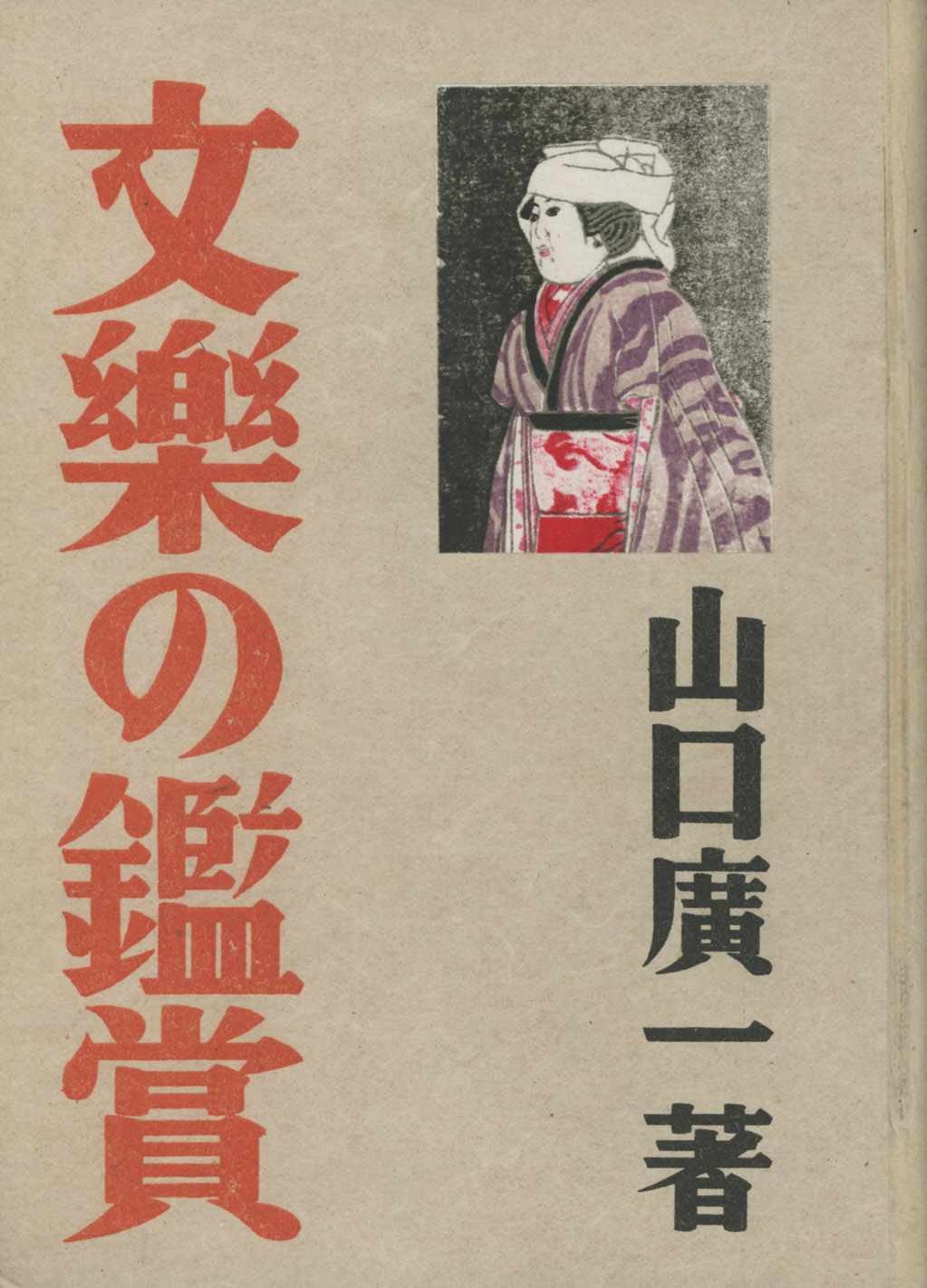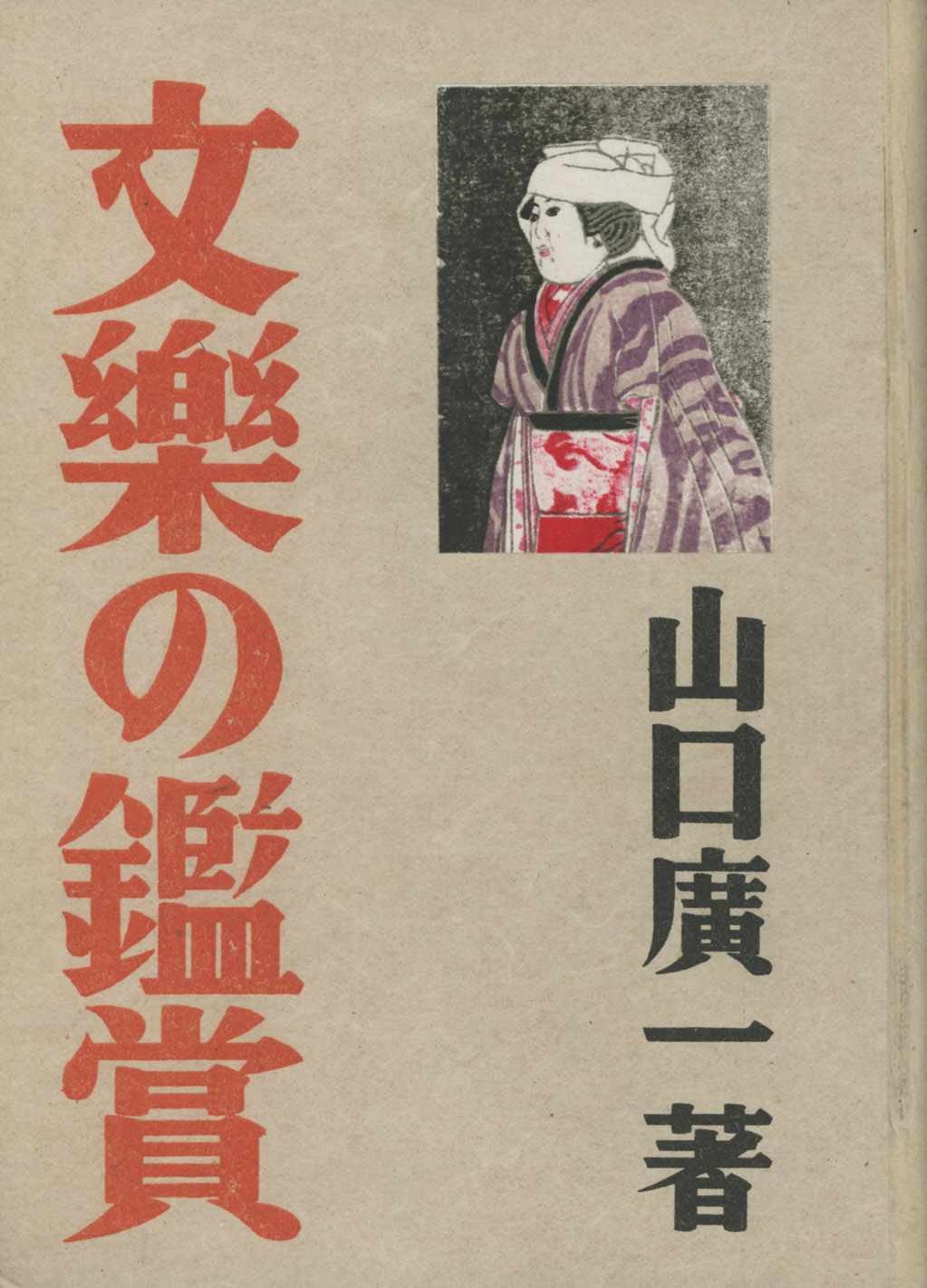| 初版 | 再版 |
| ページ | | ページ | |
| p1 L1 | 序 (文樂鑑賞の總括的緒論を含めて)今、祖國日本は正に國運を賭して戦ひ抜いてゐる。その苛烈な決戰段階にあつて、然もなほ本著のごときわが古典藝能への心ゆく鑑賞に、ひと時の靜けき憩ひを享け得る欣び、その聖代の鴻恩を、先づ開巻に當つて讀者諸兄とともに深く感佩したいと恩ふ。/ 最近、わが古典文學、乃至は古典藝能に對する新しい注視が國民的思惟の上に顯著な漸層を示しつゝあるやうだが、勿論これは單なる過去の低回や現實の逃避であつてはならない。それは光輝ある古典を通じて、わが民族精神本來の優越性、獨自性をより適確に把握し、然してそれを來るべき大東亞文化の創建にまで生成發展せしめんとする雄渾な意圖の―つの具象化でなければならない。そこにこそ、わが古典探求の力勁くも麗はしき結實が約束される。/ 扱て、さうした古典藝能の一分野としての人形淨瑠璃、それが最も完成された形において傳承されてゐる大阪の文樂座が、特に今次の聖戰以來、次第にわが指導的知識層の間に、その關心を擴大せんとしてゐる傾向も、叙上の古典と民族精神との相關の上に、それは十分實證し得るところであらう。/ 現に、今日の文樂座はその本據たる大阪公演は勿論のこと、東京その他全國主要都市における地方公演においても、從來殆ど見受けられなかつた如何にも清新な良識人の多くを、その觀客席の隅々にまで獲得しつゝあるかのやうである。これは全く新しい文樂座風景とでもいふべきだが、そこに古典藝能としての「文樂」に對する清新な探求と清新な鑑賞とが、また同時に萌芽しつつあるかのやうでもある。 | p1 L1 | 序 (文樂鑑賞の總括的緒論を含めて) |
| p2 L13 | ところが、翻つて考へるに、今日までの文樂硏究は | p1 L2 | 今日までの文樂硏究は |
| p3 L5 | 鑑賞的硏究は從來遺憾ながら | p1 L6 | 鑑賞的硏究は遺憾ながら |
| p3 L6 | 文樂の演技鑑賞を直接に示敎したやうな論述すら未だ | p1 L7 | 文樂の演技鑑賞をその舞臺に則つて直接に指導したやうな論述は未だ |
| p3 L8 | 一つの大きな缺如であり、跛行であるといはねばならない。 | p1 L8 | 一つの大きな缺如だといはねばならない。 |
| p3 L11 | 近くは秋山木芳氏の「義太夫大鑑」その他 | p1 L-1 | 近くは秋山木芳氏の「義太夫大鑑」、岡鬼太郎氏の「義太夫秘訣」その他 |
| p3 L13 | なほそれ〴〵の不滿があつて | p2 L3 | なほそれ〴〵多少の不滿があつて |
| p4 L1 | そこで、著者はさうした不滿を補ふ意味の系統的企劃を持つて、從來の文樂硏究における鑑賞面の缺如を多少とも是正したいと考へた。即ち、本著の期するところは、叙上のごとく最近急速に擴大して來た「文樂」の新しい觀客圏を對象としての、鑑賞案内であり、その鑑賞讀本たらうとした點にある。謂はば、本著は現在までの文樂硏究が心ならずも觀過して來た鑑賞指導の隘路に、せめても一鍬の開拓を加へたいと念願したものなのである。そしてその意味において、本著は秘かに多少の自負を持つ次第でもある。 | p2 L5 | そこで、本著の主意はさうした不滿を補ふ意味で、「文樂」の新しい觀客層を對象として、實際の舞臺に從つた演技の鑑賞案内であり、その鑑賞讀本たらうとした點にある。謂はば、本著は現在までの文樂硏究が右のやうに心ならずも觀過して來た鑑賞指導の缺如に、せめて多少の據りどころを發見したいと念願したものなのである。 |
| p5 L1 | 從つて僅かに本著の一讀が | p2 L-2 | 從つて僅かに本著の意圖が |
| p5 L2 | 比較的豐かな資料に | p2 L-1 | 比較的豐かな文献に |
| p5 L5 | なほ、次ぎにこの序文を藉つて | p3 L4 | なほ、次ぎにこの序文を機會に |
| p7 L11 | 凄愴感の表現が嚴格に要求されてゐる。 | p5 L3 | 凄愴感の表現が要求されてゐる。 |
| p8 L1 | その必須性は遙かに稀薄だと | p5 L6 | その必須性はかなり稀薄だと |
| p8 L5 | (或は時にはそれを犠牲にした) | p5 L9 | (或は時にはそれを犠牲にしてさへ) |
| p9 L1 | それ以上の語り口の抑揚緩急、三味線の | p6 L3 | それ以上の語り口の抑揚緩急強弱高低、さらに三味線の |
| p9 L3 | 家元制度といふものの存在せぬことが | p6 L4 | 家元制度の存在せぬことが |
| p9 L5 | (唄ひ物としての道行を除いて) | p6 L6 | (唄ひ物としての道行物を除いて) |
| p9 L7 | 武智光秀」を古靱太夫と大隅太夫とが合唱するわけには絶對に行かない。それは古靱と大隅との語り口に大なり小なりの誤差があるからである。 | p6 L8 | 武智光秀」を山城少掾と大隅太夫とが合唱するわけには絶對に行かない。それは山城と大隅との語り口に大なり小なりの音差があるからである。 |
| p9 L13 | 最後に人形の鑑賞に關する一二の注意を添へておきたい。總じて、人形の鑑賞は義太夫の鑑賞ほど困難ではなささうだ。それは私たちの視覺に、その聽覺ほどの個人差がないからである。近ごろの文樂の新しい鑑賞家も、恐らくは床の太夫や三味線よりも、先づ人形の魅力にその藝術享受の興奮を燃燒させてゐるのではあるまいか。たゞ人形の鑑賞において、 | p6 L-2 | 最後に人形の鑑賞に關する心得を一言だけ書き添へておきたいのだが、先づ、人形の鑑賞において、 |
| p10 L9 | 世界の創造がある。 | p7 L4 | 世界の創造がある。これは甚だプリミチーヴな藝術論ではあるが、人形について、われらは先づかうした點への注視を心掛けたい。 |
| p11 L1 | 人形については、わられは先づかうした點への注視を心掛けたい。徒らに人間を對照とした | p7 L-4 | いひかへれば、徒らに寫實を對照とした |
| p11 L5 | 一般論的には、人形遣ひが精魂を打ち込んで遣つてゐる場合、その血がその兩腕を傳つて、人形の五體に脉々と流れてゐるのが感じられる。さうした人形は靜かに坐つてゐても、立派に呼吸をしてゐる。これらも實際の舞臺について、よく〳〵鑑賞さるべきであらう。/ なほ、人形の鑑賞と不可分の關係において、そのカシラ(首)への注視も忘れてはならない。/ 今日、文樂座で使用されてゐるカシラの總數は百餘にのぼるが、そのうち名品と稱されるものも十數個はある。これらの名品は能樂における能面と同樣、その鑑賞とその保存の途が、今日の文樂としては一つの大きい課題になると思はれるが、とに角その主たる種類に就いては本文中にも簡單な解説を附記して讀者の鑑賞に資した。 | p7 L-1 = p8 L1 | |
| p12 L3 | 次第にその鑑賞に關するそこはかとなき懐疑を加へた。現實の演技に對する多くの疑ひや惱みの數々が秘かに累積するに至つた。しかし、屢述のとほり、さうした難解の鑑賞に | p8 L3 | 次第に現實の演技に對するそこはかとなき疑問や不明確の數々が秘かに累積して來た。しかし、右のとほり、さうした場合、難解の鑑賞に |
| p12 L10 | 故四世竹本津太夫氏の「沼津」と現紋下豐竹古靱太夫氏の「寺子屋」の | p8 L9 | 故三世竹本津太夫氏の「沼津」と現紋下豐竹山城少掾氏(當時は二世豐竹古靱太夫氏)の「寺子屋」の |
| p12 L11 | これが著者としては意外の好評をもつて | p6 L10 | これがいささか好評をもつて |
| p13 L2 | 二十一狂言のうち、時局との照應において特にその中から十八篇選んだが、何分にも雜誌の | p8 L-3 | 二十一狂言のうちから、さらに一般的なものを十八篇選んだわけだが、何分にも最初の發表が雜誌の |
| p13 L5 | 約三倍以上の量に達した。なほ、同時に實際鑑賞の便を計つて、各狂言の後尾に三十餘項の參考項目の解説をも新しく加へておいた。/ たゞ、各章に附した作品個々の内容紹介や全篇の梗概などは、むしろ本著の企劃としては第二義的のものであり、然もさうした學的論攻は著者の領域外であるは勿論、それらに關しては先輩諸學究の貴重な業績を手近かに求め得るので、本著においてはそれらを參酌の上、單にその普遍的説明を示す程度に止めた。 | p8 L-1 | 約三倍以上の量に達した。 |
| p13 L-3 | 過去數ケ年の永きに亘つて、豐竹古靱太夫氏、鶴澤友次郎氏、鶴澤道八氏をはじめ人形の吉田榮三氏、吉田文五郎氏、桐竹門造氏らを文樂座の樂屋に、 | p9 L2 | 過去數ケ年の永きに亘つて、豐竹山城少掾氏(當時の古靱太夫氏)、鶴澤友次郎氏、故鶴澤道八氏をはじめ人形の故吉田榮三氏、吉田文五郎氏、故桐竹門造氏らを文樂座の樂屋に、 |
| p13 L-1 | 特に古靱太夫氏は説明の完璧を期して、 | p9 L4 | 特に山城少掾氏は説明の完璧を期して、 |
| p14 L6 | なほ、本著はその企劃の性質上、聲樂としての太夫の節調も、絃樂器としての三味線の微妙さも、ともに僅か五十音に限られた文字によつて表現せざるを得なかつた。即ち、そこに多少とも無理の生ずるのはいふまでもない。著者はこの點へも能ふ限りの留意を加へたつもりだが讀者諸兄においても、よろしく判讀の勞を採られたい。然も、筆者は新聞人として日夜繁忙の社務にあり、その寸餘の時間を割いての執筆だけに、その記述論考にも不十分のもの多々あらうと自責してゐる。これらに關しては大方の叱正を得て、將來の完成を期したい。 | p9 L8 = L9 | |
| p14 L-1 | 擱筆に際して、豐竹古靱太夫氏、鶴澤友次郎氏、鶴澤道八氏をはじめ、日本演劇社の安部豐氏、中央公論社の橋本政德氏、版元畝傍書房の石光葆氏ら、本著のためにはその育ての親ともいふべき諸氏に對して、今、著者は心からの深謝に浸つてゐる。 | p9 L-2 | 擱筆に際して、豐竹山城少掾氏、鶴澤友次郎氏、故鶴澤道八氏をはじめ、日本演劇社の安部豐氏、元中央公論社の橋本政德氏、初版版元畝傍書房の石光葆氏ら、本著のためにはその生みの親ともいふべき諸氏に對して、著者は心から御禮申上げる次第である。 |
| p15 L4 | ギルバート諸島の大戰果に涙する日 | p10 L3 | (昭和二十三年初夏補筆) |
| p15 L5 | 大阪にて 山口廣一 | p10 L4 | 山口廣一 |
| p4 L7 | などの縁起に見るいろんな傳説が巧みに戯曲的形態において採り入れられてゐるのである。 | p4 L6 | などの縁起傳説がその中へ巧みに採り入れられてゐる。 |
| p7 L5 | 豐かな野趣とその野趣に包まれつゝ | p6 L9 | 豐かな野趣に包まれつゝ |
| p7 L9 | なほ、この作品はその後歌舞伎に移入されてより、幾多の諸名優によつて歌舞伎劇獨自の卓れた演出法が創案され附加され、特異な舞臺的展開を見せてゐるが、わけて三段目の口に當る「車曳」の一場は全く江戸系荒事歌舞伎の樣式化によつて再構成された形で、人形劇とは全く容貌の變つた純歌舞伎美の極致を見せるに至つてゐる。 | p6 L-4 = L-3 | |
| p8 L10 | なほ、彼は舞臺装置、舞臺演出の上においても奇オを發揮し、時代の欲求に應へて近松時代の太夫本位から人形本位の竹本座へと經營の方針を變革せしめた。即ち從來單純な一人遣ひの人形から現在のごとき三人遣ひの操法を創始して動作の複雜化、寫實化を覘つたのは最も大きい劃期的革新だが、そのほか人形の指先きや眉の動く繊細な工夫を加へたり、舞臺装置にも大道具大仕掛けを多數考案して觀客大衆の嗜好に投じた。勿論、彼の背後にはその共助者として吉田文三郎といふ人形遣ひの天才を擁してゐた事實も見逃せないが、要するに彼はその惠まれたオ幹を劇作家、經營家、演出家の三方面に發揮し竹本座の全盛時代を現出せしめた。延享期の「淨瑠璃譜」はこれを「このころ操り流行し歌舞伎は無きが如し、芝居表は數百本の幟、進物など數を知らず・・・・操りの繁昌いはん方なし」と記述してゐる。正に出雲はかうした意味において操淨瑠璃史最大の傑物といふべきであらう。/ 現在の演出法 歌舞伎におけると同樣、文樂座においても四段目の「寺子屋」が最も上演回數が多い。續いて三段目の「佐太村」二段目の「道明寺」といふ順だが、御靈文樂座時代「菅原」を通し狂言として出す場合でも第二段の口に當る「道行詞の甘替」と第四段の中に當る「北嵯峨」の段だけは多くの場合省略されるのが普通だつた(「道行詞の甘替」は最近復活されてゐる)。なほ鶴澤友次郎氏の談話によると、明治二十二、三年頃の文樂座において大詰の第五段の後へ原作にない「北野天神」の場といふ景事を添へた異例があるといふ。 | p7 L-1 = p8 L1 | |
| p10 L5 | 四段目に比べて遙かに輕く扱はれてゐるものですが | p8 L5 | 四段目に比べると、かなり輕い場面に扱はれてゐるのが普通ですが |
| p10 L7 | 格式で娘景清の「日向島」や忠臣藏の「九段目」と同樣、文樂座ではたとへ紋下格の太夫ですら、この場を受取つた時は一應座元に辭退してからでないと引受けないのが一種の幕内での禮儀になつているほどのものでございます。 | p8 L7 | 格式でございます。 |
| p13 L3 | 約束になつてゐる。大體において西風は地味な語り口、東風は派手な語り口といふのが主軸をなす相違である。(著者註) | p10 L5 | 約束になつてゐる。(著者) |
| p14 L10 | 一段中での名文で、作者三好松洛の手腕の程も窺へる個所でございますが、この | p11 L6 | 一段中での名文であり、またこの |
| p15 L3 | なつてゐるわけで皆さんも十分耳を澄して聽いて頂きたいところでこざいますが、要するに、覺壽一役はかうした巧みなウレヒの音遣ひによつて、〝氣品ある悲痛味〟が惻々として聽者の胸を搏つて來るやうでないと面白くありません。/ これは三味線においても同じことですが、そのむつかしさは、名人團平さんですら〝おれのウレヒの音は女房を亡くした悲しみを味つてから、どうやら少しは満足に出るやうになつた〟と述懷されたといふ有名な逸話を思ひ合せてもその一半は知れませう。 | p11 L9 | なつてゐるわけでございます。 |
| p16 L6 | だから、親の土師兵衞に敎唆されると | p12 L3 | だから、親の土師兵衞に唆かされると |
| p17 L5 | 水死人のある | p12 L-1 | 水死人ある |
| p18 L2 | 見事に躍動させてゐた | p13 L6 | 見事に語りわけてゐた |
| p18 L8 | こんないゝ宿彌太郎はそれ以後 | p13 L-3 | こんないゝ宿彌太郎はそれ以外 |
| p18 L12 | 呂太夫さん(後註參照) | p14 L2 | 呂太夫さん(初代豐竹呂太夫) |
| p19 L4 | --宿彌太郎は純粹の端敵[はがたき]で子供染みた單純な役どころです。型といへば例の「親人首尾は」といふと士師兵衞がシーツと制する、あすこで普通なれば狼狽てて口を抑へるんですが、私は自分の耳を兩手で塞ぐ型に從つてゐます。師匠の團十郎もさうやつてゐました。これは昔の名優の案出した型ださうですが、淺墓な端敵を面白く表現したものといへませう。(松本幸四郎氏談)=演藝畫報昭和五年六月號所載 | p14 L4 =L5 | |
| p20 L3 | 終始一貫して超人間的な冒し難い崇高さが、 | p14 L10 | 終始一貫して冒し難い崇高さが、 |
| p20 L7 | この人の菅丞相はどつか成り切つてゐる | p14 L-1 | この人の菅丞相はどつか菅丞相に成り切つてゐる |
| p23 L4 | 申しても差支へなささうです。 | p16 L-1 | 申しても差支へございません。 |
| p23 L11 | --始めの木像の間はあくまでも木像といふ心持ちで、階段を下りるにもヂーツと正面を見詰めたままスーツと步かねばなりません。それであの沓[くつ]を履くのがむつかしい。自然に沓の上へ足がちやんと乘るやうにならないといけません。(故中村鴈治郎氏談)=演藝畫報昭和五年六月號所載 | p17 L5 =L6 | |
| p25 L3 | この前後から段切[だんきれ]までは | p18 L4 | この前後から段切[だんきれ](一段中での最後の部分、歌舞伎でいふ幕切れに相當する)までは |
| p25 L4 | 段切の聽きどころ/ 特に平家ガカリの「身は荒磯の島守と、朽ち果つる後の世まで形見と思し召されよと」の繊細な語り口や「今鳴いたは慥かに鷄、あの聲は子鳥の音、子鳥が鳴けば親鳥も、鳴くは生あるならひぞと・・・・」あたりのウレヒの巧拙に氣を止めてお聽きになるやうお勸め申します。即ちこゝは菅丞相が刈屋姬を子鳥になぞらへ、自分自身を親鳥にたとへて親子の別れの切々たる情をそれとなく述懷されてゐるところですから「子鳥が鳴けば、親鳥も」の一句などは正に「道明寺」一段中でも屈指のむつかしい語りどこりで、表面では泣かずして腹の底でさめ〴〵と泣いてゐる菅丞相樣の悲痛さを太夫の語り口一つで表現すべきところでございます。このあたりを本當に味つて聽いて頂かねば、どんな「道明寺」でも死んでしまひます。/ 續いて「名殘はつきず、お暇と立ちで給ふ御詠歌より」から最後の「盡きぬ思ひに堰き兼ねる涙の玉の木槵樹」あたりの段切[だんぎり]一段中での最後の部分、歌舞伎でいふ幕切に相當するは、覺壽と刈屋姬と丞相樣との義理の親子の間[あひだ]に釀される息詰まるやうな美しい愛情を謳つたところで、それだけに、こゝはまた太夫にとつても三味線にとつても人形にとつても息の根が止まるほどむつかしく苦しいところで、まことに「道明寺」は最後の一句まで、お客樣のはうでも肩の詰まる浄瑠璃でございませう。 | p18 L5 =L6 | |
| p26L10-L11 | | p18 L6 | 有名な「段切れ」/ 即ち、この件[くだ]りは菅丞相が伯母の覺壽と娘の刈屋姬に、それとなくこの世の別れを告げながら出て行かれるところ、その義理の親子三人の間に釀される息詰まるやうな美しい別離の愛情をうたつたところで、それだけに太夫にとつても三味線にとつても人形にとつても、全く息の根が止まるほどむつかしい段切として有名なものでございますから、この件りのみ少し詳しく御説明申上げてみますと、先づ、「御恩を厚く込め給ふ、伏籠にかけしこの小袖、中なる香はきかねども、銘はおほかた伏屋か刈屋、伯母御前より道眞が、申請けし女子の小袖、我身にはあはぬ筈……」のうち「女子の小袖」はもちろん小と子の掛け言葉でございますから「女子のこ・そで」と少し氣味合ひを持たせるやうに區切つて申します。但し、もちろんそれが殊更らしく聞えては却つて嫌やなものになりますから、ホン氣味合ひだけでございます。/ そして、その次ぎの「我身には合はぬ筈」はチンと受けて、出來るだけ愁ひの音遣[おんづか]ひで語ることになつてをりますが、この「我身には合はぬ筈」は俗に申す「カカリ」といふ節[ふ*し]でございます。 |
| p26L10-L11 | | p19 L5 | 「カカリ」と「大三重」/ こゝでまた少し餘談に亙りますが、このカカリと申しますのは、言葉から地合[ぢあひ](言葉に對する地の文章で節のついてゐる個所)に移る繼ぎのやうな役目をするもので、謂はゞ言葉と地合との混血兒[あひのこ]のやうな語り方で、そして特に音[おん]を遣ふ(三味線なしに音聲ばかりの變化で巧みに節を語ること)ことを主眼にいたすものでございます。即ち、こゝでも前の「申請けし女子の小袖」が言葉で「我が身には合はぬ筈」がカカリ、そして*次ぎの「身幅も狹き罪人が……」から地合になつてをります。/ カカリの他の例を申上げますと、例へば「酒屋」のお園のクドキの「今ごろは半七さん(チン)どこにどうしてござらうぞ、今さら返らぬことながら……」の「どこにどうしてござらうぞ」がカカリです。そしてこれも同じくその前の「今ごろは半七さん」が言葉で、後の「今さら返らぬことながら……」以下が地合になつてをります。さらに、も一つ他の例を引きますと「堀川猿まはし」のお俊のクドキの「そりや聞えませぬ、傳兵衛さん、お言葉無理とは思はねど……」のうち「そりや聞えませぬ」が言葉で「傳兵衛さん」がカカリ、そして「お言葉無理とは思はねど」以下が地合なのでございます。/ 以上のやうに、この「カカリ」と申す節は、言葉から地合に「かかる」といふ意味で、どんな狂言にも、しば〳〵出て來る耳ざはりのよい節まはしでございますから、こゝで一應心得ておいていただきます。/ 續いて、伏籠[ふせご]の中で刈屋姬が忍びかねて思はずわつと聲を立てるので、覺壽が「泣いたは結句あの子がため、別れにちよつと只一目、伯母が願ひを叶へて」と立ち寄るので、「お年ゆゑのそら耳か、いま鳴いたは、たしかに鷄、あの聲は子鳥の音、子鳥が鳴けば親鳥も……」の述懷になりますが、このあたり、わけてもむつかしいところで「あの聲は子鳥の音」と向ふを見込んで刈屋姬だといふ思ひ入れでいひ「子鳥が鳴けば親鳥も……」を十二分の愁ひで、菅丞相が全く斷腸の思ひに堪へ兼ねてゐる樣子を表現[あらは]します。だが、それだといつて、この「子鳥が鳴けば親鳥」を正面から泣いてしまつてはいけません。むしろ泣かずにゐて泣く以上の愁ひを帶びて、聞いてゐらつしやるお客樣を胸一杯にさせねばなりません。太夫が正面から泣いてしまつてはお客さまは泣きません。太夫の技量のわかるところです。/ さらに「いまこの里に鷄なく……」を極く高い調子で張り、續いて「父はもとより籠の鳥、雲井の昔忍ばるゝ……」のあとの「トン、トン、ツトン、トン」の撥[ばち]を強く力を籠め氣味に使ひ、そして「道明らけき寺の名も道、明寺とて今もなほ、榮えまします御神の、生けるが如き御姿……」を十分大きく、十分手強く、十分崇嚴に語りますが、これは道眞公の御遺德の偉大さを讃へる意味合ひの節付けだからでございます。/ 次ぎに「こゝに殘れる物語、盡きぬ思ひにせきかぬる、涙の玉の木槵樹、珠數の數々くりかへし、歎きの聲に只だ一と目、見返り給ふ御顔ばせ、これぞ此の世の別れとは、知らで別るゝ別れなり」で終るのですが、このうち「盡きぬ思ひにせきかぬる」が「大三重[おほさんじゆう]」といふ節になつてゐます。この節は主として「大序[だいじよ]」(一段目の第一場)での天子樣やお公卿樣の出る場面に使はれますが、こゝでは丞相樣の人形が、屋臺から船底(別項參照)へ一段づつ降りて來られるところに使つてゐるわけでございます。 |
| p26L10-L11 | | p22 L1 | 「裏六法」の一例/ それから續いて「涙の玉の木槵樹」の直ぐあとに「チン、チン、チチチチチチ……」といふ奇妙な合の手がついてをります。これはどういふ意味の合の手か*御不審に思はれませうが、私は恐らく丞相樣の悲しみに餘つた吐息を三味線の音[おん]で表現したものであらうと解繹いたしてをります。/ 註--船底へ降りた菅丞相は舞臺下手に正面向いて立ち、この「チン、チン」で瞑目したまゝ兩肩を上げて二度首を縮めるやうな形をして「チチチチチチ」で、正面向いたそのまゝの姿勢で、うしろへトントントンと退がる。(著者)/ この「チチチチチチ」が終ると「珠數の數々くりかへし」になりますが、この「くりかへし」が「裏六法」といふ節附でございます。それは「くりかへし」の「し」の產み字(語尾の母音)を引き延ばして「イーイーイー」と語り、即ち「くりかへしイーイーイ(チリ、ガン、ツン)イーイーイー(チリ、ガン、ツン)」といつた風に產み字の「イーイーイー」と三味線の「チリ、ガン、ツン」とが二度繰り返へされるわけでございます。/ これは一人の人物が行きかけるのを、他のも一人の人物がそれを引戻すといつた動作を現はすところで使ひますもので、こゝでは「イーイーイー」で菅丞相が行きかけるのを、刈屋姬が「チリ、ガン、ツン」で引き戻す、また「イーイーイー」で行きかける、「チリ、ガン、ツン」で引戻すといつたわけで、それが人形の動作とぴつたり合ふわけでございます。/ この「裏六法」の他の例は「鎌倉三代記」で三浦之助を時姬が止める件りその他、これも非常によく使はれる三味線の手でございますから、こゝで記憶しておいていただきます。/ とにかく、こんな風に、平家ガカリの「身は荒磯の島守と……」の繊細な語り口から續いて「また改まる暇乞ひ」で三味線の調子が上つてからは、特に息[いき]も繼げないほど、むつかしい段切れでございますが、さらに「名殘りは盡きずお暇と、立ち出で給ふ御詠歌より、今この里に鷄なく……」から最後へかけては、太夫よりもむしろ三味線の全責任で、全くイキが詰んでないと彈けるものではありません。もちろん、節附けとしても實に立派な名曲で、それだけに樂しんで彈けますが、氣をゆるすどころか、イキ一つの緊張が「藝」になるか、ならぬかの境ひ目で、至難中の至難、大曲中の大曲でございます。 |
| p26L10-L11 | | p24 L1 | 三味線の「表」と「裏」/ なほ、こゝでちよつと昔の思ひ出ばなしを挾ませていただきますと「身は荒磯の島守と、打ち果つる後の世まで形見と思し召されよと、仰せは外に荒木の天神……」は「思し召されよと」のあとへ「チン、シヤン」と一撥[ばち]入れて「仰せは外に……」と續くわけなのですが、私の若い時分に法善寺の津太夫師匠(先代竹本津太夫)を彈かせて貰つた時、この「チン、シャン」は菅丞相さまの御威光を示すべきところだと考へて、出來るだけ位[くらゐ]をつけて彈きましたところ、津太夫師匠は「お前があんなに位をつけて彈いたら、わしが語られへん。位は太夫のわしにつけさせてくれ」と叱られたことがありました。こんなところに義太夫における太夫と三味線との相對[あひたい]づくの(相關的な)むつかしさが秘んでゐるものだと思ひます。/ 位をつけるところだといつて、三味線ばかり一人合點で、位をつけて彈くべきでなく、太夫の邪魔をせぬやう、太夫の語り口を生かせて彈くところに三味線の本領があるべきだからでございます。/ なほ、右のやうに文章の意味をそのまゝ、悲しいところは悲しい音色で、嬉しいところは嬉しい音色で彈くのを、三味線の「表」と申します。逆に、悲しいところを、直接[ぢか]に悲しい音色で彈かずして、然かも悲しみを表現するやうな行き方が、三味線を「裏」で彈くと申しますが、例へば五代目の廣助師匠はこの「表」の名人、その反對に二代目の團平師匠は「裏」の名人だつたといへるかと存じます。 |
| p28 L2 | 初代豐竹呂太夫に就て 初代豐竹古靱太夫の門人で、本名を上西吉兵衞といふ。以前は大阪天滿天神附近の藥種商の主人だつたのが、斯道の太夫に轉向した。通稱を「ハラハラ屋の呂太夫」と呼ばれてゐたが、ハラ〳〵屋とはその藥種商當時の家號だつた。/ 音聲はどつしりと幅があつて、如何にも義太夫らしい立派な音質であり、然もその大きさの無類だつたことで知られてゐる。現古靱太夫(二代目)氏の談話によると、呂太夫が御靈神社内の文樂座で語つてゐる聲が當時、同社東門筋を平野町へ出た東北角(現在のガスビルの位置)にあつた料亭魚岩の臺所まで聞えてゐたといふ。文樂座から魚岩まで直線距離でさへ百米以上あらう。恐しい音量である。たゞ、この人の語り口はその音質、音量に比して味ひに缺けてゐた。うま味と變化に乏しかつた。すべて大味で語り口に耳を傾けしめるほどの面白さを持つてゐなかつた。得意の語り物は「御所櫻三段目」「吃又」「大晏寺」「忠臣藏七段目」の平右衞門など。家庭でも、文樂座の樂屋でも絶對に膝を崩さなかつた行儀のよさが今なほ古老の語り草になつてゐる。明治四十年三月三十日歿、享年六十四。墓所は大阪市北區富田町常圓寺。 | p25 L-1 = p26 L1 | |
| p29 L2 | 豐竹古靱太夫 | p26 L2 | 豐竹山城少掾 |
| p29 L3 | 至難の〝源藏戻り〟 | p26 L3 | 「源藏戻り」のイキ |
| p30 L4 | --この口の「寺入り」は文樂座においても、現今では歌舞伎同樣時間の關係上省畧される場合が多い。(著者註) | p26 L-1 = p27 =L1 | |
| p31 L2 | 續いて「内入り惡く | p27 L10 | 獨り言はむつかしい/ 續いて「内入り惡く |
| p32 L1 | とかく會話の調子に | p28 L6 | とかく人と話し合つてゐるやうな調子に |
| p33 L1 | 源藏が戸浪にヒソ〳〵話をしてゐる | p29 L3 | 源藏が女房の戸浪と膝をつき合せてヒソ〳〵話をしてゐる |
| p34 L7 | 結構なものでございました。 | p30 L4 | 結構なものでございました。で、私もまたそれに倣つて「因果かアアアア」と泣いてをります。 |
| p34 L-1 | 澁味が添つて來るものでございます。 | p30 L8 | 澁味が添つて來るものでございます。なほ「せまじきものは」を「せまじイイイきものオオは」と賣り込んで語る人もございますが、私は「せまじきものオオは」と眞直ぐに語つてをります。 |
| p35 L-3 | 人形獨得の型になつてゐる。(著者註) | p31 L5 | 人形獨得の型になつてゐる。吉右衞門の源藏はこの一句をセリフでいつて、その巧みな含蓄味を聞かせる。(著者) |
| p36 L5 | 聽かせたいものと、心掛けて | p31 L-2 | 聽かせたいものと、近ごろは特にさう心掛けて |
| p36 L-5 | 知つた事かいツ」でも、實檢の | p32 L2 | 知つた事かいツ」でも、また實檢の |
| p37 L1 | 手が痺れて來て堪りません。なほ現在この玄蕃に使つてゐるカシラの「金時」は文樂座所有のカシラ中での名品でございますから、よく御覧下さいますやうに。(桐竹門造氏談) | p7 | 手が痺れて來て堪りません。(桐竹門造氏談) |
| p40 L3 | 崩れたものになつてしまふものでございます。 | p34 L11 | 崩れたものになつてしまふと思ひます。 |
| p40 L-4 | 主にした特別な語り振りなのである。(著者註) | p35 L3 | 主にした文樂獨自の特別な語り方なのである。(著者) |
| p41 L1 | 首討つたは、まがひなし相違なし」と續けます。 | p35 L6 | 首討つたは」でウムと呼吸[いき]をも一度詰めて、よく死んでくれたといふ氣味合ひを持たせ、すぐ「まがひなし相違なし」と續けます。 |
| p41 L6 | その樣子が前のお客樣にも | p35 L-4 | その樣子が場[ば]のお客樣にも |
| p41 L-3 | かくして苦しい首實檢が無事に濟めば、源藏夫婦ばかりでなく太夫もやつと | p36 L1 | この苦しい首實檢が無事に濟めば、源藏夫婦ばかりでなく太夫の私も、やつと |
| p43 L-1=p44 L1 | | p37 L1 | 「持つべきものは」の表現/ それから、松王の述懷の「伜がなくばいつまでも、人でなしといはれんに、持つべきものは子なるぞやと、いふに女房なほせき上げ」のところの「持つべきものは子なるぞやと」は普通で行きますと「持つベエエーエきものはアアアーアウン子なるウーウぞやアアーと」でございます。そしてかう語れば嫌やが應でも拍手喝采と來るところですが、私は最近「持つべきものは、子なるウーウぞやアーと」と極く簡單に壓縮して語つてをります。これなども、一つには松王の語り口を出來るだけ單純にして、松王の若さを表現したい意味合ひからでございます。 |
| p45 L2 | われわれのやうな肚の薄い | p39 L4 | 私のやうな肚の薄い、 |
| p45 L-1 | 太夫はたゞそれに調子を合せて美しく唄へば | p39 L-2 | 太夫はたゞそれについて唄へば |
| p46 L5 | 演出として最も卓れたものであらう。 | p40 L3 | 演出として最も正しいものであらう。 |
| p47 L-3 | 步調音の韻律的表現 | p41 L1 | 步調音律の韻的表現 |
| p48 L6 | 二つを擧げ得よう | p41 L9 | 二つを擧げることが出來る |
| p49 L-3 | 風景的表出(水平線)となつた | p42 L9 | 風景的表出となつた |
| p50 L4 | 文樂座の舞臺は前方の | p43 L1 | 文樂座は前方の |
| p50 L7 | 「船底」で遣はれるのである。/東京新橋演舞場その他、文樂座以外の舞臺では「船底」がないから平舞臺を「船底」として使ひ「本手」(屋臺)はその後方へ舞踊の所作臺を臨時に組みあげて、大體文樂の舞臺構造に近ひものを作つてゐる。勿論「船底」なる名稱は | p43 L3 | 「船底」で遣はれるのである。勿論「船底」なる名稱は |
| p51 L8 | 口を開かないのが本格で、能面における「癋見[べしみ]」と同樣、口を一文字に締めてゐるところに性格の勁さと威嚴の深さが力強く形象されてゐるのである。/ 現在、吉田榮三が使用してゐる文七は文樂カシラ中での傑作である。これは三代目桐竹門造の作と傳へられるが、或は四代目桐竹門造の作品でないかと春陽會の齋藤清二郎畫伯が考證してゐる。要するに確たる製作者は不詳だし、時代も四代目門造なら或は明治初期で比較的新しいものだが作品としては素晴しい。榮三の松王なら必ずこれを使つてゐるから十分注意して鑑賞したいものである。/ この他に文樂現有のカシラ中に「文七」はなほ數個あるが、多くはこの名作「文七」を天狗辨が後世模作したものである。 | p43 L-1 | 口を開かないのが本格である。 |
| p54 L7 | 平家沒落後にもなほ生存せしめて、その一人々々に奇抜な趣向の結末をつけてゐるのである。 | p46 L7 | 平家沒落後もなほ生存せしめ、その一人々々に奇抜な趣向を描いてゐる。 |
| p54 L-1 | 若葉内侍と幼君六代君とは | p46 L-4 | 若葉内侍と幼君とは |
| p56 L-2 | 「椎の木」の段における可憐な平家の落人 | p48 L5 | 「椎の木」の段における平家の落人 |
| p57 L1 | 舞臺のものとされてゐる。かく全段に亘つて點綴されるかうした詩情美がこの作品の大きい特質をなしてゐるのである。 | p48 L7 | 舞臺のものとされてゐる。 |
| p59 L1 | 言葉に地合あり/ 義太夫道では〝言葉のうちに地合[ぢあひ]あり〟といふことをよくいひます。/ 地合とは御存じの通り言葉或は會話を除いた節曲[ふし]の附いてゐる地[ぢ]の文章です。即ち〝言葉のうちに地合あり〟とは、一見平淡に聞える言葉でもよく吟味して聞いてゐると、必すそこに一種の抑揚や節曲[ふし]があるものだ・・・・といつた意味なのです。例へば、この「鮓屋」に致しましても權太のいふ「母ア者人」とか、お里の「アーレ禰助さんの戻らんした」などがそれです。「母者人」をハージヤヒト、「あれ」をアーレといつた風の特殊な抑揚をつけてゐます。/ これは私たちが日常なんの氣もなく使つてゐる會話のうちにも屢々見出されるところです。例へば兵隊さんには兵隊さんの抑揚があり、商人には商人の節曲[ふし]がある。乘合バスの女車掌さんの〝次は心齋橋でございまアす。お降りのお方はございませんかア〟の一言にすら、既に或る種の言ひ廻しが現れてゐます。だから義太夫でも、この呼吸[いき]をよく呑み込んで自己の藝の中にそれを活用させる。そしてその人物なり心理なり境遇なりを一層適切に表現する―つの手段に用ひねばならない。〝言葉のうちに地合あり〟の訓へが即ちこれでこざいます。/ 時にはこの對句として〝地合のうちに言葉あり〟ともいはれますが、この機會に一應御記憶願ひたいと存じます。 | p50 L2 = L3 | |
| p61 L1 | 扨て、この「鮓屋」は「義經千本櫻」の三段目の切に | p50 L4 | この「鮓屋」は「義經千本櫻」の三段目の切に |
| p61 L-1 | 前口上が長くなりましたが、大體においてこの | p51 L2 | さて、大體においてこの |
| p62 L8 | 今日で申せば感化院の御厄介にでもなるべき不良青年 | p51 L9 | 今日で申せば不良青年 |
| p67 L5 | 續いて例のサハリ | p55 L3 | 續いて例のクドキ |
| p67 L-4 | すべて、かうしたサハリは | p55 L6 | すべてかうしたクドキは |
| p68 L3 | 肯づける素朴で、どつか野暮ツたい色氣 | p55 L-4 | 肯づけるどつかモツサリした色氣 |
| p68 L5 | これではいけないのです。いはゆる大阪言葉でいふところの〝もつさり〟した色氣が太夫の語り口にも現はれるのを理想として語らるべきものでございます。 | p55 L-3 | これではいけないのです。 |
| p68 L-4 | お里のサハリの間 | p55 L-1 | お里のサハリの型 |
| p69 L-3 | 聲に籠つた力の強さ如何が問題 | p56 L-3 | 聲に籠つた力の強さが問題 |
| p70 L1 | 昔、長門太夫 | p57 L1 | 昔、三代目の長門太夫 |
| p70 L5 | 玉造が腹に卷いてゐた腹帶 | p57 L4 | 玉造が腹に卷いてゐた腹卷 |
| p70 L7 | 三名人の三つの氣合ひが | p57 L6 | 三名人の氣合ひが |
| p70 L-3 | 好例だと存じます。/ なほ、餘談に亘りますが、この切れた腹帶は家寶として現在の四代目玉藏が傳承、今日まで秘藏してをる筈です。 | p57 L7 | 好例だと存じます。 |
| p71 L3 | この一段中での最も至難な個所です、 | p57 L-4 | この一段中での最もむつかしいところです。 |
| p71 L6 | 氣持が仄かに匂つてゐなければなりません。 | p57 L-1 | 氣持が見えねばなりません。 |
| p71 L-4 | 女房小仙)の美貌を褒めて | p58 L2 | 女房小仙)の器量を褒めて |
| p71 L-1 | 現はれてゐねばなりません。尤も、といつて全く狂言の底を割つて | p58 L5 | 現はれてゐねばなりません。しかし、それが狂言の底を割つて、 |
| p71 L5 | やり取りを原作の精神に則つて語り生かす困難さ | p58 L | やり取りを語り生かす困難さ |
| p72 L7 | --梶原が御臺と六代君(實は權太の女房小仙と伜善太)を檢分するところ「でかいたでかいた、内侍六代生け捕つたな、ハテよい器量」の件[くだ]りは歌舞伎の演出法として種々の名演技が殘されてゐる。今日、音羽屋系を代表する菊五郎の權太では「面あげい」で善太の頭を右手で押へ、左足で小仙の顔をあげさせる。上方系を代表する延若では右足をトンと―つ前へ出し、左右兩手を、それ〴〵小仙と善太の顎へかけて上を向かせ、自分は梶原に顔をそむけて極る。故雁治郎もこの系統だつたが、兩手で二人の顔をあげると同時に自分は下を向いて梶原の視線から脱がれようとする。これらに對し吉田榮三の遣ふ人形の權太では二人の顔を見て一度愁ひを含んでから前へ押し出し、自分はその後方で觀客席を背にした後向きになり、手拭ひの端を兩手で持つて背中の汗をふく。(著者註) | p58 L-5= -L4 | |
| p73 L3 | --梶原の腹は立役です。「維盛夫婦餓鬼めまで啀みの權太が討ち取つたり」といふので、ヤしまつたといふ思ひ入れをしまして、それからも始終その心で勤めてゐます。全く敵役でなさる方もあるさうですが、私は何處までも立役でやつてゐます。(故市川中車藝談)=演藝畫報大正十二年四月號所載 | p58 L-5 =L-4 | |
| p76 L1 | 五段物の形式 この機會に義太夫五段物の定型的形式について、一通りの説明をしておかう。/ 大體、義太夫狂言における時代物(世話物を除く)の場面の採り方は五段形式が原則である。即ち發端の一段目から終結の五段目まで。そしてその各段はまたそれ〴〵「口」、「中」、「切」といふ三場に細別されてゐる(そのうち一段目の口を特に大序と呼ぶ)。だから一篇の義太夫狂言は前後約十五場面から構成されてゐるわけで、これが時代物の定型になつてゐる(勿論、本書に收めた「繪本太功記」や「假名手本忠臣藏」のごとき例外もあるが、それとて詳細に場面分類をしてみると、大略この五段形式に該當することを知る)。/ 次に各段を内容的に見るに、一段目は帝王又は權威者の面前における立役と敵役との勢力爭ひを描いて全篇を貫く主題事件を紹介し、續いてそれに戀愛的場面を附加する。二段目はこの一段目を照應させた修羅場となり、續く三段目では一轉して悲運に陷つた立役の愁嘆を見せて一篇の劇的最高潮に達し、四段目は三段目における氣分の暗さを轉換させる意圖に出て、多くは派手な道行をその「口」に當て、「中」と「切」も、ともに華やかな抒情的、空想的、浪漫的構成を持つ。そして最後の五段目で複雜に絡つた筋をほぐして善人の勝利、惡人の敗北で目出度く終結することになる。/ 例へば、この「義經千本櫻」の各段をこれに當て篏めて見るに、一段目大序の藤原朝方と義經の對立から義經と卿の君の件りが〝勢力爭ひと戀愛〟であり、二段目の知盛の奮戰と入水が〝修羅場〟。三段目の權太の横死が〝愁嘆〟。四段目の「口」には定石通り靜御前と忠信との道行を置いて、それが吉野山「河連館」における狐忠信の夢幻的な美しさへ展開して典型的な四段目の形式を示す。そして五段目では能登守敎經の討死で平家の一門はすべて滅亡し「四海太平民安全、五穀豐饒の時を得て、穗に穗榮ゆる秋津國、繁昌ならびなかりけり」と語り終つてゐる。/ 勿論、この各段の内容構成にも例外は多いから一概にもいへないが、物語は大體において、かうした經路で終結する。なほこの五段物の持つ定型的形式と定型的内容とは能樂の五段物形式との類似を想起せしめるものがあり、一般に能樂より轉化した趣向立てと論究されてゐる。 | p60 L6 = L7 | |
| p78 L6 | その始めだといはれる。/ 現在の文樂座で使用されてゐる團七には團七と大團七との二種類がある。團七は前述の「夏祭」の團七のほか「千本櫻」の啀みの權太のやうな無賴漢「鷓山古跡松」の大武廣次「めし碗」の勘六「白石噺」の志賀團七「安逹原」の南兵衛など、主として世話物がゝつた | p60 L-4 | その始めだといはれる。主として世話物がゝつた |
| p78 L-1 | 要するに、團七カシラは「夏祭」の團七と「千本櫻」の權太とがその代表的なものであり、歌舞伎の役どころでいはふなら西の延若、東の猿之助あたりの藝風に一脉の聯想がある。 | p60 L-1 = p61 L1 | |
| p79 | L3 三代目大隅太夫は近世における | p61 L1 | 三代目大隅太夫は明治期における |
| p79 L5 | / この人の語り口は熱と力と量感に充ちてゐた。勿論美聲家ではなかつたが、 | p61 L2 | この人はもちろん美聲家でないが、 |
| p79 L-3 | 否めない。故三代目竹本津太夫もかつて著者に、「私が子供の時分、清水町(大阪南區島之内)の團平師匠のお宅へ使ひにまゐりますと、よく玄關で先代大隅太夫さんが大の字に寝てフウ〳〵苦しさうな息をして休んでゐられたものです。これは團平大師匠のお稽古があまりにも激しかつたからです」と大隅追憶の斷片を語つてゐた。また現豐竹古靱太夫の思ひ出話 | p61 L8 | 否めない。豐竹山城少掾の思ひ出話 |
| p80 L6 | 殘つてをります。しかし、扨て自分がやつて見ると、眞似事どころか一口も語れません」とある。 | p61 L-6 | 殘つてをります。」とある。 |
| p80 L8 | 大阪東區順慶町の出身。明治五年に太夫となり、主として彥六座系の | p61 L-5 | 大阪東區順慶町の出身。主として彥六座系の |
| p82 L4 | 時代だつた。特にこの「假名手本忠臣藏」は義太夫劇最大の傑作として、初演當初より現代に至るまで最も大衆的人氣を持續してゐるものである。初演は | p64 L4 | 時代だつた。初演は |
| p85 L3 | 古典としての國民演劇 赤穂浪士の復仇事件に取材した戯曲は恐らく數百にのぼらう。この「假名手本忠臣藏」もそのうちの單なる一篇に過ぎないのだが、然もその「忠臣藏」といふ略稱は「假名手本忠臣藏」のみでなく、むしろそれら數百の赤穗復仇戯曲群を總稱する代名詞であるかの如く用ひられてゐる。わが國劇史上において恐らくかうした例は他に求め得ないであらう。如何にこの一篇が人口に膾炙し、如何に永くわが國民全般に親しまれて來たかが知れよう。/ 古來、芝居道では「不入になれば忠臣藏を出す」といふ不文律さへある。勿論、その上演回數もわが古典劇中の最高數だし、全くこの一篇は初演當時より今日に至るまで最も普遍化されたわが國唯一の國民演劇ともいふべきである。/ この一篇がかくも大衆的人氣の標點となり得た因由として増田七郎氏は(一) 忠義と復仇を主題とせること(二)然もその題材となつてゐる赤穗事件が遠い過去の物語でなく、極く近世の出來事であること(三)全篇の構成が「菅原傳授手習鑑」や「義經千本櫻」のごとき夢幻的な荒唐性を離れて、どこまでも寫實的手法の上に現實的自然的であること。即ち人物、人情、環境すべてが觀客に身近かさを感ぜしめることなどを擧げてゐる。(同氏著「忠臣藏」 同「假名手本忠臣藏に就て」(岩波講座日本文學))/ 要するに、題材がわが國民性と合致してゐる強味、それに作劇手法としての優秀さ(特に大序、三、四、六、九の各段に示した巧妙さ)が事件を描き得ても人間を描き得ない凡百の操淨瑠璃中にあつて、比較的よく人間性の摘出に成功してゐる點などから見ても、この一篇の永く古典劇の最高地位を把握せる理由も容易に首肯し得よう。 | p66 L-1 = p67 L1 | |
| p86 L-5 | 今日の演出法 文樂、歌舞伎を通じて、最も上演回數の多い場面は大序、三、四、五、六、七、八、九の各段だが、文樂座今日の上演時間四時間半の制限内での通し狂言は全く不可能になつた。なほ七段目の「一カ茶屋場」は初演において此太夫、政太夫、島太夫、文字太夫らの〝掛合〟で上演されたものだが、今日においてもこの段のみは〝掛合〟の形式がそのままに傳承されてゐる。 | p66 L-1 = p67 L1 | |
| p87 L-3 | 義太夫になつてをります。義太夫中の義太夫たる眞隨とでも申しますか實に皮肉中の | p67 L6 | 義太夫になつてをり實に皮肉中の |
| p87 L-1 | 盬谷一家中の緊張感と悲痛感とが | p67 L-4 | 盬谷一家中の緊張した氣分と突きつめた悲しみとが |
| p88 L3 | 舞臺の空氣が亂れるとさへいふほどで | p62 L-2 | 舞臺の空氣が亂れるといふほどで |
| p89 L1 | ヤカマシ物でございます。/ 即ち、殿中で突發した大椿事から盬谷家中の言語に絶した驚愕と混亂ぶり、 | p63 L8 | ヤカマシ物で、即ち、殿中で起つた大椿事から盬谷家一同の驚きと混亂ぶり、 |
| p89 L4 | 興奮に驅り立てられた家臣達が幕府の沙汰を今か〳〵と待ち受けてゐる不安と焦慮、そして | p63 L-4 | 興奮し切つた家臣達が幕府の沙汰を今か〳〵と待ち受けてゐます。そして |
| p89 L7 | といつた息詰まるやうな情景が、 | p68 L-2 | といつた息詰まる情景が、 |
| p89 L7 | 從つて、その語り口は何處までも | p68 L-2 | 從つて、この一句は何處までも |
| p89 L9 | これがこの一句を語る解釋と腹構へ | p68 L-1 | これがその腹構へ |
| p90 L3 | 重々しい嚴肅な緊張と悲痛感とが | p69 L6 | 重々しい緊張と悲しみとが |
| p90 L7 | 先づいつて見れば三味線の調子と | p69 L-6 | 先づいつて見れば三味線につくとは三味線の調子と |
| p90 L-3 | 盬谷の「ヤ」で始めて | p69 L-1 | 盬谷の「ヤ」まで來て初めて |
| p91 L1 | 手を拍[たゝ]かせるやうな美しい節廻し | p70 L3 | 手を拍[たゝ]かせるやうな耳ざはりのよい節廻し |
| p90 L2 | 抑揚一つで沈痛な重々しい氣分一杯に語るべきもので、その精神をこの最初の一句が代表してゐるやうなものでございます。即ちこの一句の | p70 L4 | 抑揚一つ、音遣[おんづか]ひ一つで沈痛な重々しい氣分一杯に語るべきもので、即ちこの一句の |
| p91 L5 | 「忠臣藏四段目」の鑑賞において最も大切な | p70 L6 | 「忠臣藏四段目」中最も大切な |
| p92 L-1 | 花籠に……」から少し調子が和らぎます。 | p71 L7 | 花籠に……」から少し調子が和らぎ氣分が變ります。 |
| p93 L8 | といふ冷罵に對して郷右衞門は | p72 L1 | といふ冷笑に對して郷右衞門は |
| p93 L-1 | 品位がなさ過ぎるのではないでせうか。 | p72 L5 | 品位がなさ過ぎるのではないかと思はれます。 |
| p94 L1 | 隨分卑しい性格の人物には | p72 L6 | 隨分卑しい人柄の人物には |
| p94 L6 | 語つてゐるのはどうでせうか。たとへ性格的には卑しくとも、 | p72 L10 | 語つてゐるのはいけません。たとへ人間としては卑しくとも、 |
| p94 L-4 | これを單に從來通りの | p72 L-2 | これをたゞ從來通りの |
| p94 L-1 | 結局は太夫の音遣ひの | p73 L2 | 結局はこれも太夫の音遣ひの |
| p95 L8 | 今後は十分かうした點にも注意して聽いて頂きたいものと存じます。 | p73 L8 | かうした點にも十分注意して聽いて頂きたいものです。 |
| p96 L-2 | 演じられてゐるのは遺憾です。 | p74 L8 | 演じられてゐるのは感心できません。 |
| p97 L6 | 格式を持つた表現こそ本當だと | p74 L-1 | 格式を持つた扱ひが本當だと |
| p98 L5 | 複雜な描法は並み一通りの | p75 L9 | 複雜な語り方は並み一通りの |
| p98 L-1 | 餘程の天才でない限り語れません。 | p75 L-1 | 餘程の太夫でない限り語れないといふことになります。 |
| p99 L2 | 申しても敢へて差支へないと存じます。 | p76 L2 | 申しても差支へないと存じます。 |
| p100 L8 | 感じられる緊迫した悲愴な空氣が | p77 L6 | 感じられます緊迫した空氣が |
| p101 L2 | 續けて彈いてゐる間に舞臺の | p77 L10 | 續けて彈いてゐる間は太夫の「待合せ」で、その間に舞臺の |
| p102 L4 | 決して女々しく由良助の頰に落ちる涙ではありません肚の底へこぼす男の涙に | p78 L8 | 決して表面へ出して泣いてはいけないといはれます。たゞ由良助が自分の肚の底へこぼす涙に |
| p103 L2 | 急ぎ行く……」の件りもこの一段中での最後の聽きどころでございませう。即ち「しづ〳〵と | p79 L4 | 急ぎ行く……」のうちしづ〳〵と |
| p103 L6 | 正體なく」の一句は女性の表現だけに、大變派手な美しい節附がついてはゐますが、その派手な節を逆に | p79 L6 | 正體なく」の一句は女のことだけに、大變派手な耳ざはりのよい節附けになつてはゐますが、これもその派手な節を派手なまゝに彈かず、逆に |
| p103 L8 | そこに地合の皮肉な深味が | p79 L8 | そこに三味線の皮肉な深味が |
| p103 L-4 | 正體なく」と合の手が這入ります。この合の手は | p79 L-5 | 正體なく」となるのですが、この合の手は |
| p103 L-3 | この四つ間[ま]の餘韻が既に | p79 L-4 | この四つ間[ま]の音色が既に |
| p103 L-1 = p104 L1 | | p79 L-1 | 「運び」と「間拍子」/ 要するに、三味線といふものは、彈くべきものでなく、彈かずに氣分を現はすのを極上といたします。ベンベラ〳〵と彈いて現はすのなら誰にも出來る。これなら至極く樂なものですが、本當の三味線は彈かずして、彈く以上の氣分を現はす。これが眞に本筋の「藝」でございます。そして、それは結局「運び」と「間[ま]拍子」の妙によつて達し得られるものでございます。 |
| p106 L-3 | なる意味だが、總人形遣ひが僅か二十數人程度の小人數になつた現今の文樂座では、 | p83 L5 | なる意味だが、現今の文樂座では、 |
| p107 L2 | 現五代目桐竹門造氏は三代目吉田文三その他近世名手の左を長く遣つてゐた人だが「私は一人前の人形遣ひやおまへん。たゞの左遣ひだす。右を持たされたらアキまへんが、そのかはり左を遣ふ段になれば、人さんに負けん積りだす」と著者に左遣ひとしての衿持を示したことがある。次第に寂寥を加へつゝある文樂の人形陣では、既にもうかうした本格の左遣ひの修業を經た人も次第に少くなつて來た。門造氏以外では僅かに吉田玉米氏あたりが女形人形の左遣ひとして重要視されてゐる程度である。 | p82 L-1 = p83 L1 | |
| p108 L6 | 語らるべきものです。/ では、なぜこれがそれほど格式ある大物かとお尋ねに預つても、そのお答へはちよつと困ります。強ひてお答へ申せとなれば、兎に角マクラから段切まで一字一句、すべて絶對に氣が許せないやうに出來てゐると申すより外はございません。全く義太夫のうちでも「九段目」以上むつかしいものはないと | p83 L6 | 語らるべきものです。マクラから段切まで一字一句、絶對に氣が許せないやうに出來てゐる。全く義太夫のうちでも「九段目」以上の大物はないと |
| p110 L3 | 庵の戸口」の第一節からして既に | p84 L7 | 庵の戸口」が既に |
| p110 L-4 | 「人の心の奥深き」は思慮深い由良助の人物を諷してゐる一句ですから、この一句がまた由良助らしい重々しい氣分を現はさなければなりません。全く最初の一行からこの通りです。從つてお客樣のはうでもこの「九段目」こそは特に耳を澄ませて、よく〳〵鑑賞して頂きたいものでございます。 | p84 L-2 | 「人の心の奥深き」はそれとなく思慮深い由良助の人物を諷してゐる一句ですから、この一句にもまた由良助の風格が添つてゐなければなりません。全く最初の一枚からこの通りです。 |
| p111 L2 | このマクラ一句の精神は山科の | p85 L1 | このマクラ一枚の主意は山科の |
| p111 L4 | 山科への小徑をザク〳〵 | p85 L3 | 山科への小徑をサク〳〵 |
| p111 L6 | 白皚々たる比叡の峰々から | p85 L4 | 白妙の比叡の峰々から |
| p111 L7 | 雪がサラサラと落ちる氣分までが、 | p85 L5 | 雪がサラサラと落ちるやうな氣分が、 |
| p111 L9 | マクラとは申されません。攝津大掾さん(後註參照)の「九段目」など | p85 L6 | マクラとは申されません。そして、それは結局、左指三本の働き如何によります。かうした情景を現はすのは、三味線の餘韻によるのですが、その餘韻を出すのが左手の働き、左指三本の使ひ方によるわけです。撥を持つた右手はむしろ機械的に動かせてゐてよろしいが、三味線の最も大切なのは左手にあります。三本の絃をおさへ離す左手の指三本によつて三味線の音色と餘韻とが生きもし、死にもいたします。攝津大掾さんの「九段目」など |
| p111 L-1 | 雪降りどころか、干涸[ひか]らびた山科へ戸無瀨と小浪とがカラ〳〵下駄履きでやつて來る | p85 L-2 | 雪降りどころか、山科へ戸無瀨と小浪とがカラ〳〵日和下駄でやつて來る |
| p112 L3 | 一撥入れてるのが政太夫風、入れないのが仲太夫風でございます。 | p86 L1 | 一撥入れて締めるのが政太夫風、締めないのが仲太夫風でございます。/ ところが、このジヤンと締めてはならぬとする仲太夫風で申しますと、「奥深き山科」と「山」と「山科」とが掛け言葉になつてゐるのだから、その掛け言葉の間へ「ジヤン」と入れては邪魔になる、といふ理窟です。これに對して政太夫風では、それなら「七段目」の「月の入る山科」の「月の入る」と「山科」との間に「ツツン」と入れるのはどうしたことか、と反對するわけでございます。結局いづれでも語る太夫の好み次第ですが、現在では誰もみなジヤンと締める政太夫風で彈いてをります。 |
| p114 L3 | 昨今臨時に傭ひ入れた者に向つていつてゐるので、そこに相違があるわけです。まことに九段目はこんな端々の一字一句にすら油斷がなりません。 | p88 L2 | 臨時に傭ひ入れた者に向つていつてゐるので、そこに相違があると解釋されるからです。 |
| p114 L8 | 可憐な小浪の風情 | p88 L5 | 小浪の風情と「雛ぶし」 |
| p114 L-1 | わしや恥かしい、・・・・」の一句は | p88 L7 | わしや恥かしい、となまめかし」は |
| p115 L2 | 即ち小浪をその鶯に | p88 L-4 | 謂はゞ小浪をその鶯に |
| p115 L-2 | なほ、「わしや恥かしい」の「恥かしい」は色(地合[ぢあひ]と言葉の中間)で | p89 L4 | なほ、「わしや恥かしいとなまめかし」は雛ぶしと申しまして、艶のある節まはしでございます。それから「わしや恥かしい」の「恥かしい」は「色[いろ]」で語るのと「音[おん]」で語るのと二通りございます。色(地合[ぢあひ]と言葉の中間)で |
| p115 L-1 | 美しく聞かせるのが本當で | p89 L7 | 美しく語るのが本當で |
| p116 L3 | 藝の上での怜悧さで、津太夫さんにしてみれば自分の聲柄のよくないことを | p89 L9 | 藝の上での賢さからで、津太夫さんにしてみれば、自分の聲柄のよくない、音[おん]の遣へぬことを |
| p117 L-1「」 | アノまあお石樣の」後へオホ | p90 L-2 | 「アノまあお石樣の、オホ |
| p118 L6 | 頓挫の面白味を十分味つて聞いて頂きたう存じます。/ この邊りの語り口はすべて一句々々以上のやうな文章の意味をよく呑み込んだ上で語られねばなりません。 | p91 L4 | 頓挫、強弱の變化の面白味を十分味つて聞いて頂きたう存じます。/ しかし、いくら氣張つて詰合つても、それが井戸端會議のやうに聞えてはいけません。瘠せても枯れても、千五百石と五百石との家老の奥方としての氣品だけはたもつて語らねばなりません。 |
| p119 L6 | 正しい健氣さです。これを聞く戸無瀨の胸は | p92 L3 | 正しい健氣さです。そして、この件りは一樣に三味線の手が極く簡單につけてありますが、それも小身な五百石程度の家老の小娘という氣味を考慮した節付けなのでございます。/ これを聞く戸無瀨の胸は |
| p119 L-1 | かうした母の決意を聞いて | p92 L10 | さて、かうした母の決意を聞いて |
| p123 L6 | 小浪が最後に唱へる「南無阿彌陀佛」です。この一言の唱名の | p95 L6 | 小浪が最後に唱へる「南無阿彌陀佛」です。たゞ泣いてゐるだけのこととは違ひます。この一言の唱名の |
| p124 L8 = L9 | | p96 L5 | 立つた言葉と坐つた言葉/ 本藏が家の内へはいる時の「加古川本藏が首、進上申す、お受取りなされよ」の言葉は、よくよく注意いたしませぬと、本藏が坐つたまゝで、かういつてゐるやうに聞えます。これは本藏が門の外に立つたまゝいつてゐる言葉なのですから、立つたまゝの言葉に聞えるべきでございます。人形があれば、立つてゐるか坐つてゐるか判かりますが、人形のない素淨瑠璃の時は、なほさら立つたまゝの言葉に聞えなくてはいけません。微妙な違ひですが氣をつけて聞いていたゞきますやうに……。/ それから、本藏が家の中へ這入ると「やあお前は父さま、本藏さま、こゝへはどうして……」と驚く戸無瀨と小浪に向つて「やアざは〳〵と見苦しい、始終の子細みな聞いた、そちたちに知らさず、こゝへ來た樣子は追つて、先づ黙れ」という本藏の言葉も、どうかすると、女房と娘を頭から叱りつけてゐるやうに聞えるものですが、これは叱つてゐるのでなく、なるべく靜かな口ぶりで嗜[た]しなめてゐる程度に語るべきものとされてをります。これも、そのつもりで、お聞き下さいますやうに……。/ 續いて本藏の「案にたがはず拙者が首、聟引出に欲しいとな、ハヽヽヽヽ、いやはや、そりや武士のいふこと……」になりますが、こゝの「ウウフ、アアハ」といふ本藏の大笑ひは近年はあまり大業にやらなくなりました。「寺子屋」での松王の咳「帶屋」での儀兵衛の笑ひなどもさうですが、強ひて大業にやらなくともよろしからうと思ひます。太夫が名人上手なれば知らぬこと、未熟な太夫が無理無體に泣いたり笑つたりしては、却つてブチ壞はしでございませう。/ 次ぎに「邪魔ひろぐなとあらけなく」から本藏とお石の立廻りになりますが、この立廻りの間は「叩[たゝ]き撥[ばち]」の複雜な手がついてをりまして、三味線の聞かせどころでございます。そのうち「拳はなれて取落す(トン、トン、トン……)鎗うばはれじと走り寄る」のトン、トン、トン……はお石がよろける氣味合ひを現はした三味線で、それが人形の動作とうまく合ふやうになつてをります。 |
| p124 L9 | 結局、九段目はこゝまでが眼目で、本藏が家體へ這入つて力彌に突かれて本心を明かす後半は比較的餘裕を持つて語れます。たゞ本藏の表現を常に大きく強くと心掛けることと「忠義ならでは捨てぬ命、子故に捨つる親心」 といつた本藏の忠と情に挾つた武士としての自責の氣持を大事に扱つて語りさへすれば、それでよろしいものと存じます。 | p98 L1 | 本藏の最期の一句/ この立廻りで本藏が力彌に鎗で突かれると奥から由良助が出でまゐりまして、「一別以來珍らしい本藏どの、御計略の念願とどき、聟力彌が手にかかつて、さぞ本望でござらうの」と申しますが、由良助はこの言葉で始めて本心の由良助に立ちかへるわけでございます。/ それから手負ひの本藏の述懷に移りますが「忠義ならでは捨てぬ命、子ゆゑに捨つる親心、推量あれ、由良どの」といふ一句は實に名文で、わが子の愛情に惹かれる本藏の氣持をよく現してをりますが、「九段目」ではこの一句でお客樣を泣かせねばなりません。まことに情合の籠つたむつかしい一句でございます。なほ「子故に捨つる親心」のあとへ「これ、これ、これ」と三つ愁ひで押してから「推量あれ、由良どの」と續けることが一つの技巧になつてゐます。/ さて、段切れに由良助が雪持笹の工夫を見せますと「本藏苦しさ打ち忘れ、ハヽヽヽヽしたり、計略といひ義心といひ……」と由良助を讃へて喜びますが、こゝの笑ひは「手負ひの笑ひ」と申しまして、傷口の痛さを辛棒して笑ふこれも一つの技巧で、義太夫ではしば〳〵用ひられる手法でございます。/ そして、とど、由良助が本藏の衣裳を借つた虛無僧姿で出て行くところで終りますが、こゝの最後の「心殘して、立出づる」の「心殘して」が前に「道明寺」のところでも御説明申上げたと同樣、これが「裏六法」になつてをります。即ち「心殘してエエエエエエーエチン、チン、トチンチチンチンエエエエエエーエチン、チン、トチンチチンチン」と二度繰り返へします。これは由良助が一步行つては、後へ心が惹かれてまた一步退く、といつた思ひわづらふ形容で、前述しましたとほり「裏六法」はいつもかうした行きつ戻りつ思ひわづらふやうな個所に用ひるものでございます。 |
| p125 L1 | --本藏の「日本一の阿呆の鏡」を五代目菊五郎さんは自分にもかけて云ふ心で、ジツと目を自分に落しました。主のために死なずに娘のために死ぬといふ自分の立場にも引つ掛けての周到な用意なのでせう。(故市川中車藝談)=演藝畫報昭和六年二月號所載 | p99 L8 = L9 | |
| p126 L7 | 當時文樂座はまだ松島千代崎橋畔 | p100 L6 | 當時文樂座はまだ松島花園橋畔 |
| p127 L1 | また現古靱太夫は大掾の節廻しを評して | p100 L10 | また現山城少掾は大掾の節廻しを評して |
| p128 L6 | 廣く使はれる。歌舞伎の役どころでいへば、故市川中車とか故先代仁左衞門といつたところでもあらうか。表情の仕掛けは | p101 L-1 | 廣く使はれる。表情の仕掛けは |
| p131 L1 | 「一谷陣屋」の段が傑作で、數ある並木宗輔の作品中でも、これは恐らくその最高位を行くものであるまいか。特にこの三段目における熊谷の人間的表出、 | p104 L-3 | 「一谷陣屋」の段が傑作で、熊谷の人間的表出 |
| p131 L4 | 修羅の巷を脱して出家遁世する | p104 L-1 | 修羅の巷を脱して遁世する |
| p131 L5 | 人間味が描出されてゐる。人間の脆さ、浮世の果敢なさ、そしてそれを倫理づける佛敎的諦觀といつたものがこの「三段目」を貫く主題精神になつてゐるのである。蓋し〝あはれ〟によつて表示された佛敎的人生諦觀は中世文學に見る傳統的性格だが、この一段はさうしたわが國文學上の傳統を演劇的構成によつて再現して見せたといつた感じがされる。少くとも人間の本性を直視しようとする或る思惟の深さが、この作品をして義太夫狂言中稀れに見る異色篇たらしめてゐるのである。/ これに關しでは故中村吉藏氏も、宗輔の一聯の作品を論究して「彼は局面構成に屢々新奇なるトリツクを求め、探偵小説的の興味を覘つて在來の型に外づれたものを見せてゐると同時に、海音乃至出雲らの強調せる義理を突破して往々人情の眞諦に觸れ、若しくは人間の本能にすら穿ち入らんとする衝動を認めしめる點に一の特色を示してゐる」と説いてゐる。(同氏著「日本戯曲技巧論」) | p105 L1 | 人間味が描出されてゐる。人の世の脆さ、果敢なさ、そしてそれを倫理づける佛敎的諦觀を背景として、少くとも「人間」を發見せんとしてゐるのが、義太夫狂言中稀れに見る文學性である。 |
| p134 L-3 | 四大作家と稱せられてゐるが、作品のそこはかとなき文學的點綴においては、むしろ、この宗輔がその最上位を占めるものではあるまいか。 | p106 L-1 | 四大作家と稱せられてゐる。 |
| p135 L2 | 豐竹古靱太夫 | p107 L2 | 豐竹山城少掾 |
| p135 L4 | 「熊谷陣屋」は昭和十七年初春興行の文樂座で、私の櫓下(紋下)披露狂言に演[だ]しましたもので、私としては誠に由縁[ゆかり]の深い狂言でございます。/扨て、この場は三段目の | p107 L4 | この場は三段目の |
| p137 L3 | いつもホツと致します。尤も、この一段では段切[だんぎり]に〝僧形の熊谷〟といふ難物が控へてはをりますが・・・・。 | p108 L7 | いつもホツと致します。 |
| p137 L5 | その前半のうちでも、及ばずながら私が最も精魂を打ち込んで語つてをりますのは最初の熊谷の出[で]で | p108 L8 | その前記のうちでも、最初の熊谷の出[で]で |
| p137 L9 | 座に直れば」までの一節でございます。 | p108 L-3 | 座に直れば」までの一節に苦心がございます。 |
| p138 L-1 | 云々の音遣[おんづか]ひでは誰よりも先代大隅太夫さんのそれが未だ耳に殘つて | p109 L9 | 云々の音遣[おんづか]ひ(三味線なしで、音聲のみの變化で節を語ること)では誰よりも先代大隅太夫さんのそれが耳に殘つて |
| p139 L3 | 注意して聞いてごらんなさいませ | p109 L-2 | 注意して聞いていただきますやうに…… |
| p145 L3 | と暗にさとすやうな氣味合ひを | p114 L7 | と暗にそれとなくさとすやうな氣味合ひを |
| p147 L7 | -ー熊谷が奥へ入つた後に相模と藤の方が殘る。こゝはどうしても中だるみがして興味が中斷される虞れがある。作者宗輔も恐らく太夫に休息を與へるため、こんな沈んだダレ場を書いたのであらう。(岡本綺堂氏)=大正五年三月號演藝畫報所載 | p116 L2 = L3 | |
| p149 L2 = L3 | | p117 L4 | 註--義經の言葉、上吊るは惡し、優美にせんとても作り聲はせぬものぞ。(岡鬼太郎著「義太夫秘訣」) |
| p150 L1 | 國を隔てゝ十六年」の「十六年」をチンと彈かせて「じうウウウろオくウウウねん……」と、例のカカリ節で大向ふ受けを覘ふところですが、お客樣の拍手の嫌ひな私は此處も | p117 L-2 | 國を隔てゝ十六年」は「道明寺」の段で友二郎さんが説明されましたカカリのところで「兩方ながらおなかに持ち」が言葉「國を隔てゝ」がカカり「十六年」から地合になりますが、その「十六年」をチンと彈かせて「じうウウウろオくウウウねん……」と、俗に申しますカカリ節で節おもしろく大向ふ受けを覘ふところですが、私は此處も |
| p150 L8 | 涙に暮れてゐる感じを出して | p118 L6 | 涙に暮れてゐる情合ひが語れ |
| p152 L1 | お客樣が「古靱の淨瑠璃は糞長いなあ」 | p119 L8 | お客樣が「山城の淨瑠璃は糞長いなあ」 |
| p152 L9 | 藤の方 女房 | p119 L-3 | 藤の方 (老女形) |
| p154 L-2 | 年齢は六十歳前後 | p121 L10 | 年齢は五十歳がらみ |
| p155 L1 | 用ひられてゐる。現在の文樂座にはこの「金時」が二個殘つてゐる。そのうち一個は初代玉造から傳つた名品として有名である。表情の動きはない。 | p121 L12 | 用ひられてゐる。表情の動きはない。 |
| p155 L6 | 紅の隈取が描かれる。このカシラも現在文樂に大小二個ある。 | p121 L-2 | 紅の隈取が描かれる。 |
| p155 L10 | 肩衣に袴をつけて人形遣ひが顔を觀客席に露呈する出遣ひの形式 | p122 L1 | 肩衣に袴をつけた出遣ひの形式 |
| p156 L2 | 黑衣よりも多いといつた逆現象さへ呈してゐる有樣である。特に東京公演などは各場面とも全部出遣ひの極端さだが、蓋しかうした出遣ひ | p122 L5 | 黑衣よりも遙かに多くなつてゐる。かうした出遣ひ |
| p160 L9 | 隱れた股肱の臣だつた。竹田出雲が時人の嗜好を先見して、床の義太夫よりも手摺の人形を重視し、舞臺本位、人形本位の趣向を凝らして、當時における竹本座の黄金時代を招來したのも、實はこの文三郎がその獨創になる操りの仕掛物を矢繼早やに考案し得たためだつた。 | p126 L1 | 隱れた股肱の臣で、その獨創になる操りの仕掛物を矢繼早やに考案した。 |
| p160 L-1 | 竹本座における至寶的存在であり、座本出雲が彼を如何に重用したかについては「假名手本忠臣藏」初演の際、文三郎と紋下竹本此太夫(筑前少掾)との間に劇しい論爭事件が持ち上つた際、座頭格の紋下此太夫を退座させても、なほ文三郎だけは極力留座せしむるの對策を採つたといふ有名な逸話でも知れよう。/ 彼の天分は | p126 L3 | 竹本座における至寶的存在だつたといへよう。彼の天分は |
| p161 L6 | 採り得たのである。蓋し、彼は人形遣ひ吉田姓の始祖といふばかりでなく、人形浄瑠璃三百年の歷史においても、抜群の天才兒だつたといへよう。しかし、この惠まれた天才兒も、 | p126 L5 | 採り得たのである。しかし、この天才兒も、 |
| p163 L5 | 一徹さに止まつてをるのみです。 | p126 L2 | 一徹さに止まつてをるのみだからでございます。 |
| p166 L-3 | かやうに緊張と弛緩が交互に | p130 L8 | かやうに緊張と弛緩、強さと弱さが交互に |
| p166 L-2 | 義太夫においても、この點を | p130 \l9 | 義太夫においても、この「吃又」に限らず、どんな狂言でも、この點を |
| p167 L8 | 女房の人並み以上の饒舌、この對照の妙を | p131 L3 | 女房の人並み以上の辯舌、この取り合せの妙を |
| p168 L1 | 多く袴をつけない。 | p131 L7 | 多く袴をつけないが東の六代目は「たつつけ」風のものを履いてゐる。 |
| p170 L-2 | 花道で遠見することになつてゐるが、勿論人形にさうした | p133 L-4 | 花道で坐つて遠見することになつてゐるが、人形にはさうした |
| p170 L-1 | 止まる。たゞし歌舞伎においても | p133 L-3 | 止まる。勿論このはうが正しい。歌舞伎でも |
| p172 L-3 | 非常に複雜に聞こえますが、 | p135 L1 | 非常にやゝこしく聞こえますが、 |
| p175 L5 | 筆の勢」までの間はこのメリヤスで | p137 L2 | 筆の勢」までの間はこのチチン、シヤンのメリヤスで |
| p175 L7 | 節を語るのでございます。 | p137 L3 | 節を語る「音遣[おんつか]ひ」でございます。 |
| p177 L9 | 琵琶湖の遠見を | p138 L-2 | 琵琶湖の遠見の書割を |
| p179 L4 | 澤市に用ひられてゐる。/ 「源太」は大正十五年の文樂座燒失の際、殆ど燒いてしまつたので、文樂座現存のものに名品はない。現在榮三の用ひてゐる二個はともに、この燒失後、天狗辨に作らせた新品である。たゞ現紋十郎の所有せるもの(初代玉造より先代紋十郎、現紋太郎を經て現紋十郎に傳へられたもの)のみは現存の「源太」中での唯一の名品といはれてゐる。/ 「源太」の名稱は勿論、「平假名盛衰記」の源太景季から出たものであらうが、要するに、故中村鴈治郎とか現在の市村羽左衞門あたりの役どころを聯想させるカシラである。 | p139 L-4 | 澤市に用ひられてゐる。「源太」の名稱は勿論、「平假名盛衰記」の源太景季から出たものであらう。 |
| p180 L1 | 即ち凡て「動きなし」なのである。歌舞伎でいへば東の尾上菊之助、西の中村翫雀とでもいつた若い賣出しの二枚目どころでもあらうか。 | p140 L2 | 即ちすべて「動きなし」なのである。 |
| p180 L8 | 二階棧敷あたりから、俯瞰するとよくわかる。 | p140 L8 | 二階棧敷あたりから、見下すとよくわかる。 |
| p180 L10 | この下駄のため、文樂座の舞臺床板には絶對に凸凹があつてはならない。少しでも凸凹があると、下駄の先きがそれに躓いて足許の安定度を失ふから、人形遣ひは勢込んで前へ仆れる。文樂の舞臺はこの點十分注意されてゐるが、東京の新橋演舞場や京都南座など地方巡業では歌舞伎舞臺の臨時使用だから、廻り舞臺の繼ぎ目などに凸凹があり、「よつぽど氣をつけませんと、下駄が引つ掛かりさうで危うおます」と榮三が話してゐた。/ また、本手屋臺から船底へ人形が下りる場所、高さの差が一尺二寸ほどあるので、人形遣ひはあの大きな下駄のまゝ少し飛び降り氣味でないと下りられない。この場合も人形遣ひが自分の重量と人形の重量との安定度をよく〳〵修得しておかないと、人形遣ひは大きい人形を抱へたまゝ前のめりに打つ仆れてしまふのである。こんな觀客の眼の届かないところにも人形遣ひの隱れた修練の大事さがある。 | p140 L-1 = p141 L1 | |
| p188 L10 | 作家的手腕の豐富さを察知し得るが、然も、これらの名作は前述の通りすべて竹本座最後の不況時代を背負つて立つた近松半二の獻身的努力の結晶たるを想ふ時、この名作者の半生に、われらはむしろ一沫の悲壯感の胸を搏つものさへ感じる。 | p145 L-3 | 作家的手腕を察知し得るが、然も、これらの名作は前述の通りすべて竹本座最後の不況時代を背負つて立つた近松半二の獻身的努力の結晶だつた。 |
| p188 L-2 | 今日の演出法 最近の文樂座では、比較的丁寧な上演ですら三段目の口「桔梗ケ原」の段の境目爭ひから切の「勘助住家」の段筍掘りそれに四段目の切「十種香」を添ヘる程度である。これだけでも上演時間は優に四時間を要する。然も、各場面の錯綜せる連繋と承應の複雜さはなほこれだけの上演場數では全篇の筋立てを推察し得べくもない。まして「筍掘り」又は「十種香」一段のみを切離した上演では今日の觀客を對象とした場合殆ど意味をなさない。最近、あれほど古風で滋味掬すべき「筍掘り」が歌舞伎において殆どその上演を絶つてゐるのも、恐らくこの難解さのためだと解釋する。然かも獨り「十種香」のみが文樂においても歌舞伎においても比較的上演の機會に惠まれてゐるのはさうした難解さを犠牲にしても、なほこの一幕の持つ花やいだ情趣と繪畫美の豐かさ、それに「奥庭狐火」における所作事的妙味が大きい魅力を持つてゐるためであらう。所詮は文樂も、歌舞伎も、官能的要素を主とする特異な演劇である有力な證左の一つがこゝにも見られるわけである。 | p145 L-1 = p146 L1 | |
| p191 L-3 | 語り物に致しませんでした。なほ大掾師匠の「十種香」は有難いことにレコードが殘つてゐます。このレコードの原板は大掾師匠が生前「出來榮えがどうも氣に入らぬ。必ず人樣に聞かさずにおいてくれ」と家人に命じて密封させ、お宅の金庫の中へしまひ込んでおかれたものを、その歿後に出されたものです。あれほど立派な「十種香」ですら、大掾師匠御自身の氣には入らなかつたものと存じます。如何にも名人攝津大掾の面目躍如たる逸話でございます。/ 私はお蔭で、大掾師匠の | p147 L5 | 語り物に致しませんでした。 私はお蔭で、大掾師匠の |
| p192 L9 | 甚だ餘談に亘りますが、こゝでちよつとその御前演奏當時の思ひ出を話させて頂きますと、それは明治三十五年九月九日、京都市河原町の田中市兵衞さんの別荘で催されたもので、御臨場の宮樣は小松宮と伏見宮の兩殿下。語り物は大掾師匠(當時越路太夫)がこの「十種香」で先代津太夫さん(後註參照)が「忠臣藏九段目」でございました。當時私は先代津太夫さんの合三味線だつたのですが當日はたまたま大掾師匠の三味線野澤吉兵衞さんが上京中だつたものですから、大掾師匠の三味線も臨時に私へとの御下命を受けました。何分にも宮樣の御前演奏だし、それに相手は名だたる大掾師匠だし、まだ當時二十七、八歳の若輩だつた私には全く背負ひ切れぬ大役で、どうなることかと、おど〳〵致してをりましたがお蔭で不滿足ながらも大過なく勤めさせて頂きました。今思ひ出すと、全く夢中だつたのでございませう。「十種香」一段が自分では十分か二十分で終つたやうな氣が致します。大掾師匠に致しましては、私の三味線など、赤ん坊の手を捻ぢるやうなもので、スツカリ太夫に引き摺られながら、無我夢中で彈いてゐたのでございませう。しかし、この時の光榮は私の一生を通じて忘れることが出來ません。なほ大掾師匠が「攝津大掾」たるべき令旨を頂かれたのは、この御前演奏後間もなくのことでございました。 | p147 L8 = L9 | |
| p194 L1 | 註--攝津大掾は實に美しい聲を出されますが、あれは巧妙に齒を使はれますからで……大掾が語られますに「われ民間育ち」と花やかな若者の聲で語り「人に面を見知られぬを幸ひに」……かやうに唇を使はず齒を使つて語れば必ず若者になる。これは秘傳ものでございます。(先代豐竹呂太夫談)=秋山木芳氏著「義太夫大鑑」 | p147 L8 = L9 | p150 L1【同文】 |
| p194 L | 最初の出端[では]は、「行く水の | p147 L-4 | 最初の出端[では]は、四段目風のオクリを彈いてから「行く水の |
| p195 L1 | そして三味線のトン、トン、トンも太夫の語り口 | p148 L3 | それから三味線のトン、トン、トン…………と一の絃[いと]で彈き流すところも、太夫の語り口 |
| p195 L3 | ものでございます。 | p148 L4 | ものでございます。途中で變に撥が止つたり、にぶつたりしますと、水の流れも妙なところで止る感じで面白くありません。 |
| p195 L4 | 「人の」で一應句切つて、 | p148 L6 | 「人の」で一應切つて、 |
| p196 L4 | 濡衣の人物説明も | p149 L4 | 濡衣の説明も |
| p197 L3 = L4 | p194 L1【同文】 | p150 L1 | 註--攝津大掾は實に美しい聲を出されますが、あれは巧妙に齒を使はれますからで……大掾が語られますに「われ民間育ち」と花やかな若者の聲で語り「人に面を見知られぬを幸ひに」……かやうに唇を使はず齒を使つて語れば必ず若者になる。これは秘傳ものでございます。(先代豐竹呂太夫談)=秋山木芳氏著「義太夫大鑑」 |
| p202 L-4 | 私たちの日常會話におきましても、話す相手方によつて、その用語なり、調子なり、 | p154 L4 | 私たちの日常におきましても、話す相手方によつて、その言葉なり、調子なり、 |
| p203 L3 | 簔作と申す花作り」は八重垣姬に對する言葉ですから | p9 | 簔作と申す花作り」は素性を隱して八重垣姬にいつてゐる言葉ですから、 |
| p203 L6 | 家臣に向つての調子であり、 | p154 L-2 | 家臣に向つての少し横柄な調子であり、 |
| p203 L8 | 語調でなければなりません。すべて、かうした話す相手方 | p155 L1 | 語調でなければなりません。勝賴も右のとほり本當の勝賴としていつてゐる語調と簑作に假装していつてゐる語調との間に區別がないといけません。そして最後に謙信が出て來るので、驚いて勝賴の語調を隱し「御支度よくば直ぐさま參上」の一言はスツカリ簔作の語調になつて出て行くわけでございます。 /すべて、かうした話す相手方 |
| p205 L4 | ならぬところで、わけて、そのうちの「呼ぶは生ある | p156 L6 | ならぬところで、わけて、三味線は足どりのむつかしい、氣分のむつかしい、全體に彈きにくいところです。然もこのあたりに上杉謙信の姬君八重垣姬、大々名のお姬樣としての貫禄と氣品とが備はつてないといけませぬ。「太功記」の尼崎での初菊や、五百石の家老の娘としての「九段目」の小浪などとは、自ら人品が違つてゐなければならぬはずでございます。/ なほそのうちの「呼ぶは生ある |
| p206 L7 | 八重垣姬も勝賴の膝にに片肱をトンと突いた色氣のある形を致しますが、この三味線のチン、チン、チンも人形の動き同樣 | p157 L9 | 八重垣姬もそのチン、チン、チンの最後の「チン」に合せて勝賴の膝にに片肱を突いた色氣のある形で極りますが、三味線も人形の動き同樣 |
| p206 L10 | おきぬなど、澤山ございますから、 | p157 L-3 | おきぬなど、他にも澤山ございますから、 |
| p209 L8 | 大掾に繼いで文樂座の | p159 L-1 | 大掾に繼いで大正初期に文樂座の |
| p212 L1 | 本文の意味を彈くものである。然も彈くべき | p161 L-4 | 本文の意味、すなはち喜怒哀樂を心に收めて彈くものである。無暗に音色にばかり氣を止めて彈くものでない。然も彈くべき |
| p212 L4 | 眞の名手とはいへない。要するに三味線といふ藝道は | p162 L1 | 眞の名手とはいへない。さらに「心すなほに」とは一つの流儀、一人の師匠に片よらず、諸流、諸師匠にわたつて素直な氣持で勉強すべきだといふ意味で、要するに三味線といふ藝道は |
| p218 L10 | 劇的進行が、上手の脊山と | p167 L12 | 劇的進行のセリフが、上手の脊山と |
| p219 L1 | 一致の上に、濃厚な演劇的リズムを加へつゝ鮮やかな舞臺效果を刻んで行く。蓋し半二のかうした並行的構成法は新しき國劇創造の上にも、將來少からぬ示唆と啓示を持つものといへよう。/ 今日の演出法 三段目の「山の段」が一篇中の傑作として最も多く上演を見てゐるのは當然だが、續いては「杉酒屋」から「御殿」へかけての四段目。特にお三輪と橘姬と淡海との道行「賤の苧環」は單獨の景事としても、現在吉田文五郎(お三輪)の當り藝として屢々上演されてゐる。二段目の「芝六住家」の段は、この一篇における最も複雜で皮肉な語り場だが、殿上人を扱つた作意に相當の改訂を加へぬ限り、今日での上演はむつかしい。 | p168 L1 | 一致した步調の上に、濃厚な演劇的リズムを加へつゝ鮮やかな舞臺效果を刻んで行く。 |
| p220 L7 | 申さば本格的な掛合物とでも申すべきでございませう。そこで、 | p169 L7 | 申さば本格的な掛合物でございます。そこで、 |
| p226 L1 | 何の報いぞや」のサハリに移りますが、 | p173 L8 | 何の報いぞや」の聞かせどころに移りますが、 |
| p226 L3 | ゐなくてはなりません。豐かな抒情味、濃やかな色氣を | p173 L9 | ゐなくてはなりません。濃やかな情合ひと色氣を |
| p227 L1 | 見せ所としては、「ナウ久我さまか | p174 L4 | 見せ所は、「ナウ久我さまか |
| p228 L-1 | ドツシリと豪快に澁い二の音 | p175 L10 | ドツシリと染太夫風に澁い二の音 |
| p237 L4 | 腰のまはりに當るところに竹の輪 | p182 L | 腰のまはりに當るところに(竹片で作つた)の輪 |
| p238 L1 | 文樂座の現有カシラ 文樂座は大正十五年十一月二十九日御靈神社時代出火。この時、多くのカシラを烏有に歸せしめたが、それでもなほ現在大阪松竹の倉庫に收められてゐるカシラの總數は三百以上と稱されてゐる。勿論、今日の舞臺に實際使用されてゐるのはそのうちの百あまりに過ぎない。/ 以前は、カシラはすべて文樂座自體の所有でなく、主として人形遣ひ或は座外の愛藏家の所有に屬し、座主植村家が興行毎にそれを賃借する制度だつた。それが明治後期に及んで次第に座主の手に買收され、遂にその大多數が植村家の所有となつた。現在大阪松竹の所有するカシラはこの植村家所有のものを明治四十二年文樂座の讓渡と同時に引き繼いだものである。/ 現有文樂座のカシラの素性を洗つて見ると、その多くは嘗つて初代吉田玉造、吉田金四初代吉田多爲藏の師匠それに扇屋三郎兵衞中村鴈治郎の母方の生家で新町の置家の所藏品だつたものが大半を占めてゐる。 | p182 L-1 = p189 L1 | |
| p242 L-1 | 今日の演出法 「酒屋」の段として | p186 L5 | なほ、この作品では「酒屋」の段として |
| p243 L1 | 上演の記録がない。 /この「酒屋」一幕のみが例の「今ごろは半七さん」の哀切を極めたサハリの一節とともに、かくも普遍化した理由は半兵衛、お園、宗岸らによつて釀される親子、舅嫁の義理と愛情との溫い交流およびお園の持つ貞操觀、結婚觀が如何にもわれらの傳承する道義の日本的性格を簡明に表示し得てゐるがためではあるまいか。結婚による實家と婚家との家族的連繋、結婚によつて、妻はその夫の妻たるよりも、先づ自我を沒却したその婚家の一構成員たるの自覺を要請される。即ち日本の結婚が單なる夫と妻との個人的連繋でなく、むしろ「家」と「家」との全體的連繋を主眼とする思想、これはわが民族傳承の上に根深い潜勢力を持つてゐろ。この一段がお園を中心に、かうした結婚の日本的性格をその背後に色濃く展示し得てゐる點に、觀客は非常に身近かな共感を感ずるのではあるまいか。この段のみの屢演も、正に當然といふべきであらう。/ なほ、この一篇については | p186 L6 | 上演された記録がない。さらにこの一篇については |
| p245 L7 | だから、お園のサハリの | p187 L5 | だから、お園のクドキの |
| p245 L-3 | わづらひに……」あたりで、口先きばかりの黄色い美聲を張りあげて、たゞもう | p187 L6 | わづらひに……」あたりで、たゞもう |
| p246 L6 | 妻の至情など、われ〳〵日本人の持つ美しい家庭愛が、誠に聽く者の肺腑を貫く底の眞實味に溢れてゐます。即ち半兵衞の苦衷、宗岸の慈悲、お園の貞節を十分引締めて語り込んで行つてこそ、この一段の精神も生きてまゐると申すもので、決して、お園のサハリの「今ごろは半七さん・・・・」を鼻唄まじりで前受けを覘ふといつた淺薄なものではこざいません。「酒屋」の「酒屋」たる眞價は | p187 L-1 | 妻の至情など、「酒屋」の「酒屋」たる眞價は |
| p248 L2 | 自然と暗くなる。--少し理想論めきますが、先づ語り口が到達せなければ、 | p188 L-1 | 自然と暗くなる。先づ語り口が到達せねば、 |
| p250 L7 | 遠慮勝ちな心遣ひなどの混淆した複雜な感情が | p190 L9 | 遠慮勝ちな心遣ひなどの混じり合つた複雜な感情が |
| p255 L6 | 無難だと存じます。咳に限らず總體に、 | p194 L5 | 無難だと存じます。「九段目」の時もちよつと申上げましたが、咳に限らず總體に、 |
| p255 L-1 | この意味からしても以つての外だといふべきです。 | p194 L11 | この意味からしても感心いたしません。 |
| p257 L1 | サハリの精神 | p195 L10 | 鼻唄式の美聲でない |
| p257 L2 | いよ〳〵お園のサハリですが、 | p195 L-4 | いよ〳〵お園のクドキですが、 |
| p257 L8 | お園のサハリに關する | p196 L2 | お園のクドキに關する |
| p257 L9 | 頂きたいものでございます。 | p196 L2 | 頂きたいものでございます。なほ「今ごろは半七さん」のあとの「どこにどうしてござらうぞ」は前に一度説明いたしましたと思ひますが、これは「カカリ」でございます。即ちこれから地合にかかるので、次ぎの「今さら返らぬことながら……」から地合になつてをります。 |
| p257 L-1 | 傾城のやうだと非難する方もありますが、 | p196 L7 | 傾城のやうだと惡ういふ方もありますが、 |
| p258 L7 | --「あとには園が憂き思ひ」で、ちよつと癪を押へながら、立つて舞臺端の柱のところまで來て、表を見る心持をして「世の味氣なさ身―つに」で上手屋臺の中を見て「繰り返したる獨り言」で行燈を持つて來て上手寄りに斜めに置き、左の膝をちよつと立て、右手を懷ろへ入れ「今頃は半七さん」を臺詞でいつて「どこにどうしてござらうぞ」のチヨボで立つて、舞臺端の柱へ手をかけて向ふを見る。(故中村歌右衞門の型)=雜誌「歌舞伎」三十一號所載 | p196 L-3 = L-2 | |
| p259 L1 | このお園のサハリが濟むと、 | p196 L-1 | この件[くだ]りが濟むと、☆☆ |
| p259 L6 | 一本の書置きをリレー式で讀ませたり、 | p197 L4 | 一本の書置きを替る〴〵讀ませたり、 |
| p259 L7 | してゐますが、蓋し、かうでもせぬ限り | p197 L5 | してゐますが、これは、かうでもせぬ限り |
| p260 L-1 = p270 L1 | | p198 L9 | 註--「聞いているさの」や「をしの片羽」のキツカケを突込んで言葉からの變り目を當て場にする人あれど、これらは太夫の數にも入れ難き厄介者にて、隣の稽古屋の唄はこちらと別々のやうに注意するが誠の心得なり。(岡鬼太郎著「義太夫秘訣」) |
| p263 L9 | 木綿橋北で素淨瑠璃の掛小屋を | p200 L5 | 木綿橋北で淨瑠璃の掛小屋を |
| p264 L-4 | (後の攝津大掾)、三味線に團平、廣助、人形に玉造、紋十郎らの名手相継いで輩出、ために強敵彥六座を仆し、その後身ともいふべき堀江明樂座、堀江市の側の堀江座、近松座などの各劇場も | p201 L4 | (後の攝津大掾)、五世彌太夫、二世津太夫、三味線に廣助、才治、吉兵衞、人形に玉造、紋十郎らの名手をもつて次第に強敵彥六座を仆し、さらにその彥六座の後身ともいふべき堀江明樂座、堀江市の側の堀江座、佐野屋橋の近松座など明治末期より大正期へかけての各劇場も |
| p266 L2 | を新築、自來今日まで、消長十四年の歷史を經てゐる。 | p202 L5 | を新築して復興。以後十五年間を經たが、昭和二十年三月十四日の大阪空襲に燒失。戰後二十一年二月、東西劇場に先きがけて復活。燒失前と同じ位置に建築も以前と殆ど同じ樣式で再建され、今日にいたつてゐる。なほ昭和二十二年六月、天皇陛下行幸、天覧の光榮に浴した。 |
| p266 L3 | 三代目竹本津太夫に就て | p202 L9 | 二代目竹本津太夫に就て |
| p266 L3 | 四代目竹本津太夫や現紋下豐竹古靱太夫氏の師匠 | p202 L9 | 三代目竹本津太夫や文樂座現紋下豐竹山城少掾の師匠 |
| p267 L2 | 呼ばれてゐたほどだつた。現古靱太夫は恩師を追懷して「なか〳〵お世辭のいゝ氣輕な方で、法善寺内のお宅の臺所では、いつも奥さんの代りに、手拭の姉さん被りで七輪の尻を煽つてゐられたものです。そのころ、われわれ弟子どもの用事といつては店先へ腰掛床几を列べること、それに師匠愛玩のインコと犬の世話が大變でした」と語る。/ 世話物畑におけるこの人の藝風は古靱太夫よりも、むしろ先年逝くなつた(四)代目津太夫の | p203 L3 | 呼ばれてゐたほどだつた。世話物畑におけるこの人の藝風は現山城少掾よりも、むしろ先年逝くなつた三代目津太夫の |
| p273 L3 = L4 | 《「作者、菅専助」のまえ》 | p208 L9 | なほ御靈文樂時代に「あられ松原毒酒」の段、「天王寺西門」の段を併せ上演された記録があるが、今日上演を見るのは下の卷「合邦住家」の段のみである。俊德丸と淺香姬が再會する「天王寺西門」の段は人形的な動きも多く、場面的な變化も多彩なだけに「合邦住家」の前に、この一段の併演など將來望ましいものゝ一つである。 |
| p273 L-2 | 今日の演出法 御靈文樂時代に「あられ松原毒酒」の段、「天王寺西門」の段を併せ上演された記録があるが、今日上演を見るのは下の卷「合邦住家」の段のみである。俊德丸と淺香姬が再會する「天王寺西門」の段は人形的な動きも多く、場面的な變化も多彩なだけに「合邦住家」の前に、この一段の併演など將來望ましいものゝ一つである。 | p209 L3 = | |
| p275 L2 | 豐竹古靱太夫 | p210 L2 | 豐竹山城少掾 |
| p275 L4 | ハラ〳〵屋の呂太夫さん、攝津大掾さん、 | p210 L4 | ハラハラ屋の呂太夫さん(この方は以前、大阪天滿の藥屋の主人で、その家號をハラ〳〵屋と申しましたところから、通稱ハラ〳〵屋の呂太夫といはれてゐました)、攝津大掾さん、 |
| p277 L5 | 致してをりますが、特にその次ぎの玉手が門口へ | p211 L-2 | 。致してをります。/ かういふところも語る太夫によつて、足どり、音遣ひがそれ〴〵に違つてまゐりますが、私は「しんたるウウウー(ツン)ウウー(テン)夜の(ツツン)道」といつた風の語り方をいたしてをります。即ち、しんたるウウウーでツンと彈かせて一度納つてから、また改めて「る」の語尾をウウーと續けて(テン)夜の(ツツン)道……となるのですが、この足どりと音遣ひで夜の更けたうら淋しい感じを出してゐるつもりでございます。そして、この一句がいはゞこの場の叙景で、次ぎの「戀の道には暗からねども」からは玉手自身の描寫に移つてゐますので、こゝでちよつと氣分を變へてから「戀の道には暗からねども」と改めて續けることにいたしてをります。このあたりも先代の大隅太夫さんの音遣ひが如何にも、そんな情景と人物とをよく表現[あらは]してゐられて、結構なものでございました。/ さらにその次ぎの玉手が門口へ |
| p277 L6 | やり取りに最も骨を折ります。即ち合邦の | p212 L9 | やり取りもなか〳〵大事なところでございます。即ち合邦の |
| p277 L-1 | なりません。先代大隅太夫さんの | p212 L-1 | なりません。同じく先代大隅太夫さんの |
| p287 L-2 | --玉手御前の仕どころは、俊德丸にかゝるサハリの所で肚に愁ひてゐて、表面で十分に色氣を見せるといふのが性根です。奥へ行くほど段々むつかしくなつて行くやうに思はれます。また「道も法も聞く耳持たぬ」と強くいつて、すぐ續きの「もうこの上は俊德樣」を色氣でいふといつたやうに、こんなところが幾つもあります。(故中村歌右衞門藝談)=雜誌「歌舞伎」第百十七號所載 | p220 L2 = L3 | |
| p288 L7 | 呼聲かなんどのやうに口先ばかりで語る方も | p220 L6 | 呼聲かなんどのやうに語る方も |
| p295 L8 | をやまカシラの一つの特長は | p225 L6 | をやまカシラの特長は |
| p297 L9 | カシラ「正宗」に就て このカシラは「合邦辻」の合邦「朝顔日記」の亭主德右衞門「鮓屋」の彌左衞門などに用ひられる老役カシラの一種で、少し時代がゝつてゐるところ、以前は武士出身といつた役柄に嵌まる。表情は溫和で律義者らしい性格を示し、動きは眉が下り、口が開閉する。名稱の起源は寛保元年竹本座初演の「新薄雪物語」の五郎正宗だといふ。現在文樂座で用ひられてゐるのは初代玉造舊藏の名作と、他に一個、合計二個ある。因に文樂座のカシラは各種を通じて、一種類につき原則として同じもの二個以上用意されてゐる。これは通し狂言などの場合、同じ人物でも、その登場する場面によつてその遣ふ人形遣ひも變つて來る場合があるから、同じもの二個乃至二個以上の用意を必要とするからである。 | p226 L-1 = p227 L1 | 《p265 L-4》 |
| p303 L4 | 今日の演出法 今日では文樂も歌舞伎もともに | p230 L8 | 今日では文樂も歌舞伎もともに |
| p303 L9 | 通し狂言として屢演されたものだが、現四ツ橋へ移轉後の「白石噺」は前述の通り七段目、又は六七段のみの上演に定型づけられてしまつた形である。 | p230 L12 | 通し狂言として屢演されてゐたものである。 |
| p303 L-4 | 登場人物名も廣い範圍に亘つて大阪向きに | p230 L-3 | 登場人物名も大阪向きに |
| p310 L7 | 言葉の工夫を喧ましく申します。 | p236 L2 | 言葉の工夫を第一にいたします。 |
| p316 L9 | 暖簾で涙を拭ふ仕草を見せた。 | p240 L-4 | 暖簾を手に持つて涙を拭く説明的な仕草を見せた。 |
| p316 L8 | 先年、文樂座の本興行で古靱太夫の「揚屋」が | p240 L-5 | 先年、文樂座の本興行で古靱太夫(今日の山城少掾)の「揚屋」が |
| p316 L-3 | 直ちにその非を悟つてか、この仕草を速刻改めたことがあつた。(著者註) | p240 L-3 | 直ちにこの仕事を改めたことがあつた。これも床本の詞章と人形の動作との關聯に一つの鑑賞上の示唆を與へるものと思ふ。(著者) |
| p319 L-1 = p320 | | p242 L-2 | 三味線の掛け聲 三味線彈きが太夫の語り口の間[ま]や三味線の間[ま]を取るために、ウン、オツ、オーツ、ハツ、ハーツ、ヨツといつた掛聲を入れることは比較的近年からのことで、昔は殆ど用ひなかつた。例へば名人團平と並稱された明治期の五代目豐澤廣助などはどんな場合でも掛聲らしい掛聲をやらなかつたといはれてゐる。蓋し五代目の野澤吉兵衞のやうな美聲家の三味線彈きの高い調子の掛聲が次第に一般に流布して來たのでないかとも考へられる。/ 例へば「朝顔」の大井川での「石になつたる松浦潟」のあとへオーツと大きく掛聲を入れて「テテンひれふる山の悲しみも」と出るところ、同じく「太功記」の尼崎で「引つそぎ竹の猪突き槍」のあとへオーツと入れて「テテン主を殺した天罰の」と出るところ、或は大笑ひで「ウ……フ、ア……ハ」を繰返し、最後にウンと掛聲してから「アハハハ……」と笑ひ落すところなど、すべてかうした掛聲によつて、太夫はその一瞬にイキが盗めるので語り易いものである。いひ換へると、掛聲によつて三味線彈きが太夫の高い調子を誘導して出し易くしてやる効果はあるものだが、このため、すなはちオーツとかウンとかの掛聲の間に太夫がイキを盗むから、全體としての語り口のイキが抜けてしまふ。また三味線彈き自身も掛聲をかけると、彈きよくなるもので、非力の三味線彈きほど掛聲を多く入れたがるが、結局、これもイキが抜けて、義太夫節としての氣力の充實感を失つてしまふ。で、掛聲は出來得る限り用ひないのが好ましい。今日の義太夫に如何に無駄な掛聲が多いかは放送を通じて聞いた場合、一番それがよくわかる。 |
| p324 L8 | お光の婦道觀 お染と久松の戀愛葛籐を主軸に、 | p247 L-1 | お染と久松の戀愛葛籐を主軸に、 |
| p324 L-3 | 當然の覘ひどころだが、それがお光の意外な切髪姿によつて悲劇的容貌に急轉し、結局この一幕はお染と久松の戀愛に發足しながら、むしろお光の女性悲劇への強調が主題へ乘り出した形で終幕する。/ お光の意外な切髪姿の點出は | p248 L3 | 當然の覘ひどころだが、お光の意外な切髪姿の點出は |
| p325 L2 | 心理的必然性は發見し得ないが、このお光が煩惱の絆を斷ち切つて、お染と久松の幸福を希ふ一種の強烈な自己犠牲の精神は、日本婦道に見る崇高な理念の代辯として、觀客に共感と敎化の二重効果を賦與するものであらう。/ 今日の演出法 最近では文樂でも歌舞伎でも、 | p248 L4 | 心理的必然性は發見し得ない。なほ最近では文樂でも歌舞伎でも、 |
| p325 L7 | 遺憾である。大正期の御靈文樂時代までは座摩社の段、野崎村の段、油屋の段が常に併演されてゐたものである。但し最近の記録では昭和十三年の五月興行で「座摩社」の段(現住太夫)と「油屋」の段(古靱太夫)とを合せて珍らしく昔どほり復活上演されたことがある。 | p248 L6 | 遺憾である。 |
| p333 L9 | お染がダンスでもせねばなりますまい。全く猿芝居のお染さんです。大家の娘としての氣品も | p254 L-3 | お染がダンスでもやり出します。全く猿芝居のお染さんです。大家の娘らしい氣品も |
| p341 L5 | この老婆が難物中の難物で | p260 L-3 | この老婆が難物で |
| p343 L-2 | 老人の笑ひといふ特殊な點で | p262 L10 | 老人の笑ひといふ變つた表現で |
| p345 L-1 = p346 L1 | | p264 L5 | 註--「嬉しかつたはたつた半時」は愚痴らしくなく、ほかの者からは哀れに思はるゝやうにいふべし、「ハイ〳〵お前も」の重ね返事、誰も大事にせず捨ゼリフの如く心得たるは情けなし「ハイ〳〵」の中に有難しとも忝けなしとも言葉にいはれぬ親の恩に感じたる心なければならず。(岡鬼太郎著「義太夫秘訣」) |
| p297 L9 | 《「8. お福」の項の次》 | p265 L-4 | カシラ「正宗」に就て このカシラは「合邦辻」の合邦「朝顔日記」の亭主德右衞門「鮓屋」の彌左衞門などに用ひられる老役カシラの一種で、少し時代がゝつてゐるところ、以前は武士出身といつた役柄に嵌まる。表情は溫和で律義者らしい性格を示し、動きは眉が下り、口が開閉する。名稱の起源は寛保元年竹本座初演の「新薄雪物語」の五郎正宗だといふ。 |
| p353 L-4 | と論究する。まことに適評といふべきである。例へば近松の | p270 L-1 | と論究してゐる。例へば近松の |
| p354 L6 | 今日の演出法 六段目の「沼津」と八段目の「岡崎」が作品的價値において、今日最も屢演されてゐる。通し狂言として上演される場合は三段目の「圓覺寺」に限つて「伊賀越乘掛合羽」のはうの「圓覺寺」の段が上演される場合が多い。九段目の「伏見の段」と十段目「敵討の段」とは近世殆ど上演を見てゐない。松島時代の文樂座で五代目竹本彌太夫がこの場を語つたといふ記録以外、恐らくその後上演の跡を絶つてゐよう。即ち通し狂言としての上演においても、この八段目「岡崎の段」が最終幕になるのが普通である。/ なほ、五段目「郡山の段」は俗に「饅頭娘」と稱され、故中村雁治郎はじめ上方歌舞伎では屢々上演を見る場面である。 | p271 L5 = p272 L1 | |
| p357 L3 | そして驛鈴入りの道中唄を賑やかに聞かせてから「東路に、 | p273 L10 | そしてカゲの囃子で驛鈴入りの道中唄を賑やかに聞かせてから床の「東路に、 |
| p358 L7 | 〝三下り〟でございますが、この語り口も平作の如何にも | p274 L10 | 三下りでございますが、このあたりの三味線は丁間[てうま]と半間と交互に彈き分けて、よろけたり立ち直つたり、平作の如何にも |
| p358 L-3 | 實は本當のものでないわけでございます。勿論、かうした藝の極致は並々の太夫では到底望みだも出來ぬことですが・・・・。 | p274 L-2 | 實は本當のものでないわけでございます。 |
| p360 L-1 | 京都に存在してゐた初代豐澤廣左衞門が | p276 L6 | 京都にをられました初代豐澤廣左衞門が |
| p362 L8 | 心にかゝる夫の病氣」でお米が印籠を盗まうとする。それが知れて親娘の愁嘆となり、「問はれて | p277 L10 | 心にかゝる夫の病氣、わが手で介抱することも、浮世の義理にへだてられ、秋の螢の消えのこる、佛壇の燈も細々と、嵐にふつと氣のつく娘」でお米が印籠を盗まうとするのですが、このあたりは如何にも淋しい秋の氣分の手がついてをりますから、しんみりとした三味線を聞かすべきところでございます。/ さて、それが見つかつて、「思はず高聲、何者と、裾を捕へて引き止むれば、わつと泣き入る娘の聲、平作もびつくりし……」となりますが、こゝで「娘ぢやないか、われア、手に印籠を持つて」と原文にない入れ言葉をするのが普通になつてをりますが、これは人形のない素淨瑠璃の場合は、かうでも入れ言葉を加へないと、この場の樣子が少しわかり難いから生まれたものでせうが、人形のある文樂では勿論、かうした入れ言葉はせぬがよく、入れ言葉をせずに、その樣子が十分わかるやうに聞かせ得たら、それは更らによろしい。/ 續いて平作とお米との愁嘆となり、「問はれて |
| p362 L-2 | この場ぎり」と續いてお米のサハリに移りますが、このサハリは場面が淋しい | p278 L8 | この場ぎり」とお米のクドキに移りますが、このあたりは場面が淋しい |
| p363 L1 | 女なのですから、サハリといつても、派手な節廻しを | p278 L9 | 女なのですから、派手な節廻しを |
| p363 L3 | なほ、このサハリの「我が身の | p278 L-4 | なほ、こゝの「我が身の |
| p363 L5 = L6 | | p278 L-1 | それから、この少し前の「その場に立合ひ手疵を負ひ、一たん本復あつたれど、このごろは頻りに痛み……」が、また以前に御説明申上げました「カカリ」で「その場に立合ひ手疵を負ひ」までが言葉、そして「このごろは頻りに痛み……」からが地合[ぢあひ](地[ぢ]の文の節)になつてをります。/ また、この少しあとの「戀の意氣地に身を碎くウウウ、心ぞ思ひ(チンチンチン)やられたり」がこれも「十種香」の時、おはなし申上げました「サハリ落ち」でございます。 |
| p364 L2 | このサハリが濟むと、 | p279 L-3 | このお米の件[くだ]りが濟むと、 |
| p364 L3 | お米を近く寄せ、いろ〳〵と原作にない | p279 L-2 | お米を近く寄せ、この件りでもまたいろ〳〵と原作にない |
| p364 L4 | 最近では古靱さんだけが、この入れ言葉なしの原作本位です。續いて「最早や夜明けに。 | p279 L-1 | 最近では山城少掾さんだけが、この入れ言葉なしの原作本位でございます。なほ「かねての願ひに書付けも、この内にくはしうござる」の「くはしう」に特に力を入れて意味を持たせ、重兵衞の口に出していへない胸の奥の氣持をそれとなく表はし、直ぐ氣を變へ「ござる」で、我に返つてガラリとくだけた調子になります。續いて「最早や夜明けに |
| p364 L-1 | 吐く息の念佛 | p280 L8 | 「おさらば」の語り口 |
| p365 L6 | 面白いものになります。 | p281 L1 | 面白いものになります。或はこゝはうまく語られても、その直ぐ次ぎの「唯今のお金を戻しに參じました」で、もう以前の苦しい息づかひを忘れて、平氣にしやべつてゐるやうな平作を語る太夫を見受けますが、これではまた何もなりません。 |
| p365 L-3 | 有處[ありか](即ち股五郎)を訊ねますが、 | p281 L7 | 有處[ありか](即ち股五郎の行方)を訊ねますが、 |
| p366 L3 | こゝの「旦那樣、おさらば」は | p281 L11 | こゝの 「さう聞きましては、申やうもござりませぬ、さやうなら歸りましよ」は如何にも精を落した風に申しますが、次ぎの「旦那樣、おさらば」は |
| p366 L4 | 即ち、この一と言[こと]は小さく霞めて申しますが、 | p281 L-1 | すなはち、この一と言[こと]はグツと押へて小さく申しますが、 |
| p367 L8 | 吐く息の『南無阿彌陀佛』 | p282 L-1 | 「吐く息の」南無阿彌陀佛 |
| p367 L9 | 逢ひ納め」の一句は大落しではありませんが、この一段中での最高のヤマとして、 | p283 L1 | 逢ひ納め」の一句のあとにチチチン、チチチンといふ非常に力強い叩き撥[ばち]を入れますが、これはこの場の平作のやうな今にも息を引きとる手負ひの表現としては、どうも強すぎて相應しくありません。だから、これはこの一段における「大落し」のつもりで節づけされたものだと解釋する一説があります。と申しますのは、不思議なことにこの「伊賀越」全段のうちに「大落し」の手が一ケ所もありません。それで、これが「大落し」のかはりになる節付けだといふわけなのでございます。/ いづれにしても、この一句はこの一段中での最高のヤマとして、 |
| p368 L2 | たゞ吐く息ばかりで發音するといふのが | p283 L-3 | たゞ吐く息ばかりで「なむあみ……なむあみ」と發音するといふのが |
| p368 L-2 | 「上方」の編輯者南木芳太郎氏 | p284 L1 | 「上方」の編輯者故南木芳太郎氏 |
| p369 L1 | 『私の沼津』 故四世竹本津太夫氏藝談 | p284 L4 | 『私の沼津』 故三世竹本津太夫氏藝談 |
| p374 L1 | そしてその他の一端が前述の通り人形の | p288 L4 | そしてその他の一端が人形の |
| p374 L-2 | 目障りな〝突き上げ〟だが、 | p288 L-3 | 目障りな竹一本の「突き上げ」だが、 |
| p376 L2 | 豐竹古靱太夫 | p289 L2 | 豐竹山城少掾 |
| p376 L3 | 苦しい語りもの/ 御靈の文樂座が全燒したのが大正十五年で、それから昭和五年に現在の四ツ橋文樂座が新築されるまで永らくの間、道頓堀の辨天座で引越興行をやつてゐましたが、私の「岡崎」の初演はこの辨天座時代の昭和三年二月でした。その後、文樂座では前後四回上演してをります。最近は本年(昭和十八年)の五月興行でございました。/ この「岡崎」では | p289 L3 | 苦しい語りもの/この「岡崎」では |
| p380 L3 | 喧しくいはれるところです。それだけに、この件りさへ十分に語り生かすことが出來れば、既にこの一段は成功したとさへいつていゝでせう。 | p291 L-1 | 喧しくいはれるところです。 |
| p380 L9 | 遠寺の鐘の余情を表現する方もありますが、私は「遠山アアア寺」と「山」のウミ字で鐘の音が雪の夜の靜寂に消え行く感じを | p292 L3 | 遠寺の鐘の餘韻を表現する方もありますが、私は「遠山アアア寺」と「山」のウミ字で凍てるやうな鐘の音が雪の夜の靜寂に消えて行く感じを |
| p381 L8 | 言葉遣ひの技巧で、音樂的に描寫しようとする淨瑠璃音曲獨自の描法でございます。 | p292 L-2 | 言葉遣ひの技巧で表はさうとする淨瑠璃音曲獨自の手法でございます。 |
| p382 L5 | 行きずりの旅人に僞装してゐるわけですが | p293 L6 | 行きずりの旅人に身をやつしてゐるわけですが |
| p386 L-1 | 先年古靱太夫の床で故玉造が | p296 L-4 | 先年古靱太夫(現山城少掾)の床で故玉造が |
| p387 L9 | ツメを大事に扱うふ | p297 L5 | 夜廻り親爺の語り方 |
| p387 L-1 | と申します。このあたりから第二段のお谷の | p297 L8 | と申しまして、いよ〳〵政右衞門の煙草切りに移り、このあたりから第二段のお谷の |
| p388 L4 | 調子になつては、この一言の面白味は | p297 L-3 | 調子になつては、この場の情景としての面白味は |
| p388 L5 | 先代大隅さんでさへ「どうも、この一言だけはこの一言だけは巧くやれない」と | p297 L-2 | 先代大隅さんでさへ「どないしても、この一言だけはこの一言だけは巧くやれん」と |
| p388 L-2 | 迫つて來るからです。 | p298 L4 | 迫つて來るからでございます。「雪の蒲團に、添乳の枕、いんのこ〳〵〳〵に、友誘ふ犬の聲々、夜まはりの番が見つける小提灯、ヤイ〳〵軒下に何んで寐るのぢや、きり〳〵、往け」と、最初は無慈悲に叱りつけてゐますが、お谷の樣子を見るにつけ、次第に可哀さうになつて來て、しまひには「どこぞ後生なところを賴んで、泊めて貰はつしやれ……」とやさしくいつてやる調子の變りかた。さらに「あつたら物を見のがすこと」と心を殘して、雪の中をとぼ〳〵と歸つて行く樣子、その「つぶやき歸るも賴みなき」の「つぶやき」をいかにも口の中でブツ〳〵いつてゐるやうに語る。すべて、この夜まはりを生きてゐるやうに聞かせるところに、なみ〳〵ならぬ太夫の苦心が秘んでをります。 |
| p389 L1 | 昔から義太夫では、ちよつと出て來る | p298 L-1 | 度々申しますとほり、昔から義太夫では、ちよつと出て來る |
| p390 L8 | 哀愁を十分表現するやう苦心致します。 | p300 L1 | 哀愁を十分表現すべきところでございます。/ 試みに、こゝを口三味線で申しますと「外は(ツツン)音せで降る雪に(ト、チンチチン、ト、チンチチン、ツンツンツン)無慘や肌も(テン)こほオーリ山アの(ト、チンチチン、チチチンツン)國に、殘りし(ツツン)女房のオオ……」となりますが、このあたりの情景を現はす音づかひと足どり、それに三味線の淋しい雪の夜の音色は、この一段中最も苦心いたします。/ 續いて、お谷が「今宵一夜さ、お庭の端に」と賴むので、老婆が可哀さうにと家へ入れてやらうとするのを、政右衛門が「戸を明けずとぼいいなせたがよござります」と心にもない無情な言葉で止めるので「宿はずれの、森の中へ(チン)往て寝やしやれ」と(音[おん]を遣うて)斷はる。そして糸車を出して糸を紡むぎ始めるのですが、こゝの「やはらかにいうて引出す糸車」のあとに三味線が糸車のブルン〳〵といふ音を利かせまして「來いとゆたとて……」の糸繰り唄になります。 |
| p390 L-2 | 「岡崎」だとさへいはれてゐる程です。靜かな雪の夜の情景がシンミリと描寫されねばなりません。 | p301 L1 | 「岡崎」だとさへいはれてゐます。それは靜かな雪の夜の情景がシンミリと描寫されると、自然に眠たくなつて來る道理だからでございます。 |
| p390 L1 | それに加へて、子をヒシと | p301 L3 | 「雪のまゝ着せて」の語り方/ それに加へて、子をヒシと |
| p391 L-2 | 足立たず」のあたりは、必ずお客樣に受けるところで、いゝ節もついてゐますし、人形も足拍子を入れて派手に遣ひますが、こゝでお客樣から拍手を頂くと、却つて語り込んで來た舞臺の空氣が亂されますので、私はむしろ出來るだけ節廻しを引締めて、逆にお客樣に手を拍かせない工夫を致してをります。 | p301 L-2 | 足立たず」のあたりは、また、太夫の腹が裂けるほど力の要るむつかしいところでございます。すなはち、「一丁南の辻堂まで、這うてなりとも行つてくれ、吉左右を知らすまで、必らず死ぬるな」は政右衛門夫婦の切端つまつたドタン場で「必らず死ぬるな」はお谷に力づけるやう、言葉をつめて出來るだけ強く締めて申します。そして、「この年月の悲しさと、嬉しさ昂じて足立たず」から「杖を力に立ち兼ねる、とやせんかたへに脱ぎ捨てし、薦に積りし雪のまゝ、着せて、人目を暗き夜を」となつて、お谷が下手へ這入ることになりますが、こゝは「薦に積りし雪のまゝ、着せエー(チンテンテン)エエエー(チンテンテン)エエ(チンテン)エエエエエエー(トントントントトン)てエエー」となり、正に太夫と三味線と四つに取組むべき力一杯のところで、その合の手の(チンテンテン)で太夫がお谷のハーハー苦しい息づかひを聞かせますが、節づけとしてもまた、實によく出來てゐる面白いところでございます。 |
| p393 L2 | 幸兵衞が庄屋から | p303 L7 | これに引續いて、幸兵衞が庄屋から |
| p395 L3 | --舞臺技巧を本位とする近松半二の諸作品は全く上乘のレヴュー劇である。彼が最後の名作「伊賀越道中雙六」も郡山、沼津、岡崎、伏見、上野と道中双六の興味をお芝居風に活用してゐる。饅頭娘、奉書仕合、沼津なども人形よりもむしろ俳優向きであり、特に岡崎の段切で「まだお手の内は狂ひませぬな、ハヽヽヽやがて吉左右々々々と笑うて」幕などに至つては全く歌舞伎芝居である。(木谷蓬吟氏著「淨瑠璃硏究書」) | p304 L-2 = L-1 | |
| p402 L1 | その初演年月にも作者にも確説のないのは | p310 L1 | その初演年月にも確説のないのは |
| p404 L7 | お俊の貞節 全篇を通じては、勿論中の巻の「堀川の段」のみが、われらの鑑賞に堪ヘ得るものだが、然も、この段は多くの世話物中、その簡明な構成と猿廻しの機智と、そして肉親の眞情を吐露した名文とによつて、十分傑作の一つに數へてよからう。特にお俊の「大事の〳〵夫の難儀、命の際に振り拾てゝ女の道が立つものか」以下の述懷は遊女といふ特殊な境遇を離れて、作者はこゝで嚴肅な日本婦道の一庭訓を述べようとしてゐるかのやうである。 | p311 L-2 = L-1 | |
| p404 L-2 | 今日の演出法 いふまでもなく今日では中の卷 | p311 L-1 | いふまでもなく今日では中の卷 |
| p406 L2 | 豐竹古靱太夫 | p313 L2 | 豐竹山城少掾 |
| p406 L7 | 派手なばかりの語り物でない。普通に聲の美しい太夫が無闇と繊細な語り口で綺麗事にやるもののやうに考へられてゐますが、冒頭[まくら]の一句に | p313 L7 | 派手なばかりの語り物でない。冒頭[まくら]の一句に |
| p407 L3 | 與次郎一家の哀れな生活悲劇なのですから、 | p313 L-2 | 與次郎一家の哀れな暮し向きなのですから、 |
| p407 L-1 | この一段の本當の精神が籠つてゐるもの | p314 L7 | この一段の本領が籠つてゐるもの |
| p409 L-3 | 却つて古靱の堀川は文句を抜いて | p315 L-4 | 却つて山城の堀川は文句を抜いて |
| p413 L4 | この「堀川」一段を通じての基本的な課題でございませう。 | p316 L5 | この「堀川」一段を通じての大事なメドでございませう。 |
| p417 L8 | サハリの意義 | p321 L7 | 半太夫のサハリ |
| p419 L-1 | 即ち義太夫以外の他の音曲の節調に觸[さ]はつてゐるところ、眞似てゐる | p323 L4 | すなはち、義太夫以外の他の音曲、例へばこの半太夫節とか一中[ちう]節とか宮園節とかの節調に觸[さ]はつてゐるところ、それを眞似てゐる |
| p420 L2 | 御記憶して頂きたう存じます。 | p323 L7 | 御記憶して頂きたう存じます。だからサハリとは極く短い一口の章句で、決して長い文句であるべきはずがありません。今日サハリと呼ばれてゐる個所は多くの場合、クドキ(述懷)と呼ぶはうが、むしろ正しからうと思はれます。 |
| p421 L-2 | ないじやくり」まで續けて | p325 L1 | ないじやくり」まで一息に續けて |
| p424 L2 | 派手に唄つてしまつては | p326 L10 | 派手に節を振りまはして唄つてしまつては |
| p424 L4 | 搏つやうでなくてはなりません。 | p326 L-3 | 搏つやうでなくてはなりません。私もこのあたりはトントンと足どりを早くして、技巧でなく氣分ばかりで語つてをります。 |
| p425 L4 | この老婆の述懷は沁々と哀れ深く扱つてをります。近世では先代大隅さんの | p327 L9 | この老婆の述懷はジメ〳〵とした音遣ひで、沁々と哀れ深く扱つてをりますが、どうぞ死ぬまでに一度でいゝから、この「堀川」の婆でお客のハンケチを濡らしてみたいものだと思つてゐます。/ 近世では先代大隅さんの |
| p425 L6 | 泛んで來るやうでした。 | p327 L-2 | 泛んで來るやうでした。むかし先代の大隅太夫の「野崎村」の老婆があんまりよかつたので、たづねてみましたら「俺の婆は初代の古靱太夫さんの眞以してるねん」と申されてゐましたが、如何にも長患ひしてゐるジメ〳〵した老婆に聞えてをりましたものです。 |
| p426 L5 | その後任の形で、辨天座時代の | p328 L11 | その後任として、辨天座時代の |
| p426 L9 | 本物の猿を使つたといふ記録が殘つてゐる。(著者註) | p328 L-3 | 本物の猿を使つたことがあるといふ。(著者) |
| p428 L3 | 座元松竹の紋どころの下に「太夫 豐竹古靱太夫」 | p329 L-3 | 座元松竹の紋どころの下に「太夫、豐竹山城少掾」 |
| p428 L5 | 當る個所に欅の一枚板で「太夫 豐竹古靱太夫」と、 | p329 L-1 | 當る個所に欅の一枚板で「太夫 豐竹山城少掾」と、 |
| p429 L3 | 四代目津太夫を經て現在の豐竹古靱太夫に | p330 L10 | 三代目津太夫を經て現在の豐竹山城少掾に |
| p436 L1 | 今日の演出法 上演時間の制限(一回興行四時間)を受けてゐる現在の文樂座では十段目の「尼崎」以外の上演は殆ど見られなくなつてしまつた。その「尼崎」ですら最近は「端場」に當る操、初菊、久吉、十次郎らの入り込みを省略して「殘る蕾の花一つ」に始まる「切」の部分のみで濟ませる。これはちやうど現在における歌舞伎の「尼崎」の省略法とほゞ同樣である。御靈文樂時代の「繪本太功記」といへば、一日の段「饗應」二日の段「本能寺」 五日の段「高松城水攻め」六日の段「妙心寺」七日の段「孫市切腹」それにこの十日の段「尼崎」などが通し狂言として上演されてゐたものである。この一例より推すも今日における上演時間の制限は次第に人形淨瑠璃の本質を崩壊しつゝあるものといふべきである。尤も、最近の同座では晝夜二部興行を採用したため、本年(昭和十八年)十月興行には、甚だしい省略ながら一日の「饗應」二日の「本能寺」五日の「高松城水攻め」六日の「妙心寺」が通し狂言として十數年振りに復活上演されてゐる。/ 端場は夕顔棚 庭の千草に風薫る攝州尼崎の片ほとり、わが子光秀の叛逆に堪へかねた母の皐月が一人住ひ、今日しも村の百姓たちを集めて妙見講をつとめてゐろところへ光秀の妻操と十次郎の許嫁初菊とが訪ね來て、十次郎の出陣を願ふ。間もなくそこへ〝西行もどきの僧〟が宿を求めて來る。この僧こそ光秀の腹臣四王天但馬守に追ひ詰められた眞柴久吉なのである。續いて十次郎も訪ね寄つて許嫁初菊と祝言の上、出陣することになる--これまでがこの段の發端で俗に「夕顔棚」と呼ばれる「端場[はば]」である。この端場が終つて一應登場人物が全部奥へ入ると「殘る蕾の花―つ」から「切[きり]」に移る。即ち、ここで床[ゆか]の太夫が入れ變ることになるのである。 | p334 L-1 =p335 L1 | |
| p438 L2 | 豐竹古靱太夫 | p335 L2 | 豐竹山城少掾 |
| p438 L3 | 氣の張る語り物 | p335 L3 | 十次郎の風格 |
| p438 L6 | 知れ亙つてゐるものも少い。たとひ、どんなに文樂と縁の遠い方でも「これ見たまへ光秀どの」ぐらゐのクドキなら先刻御存じでせう。少し文樂に足を運んでゐられる方なら恐らくいろんな太夫のいろんな「尼崎」を聽いて耳が肥えてゐられる。それだけに語るはうも妙に氣が張つて語り難いといふわけなのです。それに、この「尼崎」が今日なほ特に人氣のある所以は、義太夫の重なる節廻しが萬遍なく採り入れられてゐるので、義太夫を稽古する初心者にとつて最も適した語りものだといふ側面の理由もございませう。 | p335 L5 | 知れ亙つてゐるものも少い。それだけに語るはうも妙に氣が張つて語り難いといふわけなのです。 |
| p439 L4 | 十次郎の風格/ 扨て、最初のマクラ | p335 L7 | 扨て、最初のマクラ |
| p439 L-2 | 如何にも可愛らしい子供々々した、どちらかといへば | p335 L-2 | 如何にも可愛らしい、どちらかといへば |
| p440 L-4 | しかし、かうは申しましても私どものやうな非力[ひりき]の太夫ではなか〳〵注文通り行つてくれません。若武者の | p336 L8 | しかし、かうは申しましてもそれがなか〳〵たやすい藝でない。若武者の |
| p440 L-3 | 語調を強くすると、十次郎が少し老けて來る。 | p336 L9 | 語調を強くすると、老けて來る。 |
| p440 L-1 | 十次郎に陷つてしまひます。 | p336 L10 | 十次郎になつてしまひます。 |
| p441 L1 | 一句で表現されてゐるか、そこに先づ耳を止めて頂くのが「尼崎」鑑賞の第一步でございませう | p336 L-4 | 一句で表現されてゐるか、「尼崎」では先づそこに耳を止めていただきたいものでございませう。 |
| p442 L7 | おわさのサハリの「死出の山」 | p337 L-2 | おわさのクドキの「死出の山」 |
| p444 L5 | 人形とかなり面白い相違を見せてゐる。 | p339 L4 | 人形と面白い對象を見せてゐる。 |
| p445 L6 | なほ不可ない。なんでもなく見えて、 | p340 L1 | なほ不可ない。いつも申しますとほり、なんでもなく見えて、 |
| p446 L1 | ところが、先代大隅太夫さんのこの個所は全くこれと行き方の違つたものでした。即ち長く引張らず | p340 L8 | ところが、彥六座系の先代大隅太夫さんのこの個所は全くこれと行き方の違つたものでした。長く引張らず |
| p446 L4 | だが、これが實に素晴しい迫力を帶びて | p340 L11 | だが、これが大變な迫力を帶びて |
| p450 L3 | 私にはこんな理窟に合はぬ語り口は | p343 L10 | 私にはこんな語り口は |
| p450 L4 | 節廻しの飾り氣を出來るだけ省いて、手短かくスラ〳〵と語り、むしろ操の悲痛さの表現に重點を置いてゐます。だが、このため時をり人形遣ひのはうからは「古靱ハン、あれでは | p343 L-4 | 節廻しの技巧を出來るだけ省いて、手短かくスラ〳〵と語り、操の悲痛な氣持の表現に重點を置いてゐます。だが、このため時をり人形遣ひのはうからは「山城ハン、あれでは |
| p450 L8 | 「古靱の淨瑠璃は理窟ぽくて陰氣でいけない」などと惡評され勝ちですが、 | p343 L-2 | 「山城の淨瑠璃は理窟ぽくて陰氣でいけない」などと評され勝ちですが、 |
| p454 L2 | 義太夫道の鐵則なのでございます。 | p346 L10 | 義太夫道の言ひ傳へなのでございます。 |
| p456 L6 | 「野崎村」の老婆にしろ「合邦辻」の老婆にしろ「堀川猿廻し」の老婆にしろ | p348 L7 | 總體に義太夫では時代物の老婆より世話物の老婆はさらにむつかしいと申されるものですが、いづれにしても「野崎村」の老婆にしろ「合邦辻」の老婆にしろ、今申しました「堀川猿廻し」の老婆にしろ |
| p456 L8 | 近ごろ私は沁々と老婆の大切さを | p348 L10 | 近ごろ私はつく〴〵と老婆の大切さを |
| p457 L1 | 同樣で、文樂らしい古風な行き方でございます。 | p348 L-1 | 同樣で、文樂はいつもこの行き方でございます。 |
| p458 L-1 | 數十萬圓の遺產を殘した。しかし、それも世にいふ守錢奴でなく、慈善事業への出資や社寺への奉納には常に應分の財を吝まなかつたと一部當時の事情通から辯護されてゐる。/ 團平が舞臺で急死した時、 | p350 L5 | 數十萬圓の遺產を殘した。團平が舞臺で急死した時、 |
| p459 L8 | 五代目廣助の養嗣子に當つてゐる。然も、この現七代目廣助氏に落ちつくまで、五代目廣助の養嗣子は前後四十五人も變つたといふには、些さか驚かされる。 | p350 L-4 | 五代目廣助の養嗣子に當る。 |
| p460 L7 | 手許に置いてゐたといふ。蓋し彼の唯一の不幸は父親以上の傑物と將來を嘱望されてゐた愛息初代玉助を夭折させたことで、この極端な守錢奴ぶりも恐らくは、かうした家庭的不幸に一つの眞因があらうか、と説かれてゐる。/ なほ、彼は人形カシラの傑作を多數所持してゐた。現在文樂で使用されてゐる名品の「文七」「金時」など、すべて嘗つては玉造の所有品だつた。時に門弟たちが | p351 L9 | 手許に置いてゐたといふ。なほ、彼は人形カシラの傑作を多數所持してゐたが、時に門弟たちが、 |
| p460 L-1 | 當時における彼の權勢ぶりと傲岸ぶりがよく知れる。現在の玉造氏はその四代目に當つてゐる。 | p351 L12 | 當時における彼の藝に對する見識とその傲岸ぶりがよく知れる。昭和二十二年春、窮乏のため自殺して果てた故玉造氏はその四代目に當つてゐる。 |
| p466 L6 | 文藻よりもむしろ節付が素晴しいからだと思はれます。 | p356 L6 | 文藻よりもむしろ節付の立派さからだと思はれます。 |
| p467 L4 | 用ひられた單なる置[おき]唄です。 | p357 L1 | 用ひられた只だの置[おき]唄です。 |
| p468 L5 | 聞かせようとした團平苦心の節附ですから、 | p357 L10 | 聞かせようとした團平師匠苦心の節附ですから、 |
| p469 L3 | 哀れな氣味合ひとを象徴してゐるのです。 | p358 L6 | 哀れな氣味合ひとを表はしてゐるのです。 |
| p469 L7 | 總じて盲人の言葉には多くの場合、疑問の調子を帶びてゐるものでございます。 | p358 L-3 | 總じて盲人は自分の眼が見えないものですから、その言葉にいつも物を人にたづねるやうな調子を帶びてゐるものでございます。 |
| p469 L-2 | この疑問を含んだ「か」の言ひ廻し一つ | p359 L1 | この物をたづねるやうな調子の「か」の言ひ廻し一つ |
| p471 L9 | 三年の間秘めに秘めた抜け詣りの貞節 | p360 L6 | 三年の間秘めた抜け詣りの貞節 |
| p471 L-1 | いひやうのない感謝の氣持で一杯になります。 | p360 L8 | いひやうのない感謝で一杯になります。 |
| p475 L7 | 手さぐりで必死に匍ひ上つて行く樣子を象徴した節附に | p353 L7 | 手さぐりで石段を必死に匍ひ上つて行く樣子を表はした節附に |
| p479 L8 | 三休橋筋安堂寺橋角で絶命 | p366 L7 | 三休橋筋安堂寺町角で絶命 |
| p479 L-3 | 「志渡寺」の段を、然も初日の | p366 L-3 | 「志渡寺」を彈きつゝ、然も初日の |
| p480 L1 | 團平に關する逸話は隨分と多い。例へば藝以外に何んの慾望も持合せなかつた彼はいつも收入の全部を玄關の屑籠ヘ捨てる。出入りの商人が無斷でそのうちから請求額を持つて歸つた、など有名な挿話だが、近ごろ些さか偶像視されて來た彼だけに、この他にも虛實取り混ぜた逸話の數々を耳にするやうになつた。/ そのうち著者が鶴澤道八氏より親しく聞いたもののうち確證し得るものとしては、清水町の自宅前を流す盲乞食の三味線を天下の妙音だと稱して毎日表座敷へ出て耳を澄ませてゐたといふ話。「伊勢音頭」十人斬りの作曲を苦吟中、山陰道巡業先の旅宿で、隣室から漏れる「長唄鏡獅子」にそのヒントを得たといふ話この「十人斬り」は「壺坂」とともに團平作曲中、特に傑作とされるもの。この曲を聞いた或る劍道師範が團平は必ず武術の心得ありと肯んじながつたといふ別の逸話も傳つてゐる。それに、雪中の箕面瀧での激しい寒稽古の話。この最後の逸話に就て、鶴澤道八氏は次のやうに語つてゐる。/ 「いつも雪が降り出すと〝オイ友松、三味線持つてついて來い〟でした。行先きは決つて箕面(大阪府豐能郡箕面村)の瀧壺でした。白皚々たる瀧壺の前へどんと坐つて、轟々たる瀧の音と競爭で夢中でヂヤン〳〵彈き廻されるのです。今思ふと、ちよつと物凄いやうな景色でした。サア、どういふ意味でしたか、ようお聞きしませんでしたが、藝道修業か、それとも何か念願があつてのことか・・・・聞いておけば何かの參考になつただらうと、今だに殘念です。」因に、この道八氏の直話は映畫「浪花女」において先代大隅太夫が海邊の波浪に向つて聲の鍛錬を行ふ場面として取材されてゐた | p366 L-1 = p367 L1 | |
| p481 L1 = | | p367 L1 | あとがき/ 本著の初版は戰時中の昭和十九年一月、畝傍書房より刊行されたものである。/ その後、久しく絶版になつてゐたところ、今回、雪月花書房の需めに應じて、版を新らたに再刊することとした。/ 版を新らたにするに當り、内容に多少の追加と改訂を加へ、能ふかぎり初版の缺を補つたつもりだが、然もなほ今日の不自由な用紙事情のため、心ならずも部分的な削除を敢へてした個所も少しとせない。記して讀者の諒恕を待つ次第である。/ かつて、本著初版の起稿に際し、多大の示敎を賜つた初代鶴澤道八氏はじめ初代吉田榮三、四世吉田玉造、五世桐竹門造の諸氏、いま既に逝し。謹んでその靈前に再刊の欣びを報告する。/ 昭和戊子盛夏 著者 |