
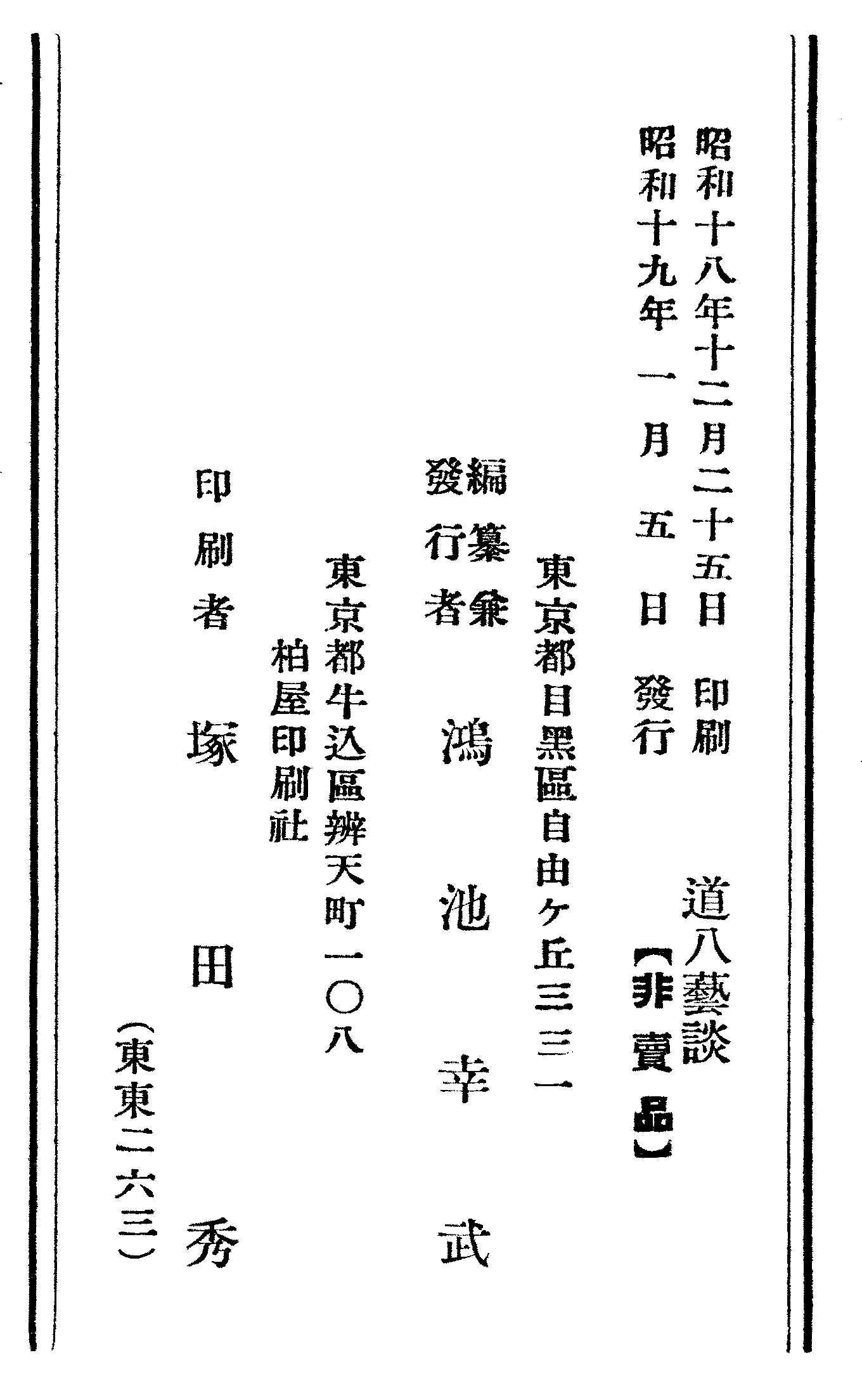

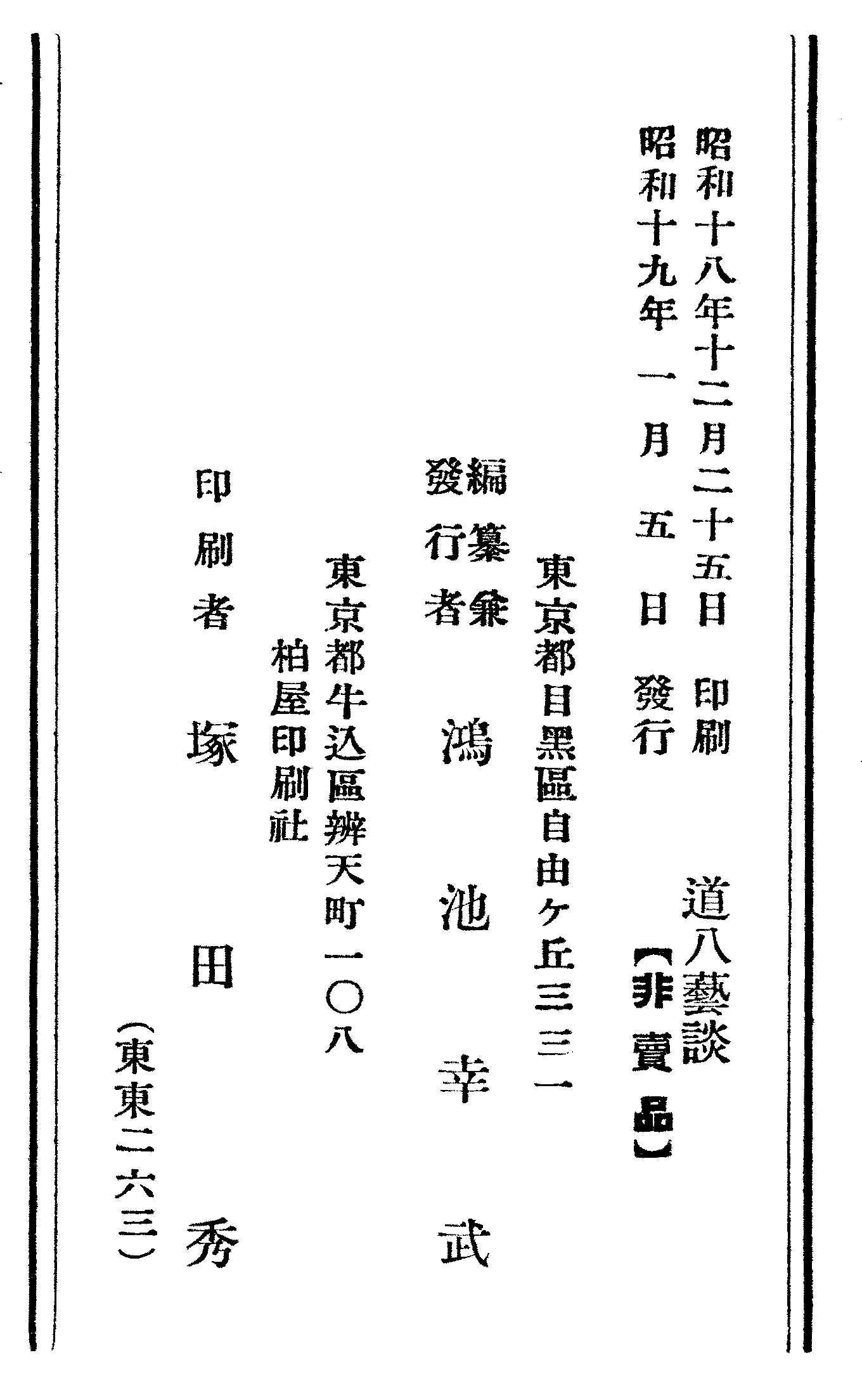
原本は正字体、ルビなしです。
[○]:誤字、[+○]:脱字、[○-]:衍字
ぺりかん社版を参照しました。
鶴沢道八著
鴻池幸武編
序
老生の日頃から別懇にする友人鴻池幸武君は常に熱心に徹底的に人形浄瑠璃に関する総ての事を深く研究して居らるのである。而してその研究の方法が大局を掴むと共に一面また微に入り細に及びあらゆる角度から観察して鋭利で正当なる判断を下して居らる点は老生の敬服するところである。嘗て人形遣の名人吉田栄三師に関する「吉田栄三自伝」を編述刊行し斯道に貢献せられたが今回更らに「道八芸談」を著わしこれを公にさるゝにつき序文を老生に需められたのである。
元来老生は人形浄瑠璃を頗る愛好する者であるが半以上は自身の趣味に駆られ大に嬉しく面白くこれを観且つ聴き稀には多少の批評を試むの場合もないではないが先づそれよりも兎も角愉快に観て聴いてそれで心から満足して居るが鴻池君のは決してさにあらずしてすべて真面目に専門の態度で組織的に研究されるのである。従つて老生は約五十年近くも人形浄瑠璃を賞翫し以て唯一の楽しみと致して居るが年若き鴻池君から折々全く思ひも寄らぬ驚くべき斯道に関する有益なる高見を承り成る程そうかなと思ふことが屡々ある。老生はたゞ年の功で故人摂津大椽[掾]や又団平師の至芸を幸にして知つて居て時々あの折はこうであつたとか又あ[+あ]であつたとかの通を鴻池君に申すのであるが尽[蓋]し此の通たるやたゞ年齢の累積に基く一の誇りに過ぎざるのであつて鴻池君は大椽[掾]や団平師を知らずといへども老生に比すると斯道の大通であり先覚者であることは断言して憚からぬのである。此の「道八芸談」も全く大通の結晶に依る産物で老成の大家道八師の最も尊むべき至芸の極致談を直接に同師より聞いて記述されたので此の書の内容が豊富で且つ趣味津々たると共に斯道研究者の為めにも亦た有益なることを推奨するのである。
そこで此の次には是非とも鴻池君が現今の文楽座の櫓下で斯界の第一人者たる太夫古靱師の芸道に関する詳細なる著述の編纂を企てられその完成の刊行の一日も早きを切望してやまぬのである。なほこれが完遂の暁に於ては即ち人形三味線及太夫の最も権威ある人々に関する代表的の著述が成し遂げらるゝ次第でまたこれは鴻池君に最も適応した事業と確信するのである。
序文を書けよとの懇請に依り率直に以上の所感をもつてその責を果したのである。
昭和十八年仲秋
伯爵柳原義光
はしがき
昭和三年の晩春、亡父が大阪瓦屋橋の別荘に躑躅の宴を儲け、その余興として大隅太夫を招き「寺小屋」を語らせた。そのときの合三味線が道八丈で、このときが道八丈と私の個人関係の始めである。
その後私が人形浄瑠璃史を研究し、清水町団平の斯道に於ける絶対的地位を識るに及び、団平師に規しく薫陶を受けた道八丈との交際が密になり、団平師の思ひ出話をはじめとして、彦六座当時の懐旧談、それに関して斯道の現状を歎き合つたことは、こゝ十数年間幾度あつたか知れぬ。
その時の話を綴り、年代を調べて纏め上げたのがこの冊子である。
茲に道八芸談のはしがきを草する序に一言加へたいのは、近年諸芸名人の芸談の刊行が多く、これが衆人より貴重なる文献として讃美せられてゐることは実に欣ぶ可きことであるが、時折語り手の芸よりその芸談の方に重きを置く気風が見受けられるのは誠に遺憾に堪えぬことである。かりに芸より芸談の方が面白い芸人があればそれは名人でも何でもなく、唯話上手といふだけである。尤も名人の芸談の中には幾多の味ふ可き語があるが、それらはその語り手にのみよつて実地の芸と結びつけられてゐるものであつて、そこが芸談の値打である。言葉を換へれば実際の芸が出来てゐるものが語つた芸談でなければ三文の値打もないのである。従つて第三者にとつて芸談は、語り手の芸を具体的に理解する手蔓でなくてはならぬ。而して名人に於てはその芸の極く根本的な心構への抽象的なことか、又はその人としては極めて末梢的な技巧かゞ芸談として語られるのみであつて、その芸の全てはとても語られないのが常である。これは私が道八丈やその他数名の名人との対談によつて知つたことである。
そこでこの冊子の読者は、各自の御勝手ではあるが、道八丈の芸談を読まれると共に、それ以上に丈の芸を鑑賞されたいのである。
昭和癸未孟冬
鴻池幸武
道八芸談 目次
| 1 | 団平師匠の御教訓 | 3 |
| 2 | 団平師匠の芸 | 3 |
| 3 | 清水町の師匠の三味線 | 8 |
| 4 | 足取 | 12 |
| 5 | 撥 | 13 |
| 6 | 指遣ひ | 16 |
| 7 | 具合 | 17 |
| 8 | 間拍子 | 18 |
| 9 | 清水町の師匠の義太夫節 | 21 |
| 10 | 清水町の師匠の日常 | 28 |
| 11 | 清水町師匠の節付 | 31 |
| 12 | 団平師匠の「朱章」 | 37 |
| 13 | 千賀女離縁話 | 39 |
| 14 | 清水町の師匠の御最後 | 41 |
| 15 | 清六さんと清水町の師匠の「質店」 | 48 |
| 16 | 清水町の師匠と検校 | 50 |
| 17 | 「壷阪寺の段」 | 53 |
| 18 | 「伊勢音頭油屋の段」 | 68 |
| 19 | 「阿古屋琴責」のこと | 80 |
| 20 | 「源平布引滝四段目」のこと | 85 |
| 21 | 二上りの中将姫 | 87 |
| 22 | 名人の芸談 | 89 |
| 23 | 私の生立ち | 92 |
| 24 | 二代目鶴沢吉左衛門さん | 94 |
| 25 | 明治初年の大阪風景 | 97 |
| 26 | 素人義太夫のこと | 100 |
| 27 | 二代目鶴沢勝七師へ入門と松島文楽座時代 | 103 |
| 28 | 長登太夫(四代目)さんを弾く | 109 |
| 29 | 土佐江戸昇切腹事件 | 111 |
| 30 | 各先師の通称と住所 | 115 |
| 31 | 初代鶴沢勝七さん | 117 |
| 32 | 四代目住太夫さんのこと | 121 |
| 33 | 勝七師匠のこと | 125 |
| 34 | 初代豊沢新左衛門さん | 130 |
| 35 | 明治中期の三羽鳥 | 135 |
| 36 | 富司太夫(三代目)さんの声 | 137 |
| 37 | 初代柳適太夫さん | 140 |
| 38 | 中野源松さん | 144 |
| 39 | 東京猿若町文楽座柿葺落しに上京の事 | 146 |
| 40 | 手打事件 | 146 |
| 41 | 住太夫の名跡について | 150 |
| 42 | 二つの元服 | 151 |
| 43 | 私の役 | 151 |
| 44 | 円朝さんの人情噺 | 152 |
| 45 | 寄席巡り | 152 |
| 46 | 数々の思ひ出 | 153 |
| 47 | 彦六座の事 | 156 |
| 48 | 芸所名古屋 | 160 |
| 49 | 昔の勉強 | 163 |
| 50 | 清水町の師匠に教を乞ふ | 170 |
| 51 | 清水町の師匠のお稽古 | 177 |
| 52 | 清水町の師匠の連弾 | 178 |
| 53 | 長崎での清水町の師匠の病気 | 181 |
| 54 | 東京東海道四国巡業のこと | 185 |
| 55 | 清水町の師匠の代役 | 191 |
| 56 | 天聴義太夫の御計画 | 193 |
| 57 | 五代目菊五郎と私 | 195 |
| 58 | 明治座の義太夫常盤津合同興行のこと | 201 |
| 59 | 「寿式三番叟」 | 203 |
| 60 | 後藤伯爵御親子のこと | 205 |
| 61 | 杉山其日庵先生のこと | 209 |
| 62 | 神戸花街のこと | 210 |
| 63 | 舞踊振付のこと | 214 |
| 64 | 三味線の話 | 217 |
| 65 | 三味線屋 | 217 |
| 66 | 三味線の拵へ | 224 |
| 67 | 棹と胴 | 232 |
| 68 | 撥 | 235 |
| 69 | 調子笛 | 237 |
| 70 | 二代目新左衛門の思ひ出 | 238 |
| 71 | 出勤のおぼえ | 245 |
とにかく清水町の師匠(二代目豊沢団平、大阪南区清水町に住居せし故かく称呼す)の御教訓の根本は、専ら「舞台で死ね」、といふ命令で、明治三十一年四月一日師匠は大隅さん(三代目)の「志渡寺」を弾きながら舞台で死なれ、兼々御自身の教訓を実行されたのですから、これには一言もありません。
右のやうなわけですから、清水町の師匠の芸を学ばうとしたら必死の修行したものだけが及第するのです。勿論清水町の師匠御自身も、必死の修行をして来られたので、名人の長門太夫(三代目)さんを弾いて居られる間はずいぶん苦しまれたさうです。我々の知つてゐる時代で清水町の師匠に及第させてもらつたのは、太夫では大隅さん(先代)、組(六代目)さんの二人でした。大椽[掾](二代目竹本越路太夫事竹本摂津大椽[掾])さんはその以前に及第で、それなればこそ老年になられて耳が非常に遠くなつてから、舞台では三味線は殆んど聞こえず、楽屋で松屋町の広助(六代目)さんに三味線の調子を聞かせてもらつて、それで舞台で堂々と語られたさうです。組さんは彦六座で「伊賀越の岡崎」を語つて、舞台で脳震蕩を起してゐたことがありました。それが語り続けてゐる中に自然に治つて来て、舞台は穴があかずにすむのですから実に不思議なことです。尤も脳震蕩は組さんに限らないと思ひます。私もお蔭で今でも舞台で軽いのを起すことがあります。「バン/\」と手厚く打込んで、すぐ息をぬかず、そのまゝ暫らく詰めてゐますから、そういふときに軽い脳震蕩が起つて、舞台で役を勤めてゐるのか何だかわからぬやうになります。といつて別に間違ひもせず、暫らくして自然にはつきりして来ます。その瞬間の気持のよいことは経験したものでなければわからないと思ひます。
大隅さんは清水町の師匠が彦六座へ入られて間もなくしてから、亡くなられるまで弾いてもらつて居られましたから、ほんとうにはげしいお稽古を受けた方で、一番初めに清水町の師匠が合三味線を弾かれたときが、明治十七年十一月の彦六座で「国性爺三段目」の切「獅子ケ城」でしたが、稽古がはげしくて、初日前から声を潰して、かんじんの晴の舞台は源(先々代)さんが代りをしたやうな仕末でした。また後に「志渡寺」のとき、例のお辻の祈りのところで語つてゐる最中にへとを吐いたことがあつて、その跡形のついた床本を今の大隅太夫が持つてゐます。また彦六座で清水町の師匠が大隅さんの合三味線になられた当座は、役がすむと大隅さんは毎日大な[き]な身体を楽屋裏のしつくい場に横たえて、弟子にバケツの水をかけさせ、ふうふういひながら「もう一杯かけてくれ」とうだつて居られました。それに引替え細いひよろ/\の身体の師匠は涼しい顔をして居られるといふ有様で、我々は毎日のやうに「えらいもんやな」と感心して見てゐました。要するに大隅さんにしても組さんにしても毎日語り死ぬ覚悟で舞台へ上られたのです――明日といふ日を考へないやり方でした。このやうな舞台は残念ながらこのお二人の死後見られないやうですが、何人によらずかうありたいものです。私は時折宅へ稽古に来る若い者共に、稽古が終つてから「明日も稽古に来る積□[り]か」とたずねてやります。すると「伺ひます」と答へますから、「それがいかんのや、稽古は今日で終り、義太夫を語るのも今日で終りの決心で命がけで憶え、語らないかん。人の運命のことや、お前は今晩死ぬかも知れん。そしたら何もかも終ひや。明日朝目を醒ましてみて幸ひ生きてたら稽古に出といで、またお前が無事でも私の方が命があるやないやわからん。まして近頃のことや、一時間後に空襲でもあつてどんなことになるやわからへん。その積りで憶えてかゝらないかん。まして舞台は尚更や」と諭しますが、中にはこの意味がよくわからぬ者もあります。全く芸はこれでなくてはいけません。戦争でもさうだと思ひます、明日また戦争があるだらうから今日はまあこの位にして置かうか、といふやうなことはないでせう。
清水町のお宅での大隅さんのお稽古は実に大変でした。「一の谷の熊谷陣屋」の枕で、師匠が「シヤン」と弾かれて、「相模――」と大隅さんが語り出すと「いかん」でやりなほし、それがなんと数日間続くのですから驚きます。どの音(オン)から出ても「いかん、いかん」だけで、「相模は」の「は」まで行かないのです。つまり息が不十分だつたのでせう。数日後初めて「出来た」で、奥へ進んだのです。これはそのときお稽古について行つてゐた弟子の隅栄太夫が、「うちの師匠もあゝまで不器用やと思ひまへなんだ」と歎息しながら私にいつた話でした。いつたい名人のお稽古は一箇所つまると中々並大抵では通しません。その代り通過するとずうと進みます。つまり引かゝるところが大切なところなのです。大隅さんは清水町の師匠に「違ふ」といはれるとぢいつと、凡そ五分間も――もつと長いこともあります――考へ込んだ揚句「お願ひします」といつて続けられるのですが、それが一度ですむときもあり数度、十数度のときもあります。稽古はこれでなくてはいけません。師匠がいつてゐる中にもう口を開ける人がありますが、そんなのは何にもなりません。三味線でも同じです。自分一人で本読みするときでも、声を出してしまつては、自我がすつかり出てしまつて何を語つても同じといふ結果になります。よく文章を読みつめて、肚の中で目算を立てゝから声を出さねばそのものになりません。
清水町の師匠の三味線は何に譬へればよいでせうか。まづ雄大なことはこの上なく、手厚いところは大砲の音のやうな力があり、手薄いところは紙よりもうすつぺらい感じでした。中でも手厚い芸がこのお方の本領で、だいたいはきやしやな身体つきですが、肩から腕にかけての骨組は頑丈で、殊に右手が大きうございました。その腕に河堀口の長門太夫(三代目)さんを弾いて居られた時代から芸がぬけるほど叩き込んであつて、舞台で力を込めて弾かれるのですから、その音といつたらありません。こんなとき師匠の癖として一寸お体を振られました。この仕科は今の仙糸さんが真似をしてやつてゐますが、師匠がこの仕科をされるとその後からどんなえらい芸が出てくるかわからなかつたのです。師匠の音に関してはいろいろいひ伝えもあります。「太功記十段目」の光秀の出の「タヽキ」を弾かれたとき、その音がえらい音であつたので道具方が何か倒れたのかと思つて飛んで来た、とかいふ話もありますが、これは造り話かも知れません。私は日々舞台の後ろできかせて頂いたり、またはツレ弾きですぐ隣に座つてゐてその都度「大きな音やなあ」と感心したことですが、一つ面白い話があります。「吃又」の枕で、「爰に土佐の末弟、トン」と一を打つのですが、その音がとても大きいのです。大隅さんはさんざん稽古してもらつて「爰に土佐の末弟」がいへるやうになつて、彦六の舞台で度々語つて居られましたが、清水町の師匠が亡くなられてから、田中の清六(三代目、当時鶴沢叶)さんが弾くやうになつて、東京の歌舞伎座へ社長の井上竹次郎と伊達(後の土佐)太夫との関係で、はじめて義太夫がかゝつたとき、私も二枚目の伊達さんを弾いてゐて、大隅さんらと一緒に芝居茶屋の越後屋で泊つてゐました。そのときに「吃又」が出て、宿で大隅さんと清六さんが稽古してゐましたが、清六さんが「トン」と打つと、大隅さんは「そやない、そこはゴオンや」とダメを出しました。清六さんが力を込めて「トン」と打つても「違ふ」といつて通しません。清六さんは「そんなゴオンてな音三味線にはおまへん」といふと、大隅さんは三味線の心得は全然ない方でしたから、「そやけどこゝはゴオンやないといかん」と押問答になりました。終に大隅さんは傍にゐた私に「おい友(当時道八は友松)やん、これ一寸いふたつてんか、ゴオンが弾けんね」といはれるので、「そら師匠のやうな音は誰かて出えしまへん、しかしこゝはまあこんな風の芸をしてはりました」と説明しますと、流石は清六さんです、「考へさせてもらいます」といつてその後研究したのでせう、その後追々出来て来ました。
とにかく清水町の師匠の音は、雄大なことに於いては他の者と世界が違ひましたから、叶ひません。物に譬へれば南画の名人の筆の勢と同じです。やはり「吃又」で私が連弾きをさせて頂いたとき、「名は石魂にとゞめん、ツヽヽヽツン」の音の大きいことゝいつたら、地響きがするやうで、隣に座つてゐて毎日びつくりしました。ですから連弾きなどあつてもなくても同じで、よく大隅さんに皮肉をいはれました。「友やん(私のこと)お前弾いてんのか、お前の三味線の音ちよつとも聞えへんがな」と、全くその通りでした。
師匠は我々のお稽古のとき常に音をやかましく申されました。初めは「その『チン』いかん」位のところから始まつて、「撥が遣へてまへん」、「左が皆目利いてない」、「だいたい音がいかん」と、終りにはたいてい音のダメが出ました。かうなるともう万事休すで、「太十」も「酒屋」も何もあつたものではありません。そして師匠はいつも「もつと幅のある音を出さないかん」と仰言つしやいました。糸張りを高くして、大きい撥を持てば自然大きい音にはなりますけど、そこに工夫と鍛錬がないことには大きいばかりで、底へ抜け切らぬやうな音になつてしまひます。所謂雄大な、幅のある音になりません。道理からいへば我々が師匠と同じ音が出る筈がなく、出たら稽古にも何も行く必要はないです、がこれは近頃の理窟で、以前は師匠にさういはれると、「成程、有難い」と思つて音の研究――三味線の拵へと撥遣ひに一生懸命凝つたのです。
師匠の三味線の雄大なことはだいたいこんな風でしたが、さうかと思ふと軽妙なあしらいのところなどまた無類で、「吃又」なればお徳の瀬田鰻の条など実に結構で、丁度戯画の名人の筆の運びのやうでした。畢竟考へてみますに、師匠はまず手厚い芸を完成されて、軽いところは後からまた別に修行されたものでせう。それに師匠の芸は水の器に従ふやうで、前に申した通りの雄大さでありながら、狭い場所で弾かれてもやかまし過ぎるといふことは絶対ありませんでした。東京の旅で寄席を巡りましたとき、僅か一間半か二間位の舞台で、それにしつくり適つてゐました。といつて広い所で弾かれても隅まで聞えぬことなど絶対ありません。つまり雄大なことはどこまでも雄大ですが、締まりがついてゐたからです。大隅さんの義太夫もその通りでした。義太夫節といふものは広い場所でやつて隅々まで届き、四畳半でやつてやかましくないのでなければいけません。先年市川猿之助さんの「三番叟」を弾きに浅草の国際劇場へ出ましたが、その大きいのに驚きました。まるで野球場のやうで、皆が広すぎるとぶつぶついつてゐましたが、私はこんな大きいところへ出してもらふのは雄大な勢[芸]を勉強するためには実に結構だと思つて勤めてゐました。
義太夫の三味線で足取が重要なことはお話しするまでもないことです。世話時代の弾き分け、文章のすがたを弾き表すのは第一に足取です。これは一寸口ではうまくいひ表せませんが、例へば一つの「フシ」の長さがかりに一尺あるとしますと、その一尺のものを等分に割らずあるところは一寸五分、あるところは三寸二分、また次には五寸、その次は四分……といふ風に辿つて、結局は一尺のものに納めるのが足取で、その割り方、辿り方によつてその場その場のすがたが表れて来るのです。一尺のものを一寸づゝ十に等分する場合もないことはありませんが、まづ少く、何時でも等分ではそれは足取といへません。ですから同じ一つの「フシ」でも足取をつけ変へると全く別のものになります。
清水町の師匠の足取の結構なことは申すに及ばぬことで、師匠は余程足取を研究されたに違ひありません。従つてお稽古もやかましく、世話と時代の袖のふり様――お染、初菊、八重垣姫などの区別が特に厳重でした。
それに師匠の節付された曲の値打はどこにあるかと申しますと、第一に足取です。お聞きになればわかることで、「壷阪」、「良弁杉」何れも足取が結構で、この二つの曲の足取は全く違つてゐて、まるで同一人の節付とは思へません。それから「伊勢音頭の十人斬」になると、足取が一層複雑に烈しくなつて来ます。この「十人斬」は書卸しの初代清六さんの節付をそのまゝで、足取だけつけかへてあんな結構なものにされたところもあると思ひます。
ところで足取をほんとうに勉強するには、同時に撥遣ひ、指遣ひを勉強せねばなりません。撥の遣ひ方、指の動きによつて足取が生れて来るのです。撥や指が悪くて足取は無類だといふやうなのはありません。つまり足取、撥遣ひ、指遣ひは三位一体のものなのです。
彦六座の極く初めに朝さんの八重桐、源さんの蔵人で、「嫗山姥」が出て、師匠が弾かれましたが、築地の外で八重桐が替唱歌をきいてゐる間の足取は実にたまらないものでした。あんなに弾かれると自然に振りが出て来ます。
清水町の師匠の撥遣ひは千変万化でとても口では申されません。まづ表撥と裏撥の遣ひ分けですが、表撥とは普通に下ろした撥で、裏撥とは拵らへた、「テ」、とか「チーン」とか、その他いろいろありますが、文章の意味、舞台のすがたを弾き表す撥をいふのです。お稽古のときに、「そこは裏、それは表」とかいつてもらへる者は余程お気に入りの者でないといふて頂けません。弟子の中でも、源吉(後の三代目団平)さんのやうな腹心の者でないと駄目です。「裏や」いはれて撥を裏返へしたりして眺めてゐるものは一度で落第です。
それに師匠のは根本から撥遣ひが他と違ひました。総て撥先の活用が自由自在で、総て前へ勢よくはねて出た撥遣ひでした。あの雄大な音も一つはこの撥遣ひが原因になつてゐるのです。またこの撥遣ひの為に、勿論「間」もよいのですが、絶対に皮へ突込まれませんでした。その撥遣ひといふのは口では申されませんが、撥の持ち方が根本で、撥は中指と薬指と小指の三本で、叩かれても落さぬやうにしつかりと持ち、後の二本の指で撥を遣ふのです――親指と人差指の動きは自由自在でなくてはなりません、そのために指ずりがはつてあるので、指ずりの長さだけ二本の指が動かねばならないのです。
使つて居られた撥は到つて小さい、先の薄い、開きの狭いもので、最後の舞台で使つて居られたものは私がお形見に頂いて宅の家宝にして居りますが、撥先の開きは二寸七八分、厚味が三分位で杓子のやうな形です。これは大きい方で、もう一つ小さいのがありました。昔は腕の強さを自慢するのに競争のやうにして皆大きい重い撥を使つたもので、百五十匁、八十匁は普通で、中には二百匁などゝいふのがありましたが、師匠のは百二三十匁位でせう。大きいのは撥が弾いてくれますが、模様やワザは弾けません。そして撥を遣つて仕事をするといふことになると、大きいのでは全然出来ません。「タヽキ」にしても大きい撥だと、撥に叩いてもらへますが、それでは「タヽキ」でも何でもなく、撥先の力をぬいて腹の底から力を出して腕で叩かねば「タヽキ」とは申せません。
師匠の撥は、長年の間御自分の思ふまゝに仕事の出来るやうな形を工夫されて出来上つたもので、そのお蔭を頂いて今でも彦六座系の三味線弾は、この間死んだ新左衛門でも、仙糸さんでも私でも皆小さいのを持つてゐます。松太郎さんも極めて小さいのでした。源吉さんなどは師匠と寸分違はぬ撥を誂へて使つてゐましたが、思ふやうに弾けなかつたときは、盛んに撥を返へしたりして具合を見、握りをもう五厘程削つてくれ、などゝ撥屋へ注文してゐましに[た]。また師匠は常に舞台へ撥を二挺持つて出られました。これは今では長い役のときはたいていの人がさうしてゐますが、昔はなかつたことで、どういふ理由で二つ持つて出られるのか、といふことが、先年東京の新派の芝居の「浪花女」で喜多村さんが団平に扮されたとき楽屋で疑問になつて、丁度当時私も東京に居りましたので、手伝に行つてゐた若い者が喜多村さんの言伝できゝに来ました。それは長い役で撥先がへるからではなく、一段中仕事をされる(ワザを弾くとか、模様を弾くとか)その箇所によつて少しばかり違ふ握りの手勝手のよい方で弾かれる為なのです。
指遣ひも亦清水町の師匠が特に苦心をして居られたことで、際さえあれば棹をさぐる手つきをして考へて居られました。御飯の間でもよくお茶碗を置いて思ひ出したやうにして居られ、他から見ると気違ひのやうでした。ですから御便所の中でもきつとやつて居られたに違ひありません。師匠のお爪は到つてうすい悪いお爪でしたからとても大切にして居られ、お風呂では左手はお湯につけられませんでした。その代り手先は頑丈で指先が蛙の水かきのやうにひらいてゐました。師匠の指遣ひは荒くて細かく、丁度蛸の足が延びるやうに行亘つてゐました。そしてそれが力強く、棹に溝が出来、時には絃を指ではじかれるはずみに棹のふちが欠け、弾いて居られる中に指にそげを立てられることがありました。床をこつこつと叩かれるので御用を伺ひに出ると「そげ抜き」と仰つしやつたことがよくありました。
このやうな指遣ひですから、余韻が活きて、模様が鮮かに出ました。三味線は模様が大切でたゞ「チン」だけではそこに何の意味もなく、「チンウ」とうなりが活きて来てこそ模様も生れ、間も生れて来るのです。余韻は丁度太夫の音遣ひと同じ意味のもので、謂はゞ三味線の音遣ひで一段中色々複雑になつて来るのです。
これについて最近感心しましたのは、先日東京で日比谷の公会堂へ宮城道雄さんの演奏会に行きましたとき、宮城さんが爪音だけで余韻の足らぬところを左を働かせて補つて居られたのを拝見して、成程左指の大切なのは我々の方だけでない、何でも左は大切なものであることをつくづく感じました。
具合といふのは口では説明が出来ません。教へるに教へられぬ所謂芸の妙といふものです。ですから却つて天性よい芸を持つてゐる人などはたいした勉強をしないのに具合だけよく弾けることがあります。こんなのは俗に「具合弾き」といつて、今ではあんまりないやうですが、以前はよくありました。その代り他の技巧は別問題です。といつて習ふに習へぬ[る]ものでなし、どうしたらえとく出来るか、それは一概に申せません。
清水町の師匠の具合はとても結構なもので、側近者は皆習得しようと苦心した□[も]のです。チンバの吉三郎(後の六代目吉弥)さん、新三郎さん、松太郎さん、源吉さんなど、勿論天分もありましたが、苦心の結果師匠の具合を学ばれました。下つて新左衛門(二代目)や私も師匠の具合に憧憬れ随分苦心をしました。今では仙糸さんがその方の天分が豊かな上、清水町の師匠の結構なのもきいてゐますから研究してよい具合を弾いてゐますが、その後に続くものがないやうです。しかし三味線は具合が弾けなければ駄目です。
俗にいふ「間」で、口で申されませんが、お聞きになればわかるもので、これが悪いと芸の形が崩れます。皮へ突込んだり、絃を切つたりするのはたいていは「間」を外したときです。名人になりますと、芸だけでなく、平常の動作に既に「間」があります。清水町の師匠もその甚しい方で、お咄しされるときの手振り、何か物をされるときの手の動き、お召替えのときの段取、総て一つの「間」がありました。最も甚しかつたのは、舞台へ出られる前のお召替のとき、介錯人が袴の腰板を充行う「間」で、前をポンと叩いて合図をされると、それを取つてよい「息」と「間」で充行はないとお気に入りませんでした。「間」を外したら何回でもやり直しをさゝれました。後に源吉されもこれを真似してよく弟子を叱つてゐました。
要するに三味線は文章の意味を弾き、舞台のすがたを表すのが役目で、文章は太夫が語り出しますけれども、枕一枚でちやんと情景を出してしまふことは、何としても三味線弾の逃れぬ責任であります。しかしこの、文章を弾くこと、すがたを弾くことは中々むづかしいことで、自分でえとくしないと教へられても出来ないものは何時まで立つても出来ません。つまり沢山の中にはその意味がわからない者さえゐます。しかし気が付いてからがどうしても殊更に弾きに行きたがるもので、それでは芸といふことになりません。近頃私が稽古に来る若い者へ「そない弾いたらいかん」とよく申しますが、憶え込んでしまつて自然にそこへ行くやうにならなければいけません。それには結局稽古を励むより方法はないのですが、無意味に繰り返へすだけの稽古は何にもならず、三味線の真髄を掴むやうに心掛けねばなりません。幸それが掴めてそれによつて一段上つたら、故実は別として、その一段で全部応用出来るのです。そこまで一つの外題を稽古せねばならないのです。何も珍らしい外題や変つた手を知つてゐるのがえらいのではなく、人間の頭脳のことですからそんなに沢山憶えて居られるものではなく、殊に我々の勤めてゐました彦六座は割合外題の種類が沢山出なかつた為、私など外題の数をあまり沢山知りません。しかしその為に師匠にお小言を頂いたことはなく、「寺子屋」、「太十」、「酒屋」などありふれた外題で、随分長い間苦しみました。とにかく芸はたくまずして自然にそこへ行くといふことが大切です。師匠が浄瑠璃は語らずに語れ、三味線は弾かずに弾け、と教訓して居られたのはこのことなのです。そしてその自然は年が経つたらひとりでに出来るものではないのです。そこを考へねばなりません。
古くは珍らしい外題を、――「蝉丸」の道行とか「花襷」の道行など憶えてゐて、中々見識張つてお稽古に行つても簡単に教へられなかつた方がよくありましたが、清水町の師匠のは全く反対で、彦六座で下廻りのものでも弾いてゐるのをおきゝになれば、わざわざ呼び寄せて悪いところは規切に、秘伝も何もなく教へられ、決して出し惜しみなどされませんでした。
清水町の師匠も色々珍らしい外題を勿論よく御存じであつたに違ひありませんが、これについて一つ面白いお話を聞いて居ります。私がこの道へ入る一寸前の頃でせう、チンバの吉三郎(後の六代目吉弥)さんが芝居で何か知りませんが珍らしい道行を弾かねばならぬことになつて、それを知つて居られるある古老の方のところへ教はりに行かれました。ところがその師匠が丁度旅へ出て留守だつたのです。それを清水町の師匠がお聞きになつて、初日が間近だから仮りに作つて置いてやる、と新しい節付をされ、その古老が帰られるまでそれを弾いて居られました。その中にその方が旅から帰られたので改めて習ひに行かれたところ、それが清水町の師匠の仮の節付と、少しも違はなかつたといふのです。これは造り話のやうですが、芸の基礎が定つてゐて、丸本の黒朱がお読めになつた(これは清水町の師匠以後誰も読めません)のですから、この話も決して造り話でないと思ひます。
清水町の師匠はよく「ほんまの太夫は春(五代目竹本春太夫、竹本摂津大掾の師匠)さんで終ひや」といつて居られました。その意味を伺ふと、「古浄瑠璃の風は春さんで終りで、それから後はえせ浄るりや」といふて居られました。それはどういふことですかと追究しますと、例えば「野崎村」を語るとき、枕の「後に娘は――」と語り出すのに、今は娘の「地合」としてやさしい語り方をしますが、さうでなくて大音で、声でなく音を遣つて、ぶつつけて語り出すのです。それは娘は舞台に出てはゐるが、物もいふて居らず、唯舞台の有様を書いた文章を語るのだから娘の声色めいたことではいけない、といふ意味です。その中に芸の力で自然その場の情景が表れて来る。それが義太夫本来の語り口、古浄瑠璃の風だ、とのことです。「寿しや」の枕の「春は来ねども――」でも、「阿波鳴戸」の枕、「後うち眺め女房は――」でも、「堀川」の「同じ都も――」でも同じことです。総て咽喉を廻さずして、腹から声を出して、顎で音を遣ふのです。節を廻すのは咽喉でなくて顎で廻すのです。高いところは顎で声をつり上げ低いところは顎で沈めるのです。義太夫は大の男が娘や子供の真似をしなければならないものですから、さうしないとやれません。松屋町(六代目豊沢広助)など稽古のとき、「□[顎]や□[顎]や、顎やがな」といつてよく怒つて居られました。
また「太夫は浄るりを語つたゝめに声を潰すといふことは絶対ないのが本道や」と常にいふて居られました。全くその通りで、病気なれば知らぬこと、浄瑠璃を語つて咽喉を害した場合、音遣ひのどこかに無理があつたに違ひないのです。力を入れすぎて――力を入れるのはよろしいが――間違つたところへ入つて、きばつてしまう、それがいけないのです。だいたい我々の声帯――のどぶえといふものは細いもので、極く弱いものださうです。だからそれへ力を注いで無理な遣ひ方をすると一度で潰れてしまひます。力は丹田に入れて、上半身は出来るだけ軟らかく構えるのです。殊に眉に力が入つてはいけません。腹から声を出して第一に顎で音を遣ひ、次に鼻ヘぬく音、舌の音、唇を遣ふ音、歯を応用する音、これが五音で、これを遣ひ分け、息と腹とでつめて文章を語るのが太夫で、それによつて「風」が定るのです。
義太夫節は音遣ひと運びの上から大別して「西風」、「東風」の二つがあり、外に特殊なものとして「駒太夫風」、「景事」があり、それぞれ音遣ひと運びの憲法が定つてゐるのです。中古以後沢山名人の太夫さんが出られて、各々の語り風を創められましたが、根本は皆「西」、「東」の両風に基いてゐます。従つて一段の中に東西両風を語らねばならぬことになつた[+も]のが沢山あります。例へば「寺子屋」は前が「西風」、「小太郎が母」から奥が「東風」でやります。「壷阪」が前が「西」、「こりやまあどうせう」からが「東」、「講釈の七ツ目」のやうなもので[+は]段切一枚が「東」です。このやうな「風」の語り分けは総て今申した五音の遣ひ分けによつて定るのです。
音遣ひのことについて、次のやうなお話があります。二代目の義太夫になられた政太夫さんが、師匠の元祖義太夫さんの歿後櫓を預つて興行して居られましたが、天性の小音で、興行毎に不評つゞきで、すつかり考へ込んで居られたのです。そこへ近松(門左衛門)さんが「国性爺」を書かれたのですが、ある日お宅の縁側の障子の小さい破れ目から木枯しが吹き込んで、それが「ぶうん/\」といふ音をたてゝゐます。政太夫さんは何気なくそれをきいてゐる中、ハツと思ひつかれたのです。障子の小さい穴を御自身の咽喉ぶえになぞらへ、外の大気の風を肚から出た声と見て、声の遣ひ方、音遣ひを案じ出されたのです。そこで早速舞台で応用されたところ、「国性爺」は古今の大当りであつた、と申すのです。このお話は清水町の師匠から夜酒のとき度々伺つたもので、当時は源吉さんなども一緒でしたから皆知つてゐましたが、もう当時の連中も殆んど亡くなり、このお話を知つてゐるのは恐らく私一人だと思つてゐましたら、数年前ラヂオで近松さんの事を仕組んだ芝居か何かの放送のとき、右のお話が中に仕組まれてゐたのをきいてびつくりしました。
音遣ひの修業では大隅(先代)さんが他人一倍苦労して居られます。前にも申した通り、清水町の師匠がはじめて合三味線を弾かれたときの「国性爺」では一生懸命で、咽喉へ力を入れすぎて、稽古から声を潰し、それからしばらくは始終声を潰して居られましたが、次第に音を遣ふこつをえとくして、少しも声を潰さず、私の知る限りでは盲人の住(四代目)さんと共に音遣ひの名人となられましたが、音を遣ふことを師匠から授けられて、やつてゐる中に涎がだら/\と出て「大隅の涎くり」と綽名がついた程でした。
義太夫の発声法はだいたい右のやうなものなのですが、先年お名前は忘れましたが西洋の歌の発声法を研究して居られる方が、日本の歌の発声法はどうも腑に落ちぬ点があるといつて私に会ひたいといつて居られたさうですが、日本にも今申したやうな立派な発声法があつて、根本は西洋のも変りないのですが、それを実行してゐる人が非常に少いだけなのです。
次に間拍子は総て初めから定つてゐて、つまり「八ツ間」といふ「ノリ間」がそれで、これをいろいろ応用して行くのが太夫であります。「八ツ間」は義太夫の土台の「間」で、どんな時でも忘れることは出来ません。これを忘れると、太夫は絶句したり、「間」を外したりします。また他流の音曲が取り入れてあるところでも、それを「八ツ間」にあてはめてやると、義太夫化されるのです。
そして間拍子の応用とは、例えば三味線が十撥弾く中に、太夫は七ツで語り納め、また逆に太夫が八ツゆるところを、三味線が五撥であしらふといふ風に、太夫は三味線の数を拾ひ、三味線は太夫の数を拾つて行くので、それで「足取」を運んで、時代世話、語り物によつていろいろ工夫されるのです。
それから詞は根本の「間」を表面へ出すといけません。「何とやらして、ア物とやら」といふ風になつて、これを「杖つき間」と申して、清水町の師匠は非常に厳重でした。「ア何とやら――」と声を出して杖をつくのは勿論のこと、息がそうなつてゐても「杖つきッ」と注意されました。それから引字、「何とやら―」と産字でなく無意味に引張るのは、世話時代によらず絶対にないものです。
総て詞に限らず、文章でも息と肚でつめるとその根本の意味が表れます。それを「語る」といふので、義太夫節は唄つたり、唸つたりするものではありません。語るものですから、「道行」や「ちやり場」は別ですが、三段目物の込み入つたものは、語る方は勿論、聞かれる方も自然息が積んで来て、後で肩が凝るやうなことがあります。住(四代目)さんや大隅(先代)さんや組さんの浄瑠璃などそれでしたが、義太夫節といふものはそんなものなのです。いや義太夫節だけではありません。何芸でも名人の芸は聞く方も自然息をつめねばならぬやうになつて来ます。常盤津の名人林中さんもさうでしたし、円朝さんの人情噺もさうでした。
考へますに義太夫節も初めは、今日我々が考へさせて頂く程難しいものではなかつたに違ひありません。それが中古幾多の名人が出られて、あんなことも、こんなこともといふてやらねばならぬ憲法が追々沢山出来てこんなになつてしまつたのでせう。そして最後に清水町の師匠が出られ[+て]、いろいろなことを完成せられたのでせう。かうまで込み入つて来たのは清水町の師匠から後の事に相違ありません。その証拠に清水町の師匠より古い方と、清水町の師匠とは芸がすつかり異つてゐました。
明けても暮れても、芸のことより外考へられなかつた、といふのが師匠の御生活です。私は十数年間師匠のお身近く仕へさせて頂きましたが、その間「今日は一つ遊びに行かうか」などと物見遊山を思ひ立たれたことは一度もありませんでした。
お宅は清水町どぶ池西入北側の二軒目で、間口二間半に一間の入口(間中の戸)で簀戸なく、上つたところが三畳で一間の押入れがあり、これが次の四畳半の押入に続いてゐてその真中に階段がありました。奥に六畳の間があつて、その向ふが一坪位の中庭で三畳の離れがついてゐました。こゝはお千賀さんのお部屋で、三階は屋根裏のやうな低い天丼の三畳で、これをお稽古場にして居られました。は入つて左側はお台所で小さいながらも大阪風で天窓があり、へつついがありました。
昔とはいひながら勿体ない質素なお宅で、太郎助橋の住太夫さんのお家もこの位、これよりまだ一つ位間数が少い位でした。尤も師匠は三度引越しをされたさうで、私の知つてゐるのは三度目のお宅ですが、以前のも二度とも清水町だつたさうです。
朝は五時頃にお目醒めで、それから神棚の御拝礼が二時間位ありました。大変な信仰家で、まず大神官様、金毘羅様、聖天様その外いろいろお祀りになつてゐたやうです。わけは存じませんが、中でも金毘羅様の御信仰が特に厚く、旅興行で初めての土地へ行かれますと、宿に着いて一番先にその土地の金毘羅様をお祀りしてあるところをおたづねになり、あれば早速お詣りに出掛けられました。
それにこれは我々が見習はねばならぬのは、師匠は神様への信仰と、芸に対する信仰が一緒であつたといふことです。これは私の想像ですが、例えば三味線の上り絃など決して粗末にされませんでした。御自身では勿論のこと、お内儀さんへもそのことは云ひ渡しをされてゐたやうで、こんなことなど芸に対する信仰心の一つの表れだと思ひます。
朝御飯がすみますと、そろそろお稽古の方がつめかけて来て、芝居へ御出勤までお稽古が続きます。お稽古に来る方はそのときによつて定つて居らず、たいていの方が見えました。太夫の大所では太郎助橋の住(四代目)さん、三味線では松葉屋五代目(豊沢広助)さんも時折お見えになりました。松葉屋さんは師匠に「兄貴々々」といつて居られ、お稽古の外によく節付を頼みに来られました。いつかも「七賢人」とかいふものを手を付けてほしいと頼みにお見えになつてゐたのを傍でちらと拝見した憶えがあります。尤も大隅(先代)さん、組さん、チンバの吉三郎さん、新三郎さん、松太郎さん、源吉さん、後に私などは清水町の常連でした。また、お素人の御連中では、道頓堀芝居裏の鰻屋の東呉さん――この方は前髪時代からの御連中で、師匠のお家の会計の相談役になつて居られたさうで――、大宝寺町どぶ池東の紺屋の万鳳さん(本名鵜飼)のお二人、東呉さんは「沼津」に「薄雪の蔭腹」に「組打」、万鳳さんは「陣屋」のお稽古だつたと憶えてゐます。
お稽古が終るとお食事を召あがつて芝居への御出勤で、お宅から彦六座までの道順はいつも定つてゐて、畳屋町を廻つて心斎橋を渡り、北詰からすぐ西へ曲つて御堂筋を北へ博労町まで行つて南門から稲荷境内へ入り、参拝して楽屋へお入りになりました。私はよくお伴をしましたが、ある時御堂筋の辺で、「ここは昔長門はんが毎日通りはつた道やで。今は下手ばつかり通りよる」と仰言つたことがありました。
夜分芝居からお帰りになつてからは、一日中のお楽しみの夜のお酒で、十分寛いで粗末なお肴で二合足らずのお酒をちびりちびり長い時間掛つて楽しまれました。そしてこのお酒のお燗お酌は皆我々の受持で、我々としてもこの時が芸談を伺ふ楽しみの時でした。ですからたいてい二三時間かゝり、十二時過ぎになるとお千賀さんの御注意で切上げられましたが、旅先などではお話がはずむと夜明けまで続くことがありました。
お内儀さんはお千賀さんと申して、「壷阪」や「良弁杉」の作者として有名な方です。もとは京都の方で、よく「何々やそうえ」と京都弁をお出しになりました。三十一文字などもお達者で、御筆跡も綺麗でした。お作の中大物は「壷阪」、「良弁杉」、「三信記」などですが、ちよいちよいと加筆をされたのは随分あります。「合邦の端場」、「鰻谷の端場」、「加賀見山草履打の枕」、「同奥庭」など、まだ外にも沢山ある筈で、その節付は皆師匠がされました。「勧進帳」はお千賀さんと違ひます。
恰幅のある大柄の方で、中々しつかりして居られました。師匠が芸だけの方ですからお家の中は総てお千賀さんが切廻して居られ、従つて師匠は一目も二目もおいて居られ、お呼びになるときは「なあもし」といふて居られました。尤もお千賀さんは後妻さんで、先妻さんは私は知りませんが、今堺に居られる御長男の平三郎さんを残して亡くなられたのです。
清水町の師匠の節付の内「壷阪」、「良弁杉」、「勧進帳」の三つは最近文楽で度々出ますが、この外大物では「三信記」、「西郷隆盛」(逆巻浪夢夜風)、「一心太助」(忠孝義誉松枝)など、その他短い物は数へ切れぬ程あり、悉くが結構なことはお聞きの通りです。師匠が節付をされた時代にはもう義太夫のよい作者がゐませんでしたから、その趣向や文章は皆あまり感服出来ないものですが、それが師匠の節付だけで立派なものになつてゐます。いつたい文章の悪いのは節付をするとき少し苦労が多いだけで、師匠のやうに結構な節を付けられて出来上つてしまえば、総て立派な芸術品になるのです。それについて当時源吉さんと私とが二人で、「『赤垣出立』を師匠に節を付け変へて頂いたら結構やがな」といつも咄し合つてゐました。そこでどういふところが結構なのか、と申しますと、それは第一に「足取」です、つまり総てのものを取入れ、それの用ひ方です。それは総て師匠の案なのですから、節付の虎の巻といふものはないのです。そして取入れるものといふのは、音曲に限らず世の中の総てのものが取入れられるのです。そんなものを入れたら義太夫にならぬ、といふやうな狭いものではないのです。なるもならぬも扱い方一つです。これについては師匠は随分勉強されたと思ひます。勿論私の知らぬ時代ですが、「薄雪の鍛治屋」の道具替りの間のメリヤスをお作りになるとき、毎日夜明けに立売堀の鍛治屋まで鎚の音をきゝに行かれたさうです。夜明けに行かれたのは、職人の腕に一杯の元気がある間の鎚の具合をきかれる為なのです。かりに今日まで師匠が長らへておいでになつたら、当時より世の中が総て繁雑になつてゐますから、どんなものを芸の中にお入れになるかわからず、定めし面白いものが出来上ることゝ思ひます。嘗て私が師匠のお使ひで三味線屋の「桝東」へ行きましたとき、注文をして大急ぎで帰つて来ましたら、「早かつた」と賞めて頂けると思ひの外、「なんでそない早う帰つて来たんや、もつとよう町の中のいろいろなことを見て来て芸の参考にせないかん。世の中の目に映るもん、耳にきくもん全部芸になるのやで」とお小言を頂いて恐れ入つたことがありました。全くこの心掛けでなければなりません。
さうかと思ふと、彦六座で「勧進帳」(これはお千賀さんの作ではありません)の書卸しのとき、曲が出来上つて狂言師の和泉助三郎、堀千助さんのお二人が人形の振付に見えましたので我々連弾きのものが前茶屋の二階できかせましたとき、お二人は感心して「団平さんは能の方はよほどお詳しいとみえます。このまゝで我々の方の『間』にぴつたり合ひます」といはれましたが、我々は「あゝさよですか」とわからぬなりに感心しました。といつて師匠が能へ行かれたことは話にもきゝません。また「伊勢音頭の油屋」の貢と喜助のやりとりの間のメリヤスなど歌舞伎の下座の三味線の「間」にちやんとなつてゐます、歌舞伎とても師匠はむしろお嫌いな方で一度も見物に行かれませんでしたが、総て芸の根本が定つて居られるから、自然にそれになつて来るのです。これから考へますと、その時その時にわざわざ参考に採りに行かねばわからぬやうではいけません。行つてもわからぬなどは問題外です。それからこの「勧進帳」の節付は勧進帳を読む間だけで一段の仕組になつてゐます。
師匠が拵へもの(節付)をなされるときは、たいてい二階の三畳で、その間は御飯を召上らずお供餅を火鉢の中へくべて、その黒焦げになつたのをかぢつて居られました。そして芝居でそれを演らせて頂く者が前に控えてゐて、出来たらすぐお稽古にかゝるときもありました。何の外題のときでしたか忘れましたが、例によつて皆が師匠の前に控え、朝太夫さんの役で、師匠のお机の前に座つてゐましたが、夜遅くて眠く、朝さんがこくりこくり舟を漕ぎはじめました。師匠は紙と筆とを持つて朱をお入れになりながらときどきちらと御覧になつてにこにこして居られました。我々は朝さんの様子が可笑しく、その中に面白いことになるだらうと見てゐましたら、案に違はず遂に師匠のお机でゴツンとひどく頭を打ち、師匠も我々も一度に大笑ひをしたことがありました。朝さんは我々に「いふてくれたらえゝのに」とふくれ面をしてゐました。
師匠の節付は、前に申しだ[た]「三十三所」とか「三信記」[+の]やうな通し狂言のときは、さきに役割を定めて夫々場を語る太夫に合ふやうに節付をされだ[た]ので、例へば「良弁杉二月堂」は柳適さん、「志賀の里」は朝さん、「壷阪」は前の島太夫さんのと別にまた大隅さんに合ふやうに付け変へられたのです。また「油屋」は組さんの為に作られたのです。こんな風ですから、書卸しの方は大当りに定つてゐたのです。この外短い物でも、勤める太夫によつて「お前がやるのならこの方がえゝ」と仰つしやつて、ところどころ直して渡して居られました。語る太夫の芸のたちに基いて節を付ける、または付け変へる。といふことは義太夫の節付の骨張です。
もう一つ大切なことは、出来上つた曲を語り活かし、弾き活かすといふことです。節付といふものは手数(てかず)を定めたのではなく、芸の道筋のヒントを与へられたものですから、それから凝るのはやらせて頂く方の責任なので[で-]す。実際折角苦心をして作つた曲を無意味に弾かれてゐるのをきく程情ないことはありません。私が旅で「十人斬」を弾いてゐましたとき師匠が床の後ろへきゝにみえて、にこにこ笑つて居られたところもあり、ときどきはしかめ面をして居られたところもあつたさうです。そんなところは師匠の節付のお心を掴めず無意味に弾いてゐたところなのです。
三味線の「朱」といふものは、手数(撥数)の控へですから、「朱」そのものは芸でないことは申すまでもありません。ですから清水町の師匠などは「朱」に重きを置いて居られなかつたことは勿論であります。しかし「朱」を入れて居られたことは入れて居られましたが、すぐお弟子などに惜気もなく遣つてしまはれました。ですから師匠の「朱」の本は方々に散らばつてゐると思ひます。二代目の広助さんがやはりさうだつたと聞いて居ります。このやうに清水町の師匠は「朱」に極く無関心であつたにかゝはらず、お入れになつた「朱」は実に結構なもので、「トン」と手厚く打つところは、筆に力が入つてゐて勢よくはねてあります。つまり筆遣ひがもう撥遣ひになつてゐるのです。その外「替へ手」のあるときは別にていねいに書かれてあり、太夫の節だけのところも「朱」が入れてあつて、傍に「引かず」と書いてあつたり、実に親切の極みで、清水町の師匠の芸の根本を呑み込んでゐるものが拝見すると、『足取』までちやんと読めますが、たゞの繰り方しか知らぬものは、猫に小判で、読めません。清水町の師匠の門弟の中でも読めぬものがありました。
私の宅には清水町の師匠の「朱」の本が三冊だけあります。一冊は「合邦」の端場でお斎よばれをお千賀さんが加筆されたのを師匠が節付されたもので、文章はお家の直筆で、伊達(後の土佐)さんで私が勤めました。後の二冊は「廿四孝」の『下駄場』(三段目中景勝下駄の段)と、「三信記」(加古千賀女作「弥陀本願三信記」)の『三国』(第六冊目三国汐待の段)とです。これは清水町の門弟の神戸で亡くなつた団左の家にあつたのを、その息の平八が始終宅へ来てゐまして、「我々が持つてゐても宝の持ち腐れです」といつて持つて来てくれたのです。団左は師匠によく仕へてゐましたから、お遣りになつたのでせう。
私が清水町の師匠のお宅へ繁々伺ふやうになつてからのことです、たしか冬の寒い日であつたと思ひます。おとなひがあるので玄関へ出てみますと、四十がらみのみすぼらしい門付風の男が立つてゐます。「御用事は」ときくと、何やら口ごもりながらぶつぶついつてゐましたが、要は義太夫の門付をしてゐる冥利に一度は師匠の三味線を一段でよいからさし向ひできかせて頂きたい、といふことらしいのです。私はその男の風采からして、師匠に申上げる前に一度お内儀さんに伺つてみた方がよからうと思ひ、お千賀さんに次第を申上げますと、簡単にお取りになつたのでせう、「留守やちうときなはれ」と仰つしやいましたので、玄関に待つてゐる男に「折角ですけど師匠只今お留守です」と断つて、追返へさうとしましたら、最初からの様子をすつかりおきゝになつてゐたらしいのです、師匠が「団平居ります、どうぞおあがり」と出て来られたのです。留守だといつたすぐ後から御本人が中から出て来られたのですから、そのときの私の体裁の悪かつたことゝいつたらありませんでした。隠れるわけに行かず、致し方なく俯向いてゐましたら、師匠は独り言のやうに「折角きゝに来てくれはつたのに――」と仰つしやりながらその男を連れて二階の稽古場へお上りになりました。そして「安達の三段目」(袖萩祭文)の一くさりを弾語りできかせておやりになり、まるでお客さんのやうにていねいに扱つた上お帰へしになりましたが、帰りがけにその男はほんとうに泣いて喜んでゐました。私はこのときの師匠のお様子には感心を通り越してむしろ不思議に思ひました。しかしまずうろんな男でなかつたのでやれやれ一安心と思つてゐましたら、それから先が大騒動で師匠は,直ぐお千賀さんをお呼びになつて、「ほかのことならえゝけど、こゝの家にゐてゝわしの芸を慕うて来るもんに嘘ついて返へすといふやうなことをしては、うちの家風に合ひまへん。今日かぎりいんどくなはれ」と、厳格にいひ渡されました。私は傍にゐて二度びつくり、平常はお内儀さんに「なあもし/\」といつて意見一つ出されず総ていふまゝになつて居られた師匠が、今日はまたまるで別人のやうにお内儀さんを叱りつけられ、しかもいきなり離縁話が出てお千賀さんがいくらお詫びになつても、師匠は怒い顔をしてどうしてもお許しにならないのですから、「こらえらいことになつて来た」と思ひましたが、我々共が口を入れられるところでなし、たゞどうなることか、と心配をしてゐました。しかし事が芸に関することである以上お千賀さんもいくらあやまつても駄目だと思はれたのか、一旦身繕ひして師匠の家を出られ、その足で御連中の万鳳さんと東呉さんのところへおいでになつて、師匠への取成しをお頼みになりました。お二人のお口添へでやつと元へ納まつたのですが、このときばかりは私も初めに引かゝりがあつただけ蔭で随分心配しました。
しかし芸に関してかほどまで徹底した心掛けは清水町の師匠位の方ならでは持てないものだと思ひます。このお話を私がずつと以前東京の中央新聞の方にして、当時新聞に出ましたが、それからずつと後に、私は知りませんでしたら、私の死んだ娘が「お父さん[の-]うちの教科書にお師匠さんのことが出てるよ」といひますので、見ると右の話が芸人の心掛けの鑑といふことで出てゐました。それからまた後に、講談倶楽部か何かの雑誌に私の話として出ましたが、それをお読みになつたのか、東京の高輪辺の何とかいふ学校の校長さんから、結構なお話で、学生の教訓にしたい、とのていねいなお手紙を頂いたことがありました。
常々から「舞台で死ね」との御教訓で、勿論御自身も座右の銘として居られたのでせうが、実際その通りの御最後になつたのですから恐れ入る外はありません。
明治三十一年四月一日、稲荷座の四月興行の初日の夜の八時頃でした。その興行の狂言は、前が「恋女房染分手綱」で組さんの「沓掛村」に住(五代目)さんの「十段目」、次が弥太夫(五代目)さんの「帯屋」次が大隅さんの「志渡寺」で師匠の役場、切が「みばえ源氏伏見の里」を春子太夫が語り、三味線の松三郎が二代目新左衛門を襲名した披露の外題でした。私の役は前狂言で「坂の下」、それと「志渡寺」の「次」で二つとも伊達太夫の役場でした。
師匠はこの日平素と変りなく、舞台へ出られ、私は役の「端場」をすませて、身終いをしてすぐ床の後ろにいつもの通り控えてゐましたが、段切近くの
「さつと吹き来る風に連れ、杉の梢にありありと現れ給ふ御姿は、正しく金毘羅大権現と、神ならぬ身の白砂には、睨み合うたる晴勝負、エイヤツと打合う早業早足」
この合の手でいつになく師匠の撥が一寸縺れました。私は「妙やな」と思ひましたが、すぐまた立直つて、それから一段と烈しくなり、その勢は今でもはつきり耳に残つて居ります。後で考へえますと、初めに縺れたときに御病気の最初の徴候が起りそのあとは病苦をこらへて懸命に弾かれたに違いありません。勿論段切まで弾いてしまはれるお積りだつたでせうが、少し奥の
「顔は笑へど胸の中、早せぐりくる断末魔」
で、突然コツコツと床板を叩かれ、三味線はそのまゝ途切れてしまひました。私は慌てゝ床へ出て見ますと、師匠は斜にぐつたりうしろの衡立に倒れかゝつて居られます。私は師匠の持病のさしこみのひどいのが起つたのかと思つて鳩尾のあたりを圧へますと、師匠は殆んど夢中で御自分の肩を叩かれましたので、私も首筋のところを揉みましたが、とにかく師匠の両手を肩にかけて背負つて舞台裏へは入りました。そこへもう肩衣をつけた新左衛門も飛んで来ますし、座の人々も集り大騒ぎになりましたが、当時は脳溢血といふことを皆が知らず、痃癖が肩を越した位に思つてゐました。しかし重態には違ひないから、深沢先生が来られるまで応急手当として足の裏ヘ芥子を塗らねばと、「からしを買ふて来い/\」と皆が叫びましたが、慌てゝゐるので何処へ買ひに行つたらあるのか急に思ひ出せないのです。するとそのとき師匠が「玉水玉水」と仰つしやいました。「ほんにそや、玉水へ行け」と瀕死の病人に教へられて使を走らせましたが、この「玉水玉水」と仰つしや[+つ]たのが師匠の最後のお言葉でした。
師匠はこのときまで撥をしつかり握つて居られましたので、それを離して居合せた龍助(二代目)さんに渡し、代りに舞台へ上つてもらひ、師匠のお体は私が背負つたまゝ、皆が介添をして、階下の弥太夫さんの楽屋へ舁ぎ入れ、とりあへず私の右膝を枕にして寝させましたが、このときはもう全く意識がなく師匠は鼾をかいて昏々と眠り続けて居られました。舞台では大隅さんが師匠の容態を気遣ひながら、も扇拍子で咄瑳の間をつないて[で]居られました。
「物いひたげに延上る手負の目にはまざ/\と拝まれ給ふ梢の方」
以上が三味線なし、こゝで龍助さんが出て段切まで弾かれたのですが、龍助さんは常着に前垂れかけのまゝの姿でした。
急の知らせにより三休橋の深沢病院の院長先生、お宅から御長男の平三郎さん、靭館(今の靭の電車通辺りにあり女太夫の昇之助の親の家でした)で此太夫(元当昇といふ素人出の太夫)さんを弾いて居られた源吉さんなど相前後して駆けつけ、もう大隅さんも役をすませて皆枕頭に詰めてゐましたが、平三郎さんが見えたとき、師匠の耳の側へよつて
「お父さん、平三郎です。わかりまつか」
といはれたとき、眠りつゞけて居られた師匠が一度だけ
「うムツ」とお返事されましたのは実に不思議でした。これが師匠の最後のお声だつたのです。このとき、私は肉親の間柄といふものはえらいものやな、とつくづく感心しました。
それから間もなくして釣台が用意されて来ましたので、すぐ病院へお入れすることになつて、深沢先生をはじめ側に居つたもの皆と外に座の者一二人と看護婦が附添つて、稲荷座を出ました。このとき新左衛門は稲荷座の提灯を持つてゐたと思ひます。深沢病院へ行く途中、二度程立止つて先生が脈を見られましたが、三度目に立止つた塩町三休橋の角、今もあります交番の横で師匠は遂に息を引取られました。先生からそれを聞いたとき附添つて居た我々は思はず知らず地べたへ蹲つてしまひ、ぼうとなつてしまひました。先生の言葉でやつと立上り歩き出しそれから何かの都合で病院の玄関まで寄つて、すぐ清水町のお宅へ向ひました。
お宅へ着いてお祀りをして、早速お葬式の相談にかゝりましたが、こゝで一つの問題が起りました。それは平三郎さんは明治十八年頃から数年間薬学の勉強に米国へ渡つて居られ、向ふでクリスチャンになつて帰つて来られた為、師匠のお葬式を基督教式でするといひ出されて譲られないのです。それに対して我々は勿論大反対で、若し平三郎さんが譲られなければ我々で別に仏式のお葬式を行ふとまで申立ました。そこで平三郎さんも、それまでいふのなら万事お任せする、と折れて総て我々がお世話することになりました。
それからもう一つ、一寸笑ひ話があります。それはお通夜のお念仏のときに、我々の唱へてゐるお念仏と、打つてゐる鐘が、初めははなれてゐても、すぐべた附きになつて来るのです。このとき私は常々師匠がいつて居られた「太夫と三味線が附きすぎてはいかん」といふ御教訓――実際これには私も長い間苦心したことです――を思ひ出し、思はず「これやな、師匠がいひはつた太夫と三味線が附きすぎるといふのは」と叫びましたので、一座の者共も悲しい中にも可笑かつたと見え大笑ひをしました[+。]
納棺は、経帷子などお着せゝず、舞台の衣裳に肩衣を附け、お扇子をお持たせして、正座の形で我々が涙とともに抱きかゝえ、座棺へ納めました。火葬にするといふ話もありましたが、源吉さんや我々が「師匠のこのお手を灰にして堪るものか」と反対して土葬になりました。
お葬式は四月五日、阿部野で行はれましたが、門弟は白装束、他の因講の太夫三味線は全部小紋の裃で股立を取つた揃への姿でお供をしました。葬列は清水町を西へ、心斎橋筋を南へ、戎橋を渡つて道頓堀を東へ進み、堺筋を真直ぐ阿部野へ向ひましたが、先供が道頓堀の芝居前のあたりへ行つた頃に、やつと棺がお宅を出ようといふ位長いものでした。そしてその中で雇つた者は輿を担ふ人足数人だけで、後は全部会葬者でしたから、全く師匠[+の]芸の徳といふものは大したものだと思ひました。只今阿部野墓地にあるお石碑は、一年程立つてから出来たもので後藤猛太郎伯爵のお筆で、御先代から御贔気であつた関係でお書きになつたのです。法名は大達絲道居士、お年は七十二歳でした。
師匠は、播州加古川のお生れで、三代目広助さんのお弟子でしたが、三代目さんからも大変可愛がられて居られたさうで、はじめ豊沢力松、次いで丑之助、それから二代目さんの幼名の団平を襲がれたのです。勿論御幼少の頃から抜出た芸であつて、いろいろな方から引立られ、中でも三国屋の巴太夫(三代目豊竹巴太夫)さん、河堀口の長門太夫(三代目)さんのお二方に引立てられたと、御自身よくいつて居られました。師匠の御逝去は私の一生の中で一番悲しかつた事件で、ほんとうに真暗闇の中へつきやられたやうな気で、「どな[+い]しやうかしら」と思ひました。今でも「志渡寺」をきくと当時を思ひ出して悲しくなります。
このお話は私がまだこの道へ入る前のことですが、非常に有名なお話であります。清水町の師匠がまだ春太夫(五代目)さんを弾いて居られた時のことかと思ひます。春さんが「染模様妹背の門松」の『質店』を語られるについて、清水町の師匠が初代清六(畳屋町)さんのところへお稽古に行かれました。清六さんの「質店」は初代古靱さんの合三味線でやかましいものだつたからです。お稽古を申込まれた時、清六さんは「団平どん(当時顔の古い方はかう呼んで居られました)はよう知つてるのやろ」といひつゝ、喜んで日を約し、当日は早朝から畳屋町のお宅で待つて居られました。やがて清水町の師匠が見えて、一段きいて帰られましたが、清六さんは「団平のことやさかい、きつと上手にやつてくれるやろ」と、総稽古の日にきゝに出て来られたのです。やがて高座で弾かれた清水町の師匠の「質店」といふものは、清六さんが教へられたのと全然違ふものでした。そして、それは清六さんのより以上結構な「質店」だつたので、前で一生懸命きいて居られた清六さんは、すつかり感心してしまはれた、といふことです。この時の「質店」は、例の「質置」の条や久作の出など特に結構だつたときいて居ります。稽古に来て教へた通りやらないのですから、怒るのがほんとうなのですが、感心したといふ清六さんも流石に名人です。清六さんは私の師匠の勝七さんの師匠で、私に取つてはぢい師匠にあたりますが、大きい方で、当時の義太夫界の顔のえらいことは大変なもので、相撲場へ行かれてもよい顔でした。清水町の師匠など、顔では孫ぐらいなところでしたが、その方の得意の「質店」に対して右の仕末なのですから、清水町の師匠のえらさはどれ程かわかりません。二名人の逸話として、私達の若い頃はよくこのお話をきゝました。
地唄と義太夫節との関係の密接なことは申すまでもないことです。清水町の師匠と市中の主な法師さんとはたいがい連絡がありました。そしてその時の稽古の必要に応じて清水町の師匠のお声がゝりで検校のところへ研究に行つたものです。私も清水町の師匠の御命令で富塚検校のお宅へ「廿四孝狐火」のお稽古に行つたことがありました。最初富塚さんが唄はれるのを聴かせてもらひましたが、何しろ盲人ですから間が格別長くて、音遣ひに一風特殊なところがあります。「はゝあこれが地唄の特長で、こゝを学ばんならんのやな」と思つて、私が前でやらせてもらふ番になつて、「思イー、イ、イ、イイ、イイ、イーイイ……」と、盲声で、出来るだけ富塚さんのクセを取つてやり出しましたら、「そんな盲の真似しやがつて」と怒鳴られた上、ごーんと一つげんこを喰はされました。よいと思つてやつたのにあべこべに叱られてびつくりしましたが、それなら前から知つてゐるのをやればよいのだらうと思つて、盲声を離れてやり直しましたら、今度は私の未熟なところを捉へて「だいたいそれでえゝのやが、清水町さんそんな音遣ひ教へはりましたか」と皮肉です。返答のしやうがありませんでしたが、何度もやり直してやつとのことで出来上りましたが、清水町の師匠のお声がゝりのお蔭なればこそ、ほんとうの厳しいお稽古をして頂けたのです。しかし「何と怖い盲はんもゐるものやな」と思ひました。
それから清水町へ帰つて来ましたら、「やつて見い」との命令で、富塚さんで叱られた直後ですから、義太夫がゝつた音でやりましたら、今度は「それでは何の為に法師さんのとこへ行つたんやわからへんがな」と二度のお叱りです。そこでまたびつくり、いつたいどつちをやつたらよいのかわからなくなりましたが、次は盲声で法師さんの真似をしましたら、「そうや、それを習いにやつたのや」と、やつと通して頂きましたが、この時はほんとうに困りました。
こんな訳ですから「狐火」は今でもよく憶えてゐます。文章に「アレあの奥の間の検校が歌ふ唱歌も――」とありますから、是非検校の音遣ひでやらねばなりません。また奥の「乱れ」は清水町の師匠のツレ弾きをさせて頂き、源吉(後の三代目団平)さんと一緒のときもあり、二人で大分苦しみました。
富塚検校の外にもう一人三休橋本町北入西側に菊中といふ検校が居られ、同じく清水町の師匠と繁々連絡がありましたが、これらの方を初めとして、市中の法師さん達は休日の朔日十五日には、たいてい三四人彦六座へ清水町の師匠の三味線をきゝに来て居られました。いつでも桟敷の一か床の真下で、熱心にきゝ入つて居られ、特に足取の面白いところなどでは、盲人特有の笑みを満面に浮べて、独りで悦に入つて居られました。そして床が廻るときには、小声で「お師匠はんおゝけありがと」と礼をいふて居られました。そんなときは師匠も格別御機嫌がよく、「お疲れさん」をいひに行つても御機嫌のよいお返事でした。
この浄瑠璃は清水町のお内儀のお千賀さんの作といふことになつてゐますが、一番初めは誰が作つたものかわからないと申すのが本当かと思ひます。西国卅三所各寺に夫々霊験のいひ伝へがあつて、それに幾分色をつけて本になつて出てゐたのをどなたがゝ浄瑠璃に作られたのが初めでせう。書卸しは明治十二年十月大江橋の席で、太夫は島太夫(六代目)さんで、三味線は新三郎さんでした。この興行には私は出てゐませんでしたから詳しいことは知りませんが、「西国卅三所観音霊場記」の通しで、各段よせ集めのやうなことだつたときいてゐます。「壷阪寺」はこのときから清水町の師匠の節付ですが「長谷寺」は大助(二代目)さんだつたさうです。このときの「壷阪寺」は只今の五行本の文句と大分違ふところがある筈で、枕の「まゝの川」や「菊の露」はなかつたらしく、この辺をお千賀さんが加筆されたものと思ひます。只今の五行本の「壷阪寺」の書卸しは明治廿年二月のいなり彦六座で先代大隅さんが清水町の師匠の絃で語られたもので、こゝにお咄しするのはこの「壷阪寺」です。
それから住太夫(五代目)さんも「壷阪寺」を語つて居られますが、これは大隅さんよりも以前で、まだ雛太夫時代、京都の首振り芝居でのことです。三味線は竹沢弥六さん、ですから島太夫さんが初演せられて後間もないことでせう。
書卸しの島太夫さんは、当時の昔風の芸人で、浄瑠璃は極めて平凡な語り口でしたが、どちらかといふと世話畑の人で、まづ悪声の部でした。柄も小柄で、従つて非力でしたが、何分当時は大きい浄瑠璃の太夫さんが沢山居られましたから、この方など非力の部になつてゐたのですが、只今の斯界の有様から申すと、島太夫さんは大きい浄瑠璃の部に入ります。「猫島」といふ綽名がついてゐましたが、それは語る中に音を遣ふところどころが猫の鳴声のやうに聞えたからです。またこの方は立派な貧乏人で、坂町に住んで居られ、太夫の傍「おもちや屋」をして居られたさうですが、これは御維新直後のことかと思ひます。三味線の新三郎さんは、当時の三羽烏の一人で、時代弾きで、芸は大きく、よい「間」でした。師匠の新左衛門(初代)さんが清水町の師匠の預りになつて居られましたから、孫弟子のやうな関係で始終清水町へ出入して居られました。
まず、枕の「夢が浮世か――」の唄は、先程も申した如く、後からお千賀さんの添作で、これは御承知の地唄の「まゝの川」で、奥の「鳥の声――」は同じく地唄の「菊の露」ですが、この二つの地唄の曲を義太夫化して、義太夫節の足取と音遣ひで演るところに、味ひがあるので、同時に清水町の師匠だけの芸力があつて初めて出来る節付です。それではどうすれば義太夫化されるかといひますと、だいたい地唄といふものは、唄でも三絃でも「常間」でスウーと運ぶものですが、これに対して義太夫節は、「ノリ間」(「八ツ間」)といふことが根本の約束ですから、万事その「間」で運ばねばなりません。しかし、初めから終ひまでそれ許りでは折角地唄を取入れた面白味が消えますから、あるところは地唄で、あるところは義太夫節で運びます。ですから、この枕は、特に「間拍子」に深甚の注意が必要になつて来ます。
で、弾出しで、「シャン、シャン」と二つ弾くのは、その一つ宛の音の尻に「ウナリ」(余韻)が必要で、従つて撥遣ひも特殊なものでなければならず、その「ウナリ」が「間」になります。「シャン、シャン、『ハッ』(と掛声をするところですが、地唄には掛声を禁じてありますから、こゝは声を出さずハット[と]掛声を掛ける「間」だけを取ります、以下之に同じです。)テチチンウ(といふ風に音の尻の「ウナリ」が大事です)、チンウ、『ヤ』チリンチリツ(とこゝは余韻を消して)、ツン、ツルンウテツン、『ハ』テチヽンウ、チリンウテツンウ、『ハ』ツトン、ロン、ロンロヽトン、『ヤ』チン『ハ』チテンテン、『ハ』ツトン、『ヤ』シャン」と、これだけの撥数と「間」と音とは必ず正しく弾かねばなりません。殊に注意せねばならぬのは、音の「ウナリ」で、これがこの弾出しの骨組である「間拍子」の生命であります。そこで弾出しがすんで、「シャン、ゆめが――」と、太夫が語り出すのは、地唄の音遣ひで出て、次に「トテチン」に「チンウ」とうねつたウナリが必要で、これは義太夫節の三味線でなくてはいけません。そしてすぐ「うき――」と太夫が義太夫節の音で出て、「ヨヲカーア」は又地唄になります。それから「浮世が夢」は義太夫節で、「カアヽ」は再び地唄に戻ります。だいたいこんな風に運ぶので、奥の「菊の露」でも、「鳥の声鐘の」は地唄で出まして、「オヽトサー」は義太夫節になり、「エ」で再び地唄になり「思ひ」で「ツトン」とノッて「出す」となるのは義太夫節の「間」であります。それから「出す程涙が先へ」まで(中でも「ダス」で特別に)は、はつきりと座頭の音遣ひ、即ち盲目声を表さねばなりません。尤も、総て盲目声を忘れてはなりませんが、こゝは格別に注意を要するところで、次の「落ちて流るゝ妹背の」は稍普通の声で、「川を」で再び盲目声を大切に遣ひます。五行本に「妹背の川に」となつてゐますのは、「川を」と訂正す可きと思ひます。それから盲目声ですが、同じ盲目で遊芸を業とするものにも、座頭と検校と二通りありまして、詞にも音遣ひにも、その区別がはつきりせねばなりません。座頭の方は、真世話の「間」で、俗つぽくドス汚くやりますが、検校の方は、時代がゝつて、幾分位をつけてゆつたりと演らねばなりません。「布引」の松波検校の詞がそれで、又「廿四孝」の『奥庭』の「思ひにや」の唄は、検校の音遣ひ、即ち茨[蕗]組のやうな音を遣はねばなりません。
順序が後先になりましたが、始めの「沢市といふ座頭あり、生れ、ついたる」から十分ノッて「正直の」で止まり「コトー」は一寸へたつて「の」が[か]ら再び十分ノッて「の稽古や三味線の糸より細き身代の」まで続け、「間」を置いて「ウスーキ」は、下の音をていねいにつたつて、ほんとうに薄き暮しといふ文章の意味を音遣ひで表はします。「夫の手助けちん仕事」は十分世話にくだけ、「つづれ」は一寸押さえ、「させてう」からまた十分ノッて畳み「糊かい物を打盤の」の三味線が、唯「ツン、ツン、ツン、ツン、ツン、ツト、テン、テン、テン、テン」ではいけません。これは、砧の打盤を打つ音を三味線で出すといふのが、こゝの節付の本意で「ツウ、ツウ、ツウ、ツウ、ツウ、ツト、テ、テ、テ、テ、テ」と、左で余韻を消すのですが、その「間」に、打盤の「音もかすかの暮なり」といふ余情を漂はさねばなりません。それには、左の遊んで居る三本の指を働かす修練を要します。そして、撥はなげて撥先に力を入れて荒く、色気を禁じて弾きます。
「互に心も知つて居るにマなぜ」のところの三味線がよく「ツトン」と弾き勝ちですが、これは、「ツト」と音を消して弾きます。何故かと申しますと、次の「そのやうにかくしてやるぞ」といふ沢市の詞は、心から寂しい気持なのですからそれを迎える「チン」も寂しい「チン」でなくてはならず、さうするには、「ツト」と余韻を消して置かぬと、「チンウ」と心から寂しく弾けないのです。次に「ドコーヲヤラ」の「ラ」からもう濁りかけて、「ニゴル」の「ル」で十分濁つた音を弾きます。「言葉のハーシ」「テン」は、お里の合点の行かぬ「テン」を弾かねばなりません。そして、「フシン」は「トツ」ときつぱり弾きます。
それからお里のサワリになりますが、一般に「サワリ」と申して居りますのは、これを「クドキ」(口説)といふのが正しいので、「サワリ」といふのは「節名」でありまして、極く僅かな条で、「壷阪」に例を取りますと、「――なんのその、一旦殿御の沢市さん――」とかゝつて行くところが「サワリ」であります。それをどうしたことか何でも全体を「サワリ」といつてしまつてゐるので、正しくは「クドキ」であります。
お里のサワリは、近頃では前受け許り狙つて、お里の真情が少しも語れてゐないやうです。「節数」は正しく辿らねばなりませんが、その中にお里の肚――夫を思ふ一生懸命の貞節の情が溢れないといけません。それは、ネバつかずサラつと、この結構な足取――「ノリ地」を片時も忘れず、緩急を正しく踏んで行きますと、自然と文章の意味が語れ、又弾けて来る筈になつて居るのです。で、「思ふ計りか」の三味線を、「テヽヽヽテンテ」とタヽいて弾くのがありますが、これは、次の「コレ申し」をあてる為の外何の意味もないことですから、タヽかない方がよろしい。次の「この壷阪の観音様へ」は、お里が真から観音様を有難いと信心してゐる肚を音遣ひに表わし、「明けの七ツの鐘を聞き」の「上タヽキ」の「間」を「キヽ、チチンリン、ハチヽン、ハ、シャン、シャン、シャン」と取り、ほんとうに人知れずそつとぬけ出る意味を弾き、大夫にもその肚で「ソーヲヲット」の音遣ひが大切です。そして「ト」から十分ノッて「唯一人」まで続けます。「外に、オトーヲコが」は、お里の悋気したいやらしい音を一寸表わし、「――ア、ル、ヨ、オ、ニイ、ヽヽ」はノッて、「今のお前のヒトーヲ、コトが、チンチン」からは荒く、「私は腹が、ターツ、ワ、イ、ノト(とつめ)、オヽヽヽ、チンチン、オヽ、チンチン、オヽ、チン、オヽ、チヽヽヽヽ」と節に流れるのですが、こゝは、左に力を入れ、右は撥先に力を入れ、荒くタヽかず弾きます。
次の沢市の改心は、これ亦余程よく情を畳み込んでもたねばなりません。「アヽコレ女房共何も言はぬ――[+」]と唯言つてしまつては丸潰れで、「女房共、○、何もいはぬ――」と、無のところを語らねばほんとうの情が出ません。それから、「愚知許りコレ」「ヤア、テヽン」ではいけません。グツと息を詰めてゐなければ、ほんとうの腹が弾けません。「手を合したる詫涙、ソデヤ、タモトヲ、ヒタスラン」と文字を詰めて語り、また、「連添女房に何の詫び○、私しや死んでも」と「無の間」を語り「本望じやわいな」と次の「イヤモウさういふて――[+」]との中間の無のところと、「イヤモウ」の音遣ひとに沢市夫婦の情を語らねば、「壷阪」が語れたとは申されません。そして、「面目ないわいの、が夫程に――[+」]の「が」が大切で、これが沢市の心が観音様の方へ向いて来る萌芽の一句であります。少し奥へ行つて、「枯れたる木にも花が咲く」まではしつかりといひ、一寸間を置いて、「とやら」は極めて危げに、そろそろ死ぬ心を表し初め「見えぬ此目は――」は、潰れた目を手で指さす振りを語り口にはつきりと表します。話が脇へ入りますがいつたい盲目を語るコツは、耳を目として扱ふことにヒントを得て工夫しますと盲になります。尤も、盲目にも色々種類がありまして、「天王寺村」(極彩色娘扇)の兵助などは亦違ひまして、あれは俄盲目ですから、目を閉ぢて物を見るやうな形からヒントを得て詞を工夫します。「――花が咲かしたいなア、(カハッテ)といふたところが、(ウレヒの間を置いて)、罪のフカーイ(と突込み)此身の上、せめて来来は(十分泣いて)」、「イヤサアノ」は、てれかくしの詞で、「女房共、手を引いてたも、いざ/\と――[+」]と次第に「間」を速め、女房は十分勇んで「踊り間」風に運んで行きます。「いたはり渡すホソーヲヅエノ」の次の「合の手」は、「チヽチンチヽチヽヽヽチーントン」と撥数がありますが、これを、「チヽチン」「ハッ、チヽ」、「チヽヽヽ」「ヤツ、チーン」、「ヤツ、トン」と、五ツに区切つて、その「間」に盲目が杖を探つてこそこそと家を出掛ける足取りを弾かねば、折角の師匠の苦心を台なしにするといふものです。で次の」[「」細き心もホーソーヲ(この「ヲ」にウレヒがあつて)、『ヤ』カーアラアヽヽ、アー(これにまたウレヒがあつて)アヽヌ、ウウ(ウレヒ)、ウヽヽ(ウレヒ)」とこれだけあつてから、「ウー」と直ります。そして、「誓ひは――」からは、沢市のことから離れて、ハツて出て次第に雄大に語つて行きます。
次の「辿り行く」の「上三重」はうんと立派に出ます。[+(]これは現今の昔もさうでしたでせうが)壷阪寺の実景に反しますが、高野山か比叡山のやうな霊験灼然な深山幽谷の気持で演りませんと、劇になりません。そして、「伝へ聞く――」以下は、位をもつて、ノツタ「常間」の「早間」で、ねばらずさら/\と運び、「実に有難き霊地なり」は、この浄瑠璃が観音様の霊験灼然なことを仕組んだものですから、特に位を附け、ドツシリと納めます。
その次の「折しも――」の前に、「チントン/\ツトンジヤンジヤン」と弾くのがありますが、これは弾かずに、太夫から「ヲリシモ」とカブツて出て、「テントン/\」と受けるのが正しいのです。「詠歌を道の――」の所は「詠歌」といふ名前の「節」で「しほりにて」までは、「常間」で歩けるやうに弾きます。それから、沢市の唄は中々むづかしく、それは唄を唄いつゝ死ぬ覚悟を定めてゐるといふウレヒの心を、表面へ出さず、それを「間」に表すといふことです。それに、近頃見てゐますと、よくこゝの沢市の人形が立留つて唄つて居るのがありますが、それは大間違ひで、一足づゝ歩きながら唄ふ「足取」に節付がしてある筈です。舞台では三味線は弾きませんが、三味線の朱章もちやんと出来てゐます。これはたしか姫路あたりを旅廻りして居られるときに出来上つたと思つてゐます。こんなところは語る太夫がそれを心得ず、たゞ唄ひますから、人形まで立留つてしまふのです。で、「うきが情か」で一寸「間」をおいて、その無の間にウレイ[ヒ]の肚を語り、カワツテ今度はカブセテ「情がうきか」と続け、また次に無の間を語り、「チンツ、チヽンツチツンツ」は気を替へ、「露と(間をおいて)、消え行く」は十分寂しく、次の「テチン」は特に大切に、沢市の気持でカブセ、「我身の」は極めて寂しく、「―の」について「オホツ」と涙がこぼれ[(]こゝまで来てはじめて「ウレヒ」を表面へ出します)、そのてれかくしに全然カハッテ「ウヽヽヘハ」からノリはじめ、「チンチ、チリンツー」以下の「合の手」は、蹴褄づけるやうに、十分ノツテ、「踊り間」で唄ひます。
次の御詠歌は、只今では長くなりますので、殆んど上の句だけよりやりませんが、五行本には「庭のいさごも浄土なるらん」の下の句もあつて、これはお里にあげさすのがよいのですが太夫衆の声柄でさう行かぬときは、沢市でやつても差支へはありません。追善会などでは全部語る方がよいと思ひます。
奥へ行きまして、「坂を登りて右へ行けば――」のお里の詞をきゝ、沢市の「ヲヽどこヘ――」の一語は、沢市が自分の死場所を教へられたところですから、慌て気味の動揺した肚で語り、「行うぞ」で一寸留り、無の間を語つてそのてれかくしに、カハツテ、「今夜から観音様と『ヤ』ク、ビ、ビキ、ジヤ」と拍子を十分ツメていへばこそ、次の「アハヽヽヽヽ、オホヽヽヽヽ」の笑ひとのやりとりが面白くなるのです。この辺の芸の仕組の巧妙さは実に何共いへぬ結構なもので「この「首引じや」が沢市の「常間」の最後で、後はどつと乱れてしまひます。
それから、沢市が一人になつて「これ、うれしいぞや――」から「不便の者やいじらしや」迄は、遍にお里の貞節に謝す肚一杯で、「今別れてはいつの世に又逢ふ事のあるべきか」の「カ」の産字は泣さ[き]ながら「アヽヽヽヽ、チョン、アヽヽヽ、ア――」と語り、三味線も一つ一つ音を消して弾きます。が、「三歳が間――」からは、盲根性を出し「願ふても」の次に「フン」と鼻で嘲笑し、「ナアーンの利益もないものを」と、観音様を馬鹿した肚です。その次の「何時まで生きてもせんない此身」は十分のウレヒで、「わしが死ぬのはそなたへ返礼――」は、帰つて行つたお里にいふ肚一杯で、「よき縁付をしてたモヤ、ヤ、ヤ」の最初の「ヤ」は勢のよい高いウレヒ、次は稍低く、最後の「ヤ」で泣き入ります。□□カハツテ、「最前聴けば――」は締めて「――谷間」といふ一句は、自分の死場所なのですから十分の注意をして「息」でいひ、一寸止つて「とのこと」は寂しく、「是究竟の最後所」は突込み、「かゝる霊地」から「助かることもあらん」までヘタツて、「ムヽ幸に夜は更けたり」は力を入れ、「人なき中に」をウレヒで締め「ヲそふじや」はいよいよ最後の決心をして立上るのですから十分力を入れて出、その「チン」にも十分力を込めて弾きます。つまり、緩急緩急となるわけで「そふじやと立上り、ミーイヽヽヽダアル」と音を廻はし、「コヽロ」で直ほり、「トヲリ」、「エツ」と掛声があつて、「ナーホシツ」を「チテンツン、ツン」とうけ、「上る」からは「探り間」で運びます。それから、よく「コヽロヲヽンノヲ」と語る人がありますが、これでは「取直し」になりません。次の「上る」からは太夫も三味線も「探り間」で、「上ル」「チン、チン」「ダーン」「チンチン」、「サエ」「チ、」「チヨン」と一つ「間」があつて、「ヨ、ツ、イツヽウ、ハアヤ暁(これを「更け渡る」と語る人がありますが、こゝは原文通りで差支ないと思ひます)ノ」の「ノ」は、太夫も三味線も「ウレヒ」から「中ギン」ヘニジリ、「カネノコー」は音を遣つて出、「エーツ」を強く、尻張りに、三味線も「トツツンツンツン」と手厚く一気に弾きます。即ち「エ」で鐘が深山にひゞき渡るのです。次に鐘の合の手から続いて、「ツヽツトツヽヽ」から「チン/\/\」は、左指の仕事で、「チユ/\/\/\/\」いふ音が出るやうに弾きます。
「イザ最後時急がんトヲ、杖を力に盲目の、サグウヽヽヽヽ、ウヽヽヽヽ、ウヽヽリ、サアヽ(これは一寸色気を持つた音で)グウヽ、ウヽヽ、リイヽヽ、テ、ヨオヨオヽトコナアタノ、チヽン、チヽン、イヤ、チヽ、○○チヨン)[(]と拵らへてノリ[+)]、「チヽヽヽヽヽ、岩に――」となります。それから「迎ひぞと、ツン、杖を傍に――」の「ツン」は沢市が岩の上から谷底をハタと瞑[睨]んだ「ツン」ですから手厚くキメテ大切に弾きます。「身の果は」で沢市を飛込まし「哀れ、チン」は十分ウレヒで寂しく弾くのはいふに及ばぬことです。
お里の出は前と全く足取をかへて、「かゝることゝも露知らず」は三味線より先にカブセて出て、「知らず」で一寸留まり、「ハ、チヽヽヽヽヽ――」と続け、「気はそゞろ」で押え、「常になれにし山道も――」からはお里がころび/\坂を登る息を弾かねばなりません。「坂の上、チヽン、チヽン、/\――」は「常間」でなく、「キヨロ/\間」で、「沢市さん々々」は三度いふのがよく、三度目のは全く泣いて語ります。そして「たづね」は「上(カミ)」から出て、「ウレヒ」に落します。
それから「こりやマアー」から「ギンウケ」になり、曲風が陽気になり、以下お里の「クドキ」も全部「ギンウケ」で且「踊り間」で行きますが、かう節付されたところが実に結構です。しかしそれをたゞ無闇に浮かれて語つては折角の節付をこはすもので、心は踊らず、間で踊るのです。そこで「この世も見えぬ盲目の闇」の「説教」は変つた足取にしてつけてあるので、「ヤミイヽヽヽヽ、イヽ、イヽヽ、イヽヽ、ハ○○○○○(こゝは掛声なしで息だけでこれだけの「間」をとり)ヨイ、チヽヽヽヽヽ――、イーヨリ(チンチン)、ヤーミ、ノオヽ、オヽヽ、オヽヽヽ、シ、デ、ノ、イヤ、タアヽヽ、ビー」とこれだけの「産字」を拵らへます。そしてお里を死際に十分踊らせた節付がまた実に偉大なものと申さねばなりません。
谷底になつてからは、「夢ともわかぬ二人とも、テヽン」のこの「テヽン」が無意味にならぬやう、それからお里が、「お前の眼が明いてあるわいな」といふと、「ヒエー」と一旦驚いて、あたりをキヨロ/\見廻す間をおいて、「ホンニこりや眼があいた」と語ります。「眼が明いた/\/\」は喜ぶといふよりはむしろウレヒで、土になき入る形を語り表はします。「観音様のおかげ」はいはぬ方がよろしく、すぐ「有難うございます/\」になつて、最後は泣き入ります。そしてふつと気がついて、「ウムそしてアノお前はマア誰方じやぞへ」となります。
段切の「万歳」はこのときはじめて「万歳」の替手を師匠が作曲されたのですが、実に結構に出来て居ります。
この間(昭和十七年九月)文楽で、古靱さんが初役で「十人斬」を語るについて、半月程毎日神戸の私の宅へ稽古に見えました。古靱さん位になれば一度きいたらわかつてゐるのですが、十一日間も私のをきいてくれ、十二日目に口揚げでした、これが中々出来ぬことで、我々は商売ですから旦那衆のやうにいつまでかゝつてもよいではいけませんが、ろくに憶えもせぬ先から口揚げしても何にもなりません。近頃では平常に稽古をしませんから、いざといふ場合になつてよう憶えなくて無茶ばかりいつてゐるのが多いやうです。古靱さんは私のをきいてゐる間に、すつかり自分の案をお腹の中で立てゐたのでせう。総て稽古に行つて教へられた通りやるやうでは駄目だ、と昔からいひ伝えてゐますが、殊にこんな真世話物で、捨ぜりふのやうなうの多いものは格別さうで、与太にならぬ限り本にないことも自然にしやべれる位憶え込まねば品物になりません。
この浄瑠璃は書卸しは初代の大隅さんださうで、ですから多分畳屋町の清六(初代)さんが節付せられたのでせう。それに清水町の師匠が手を入れ、足取をつけ替え、奥の「十人斬」の条をお千賀さんが加筆して節付されたもので、中国筋へ旅廻りの間に出来[+上]つたものですが清水町の師匠御自身は一度も弾かれませんでした。それの書卸しは組さん、三味線はチンバの吉三郎(二代目)さんでお二人とも実によくやつて居られました。殊に吉三郎さんは天性雄大な芸で、それに色気がありましたから、この段には打つてつけの三味線でした。その後は松太郎さんが弾いて居られましたが、これも結構でした。まづ「十人斬」ではこのお二人です。今度古靱さんを弾く清六など吉三郎さんは勿論、松太郎さんのも「十人斬」はきいたことがないので、よいお手本を知らずほんとうに可愛想です。
その後伊達(後の土佐)太夫も語つて、それを私が弾いてゐたのですが、東京の寄席や旅廻りのときに、たいてい初日に出して随分好評をいたゞきました。いつかも東京の寄席でやつてゐましたら、名前は忘れましたが神影流の先生が私のところへ「これをお作りになつた方は剣術はよほどお上手でせうな」といひに来られましたが、「剣術みたいなもん一つも知りはらしまへん」と申しましたら、感心して「フム、しかしこれでないと人は斬れません」といつて居られました。また旅でこれを出してゐましたとき、床の裏へ清水町の師匠がきゝに来られて閉口したことがありました。自分の作つたのを弾き活かせてゐるか、弾き殺してゐるかをきゝに見えたのです。こつちが弾き活かせてゐるところではニヤ/\笑つて居られたさうですが、時折顔をしかめて居られたこともあつたさうで、そんなところはこちらが拙いので、毎日下廻りのものが注進してくれました。
今更申すまでもないことですが、枕といはず、殺しといはず、どこもかしこも結構な節付で、古靱さんのお稽古の間毎日弾いてゐて少しも飽いて来ません。毎日有難いと思ひながら楽しんで弾いてゐました。しかしものとしては弾きにくひもので、それはサラツト手厚く弾かねばならぬからです。総体に手厚くなくてはいけないので、綺麗ごとではこの段になりません。
では少し「油屋」のお話を申しませう。
△どの浄瑠璃でも枕が大事ですが、それはその段の情景を枕一枚で定めてしまはねばならぬからです。この段でもやはり枕は特に鄭重に扱はねばなりません。お紺が油屋の店先でたゞ一人、物思ひに沈んでゐる、ところへ暮の鐘が聞えて来るといふ舞台を、太夫も語り出しますがそれを弾き定めてしまふのが三味線の役目です。この枕は寂しくなくてはなりませんが色気がないといけません。
△そこで「後にお紺はうつとりと」を太夫はほんとうにうつとりした息と音で語らねばなりませんから、その前の「ツン」の一撥も息が大切です。
△「暮告ぐる」の次の「チン、トン、トン」の「間」が雄大でないと、「遠寺の鐘」といふ舞台になりません。
△「あなたをのいて片時も」は「地色」「浮世の日影が見られふか」は「地合」、「むごい、つれない、胴慾な、別れといふ字をきいてさえ」が「地色」、「胸にしみ/\」が「地合」ですが、特に「地色」は大切に語らねばなりません。
△「折紙の詮議」といつて、息でカハツて「アノ奥の客が――」をいひ、「――肌身は許さず」の次に思案する「間」をおいて「アヽどうせうぞ」は肚で泣いて語り、カハツて「オツそれよ」をいひます。
△「硯引きよせて」の「冷泉かゝり」は、「チヽヽヽ――」とスーツとした足で弾いて出ますが、その中に手紙を書きにくいお紺の肚を弾き表すやうに、私は心懸けてゐます。
△「鹿の巻筆も」の次の合の手の足取を大切に弾き、「今宵で――」で直ります。
△「固めの盃」の詞にハナして弾き、「――引立て」まで畳んで、「られて、せん方も涙かくして入りにける」はお紺の肚を足取に表すやう大切に弾きます。
△[「-]貢の出の「ウクハル」も清水町の師匠のは普通の足取ではありません。そして「恋には心引かれくる」は太夫と三味線との位取が大切で、三味線は「心引かれくる」足取を弾かねばなりません。
△貢の詞の間の「メリヤス」は、詞の中にある如く、面白さうに弾かねば貢が油屋へはいれぬことになります。これも足取一つで弾活かすか弾殺すかになるのです。それからこの「メリヤス」は「伊勢音頭」の極く古いところから取つて来られたので、「伊勢ようだの一踊り、二見ケ浦に曳く網の――」、中の句は一寸忘れましたが、「塵取手桶にかんちろり」といふ文句で、古市の備前屋などの大茶屋で女郎の三味線で女郎が踊る、亀の子の踊りのやうな極く野卑な踊りで、明治の中頃まで残つてゐました。その頃は女郎を買はなくともこの踊りだけを女なども見に行つたものです。油屋は中茶屋ですからこの踊りを催す資格はありませんでした。
△喜助はその性根をシツカリ語らねばいけません。唯の料理人になつてしまつては台なしです。そして意見の間の「メリヤス」は詞のよい合間へ入つて「間」がよくないと太夫が絶句したりします。
△「――と、先に立つ、案内につれて福岡貢暖簾の内ヘ――」から岩次が刀をすり替へる間は「常間」でノツテ運びますが、「一腰」ので一寸止つて、息を拵へて「ツン/\/\/\」とタメテ、「手早に――」は一寸「間」をマクツテ弾きます。
△「お紺は過す無理酒に――」からは前と全然気を変へて出ます。
△北六の謡ふ「相に相生の松こそ目出たけれ」の謡や「――とりどりに」の「道具屋節」はせいぜい安ツぽくやり、「サア/\申しお紺さん――」はワザで弾き、「床入り」は「チヽテツ[+」]と洒落れて弾きます。すべて岩次は田舎侍ですから貫目がつきすぎるとうつりません。
△貢が盃を引つたくる間は十分畳んで手厚く弾きますが、「誰かと思へば貢さん」のあたりはお紺の詞の中で一番むづかしいところです。
△「岩次は引のけ」の「イロ」はツメテ弾きます。
△「一一貢が見てびつくり」の「イロ」には貢が手紙を見る間を置かねばなりません。
△「あたきたない」は音を遣つた詞です。
△お鹿の出は「――カァケェデエルお鹿――」と「大間」に十分マクツテ、「台臼なり」は模様で、「コレシコレ」で太夫と同時にキメルのですが、この辺の節付は醜女のお鹿が大きなお尻をふりながら出て来るすがたがみすみす表れてゐて実に結構に出来て居ります。
△「手をもぎはなし」の「イロ」は手厚く、一ぱいの「間」をもつて弾きます。つまりもぎはなす「間」がなければいけないのです。
△「身不肖なれども福岡貢」は大切な詞であることはいふに及ばぬことですが、きばりすぎると貢が気違ひのやうになつたり、大時代になつたりしますから、その辺の加減を心得ねばなりません。
△「これがほんの伊勢乞食じや」は普通ぬかします。
△「お紺が膝を仮枕」から「脛ふんぞらす」の次の「合の手」は時代で十分手厚く、シツカリ畳み込んで弾きます。
△「涙まぎらす」の次に咳があつて、一寸カハツテ「煙草さえシヤン」と受ける撥は出来る限り薄ツペらい撥でなければいけません。「トテン」や「ジヤラン」では品物になりません。かういふところが勉強で、「シヤン」と薄い撥で弾いて、その音が小屋の隅々まで聞えなければいけないので、つまり撥遣ひの修行です。
△喜助の「お預り申した、お腰のもの」は切つて鋭い息でいひます。
△岩次とお紺の遣り取りの「ナニこれか、アイ、コリヤ大切な――」を語り活かすのは全く息一つです。
△「アイ/\合点も――」のお紺の引込みは大難所で、「うれしさこはさ」と語つて「チン」と残し、カハツテ息で「胴ぶるい」を弾き、次の「合の手」も息と足取が大切で、「アシヲフミイシメ、ダンバシゴ、ニカイイヘ」、「ヨウ」と掛声を入れて模様で「フシ落」まで持つて行くのですが、こゝのすがたを弾き表すには、中々の修行を要します。
△万野の追駈はワザで十分面白くやり[。-]「声は先――」から直ります。
△「又引返す福岡貢」から、お紺の出まで、所謂十人斬の間は、それこそほんとうに油断も隙もなりません。時に取つての些細な間違ひは許されても、息、間、撥が唯の一つでも死んではもう駄目です。そこで、「又引返す福岡貢、合、取違へたる脇差の身は正真の下坂とも知らず知らねば気もそゞろ、門の戸引明け内に入り、誰ぞいぬか、喜助々々、万野はおらぬかと見廻す折しも」の間に三味線は、まず貢の引返す心組と足取、戸を明けて一度奥までズーツと入る容姿、誰もゐないがらんとした油屋の店の情景、貢が辺りを見廻す容姿、あせる気持などを弾き表はして行かねばなりません。
△万野を殺すのは十人斬の最初で、勿論貢は最初から十人も人殺しをする積りはないのが、せつぱ詰つて手を下して、それがきつかけで心にもない十人斬をしてしまふのですから、その気持を「南無三手が廻つたツ、カツ、ツン。もう百年目――」に語り表さねばなりません。三味線も一ぱいの「間」を堪へて「ツン」を手厚く弾きます。
△「折しも奥より北六岩次――」は一寸気を替へて稍普通に運び、お鹿の「ヤア貢さん」の一語がもう人殺しを知つたやうな詞つきになり勝ちですが、これはいけません。こゝは何気なくいつて、カハツテ「アレ人殺し」と叫ぶのです。
△「コリヤさせぬわと北六岩次――」以下は「常間」で運び、「奥庭さして、ジヤジヤン、/\、ジヤン、/\」の撥遣ひと「間」は出来るだけ烈しくなくてはいけません。それから「タヽキ」でパツと気が一転して、模様に心掛け、「はいまわる――」の産字に「大落し」が「裏」でつけてあります。こゝをお稽古して頂いたときに、清水町の師匠が『大落し』と仰つしやいましたが、一度でその意味がわからず、「えゝ」と伺ふと、「『大落し』を弾いたらえゝのやがな」といはれて、改めて譜を探つてみると、成程「大落し」が「裏」でつけてあるのです。私が「アツ、ほんに恐れいりました」と平伏するのを師匠はにこ/\しながら御覧になつてゐました。この節付などでも「大落し」といふことをいはれてもわからぬ位、すつかり姿が変つてつけてあるのが普通ではとても出来ぬことです。それに、「る」の産字を太夫が音を遣つて多少ねばつて語り、尻を詰めるとその息を取つて「ツン/\/\」を猛烈に烈しく弾き切りますから、その位取がまた何共いへぬ面白くなるわけです。文章からいつても逃げる方と追駈る方とで、烈しく弾かねば太夫が「おのれお鹿」といふことが語れません。よく「――ウツ、ハツ、ツン、ツン、ツン」になり易いやうですがそれでは台なしです。
△「唐竹割」は全く文章の如く烈しさ唯一つで、「テヽントンツトン」と受け、一度棹をする位の「間」をおいて「合の手」にかゝります。
△「起番男仲居下女」は太夫も三味線も語り且弾き分けねばなりません。即ち起番男はハツて、仲居は色気を持ち、下女はげすつぽくやります。
△「三人足わな/\、ヤレ人殺し/\」は太夫と三味線がつかぬやう注意せねばなりません。
△「水もたまらず斬りツ、テヽンツン落す、ツレ[ン]」と烈しい気合で弾きそして合の手からカハツて「シヤリシヤンリン――」の同じ手は前よりもかすめて弾きます。この「水もたまらず――」の気合をお稽古のときやかましくいはれました。
△「いふ間もなく片足丁と斬り放せば」は一気に運び、「片足立に、一二、三よろ/\」はちんばで歩く足取がつけてありますからそこによく注意をせねばなりません。
△泊り客の「朝桜」は音(オン)の落所に注意せねばなりません。二をハナシタところへ落ちると、「薄墨」になりますから、少しニジラさねばなりません。
これから合方女郎の追掛けの段取は実に結構に出来てゐまして、「――追ふて行くツトン、トン/\/\」から自然にカハツて次の合の手は」[「]越後獅子」から取つてあるのです。これも「越後獅子」といふことは一寸気のつかぬことで、清水町の師匠が中国筋へ旅に出られましたとき、尾道で「竹半」といふ料理兼旅館に泊つて居られ、その附近の色掛で小娘が弾いてゐたのをお聞きになつてふと思ひつかれたのです。「竹半」は今は名前も場所も変つてゐますが、やはりその筋の人がやつてゐます。
△合方女郎の詞の間のメリヤスもこの時に出来たもので、同じく「竹半」の部屋の地口行灯に落書してあつた当時流行の「お前まち/\蚊屋のそと蚊[、]にくはれ、七つの鐘の鳴るまでもこちやかまやせぬ」を取入れられたのです。この合方女郎の条は澱みのないサラツとした足取の中に一種の模様がなくてはいけません。
△お紺の出はその容姿を大切に弾き、それから奥は大体普通の義太夫節になりますから一通り注意して行けばやれます。
「琴責」は清水町の師匠の連弾きを度々させて頂きました。彦六座では源吉(後の三代目団平)さんがツレ弾きで、私がツレ弾きと三曲を勤めましたし、旅の中で源吉さんのゐないときは、ずつと私がツレ弾きをさせて頂きました。
この場は「壇浦兜軍記」の三の口で、書卸しは竹本大和太夫さんださうですが、後に初代駒太夫さんが語られて評判よく、「駒太夫場」としてやりますが、清水町の師匠は、これを「景事の風」でやらねばいかん、と仰言つてゐました。ですから「二の上」の音を大切に遣はねばなりません。
そこで、枕の「鳧の脛短かしと雖も」を、よく「カーモーヲノハギ」と語る人がありますが、これはいけません。「カモヲーヲノ、ハギ」と一の絃をはじいた音に響くやうに、字を詰めて語らねばなりません。そして、往々「ノハギ」になりやすいのですが、これを注意せねばなりません。それから三味線が「ツン」と強くうけると、太夫は詰めてゐた息をはいて、「短しと」をまた詰めて語つて、「雖も」を音を遣ふのです。「民を制すること」も同じで、「ターミ」ではいけません。
「厳命に従ひ」は、先代の大隅さんが無類で、その音遣ひは旭日の昇るやうでした。清水町の師匠も大隅さんに「お前の重忠は日本一や」と賞めて居られましたので、大隅さんは「わいの重忠日本一や」と大天狗でした。またそれに違ひなかつたのです。こゝは出来ても出来なくても、十分立派に音を遣ふように心懸けねばならぬところです。
それから、阿古屋の出までに、重忠、岩永、捧[榛]沢の三人の位(クライ)がちやんと語り、弾き分けられねばなりません。それは「息」と「間」と「足取」で、重忠は厳めしく、抑揚を大切に、「ノリ間」を忘れずに運び、岩永は重忠と全然「足取」を変へて烈しくひつ立てた「間」で、捧[榛]沢は「常間」でサラツと運びます。
「同席に相列ぶ」は、同じく席に、といふ意味でなく、同格の席にの意味であります。「押止り」の「止り」は「ワザ」で申します。そして、「狐とは」では太夫も三味線も、「キヨロツク間」でやり、「きよろ」はハツて、「つく」は軽く「ワザ」に逃げます。
阿古屋の出は勿論気分と「足取」をすつかり変ねばなりませんが、とかく位が低く安つぽくなり易いのです。阿古屋は傾城ですが、宮城野や夕霧とはまた別で、名にし負ふ景清程の勇士の相方で、五条坂の遊君ですから、大時代でなければいけません。よく宿場女郎程度のやうなのをきゝますが、以つての外です。そして、「気はしほれ」の次の合の手は、八文字を踏んで出てくる姿、その裾捌きを「足取」に弾き表はします。「シヤンシヤンシヤン」は「ウレイ[ヒ]」から「中ギン」ヘニジツて、出来るだけ薄い撥遣ひです。そこで「気はしほれ、筒にいけたる牡丹花の水上兼る風情なり」の文章が弾ける、といふことになるのです。考へてみると、遊女が天下の決断所へ八文字を踏んで出てくるといふのですから、実に破天荒な考へですが、そこに作の力があり、面白さもあるのだと思ひます。清水町の師匠がこゝを弾かれた時は、みす/\容姿が出て実に結構でした。私はそれを度々きかせて頂いたおかげ[+で]及ばずながらそれに倣つて弾いて居りますので、何時かも阿古屋を遣つてゐた文五郎さんが、「えゝ気持で八文字が踏めました、おゝきに」と礼をいふて来ました。この「風情なり」の「フシ落」までゞ、この段の登場人物が皆出揃つて、夫々の居所に座るので、こゝまでゞ四人の位取が定つて、各々の風格が出なければいけません。
重忠の説諭では、「さなきだに――」から「友朋輩の顔汚しなどゝ思ふてのことならんが」までが特に大切です。
「物やはらかに理を責めて――」が大性根所で、「物やはらかに」は緩かに、急転直下して「理を責めて」は強く、手厚く、三味線は撥が一つ一つ別々になつては駄目で、「ツツツトツン」と一気に手厚く弾き切ります。でないと、太夫は力が入つても「リヲセメテ」と仮名を拾い読みせねばならぬことになり、「理を責めて」といへません、そして「しかも」は十分ハツて、「ツン、トン」の「ウケ」はこれまた出来るだけ手厚いものでなければなりません。こんな所の清水町の師匠の音は実に恐ろしい音がしました、また独壇場でした。「ジヤン」と〆て「こたゆる」で太夫は十分強く押して出、「ツヽン」と弾くと、それでカハツて、「詮議の」は音を遣つて出ます。「責められふわいな」は「ウレヒ」から出ますが、三味線もこゝの「ウケ」は中々弾きにくいもので、肚一つです。
「問はれし時のその苦しさ」も同様、太夫三味線共に苦しいところです。
「とんと投出す身の覚悟」がまた容姿をよく弾かねばならぬところで、三曲は別として、こゝまで来れば後は大分楽になります。
次に三曲は、その三つの位取が困難で、楽器が変つたゞけで、位がのべたらでは三曲とはいへません。まづ琴唄は蕗組ですから、位を雄大に、「音遣ひ」が中々むづかしいものです。三味線の条は謡曲の「班女」を義太夫化したもので、胡弓の条は「相の山」で、これは元祖の義太夫さんが他流から取り入れた一節を骨子としたものです。つまり、琴と三味線と胡弓の三つ曲の位取が天、地、人の格合に相当するものです。これが弾き分けられぬと、三曲といふことになりません。この格合さえ正しく守つて居れば自然に三曲が弾けるので、我々が小細工をしなくともよいやうに古人がちやんと結構に拵らへてくれてあるもので、いつも有難いと思ひます。それが近頃では往々にして「阿古屋一曲」が多いやうです。
五条坂の物語は、「平家の御代と――」から太夫も三味線も特に「ノリ間」に気をつけて、腹でノツて、サラ/\と運び、太夫は音遣ひが大切で、その中に情が出ねばなりません。
それから胡弓の終りの「是が浮世の誠なる」の「誠なる」は丁寧にしつくり音を遣ひ納めねば文章が語れません。
清水町の師匠は「源平布引滝三段目」の『実盛物語』の段が大変お好きで、少々御機嫌の悪いときでも「実盛のお稽古を」と願出ると、「よつしや」と「――眉間尺が首――」とえらい勢でやられました。が私は芝居で師匠の「実盛物語」をきかせて頂いたことはありません。
私どもが知つてからは、彦六座で「布引」が立つても、たいてい四段目が大隅さん(三味線は清水町の師匠)でした。この四段目も清水町の師匠は実に結構で、最初の「三重」でもう驚いてしまひます。そして枕一枚、「ユリナガシ」までの位、行綱の出、「木々の梢も哀そふ峯にひゞきしさびしさを、こゝにこたふる塵塚や」の雄大さは全く口で申されません。清水町の師匠は「こゝ長門はん結構やつたで」といつて居られました。その長門太夫さんの四段目を弾いて来られたのですから結構な筈[+で]す。それから、「木の葉かきよせ摺り火打、ほくちにうつせば」で、「チエツ」といふ摺り火打の音を弾かれますが、それがほんとうに摺り火打の音のやうで、三味線でないやうでした。
奥の平家琵琶の音には始終凝つて居られましたが、その遺志をうけついで、私が芝居を休んでゐました間いろいろ考へてゐましたところ、鰻屋の「柴藤」へ稽古に行つてゐる中、そこへ出入してゐる者で一寸器用な男がゐて、それに注文して金属性の駒を造つてもらひました。それもやり直ほしをして三度目に出来上つたのですが、普通の駒の上へその駒をかけますと、従来の如く普通の駒を二つかけるよりはずつと琵琶の音に近くなります。清水町の師匠の在世中にこんなものが出来たらきつとお喜びになつたのにといつも思つてゐます。この駒は同じものを三つ拵らへ、今の清六と女義太夫の素女に一つづゝやりました。
大正十三年の秋に久々で私が文楽座へ津太夫さんを弾いて出ましたときの役が「布四」でしたので、丁度幸ひにこの駒を舞台で使ひました。その後下へ旅に行つたとき、広島で少し日がありましたので、こんな駒が出来上つたのは弁天様(琵琶の神様)のお授けものだと思ひ、その御礼に厳島神社へお詣りして、当時弾いてゐた今の大隅太夫を連れて、「布四」の琵琶の条りを奉納しました。勿論一般の参詣者は廻廊より中へ入れず、神主さんや巫子さんが沢山竝んで、神前の御神楽殿で勤めたのですが、何しろ場所が場所でしたから、実によい気持でした。そのときの御礼に神社から頂いた大杓子は今でも宅にあります。
「中将姫雪責」は越路(後の摂津大掾)さんの得意の語り物であつたゞけに、越路さんを弾いて居られた頃、清水町の師匠はこの段には随分凝つて居られます。その揚句、「説教」の条を「二上り」に付けかへられたのですが、「――中将姫七日七夜――」から上つて、「息もたえだえ」で本調子になるのです。ところが、京都の興行のとき、建仁寺町の友治郎(五代目)さんがこれをきいて、「新作はいかん、『二上り』の説教はどうかと思ふ」と評をされましたが、清水町の師匠は、「『振袖始』の稲田姫の出は『二上り』の説教やが、あれはどうや」といはれ、新作でなく、ちやんと昔にあつたものでしたから、建仁寺町は一言もなかつたといふこ[+と]です。そして、「もとの節付を見たら『二上り』になるものかならんものかゞわかるがな」といつて居られました。今でも私達彦六座出のものは多く「二上り」の説教で弾きますが、太夫の音遣ひが陰気ですから、三味線は「二上り」にして派手[+に]して弾いた方が位取が面白くなつて、実に結構なものになります。
当時は、清水町の師匠の反対派もあり、いろいろ節付を変へられるのに対し、「あんなものは義太夫節を破壊するものだ」などと勿体ないことをいふものもありましたが、皆義太夫節の真髄を掴んでゐない人なのでせう。すでに一般評が「結構だが、よくわからん」といふのでした。現今でも、殊に彦六座系の芝居が跡を絶てゐる折から、我々が師匠のお形見の足取などを弾くと、新案のやうにいはれます。とにかく、清水町の師匠の行き方は、同じ外題でありながら、むづかしい、やりにくひ方で、余程深く注意をしないと辿れぬものですから、普通ではどうしてもやりよい方ですませたくなるのですが、それでは文章の意味が弾き切れん場合があるのです。今日では義太夫は文楽座一つぎりになりましたので、芸人は文楽風を学ばうと、彦六風を慕はうと勝手ですが、我々にすると、苦しいからうが清水町の師匠の残された風を学んでほしいのは申すに及ばぬことであります。
いくら名人でも口にされること全部が全部結構な芸談といふわけではありません。清水町の師匠のお話をきかせて頂けるのはたいてい晩酌のときで、師匠のお酒は普通一本、多いときで二本で、お肴はちよつとしたもの二三品で、お話がはづんで長引いたときはたいがい海苔になりました。そんなときは一寸吃られ、一度持ち上げられたお猪口が、中途からまたお膳へ逆戻りするのが例でしたから、短いときで二三時間はかゝりました。この夜のお酒のお世話、お燗やお酌は皆我々がよつてするのですが、お肴に何か一寸見つくろつて変つたものを造つて置い[つ-]て出すと、とてもお喜びになつて、「おいしい、/\」と召上りました。さて師匠のお話ですが、最初はたいていお大師さんがどうとやら、聖天さんがなんとやらといふ風なお話ばかりで、こつちはそんなことはどうでもよいので、早く芸のお話が出ないかとそればかり思つてゐるのですが、その中にふと「お釈迦さんがどうとかした」と出ると、その端をすぐとらまヘて、「釈迦如来誕生会」のことを切り出しますと、「あの道行の『檀特山』の段切の手が『ヒバリ』といふ手で、めつたにないが、それが『組打』(一の谷)の『片手綱』のところに持つて来ためるのや」といふ風になり、(この「ヒバリブシ」は清水町のお作の「良弁杉二月堂」の「良弁杉と名に高き」の所についてあります。)それから糸をたぐるやうに結構な芸のお話が出て来るのです。総て名人方は余程御機嫌のよいときでないと、向ふから芸の話をきり出されることなく、そこをこつちが何とかして引出さすのですが、それには、既に円いものとよく知つてゐるものでも、わざと「あれは四角うございましたな」と、反対をいふのです。すると「イャそやない、あれは四角やない、われは円いもので、かうかうしたものや」といふことになつて来てそれからまた次々と芸談が出て来ます。さうなればもうしめたもので、お酌をしながら明方よでお話が聞かせてもらへるのですが、これと反対に自分の知つてゐる通り、円いものを円いといつてしまつては、「そや」と一言だけで終つてしまつて後も何も続きません。
その外日常でも、思ひがけないやうなところに芸に関したかんぢんのつぼがあることがあります。それをすかさすずらなければならぬのですが、そんなのはお話し願ひますと頼んで出るものでなく、ふつとした拍子に出るのですから、それを採るのには何としても又ものであらうが、何であらうが清水町へ入浸つて、始終様子を伺つてゐなければなりません。悪く譬へれば盗人が他人の懐をねらつてゐるやうなものですが、中々苦心もし、そのために無駄な時も費します。それに思ひついたらすぐ走つて行つてゞもきいて置くもので、私は一つ、いつかはきかうと思ひつゝ、終にそのまゝになつてしまつて、今だにわからず終ひ、えらいことをしたと思つてゐることがあります。それは「国姓爺三段目、獅子ケ城」で前半を西風、後半を東風で語ることになつてゐるのですが、さうやることにどういふ意味があるのか、といふことです。こんなことは清水町の師匠でなければ御存じのないことです。
今の人はかういふ苦しみを少しもしてゐないやうです。目当になるやうな者がないのかも知れませんが、附き切りといふことがありませんから、たまに話をきいても、その中の何処がつぼなのか、それをよう採らないやうです。
私は本名を浅野楠之助と申しまして、明治二年六月十七日大阪島の内坂町天神さんの表門前で生れました。この天神さんは、今は廃社になつてしまつてありませんが、当時は有名な古社で、ずつと昔はお寺であ[+つ]たさうです。一説に、御神体として竹田からくりの菅丞亟の首(かしら)をお祠りしたものときいてゐます。
父は元は商人で、安治川で柏屋といふ荷問屋をしてゐましたが、後に身をもち崩して当時大阪の劇壇の大御所であつた尾上多見蔵の床山になりました。もともと器用な人でしたから、床山になつてからも腕がよく、門人も出来、後に市川右団治(後の斎入)附の有名な床山のチンパの吉(俗に「チン吉」で通つてゐました)などは父の門人でした。母は実家の姓を中川といひ、中川蘆月などの親類で、島の内堺筋で薬屋をしてゐました。
私は生来音曲が好きで、八つのとき母へは内証で、当時骨屋町に居られた地唄の師匠徳永里朝さんのところへ入門しました。手ほどきはお定りの「雲にかけ橋」、「黒髪」のやうなもので、一年程徳永さんのところへ通ひ、その間琴や胡弓を稽古しましたが、その内徳永さんが「いつそ芸で身を立てたら」とすゝめてくれましたので、母とも相談し、誰のつてか知りませんが、二代目鶴沢吉左衛門さんのところへ弟子入りをして、鶴沢吉松と名をつけてもらひました。これは九つの春(明治十年)のことでした。
これより先、明治八年私が七つのときに父に死に別れ、阿部野でお葬式をしたときのことはよく憶えてゐます。当時の阿部野の墓地は草ぼう/\の野原で、どこに石碑があるのかわからず、名々高い竿竹を立てゝその先に目印をしてありました。その頃は山菓子はなく、会葬者にはお茶処で、「仕上げ」といつてお酒付で五品位の食事を供養しました。また夏なれば行水程度の風呂もありましたが、これで一人前が三十銭でしたからいかに物価が安かつたかゞわかります。もつとも香奠にしても当時我々程度の家で十銭が普通、何か祝事なれば鯖か鯵が一本か、または当百(天保銭)一枚が慣ひでした。
私の初めの師匠の二代目鶴沢吉左衛門さんは、鶴沢清八(初代)さんのお弟子で、当時船場唐物町旧難波橋筋、「大平餅」の隣に住んで居られ。[、]通称「唐物町さん」で通つてゐました。
初名を新介といひ、次いて万八と改名されたのですが、性来おとなしい方で、人間は到つてよく、身のこなしが女のやうでしたので、「おやまの万八」といはれてゐました。従つて芸も綺麗な芸でした。
師匠は始終芝居へは出勤して居られず、時折竹本久太夫(三代目で、元頼母太夫)さん、竹本鳴戸太夫さん、竹本対馬太夫(二代目[+)]さんなどを弾いて居られましたが、私が入門する一寸前に、新靱さんが化物で出るについて合三味線として大江橋の席へ出て居られました。
大江橋の席は、大江橋北詰東入北側俗に鍋島の浜といつてゐたところ、今の堂ビルの裏手にあたるところにあつた小さい寄席風の小屋で、御霊の小屋は、後明治十七年から先年焼けるまで文楽座のあつたところにあつた小さい小屋で、土田の席といつてゐました。明治十一年の二月にこの土田の席で初代の古靱さんが道具方のかぢ徳に殺されたのですが、古靱さんは下ぶくれの可愛らしい顔の小男で、名人でした。
入門後しばらくして、淡路へ旅に行きました。勿論私に取つて初旅で、久太夫さんが淡路の人形芝居へ「追抱(おいだき)」に行かれ、合三味線の吉左衛門師匠のお伴をして行つたのです。当時は大阪の川口から洲本まで船で行つたのですが、淡路の座は、劇場程度のときと、ほんの小屋がけで、むしろが敷いてあるだけのやうなときとあり、出しものは「賤ケ岳七本鎗」などの陣立物が多く、大阪から買はれた久太夫さんは「宿屋」などをよく語つて居られました。あちらではこれを本太夫といひ、楽屋では若くてもなんでも、「おやつさん、おやつさん」と呼び、皆が「御苦労さま」と挨拶に来るので、中々物入りでした。その楽屋は、時によつては随分ひどい場所もあり、三味線の調子を合はせてゐると、隣で牛が「もう」とないてゐるといふやうな情景でした。
この旅興行のとき、洲本で初めて後の六代目野沢吉兵衛さんに会ひました。まだ兵三時代で、堀江の坊々でこのとき阿波へ初旅に行つたのですが、途中で帰りたいといひ出し、船の長いのを怖わがり、津太夫(法善寺)さんの弟子の、たしか津弥太夫とかいつた者が附添つて、撫養から淡路へ渡つて、洲本から大阪行の船に乗つて帰るところでした。それ以来吉兵衛さんとはずつと懇意にしてゐました。
吉左衛門師匠は明治十二年十月十六日に病気で亡くなられました。しばらくの間、日本橋毘沙門天西門に硝子玉製造屋をして居られた親戚の離れに出養生して居られそこでなくなられました。その頃辺りはずつと畠でした。まだ四十余りだつたと思ひます。俗名は辻新次郎、法名鶴山霊翁信士と申し、お墓は当時出来ませんでしたので、先年私が高野山に建てました。師匠がなくなられたので、私はすぐ二代目勝七さんのところへ入門しました。私の吉松時代はほんの下廻り、手伝ひでしたから、吉松で出てゐる番付はないと思ひます。
私が物心ついてから吉左衛門師匠の間にゐた頃の大阪の風景は実にのんびりしてゐました。殊に吉左衛門師のお宅が唐物町でした関係上、色々の用事で私は船場辺を歩き廻ることが多く、大阪中で船場風景はまた格別奥床しいものでした。
大阪の上流家庭はたいてい船場にかたまつてゐて、言葉つきでも大阪弁の中で一種特別な船場風があり、その中でも南船場と北船場とは少し違つてゐました。道を歩いてゐる人のなりも格別で、大どころの腰元は小さい筥ぶんこに結び、朔日十五日の主家への御挨拶のときは必ず繕つた足袋をはいてゐました。つまり身分相応の慎みを表してゐるところなのですが、こんなことは誠に奥床しい風景で、近頃の若い者などがお手本にするとよいことです。乳母はまた違つた風俗で、お寮人さんは皆両輪に結つて居られました。
それから大家の丁稚さんの風俗がまたよいもので、勿論木綿の着物に小倉の帯、前掛は中以下で、竹の皮の雪駄で、花尾はなめし(かけ出しはりんぼでした)でチャリ/\いはせて歩いてゐました。大丸の小僧さんなどおかつぱであつたことをよく憶えてゐます。当時はまだ男の髪結がゐた頃で、どこそこの筋はどの髪結と銘々縄張りがあつて、丁稚が「かみさん(かみゆひさんの上方音便)どこぞにゐてやおへんか」と呼びに歩くのです。すると髪結の来てゐる家から返事があつて、注文をするのですが、その頃「かみさんどこぞにゐてやおへんか、いてゝやおへん、来てゝだす」といふ歌のやうなものが流行しました。私も師匠の髪結さんを呼んで歩いたことがありました。
夏になると丁稚の風俗はかぶり笠にきびらの甚兵衛に変り、これも中々趣のあるものでした。そして中北船場の上流家庭では用水桶の隣のはしりに台子を置き、炭団で湯を沸かして中に三味湯(さんみとう)が入れてありました。三味湯は一寸にがみのある京都の琵琶湯のやうなもので、暑気払ひとしてありました。それを道を歩いてゐる人が「頂きます」と軽く挨拶して飲んで行きました。この外麦茶か砂糖水のところもありました。夜になるとどこの橋でも細い牀机をならべて、かきもち茶、昆布茶、砂糖水、くず湯などの店が出ました。当時は勿論喫茶店のやうなものはない時代ですから、これが中々よくはやり、天神橋など盛んなものでした。沸騰水、つまり今のラムネが出たのは大分後のことでした。
夏祭は神様によつて夫々違ひますが、祭になると「けた」といつて、一かどの旦那方が門附の真似をしました。「今日は一つけたに行こか」といつて、義太夫なれば置手拭で師匠を連れて出掛け、祭の飾附をして商売を休んでゐる店から「所望々々」と声がかゝつて一くさりづゝ語つて歩くのです。また俄もあつて、これは「にわか」と書いた手触[燭]を持つて、到つてむづかしい顔をして歩いてゐました。「所望々々」の声がかゝると一人俄をするのですが、これは中々いきな人がしてゐました。
我々商売人の有様の変つたことは申すまでもありませんが、素人義太夫の模様も、今と較べると随分変りました。
私共の修行時代には玄人裸足の素義の旦那衆が沢山居られて、語り物によつては玄人が旦那方のところへお稽古に行つたものです。私の憶えてゐる方では、ごく晩年ですが大馬斎、初代古靱さんを贔負[屓]にして居られた北久宝寺町難波橋東の漆器商の桝文といふ方などが当時の素義の大ドツサリでした。同じく晩年の弥松軒、小清水も知つてゐます。このお二人はチヤリ語りで、「宝引」(「一の谷嫩軍話」三の中)、「三国関所」などが得意でした。それから鹿の子、これは初代と二代目とあつて、初代は心斎橋久太郎町南の鹿子商で私の師匠の吉左衛門さんの御連中、二代目は久宝寺町板屋橋の硝子屋で勝右衛門(四代目で現綱造の父)さんの御連中で、大掾さんのやうなよい声でした。外に吉左衛門師匠の連中に、堺筋唐物町北の紙屋で蟻松、難波橋唐物町角の糸屋で、かいこのお二人をよく憶えてゐます。有名な砂子、貴鳳、貴雀の三人兄弟は松太郎さんの御連中で、この外唐物町三休橋の煙草入屋で千倉、西横堀の多々忠といふ材木商で閑多、道修町の薬屋で勝好といふやうな方がありました。
このやうな錚々たる方が沢山居られましたから浄瑠璃の会の盛んなことも亦大したもので、年に一度の大会は市中の一流の料亭で開かれ、勿論宵から夜通しで、このときの旦那衆の色々の御祝儀が中々大したもので、昔から義太夫で身代を崩した方が沢山あるのは大会の経費のためでした。平常は順会といふのが中々盛んにあつて、これは旦那衆の知り合ひのお家で催され、五人位で、ドツサリが一段丸ごかし、モタレは顔がよければ一段語りました。そしてこのときは露払ひを勤める旦那が箱屋の役をするのが定りで、燭台を用意したり、お湯を沸かしたりして、つまりお素人でも修行をされたのです。それでドツサリがよい顔の旦那であると、「わしは誰某のかさで露払いを勤て来たのや」と一つの誇りにしたものです。この中で芸はよいが経済的に続かないものが化物として太夫になつたので、新靱さんなどその類で、八代目の染太夫さんも二ッ井戸の酒屋の小僧から素人義太夫になり、本職になられたのだと聞いてゐます。順会では会場の家から師匠へ絃代と御飯とが出て、これをのせといひました。当時の主な師匠は、豊造さんを頭として、吉左衛門師、道修町の一平さん、ちんばの吉三郎さん、松太郎さん、龍助さん、淀屋橋の布団屋の兵吉さんなどでした。たいてい店の間に屏風をひいて、外側はランプですが、中側は息がかゝつても消えぬやうに行燈で、その前に家族をはじめ親類のお好者や番頭手代などがならんで静かにきゝ、暑い時は表の格子を外し、中はすつかり見え、道行く人も聞けるやうにしてあつて、好者は「聞かせて頂きます」と番頭か手代に一寸挨拶して聞くのですが、総体の雰囲気が誠に上品なものでした。
師匠の吉左衛門さんが亡くなられましたので、私はすぐ二代目鶴沢勝七さんのところへ入門することになりました。口次ぎは道具方の中野源松でした。しばらく内弟子のやうにしてゐましたが、「やつぱり芝居へ出んといかん」との師匠や源松のすゝめで、師匠の出て居られる松島文楽座へ出ることになり、明治十五年六月頃から友松で番附に名前が出たと思ひます。この友松といふ名は勝七師匠の実名が友太郎で、その一字を頂き吉松の松を残したのです。
松島の文楽座は明治五年の一月に大阪府の命令で博労町の稲荷境内から引越して来たもので、花園橋の東詰から桜筋の角までが文楽座の敷地になつてゐて、植村さんの帳場は桜筋の角にありました。今の八千代座がその跡に建つてゐるわけです。文楽座が松島から御霊社内へ移つたのが明治十七年の九月ですから私が知つてゐる松島は極く晩年ですが、今生きてゐるもので松島文楽座を知つてゐるのは私の外は文五郎さん一人です。新左衛門や栄三さんは芝居が違ひましたから、知らないと思ひます。先年映画の「浪花女」を作られるとき、監督さんが松島文楽座の附近のことをおたずねでしたが、今と較べると大変な変りやうです。口では上手く説明出来ず、写真は残つてゐず困りましたが、とにかく楽屋の向ふは川(尻無川の上流)を隔て向ふ岸の上手には松の木が竝んで生え、その向ふは一面の野原で、右手に茨住吉さんの森がぽつんとあるだけで正面は天保山まで何もなく、晴れた日には大阪湾の彼方に淡路島が見えました。また向ふ岸の上手では、雨でない限り毎日昼網の市が立ちました。下の方から漁舟がのぼつて来て、笛を吹いて商人に知らすと小屋で取引が行はれました。今から考へるとまるで嘘のやうです。それから我々が楽屋入りのときはたいてい千代崎橋を渡つて楽屋入りをするのですが、これが開閉橋で運の悪いときは通行止を喰つて、松島橋へ廻れば大分距離があり、下へ廻ればそれ以上遠く、どうかするとトチルことがありました。
小屋は人形浄瑠璃の小屋としてとてもよい小屋で、天井は張つてなく、床の板が薄く、下は大分深く掘り下げてあつたに違ひなく、よく籠りました。私の知つてゐる小屋では恐らく一番よかつたやうに思ひます。
勝七師匠は盲人の四代目住太夫さんを弾いて居られ、清水町の師匠は櫓下の越路(後の摂津大椽[掾])さんの合三味線でした。そして三階の川添の楽屋に清水町の師匠、住さん、越路さん、実(後に長登)さんが居られましたが、よく清水町の師匠と住さんとは非常によくお話が合つてゐるやうでした。「あのときの長門はんは結構だしたな」とか、「内匠(六代目)さんは何々をうまいこと語りはりましたな」とか、とてもお話がはづむことがありました(これは彦六座の楽屋でも同じことでした)。後にこのお部屋に「かぶら」と緯名のあつた茶瓶の時太夫さんが入つて来られました。この方はもと文駄といふよい三味線弾きでしたのが業を替へて出て居られたのですが、どういふものか皆に嫌はれて、皆が意地悪をして、それが段々嵩じて来ましたので、一緒の部屋に居られたのを越路さんが呼び入れられたのです。
そこで私が初めて文楽座へ行つたのが、明治十五年の六月で、清水町の師匠は越路さんの「熊谷陣屋」を弾いて居られました。私が初めて清水町の師匠の芸をきかせて頂いたのがこの「陣屋」で、その三味線の大きくて、えらくて、(傑出してゐて)足取が外の人と全然違ふのにびつくりしてしまひました。それから「宿屋」、「紙治炬燵」、「長局」など次々ときかせて頂き、芸はこれやないといかん、とぞつこん思ひ込んでしまひました。
殊に「炬燵」は印象が深く、もつとも彦六座になつてからも度々きかせて頂き、またお稽古も願ひ、後年私も及ばずながら勤めましたが、とてもえらいものです。「合邦」や「太十」の方がまだらくです。それは枕から、段切まで普道[通]の三味線を弾けばよいところがなく、おさんのクドキ、質入れの間にも大分仕事があります。そして奥へ行く程気を遣はねばなりませんが、殺し場の息込と手厚さはこの段に限らず清水町の師匠の独壇場です。それからこのやうなものになると、よく語る小手先の利く太夫程三味線弾はえらいので、どうしても語りすぎますからそれをグツと喰ひ止めるのが三味線弾の役目で、それに大分力を要しますが、これはお客様方にわからぬことです。またわかるやうではいけません。こんなところが「炬燵」ひいては世話物のえらいところです。
「長局」は越路さんおと[とお]二人でよくやつて居られました。これも後年大隅さんで度々きかせて頂き[さ-]ましたが、枕の「と息つき、ツン」は皆キメて弾きますが、清水町の師匠のはカスメて弾いて居られました。文章の意味からいへば当然かうでなくてはいけませんが、余程芸力がないと撥が死にます。キメた方が太夫も三味線もやりよいことは申すまでもありません。それから書置の条の「冷泉」、これが清水町の師匠の足取と、越路さんや大隅さんの音遣ひとの位取が何ともいへませんでした。「成程これが『冷泉』といふものかいな」と思ひながら聞かせて頂いてゐました。
翌十六年の夏、「日本振袖始」が出て、「大蛇退治」の立三味線が清治郎(後の五代目鶴沢勝鳳)さんで、私もその豆くひに出てゐましたが、人形との「間」が合はず、紋十郎さんの猩々の足が踏めないのを、清水町の師匠が出て来られて、一寸膝をたゝかれたら、一ぺんに合つたので、びつくりしたことがありました。またその秋でしたが、「鬼一」が立つて、大切の「五条橋」の文章を一寸補足して、弁慶が七ツ道具で立合ひするやうに清水町さんが節付されたことがありました。
その頃冬になると、寒稽古をやりました。皆舞台裏へ出、太夫は立つたまゝで西の方を向いて声の鍛錬をし、我々はござを敷いて腕固めをしました。そして手がかぢかんで来ると、桶に汲んでゐる水(井戸水)の中へ手を突込んで暖めました。三味線の方では又造(後の勝鳳)さん、ざこばの清七(四代目)さんの息子さんの作治郎さんなどが先頭に立つて居られました。これがすんでも、「序切」までは楽屋に火が入りませんから、「序切」になるのを待つて、裏の道具部屋の隣にある豆腐屋で豆腐を買つて来て、火鉢にかけて、名々家から持参した鰹節を入れて火鉢にかけて喰べましたが、この味は今でも忘れられません。また花園橋の向ひの土手の上にうどん屋があつて、当時うどんは八厘でした。お客様の御飯は、芝居前に河合といふ仕出しがあつて、梅わん、小鉢、御飯、お漬物で三十銭、これはとても上等で美味しく、しかし当時としては高いものでした。その頃相乗車が南から松島まで三銭でしたが、それでも高いといつて皆歩きました。清水町の師匠なども、毎日徒歩で通われ、道順は清水町から堀江の浜通りを西へ行き、千代崎橋を渡られました。
それから当時特別の慣ひとして弁当取りといふのがありました。これはだいたいは人形遣ひ専属のもので、人形遣ひは一日中芝居にゐて、芝居で食事をしますから、各の家へ弁当を取りに廻る役なのです。その係は三人位ゐて、お給金は勘定場から出るのですが、名々心附を出し、立者衆で一芝居五十銭、下廻りで二十銭程度でした。我々もこれをよく利用したもので、弁当に限らず、傘だの、いろいろのものを事づけたりしました。楽屋風呂もほんとうは人形遣ひ専用のもので、立者は別として、中以下の者が無断で風呂へ入ると、人形遣ひから叱られたものです。越路さんや住さんでも役をすまされてからは身体を拭ふだけで、芝居のお風呂へはめつたに入られませんでした。
当時私は鶴沢国三郎と仲よくしてゐました。国三郎は東京の播磨太夫(四代目)さんの息子で、越路さんの家へ修行に来てゐたもので、後に東京へ帰つて紋左衛門になりました。よい芸でしたが、酒呑みでした。
明治十六年の一月元旦初日で、文楽一座が京都の四条北側の大芝居へかゝり、「忠臣蔵」の通しで長登太夫さんが「大序」と「茶屋場」の由良之助、越路(二代目)さんがおかると九段目、住(四代目)さんが六ツ目と「茶屋場」の力弥、染(八代目)さんが四段目と平右衛門といふ役割でした。このとき私はまだ番附にも出てゐませんでしたが、破格で長登太夫さんの「大序」を弾かせていただきました。勝七師匠からは勿論、清水町の師匠や松葉屋(五代目広助)さんから「お前は幸せ者やで、櫓下を弾かせてもらふのや」といはれました。番附に大序鶴ケ岡の段、竹本長登太夫と一行に出てゐましたが、かうなると九段目と同格になるのた[だ]さうです。私は朝早くから床の掃除をして、それから縄手の南の、名前は忘れましたが、足袋屋の離れに泊つて居られた長登太夫さんを迎ひに行き、本を持つてお伴をして芝居へ入つたのですが、何分早朝のことですからお客は三四人程より来てゐませんでしたが、それでも長登太夫さんはきちつと勤められました。
このとき私は芝居の西隣の煎餅屋に、住さんや勝七師匠と一緒に泊つてゐました。清水町の師匠は縄手の何とかいふ櫛屋の離れに居られました。京都は興行のぞうよが到つて悪かつたところでしたから、皆このやうに夫々知り合の家に泊つて、食事は外から取つてゐました。
長登太夫さんは当時第一の古顔で、櫓下に座つて居られました。非常に上品な方で、従つて浄瑠璃も上品で、「茶層[屋]場」の由良之助など結構でした。お住居は新町土橋で、義太夫の本書の「かつら」と同じならびの近くでした。
明治十四年の頃と思ひます。太郎助橋の住太夫さん、新靱さん、勝七師匠などで四国へ巡業があつて私も師匠のお伴をしました。四国はだいたい義太夫の盛んなところですが中でも土佐は一番盛んで、料理屋などで、「一寸隣へ行つて三味線借つといで」といつても、それは皆義太夫の三味線で、長唄の三味線は殆んど用意がなく、太悼は品のよしあしは別として、大ていの家に備へてあつた位でした。ところで当時高知に江戸昇といふ人がゐまして、元は江戸の人だつたさうですが、早くに高知へ来て料理屋を開いてゐたのですが、それにおしなさんといふ娘があつて、別に女太夫にする目的ではなかつたのですが、義太夫を習はせてあつたのです。そこへ住さんの一行が行き合せて、江戸昇さんにもいろいろ厄介になつて、親しみが加はつたのが縁で、おしなさんは勝七師匠のところへ弟子入りすることになつたのです。そして間もなく大阪へ修行に登つて来ましたので、住さんと勝七さんの一字づゝを取つて住勝と名乗り、しばらく大阪に滞在して土佐へ帰りました。
その後江戸昇が土佐へ今度は越路太夫(後の摂津大掾)団平(清水町)を呼ばうと計画したのです。越路さんは勿論ずつと以前にも土佐へ行かれたのでせうが、そう度々やすやすと越路太夫が来るものか、といふのが、当時の土地の旦那衆の声だつたのです。そこで江戸昇は娘の住勝の関係もありますから、その筋から渡りをつければ越路団平は呼べるだらう、万事自分に任せてくれ、と大阪へ登つて勝七師匠の宅に泊つて、一部始終を勝七さんに咄したのです。勝七師匠は快く引受けて、越路さんに取次がれると、その返事が「参ることは承知致しましたが、何時といふことは只今申されません。文楽の興行の暇なときがありましたら必ず伺ひます」と、かうでした。江戸昇はその返事をもらつて喜んで郷里へ帰り、彼地でこのことを触れて自分の顔を一段とよくしたのでせう。一方越路さんの方は右の返事をしたものゝ実際文楽の興行の余暇がなかつたので、そのまゝにしてあつたのです。ところが高知では江戸昇の触れ込みで、今にも越路一行が来るといふ一ぱいの評判で皆が首を長くして待つてゐたのですが、何時までたつても来る筈はなく、とう/\その年は暮れました。さうなると江戸昇はよい加減なことをいつたのだといふことになつて、江戸昇の立場が悪くなつて来たのです。そこで江戸昇は再び大阪へ来て、二度目の交渉をしたのですが、何分初めの返事が、たゞ行く、といふだけで、月日を約束したことでなかつたので、「文楽の余暇がございませんでしたので」といふ返事に対しては江戸昇もなんともいひやうがなく、泣き寝入りで郷里へ帰りましたが、根が男気を重んずる江戸ッ児ですから遂に面晴(めんぱれ)に腹を切つて死んだのです。そのことが大阪の我々のところへ伝はつて来たときの関係者の驚きは一通りではなく、「土佐は人の気の荒いところやさかい、殺しに来よるかも知れん」と話し合つてゐましたが、中でも最初に仲介に入つた勝七師匠は真青になつてふるえ上りました。もともと師匠は到つて憶病者の、丁度「堀川」の与次郎のやうな方でしたから、そのときの有様は今だに目に残つてゐますが、ほんとうに滑稽な位でした。
ところでこの話を清水町の師匠が聞かれて、それは抛つて置けん、と植村(文楽座主)さんヘ一部始終を話し、お暇をもらつて、改めて江戸昇の追善興行といふ名目で土佐へ行くことになつたのですが、始めに話をしたのですから勝七師匠は当然一行の中に加らないといけない、といふのに恐ろしがつてどうしても行くのはいやだといつて居られましたが、遂に死を決して、出発には水盃までして行かれました。私はそのときお伴をする積りでゐましたら、「万一の場合は逃げられるだけ逃げんならんさかい、お前らゐたら足手纏ひや」といふことでしたので、お留守番をしていました。
さて土佐では土地の顔役一人の命をかけた位の大事件でしたが、もともと待ち兼ねてゐたことでもあり、総ての事情も判明し、その江戸昇の追善の為に越路団平が無報酬で来るといふので、以前の幾層倍もの人気が立ち、一行の想像とはうつて変つた優遇を受けられたさうです。そして初手向には娘の住勝が白装束で勤め、これを勝七師匠が弾き、土地のお素人が語られた後、越路さんが団平師匠の絃で語られたのですが、三日間の予定のところ一日日延べて四日打ち、越路さんは「先代萩御殿」、「堀川猿廻し」、「中将姫雪責」、「野崎村」であつたさうです。そして帰りには皆お土産を沢山もらつて帰られ、勝七師匠は「こんなんやつたらお前も連れて行つたらよかつた」といつて居られました。これが明治十六年の夏のことです。住勝さんは私も心安くしてゐましたが、一寸小器用に語りました。まだ高知にゐるさうで、もうよいお婆さんになつてゐる筈です。
| 二代目 | 豊沢 団平 | 清水町 | 清水町どぶ池西入北側二軒目 |
| 初代 | 鶴沢 清六 | 畳屋町又万屋 | 畳屋町三ツ寺筋南入東側(現今の「みやけ」精肉屋の北) |
| 初代 | 鶴沢 清八 | 唐物町 | 唐物町堺筋東入北側 |
| 五代目 | 豊沢 広助 | 松葉屋又博労町 | 博労町中橋西入南側 |
| 初代 | 鶴沢 豊造 | 越後町 | 新町越後町中程、稽古場は久太郎町中橋西入南側の露地 |
| 初代 | 豊沢 新左衛門 | 坂町 | 裏坂町大師堂東入二ツ目の露路 |
| 二代目 | 豊沢 大助 | 新町通筋 | 新町通筋塀の側西半町北側 |
| 二代目 | 鶴沢 勝七 | 法善寺 | 千日前法善寺境内 |
| 二代目 | 鶴沢 吉左衛門 | 唐物町 | 唐物町旧難波橋筋南入 |
| 二代目 | 鶴沢 叶 | 金照 | 北新地裏町 |
| 三代目 | 豊沢 広作(後の名庭絃阿弥) | 松屋町 | 松屋町筋和泉町北入東側 |
| 二代目 | 野沢 吉三郎(後の六代目吉弥) | どぶ池 | どぶ池今橋北入東側 |
| 初代 | 豊沢 新三郎 | 順慶町 | 順慶町心斎橋東入北側一間露路 |
| 初代 | 豊沢 松太郎 | 周防町 | 周防町心斎橋東入南側 |
| 二代目 | 豊沢 龍助 | 難波新地相生町西 | |
| 五代目 | 豊沢 源吉(後の三代目団平) | 法善寺西門南入塀の側露路(後に坂町) | |
| 初代 | 豊沢 仙次郎 | 松屋町広作方 | |
| 初代 | 野沢 一平 | 道修町 | 道修町淀屋橋筋西 |
初代勝七さんは、「西宮の勝七さん」といつて、元三代目の氏太夫さん(五代目春太夫の師匠)の三味線を弾いて居られたのですから余程の古顔でした。明治以前早くから大阪を見捨てゝ西宮へ隠居されたのでした。既にその当時の芸を[+う]とんじて、西宮には旦那衆も沢山居られるし、その辺りのよいお酒を呑んで、うまいものを食べて呑気に暮さうといふのですから少し贅沢過ぎます。そして名前を勝鹿斎と改めて、辰馬さんのお抱え三味線になつて居られました。こんな古い方でしたから、清水町の師匠でも松葉屋さんでもお稽古に行つて居られたといふことです。私も子供の時一度だけお使いにお宅へ行つたことがありましたが、厳格な感じで威厳がありました。挨拶をしますと、「お前何処の弟子や」と怒鳴られてゐるやうで、お土産の品を出すと、「それくれたんか、礼いふとけ」といふやうな調子で、とても怖いお師匠さんでした。丁度そのとき、浜野茂さんと申して後世東京へ出て相場で成功され、「蠣殻町の将軍」と呼ばれた方の「忠臣蔵四段目」のお稽古中で、次の間で聞かせて頂いて実に感に堪えました。後年私が上京しまして、浜野さんにお目にかゝりましたとき、このお話をしましたら、勿論先方様は御存じありませんでしたが、「あゝさうじやつたか」といつて居られました。この間も上京しましたとき(昭和十八年三月)一晩ふとこの勝七さんの「四段目」のお稽古のことを想ひ出し、あそこはあゝ弾いて居られた、あそこはあゝいふ足取やつた、と次から次へと頭に浮んで来て、興奮して情が乗つて来てとう/\夜明けの六時頃まで床の中で寝ずに「四段目」のおさらへをしてしまひました。
まづ薬師寺の品のよろしいことが今と全然違ひますが、いよいよ切腹になつてからの夫々の情といふものが無類でした。襖の向ふの諸士の詞がもう堪りません。慎んではいますが、一生懸命で涙一杯です。取次ぐ郷右衛門、判官様の答へ、めつたに叱つたりは出来ません。「尤もなる願ひなれども」に何ともいへぬ情が語れてゐました。それを承る郷右衛門の息、「聞かる通りの御意なれば一人も叶はぬ、叶はぬ」の詞を一ぱいの涙の拵へで、それでこそ、「チン、諸士は返す詞もなく一間も、ジャン、ひつそりと静まり--」の「フシ落」がほんとうに語れるのです。それから由良之助を待ち詫びる心、力弥の肚の中、ともに一ぱいですが、「ヤレ由良之助待兼ねたはやい、[+」][+「]御存生の御尊顔を拝し身に取つて何程か」の判官様と由良之助とのやりとりの息の真に迫つてゐたことゝ申したら、聞いてゐてパラ/\と涙がこぼれないものはないでせう。そして由良之助は文章にある如く、「さてこそ末世に大星が忠臣義臣の名を揚げし根ざしはかくと知られけり」の意味を語り表さねばなりません。段切は何といつても足取が結構で、「涙と共にのせ奉りしづ/\と舁きあぐれば」は如何にも大事の大事のものをそ―ッと持ちあげて運び出す足取でなければいけません。
これを勝七さんはボト/\の稽古三味線で、低い調子で語つて聞かせて居られたのですが、切腹場の情が溢れ出て、子供心に、結構やなあ、芸はこれでなくてはいかんなあ、と頭にぴーんと染込みました。
勝七さんは、初代の清六さんと仲よく、「六さん/\」と呼んで居られましたさうで、勝鹿斎になつてから、勝七の名前を然る可き人に継がせてくれと清六さんに預けて居られましたので、清六さんがお弟子の玉助さんに継がさうと、そのことを報告に清六さんの娘さんのお菊さんを西宮へ遣されました。このお菊さんは後に法善寺の津太夫さんのお内儀さんになられ、義太夫界では中々やかましい婆さんでした。お菊さんが勝七さんの前へ出て、「父申しますには、今度勝七の二代目を起すことになりましてござります」と口上を述べられますと、勝七さんは、「あゝ六さんの眼鏡に叶ふた者なら結構です、どうも御苦労さんでした。しかし、わしの名を継ぐのは一体誰や」との尋ねに、お菊さんが「うちの玉助でございます」と答へると、勝七は「わあ情ないことや」と涙をこぼされたといふ話を聞いて居ります。二代目さんは私の師匠ですが、明治前から世を見限つて隠遁されたおか方[方か]ら見ればそんなものであつたのでせう。
四代目竹本住太夫さんは私の知つてゐる太夫の中での屈指の名人であります。越路(後の摂津大掾)さん、大隅(三代目)さんに優るとも分らぬ芸でした。紀州田辺の出で、本名は竹中喜代作と申されました。幼少よりの盲人で内匠太夫(六代目、通称袋安)さんのお弟子となられ、初め田喜太夫(初代)と名乗られ、後に四代目を襲名されたのですが、これは御維新前のことゝ思ひます。太郎助橋南詰一丁南の辻南入東側の二軒目に住んで居られましたので、俗に太郎助橋の師匠と申して、私が知つてからは松島の文楽座に出て居られましたが、後に彦六座へはいられ、櫓下になられました。これは明治十七年の三月彦六座の三回目の興行からで、文楽の方で実さんの後の櫓下を人気の頂点にあつた越路さんに定めたことが主な原因と思ひます。顔からいへば住さんの方がずつと上でしたが、そこに文楽座としての興行上の政策があつたのでせう。
私が住さんに接近する機会が非常に多かつたのは外でもありません。師匠の勝七さんが長年の合三味線でしたからで、巡業のお伴をした事は度々あり、手曳きもしましたし、師匠の代役で三味線を弾かせて頂いたこともあり、住さんの方からも私を非常に可愛がつて下さいました。
その芸風を申しますと、まづ一二三の声の調つた美声で、その上に疸[痰]のあるお声で、それに腹の強いことは驚くばかりでした。また音遣ひの上手いことは当時第一と申してもよく、今だによく憶えてゐますのは、「阿波十」の『順礼歌』の「――なちのおやまにひゞくたきつせ」の条の音遣ひです。たつた十四字ですが、その間の住さんの音といふものは実に円転自在で、終ひに三味線とゝもに「ハリキリ」へ納まるのですが、私が聞かせて頂いてからかれこれ六十年、耳には残つてゐますが、さて自分でいつ[+て]みると、違ふことに気が付いてどうしても住さんの通りの音が伝へません、今だに考へてゐます。またお稽古のときなどで三味線を弾かせて頂くとき、音遣ひがあんまり円転自在なので、どこで撥を下してよいやらわからぬので弾かずにゐると、「何してんね、弾かんかいな」といはれました。清水町の師匠も住さんの音遣ひには感心して居られ、よく御簾内で開かれて「うまいこといふな」といつて居られました。
世話時代にかゝはらず、何でも立派に語られましたが、特に結構でしたのは、「大文字屋」(「紙子仕立両面鑑」)、「白石」の『二階』(「新吉原揚屋」)、「沼津」(「伊賀越」)、「市若初陣」(和田合戦三段目」)、「恋十」(「恋女房染分手綱十冊目」)、「酒屋」、「野崎」、「廿四孝四段目」、「阿波十」、「鰻谷」、「吃又」、「帯屋」などでした。
住さんの方でも清水町大信仰で、私が清水町の師匠に心を傾けてゐることをよく御存じでしたから、最初の内はそれとなく私を取り持つやうにして下さいました。そして私に「今の中に一撥でもようきいときや」といつて下さいました。またときには御親切にも私が清水町の師匠にお稽古して頂いたものゝおさらへに弾き合せをして下さつたこともありました。前にも申した通り、住さんは勝七師匠の相手太夫さんですから私は始終近付くことが多く、住き[さ]んと清水町の師匠は、合部屋に居られましたからその辺が都合よく行つたわけです。私が清水町の師匠に近付けたのは外のことのためもありますが、住さんのお蔭も大いにあり、私に取つて忘れられぬ大恩人です。ですから宅の神棚には清水町の師匠、勝七師匠と共に住さんをお祀りして毎日拝んで居ります。
住さんは盲人の例に漏れず頭が敏く、東京猿若町文楽座の手打のときの一埓は後でお話致しますが、床本の暗記などもたいてい二度目には殆んど間違ひなく憶えられました。それについて一度驚いたことは、私が松島の文楽座へ入つて間もない頃(明治十六年一月)、「信仰記」が立つて、住さんのお役は『爪先鼠』でしたが、その興行中ある日どなた様か忘れましたが上つ方の薨去があつて、急に音曲停止になり、早く打出さねばならぬことになりましたので、手代が住さんのところへ、その旨を申出て来ました。住さんは「承知しました」と仰言つて床へ上られましたが、その日の「爪先鼠」は今でいふ大カツトで、もとより無本で、自由自在に飛ばして行かれるのですが、それでゐて大切な筋のところはちやんと語つて居られました。こんなことは目あき目くらにかゝはらず、何もかも全部憶え込んでしまつてゐないと出来ないことで、ましてそれが前から準備してあつたのでなく、直前の注文ですから、住さんのえらさに驚きました。
また住さんはもとは三味線弾きだつたさうで、右も左もよく立派に弾かれました。お内儀さんはお勝さんと申して、中々よいお内儀さんで、内助の功があつたやうです。
晩酌は一本半位で、何か一寸変つたお肴を造つてさし上げるととてもお喜びになりました。
そして「もうあと三杯」といつて定量飲み終られると、ポンと手を打つて「ごつそうさん」と仰言るのが癖でした。
勝七師匠は本名を久野友太郎と申され、播州大塩の生れで、育ちは姫路ださうです。畳屋町の清六(初代)さんのお弟子となられ、初の名は実名の友太郎、次いで玉助となり、二代目を継がれたのです。お内儀さんは大阪の方で、橋筋(戎橋筋の通称)芝居裏南入東側の「丸安」といふ中々大きい乾物屋の娘さんで、この方は二十年程前まで存命して居られました。私が入門しました当時、師匠は南地法善寺境内に「梅園」といふ茶店を営んで居られました。その頃の法善寺は今とは大分変つてゐて、勿論境内も広く、ちよつと風雅なところで、今の「二鶴」の場所に、それと反対の向きに茶店が夫々茶釜を置いて竝んでゐました。だいたい法善寺では平家住居は許されず、茶店といふことで許されてゐて皆お寺の借家でした。西の端が師匠のお家の「梅園」それから「宇治の里」、「いんこの茶屋」、これが津太夫(二代目)さんのお家で、東の端が「大熊」で、これらは見合やお年寄の休息に春秋には賑はつたものでした。この外昔の金属の鏡屋があつて、十日やお午の日には夜店が出ました。それから坂町門の東には今でもあります琴太夫の夫婦ぜんざい、石川一口の講釈小屋、俄の定席、はなしの定席などがありました。当時坂町門や中筋門の大きい門は夜の十時に閉まり、芸者がお座敷からの帰りに通れなくなるので、色街から寺へかけ合つて小さい門が出来ました。それが出来るまでは我々も夜遅く師匠の家から帰るとき、裏手の高塀のくゞりから出たことが度々ありました。
話が脇道へ入りましたが、師匠は前は古靱(初代)さんの三味線を弾いて居られたさうですが、その時代は私は知りません。私が入門した頃は太郎助橋の住さんを弾いて居られ、これは大分長い間のことでした。芸は派手な方で撥の尻の方を持つて、音はよく、具合は天性よく弾かれましたから住さんには似合の女房役でした。殊に住さんのおはこ(得意)の「恋十」(「恋女房染分手綱」十段目)や「酒屋」などとても結構に弾いて居られました。しかし清水町の師匠とは根本的に芸が違つてゐて、私が清水町の師匠に魂をうち込んでしまつてゐるのを御覧になつて、「清水町さんは結構やけど、お前の師匠はわしやさかい、わしのいふこともちいとはきいてくれなどんならん。清水町さんのは中々むつかしうてわからへん、お前にはわしが分相応や」と悋気されました。「清水町は天才やその真似をお前がしたらいかん」といふ意味の注意を私にした方はこの外にも数人ありました。
師匠の人となりは、お人よしで誰にでもへい/\と頭を下げるたちで、その上天性憶病でまた大変な慌て者でした。それについては沢山滑稽なお話があります。まづ役がすんでから後片附をして家へ帰られるのが誰よりも早く、といつて別にお家に御用事があるわけでなく、帰られてからはちよんと長火鉢の前に座つて居られました。これは私か[が]入門する前のことですが、太郎助橋の住さんに師匠、組さんにチンバの吉三郎さんなどの一座で紀州へ旅興行がありました。その道すがら、紀州の蕪峠で吉三郎さんが急に大声で「えらいこつちや/\、今道頓堀が大火事で、法善寺の方へも火の延びてるさうだつせ」と叫ばれたので、慌て者の師匠は「そらえらいこつちや」と走り出され、皆が大笑ひしたとのことです。
師匠はその頃はまだちよん髷を結ふて居られ、頭の地はお風呂のとき糠袋でていねいに磨き、青光りにしてその真中へ髷を結ふのですから実に綺麗でした。髷を切られてからも、真中はやはり禿げてゐて、俗にいふ一つべつついでした。その禿頭について一つの失敗談があります。彦六座一座が名古屋へ興行に行つたときのことです。当時煙草のパイプを持つことが流行してゐて、それに煙草のづが染み込んで焦げ茶色にな[+る]のを皆得意としてゐたのです。私も一つパイプを買つて一生懸命に焦げ茶にしようと思つて始終持ち歩いてゐました。このときも持つて行つて、宿の二階でパイプの手入れをしてゐましたら、ふとしたはずみで火のかたまりが廊下の旬[勾]欄から下の中庭へころがり落ちたのです。下に誰も居ないだらうと思つてゐたところが、「あつい/\――」といふ声が聞えて、それが師匠の声だつたのです。師匠は役をすませて一風呂浴びてよい気持になつて涼んで居られる頭の上へ火の玉が落ちて来たのですからびつくりされるのも尤で、こつちもびつくりして早速階下へ飛んで降りて行つて師匠に詫びごとをしましたが、中々のお怒りで「師匠の頭を焦すなんて、何ちうことや、もう勘当します」とえらい叱られてゐるところヘ住さんが来られましたので、訳を申上げますと「とんだ野崎の久作やがな」と大笑ひをしながら中に入つて下さいましたので、やつとお詫びが叶ひましたが二三日は御機嫌が悪うございました。
師匠の晩年は誠にお気毒でした。住さんに別れてからしばらく越(後の五代目住太夫)さんを旅へ連れて行つて弾いて居られましたが、後に文楽の方へ入つて綾太夫(琴声)を弾き、最後が法善寺の津太夫さんでしたが、明治三十年一月に「壬生村」(「木下蔭狭間合戦」七冊目)のとき舞台で中風が起つて、そのまゝ引籠られ、一年程口縄坂の上の何とかいふお寺で養生して居られました。後嗣ぎはなく財産があるではなし、我々門人――高弟の玉助(後の四代目勝七)、私、徳太郎(四代目で、後の八代目三二[)-]、この人は吉左衛門さんの門弟では高弟でしたが、勝七師匠への入門は遅れてゐましたから下位でした[+)]、寄り合つてお世話をしてゐましたが、我々とても永続きする筈はなく、遂に九州の彦島の規戚が引取ることになりました。その規戚といふのはお内儀さんの方の親類で、詳しく申しますと彦島の傍にある竹子島といふ小さい島の南風止(はいどまり)といふところにあつて、山崎といふ「ピン娼屋」俗に船饅頭といつて内海の船の出はいりで風待ちのときなどに遊興する女郎屋で抱へは十五六人もゐました。そこまでお内儀さんと私が送つて行つたのですが、置いて帰るのですから俊寛のやうなもので、帰りがけに師匠はおい/\泣かれて困りました。師匠はそれから四五年後明治三十四年十月四日、遂にその地で亡くなられましたが、存命中は九州へ行く度に訪ねてゐました。今の古靱さんも清六(三代目)さんと一緒に時折立寄つたらしく、勝七の名跡に関する遺書のやうなものは古靱さんが持つてゐます。門弟の玉助が勝七を願ひ出ましたが色々な関係で中々許されず、遂に三代目は空席にして四代目といふことで許されました。もう勝七師匠の門人で生き残つてゐるのは私一人で、私の在世中に誰かよい芸の持主が出れば古靱さんとも謀つて襲いで欲しいと思つてゐます。何しろ初代は西宮ですから中々の重い名跡です。
私の知つてゐる範囲では、この方程音色の美しい方はありませんでした。中古後では、江戸堀の吉兵衛(五代目)さんの音色が金の鈴をふるやうだ、と美音の名が高かつたのですが、新左衛門さんの方がもう一段上であつたと思ひます。音は大きい方ではありませんでしたが、その美しさは、物に譬へれば、丁度結構な蒔絵の美術品といふのが適中してゐるでせう。そして綿でくるんだやうな実に具合のよい芸でした。しかし手厚いところはやはり烈しい撥が下りました。ですから「先代萩の御殿」だとか、「廿四孝の四段目」、「鰻谷」など弾かれると無類でした。そして、この方はもとは三代目広助さんのお弟子でしたが、後に清水町の師匠の預りになられて、清水町の師匠とは到つて仲よしでした。そのくせ、人柄は表面極めてずぼらで、大変な朝寝坊でした。第一調子を弟子に合は[+さ]せるのがこの方の特長で、いつも懐手して壁にもたれ、我々が何を話しかけても、「お早うございます」と挨拶をしても、「あゝ」の一点張りで、役前になるとお弟子に、「三だけ繰つといて、二もうえゝわ」といふやうな調子で、三味線の準備をさせるのですが、お弟子が弾いて見ても、時には犬(ケン)の皮の三味線など使つて居られましたから少しも鳴らず、おど/\心配してゐるのを、御自分はほんの一撥か二撥弾いて見て、舞台へ上られるのですが、それが舞台では何ともいへぬ綺麗な音がしてゐるのです。時折我々に「お前らは舞台ヘ出てる時だけしか三味線を弾かぬよつていかんのや。わしは二六時中いつでも弾いてる。腹の中で弾いてるのや」といつて居られましたから、表面はずぼらに見えても中味はしつかりしてゐたに違ひありません。
調子のことで面白い話が残つて居ります。「妹背山三段目の山の掛合」が出て、染太夫の方(背山)が清水町の師匠、春太夫の方(妹山)が新左衛門さんといふ三味線の役割でしたが、掛合ですから、相手と調子を合はさねばならず、殊に向ふが清水町さんですから、この時許りは流石の新左衛門さんも、御自身で清水町さんの所へ、「お師匠はん、調子は何本に致しませう」と伺ひに出られました。すると清水町の師匠は、新左衛門さんの平素を知つて居られますから、意地悪く、「この前ので行きまひよ」と答へられました。この前といふのが五年も七年も前のことなのですが、新左衛門さんは「かしこまりました」と引下つて、さて舞台へ出て弾き出されたら、両方ピッタリと調子が合つてゐたといふことです。このお話は大分古いことゝ思ひますが、私も一度清水町の師匠と新左衛門さんとの「妹背山三段目」(明治十八年二月、いなり彦六座)を聞かせて頂いたことがありました。これが私の知つてゐる「三段目」の最高のものでした。それから後に、松葉屋の広助(五代目)さんが染太夫の方で、清水町の師匠が春太夫の方へ廻られたこともありましたが、やはり前の方が結構でした。清水町の師匠は染太夫の方には打つてつけで、その手厚い所は南画のやうで、一方「シヤシヤシヤシヤン」と弾き出された新左衛門さんの綺麗さといつたら、全山桜花爛満の景色がその音色に浮び出ました。
今一つ新左衛門さんの逸話をきいて居ります。たしか文楽座が松島へ出来た時(明治五年一月)のことと思ひます、御祝儀の「三番叟」があつて、引抜きが「石橋」で、清水町の師匠のシンに二枚目が新左衛門さん、勾欄は初代玉造さんの得意の舞台ですが、そのつなぎの三味線の手が清水町の師匠の作曲で、とても烈しい手だつたさうです。繰り返へしてゐる中に、二枚目の新左衛門さんがついて行けなくなつて、静かに三味線を置いて正座せられたといふことです。それを道具が替るまで平気でつないで居られた清水町の師匠の力は申すに及ばぬことですが、こんな傑らい二枚目はその後ありません。合はうが合ふまいが、邪魔になつても何でも己れだけのことを弾きたがる近頃の連弾きなどにはよい薬になる話です。すべて二枚目といふ役所は非常にむづかしく、第一気を遣ひます。以前は二枚目のうまいのが沢山居られました。チンバの吉三郎さん、松屋町(六代目広助)源吉(三代目団平)さんなど上手でした。太夫の方でも掛合の二枚目はその心(コヽロ)が大切です。シンの声がかすれたら、それに準じて二枚目もかすれた声を出す心でなければいけません。シンがへたつたから己れが代りになつてよい声を聞かせてやらうといふやうな量見では、統率といふことが台なしになつてしまひます。一糸乱れず揃はねばならないのですが、その揃ふといふことが解るまでが中々で、何処まで揃へばよいといふ限りはまづないといつた方がよろしいかと思ひます。こんなことになると、近頃の連弾きなど、全くお話にならぬ[+の]が往々にしてありますが、それでゐて、「揃つてゐるではないか」といふやうな考へを持つてゐてはもう駄目です。
清水町の師匠は御自身の連弾きを格別やかましくいはれ、爽々たるお弟子でも連弾きを許されぬことがありました。
新左衛門さんは割合早死で、実に惜しい方でした。本名を稲垣新助と申して、前名は仙八といひ、中頃仙左衛門の名を望まれたさうですが、お許しがなかつたので、それならもう要らんから、「セ」と「シ」と違ひで、方々本名の「新」の字を取つて新左衛門と名乗られたといふことです。四代目の弥太夫さん、大掾さんの越路時代の極く初期、初代の古靱さん、彦六座では大隅さんの春子時代、初代の柳適さんなどを弾いて居られましたが、一番長かつたのは有名な織太夫の綱太夫(六代目)でした。私も春子さんを弾いて居られた時代、「廿四孝十種香」の琴を弾かせて頂いたことがあり、その他数回一緒に出して頂いたことがありました。
後に吉弥(六代目)になつて死んだチンバの吉三郎さん、稲垣(初代新左衛門)さんのお弟子の新三郎さん、それから数年前東京で亡くなつた松太郎さんの三人は、当時の三羽烏といはれて、芸はよし、腕は強し、男前はよし、と三拍子揃つてゐて、その人気は実に旭日の昇る如くでした。その中でも特に吉三郎さんが勝れてゐて、音もよく、天性具合はよし、撥の尻の方を持つて、撥が極り、総て雄大な中に色気がありました。勿論清水町の師匠のお気に入りでもあり、音三郎さんの方からも大信仰でした。例の「伊勢音頭の十人斬」はこの方の書卸しです。
次が新三郎さんで、この方は時代弾きでした。吉三郎さんは組さん、重太夫(四代目)さんを、新三郎さんは島太夫(猫島)さんや重太夫さんや組さんも弾いて居られました。
このお二人は惜しいかな早世され、一番年少の松太郎さんだけが近年まで長生きしてゐましたから、皆様もよく御存じでせうが、長年の間に芸も大分変つてゐました。彦六座で組さんを弾いて居られた頃の松太郎さんは我々の信仰の的の一人でした。
それから一寸下つては田中の清六(三代目)さん、仙昇の広作(四代目)さん、仙治郎さんの三人がよい芸でした。清六さんは鶴太郎さんの弟子で、大隅(先代)さんを弾いてゐる間にうんと勉強をしました。それを古靱(当代)さんに注ぎ込んだのです。広作さんは松屋町の弟子で、大変な馬力の強い三味線でしたが、確実なものでした。仙治郎さんは松屋町の門人で、彦六座で朝太夫さんを弾いてゐて、初代の新左衛門さんの面影のあるよい芸でしたが、大酒呑みでした。清六さんは私に一つ年上、広作さんは四つ、仙治郎さんは十程上で、三人とも若死で惜しい人達でした。
まだ彦六座が出来る前のことゝ思ひます。太郎助橋の住(四代目)さんに勝七師匠がシンで、後に若太夫(十代目)になつた富司太夫さんに豊沢平次郎さん、越太夫(後の五代目住太夫)さんに京都の竹沢弥六さん、新靱太夫さんに仙昇(後の四代目広作)さんといふ一座で四国中国方面の旅興行があつて、私も師匠のお伴をして行きました。四国を打終つて坂出から備後の福山ヘ渡らうと乗つた船は何でも五百石位の船で、船頭が二人で艪を漕いでゐましたが、折悪く出帆した日はしけで船は大分揺れ、一座のものはすつかり酔つてしまひました。この中で勝七師匠だけはとても船に強くて酔ふどころか、「ゆれるほどえゝ気持や」などゝいつて居られました。このときは居られませんでしたが、清水町の師匠も船はとても強く、少々ゆれても中でチピ/\呑んで居られ、我々はそのお燗をするのに随分弱つたものでした。この外江戸堀の吉兵衛(五代目)さんは前身が船頭だつたさうで、これは船に強いといふ段でなく、特別でした。船出の日はこんな有様でしたが、その翌日はがらりと晴れ渡つて一点の雲もない上天気で、景色のよい内海をぎいこん/\と帆前船の旅の楽しさは此上なく、一座の者どもは前日の船酔などケロリと忘れ、皆々上機嫌で勝手な唄など口号んだりして銘々はしやいでゐました。丁度そのとき沖の彼方に漁船が見えましたので、アノ魚を買つて一杯やらうか、といふ相談が出来て、皆で「お―い/\」と呼んだのですが、何様遠くておまけに海の上のこと故向ふまで声がとゞかないのです。そのときに「おれが呼んだる」といつて出て来たのが富司太夫さんで、船の舳に立つて、両手を腰に取り、毛剃九右衛門張りで「オーイ、ウオカオー」と一声張つたのです。すると漁船へ通じたかして「オーツ」と向ふで手をあげたのです。それからその漁船が我々の船まで漕いで来て、新しいこと此上ない魚を買ひ、早速手料理で一杯やりましたが、その美味しいことは例へやうがありませんでした。この時代の旅は実に呑気なものでした。
富司太夫さんといふ人はこのやうな大声で、彦六座が出来てからはずつと我々と一緒に勤めてゐましたが、この方などがほんとうの道行太夫で、たいがい「道行」のシンを勤めて居られました。清水町の師匠も大変お気に入りで、「千本桜」の「道行」を語つても「それより吉野に」など全部表で、一息でした。
三味線の平次郎さんは清水町の古いお弟子で、腕は鋭い方ではありませんでしたが、むつくりした色気のあるよい芸でした。早くに引退して堺に住んでゐましたが、私が津太夫(三代目村上)さんを弾いて御霊の文楽座へ出た当時ひよつこり楽屋へ訪ねて来て「おまはん出たんやとな、えらい久しぶりや、なつかしいな、もうだあれも知つてるもんないわ」といつてゐました。その後間もなく亡くなりましたが、私より十四五年長でした。
摂津御影の大酒造家嘉納家の旦那で、お好きから太夫になられた方ですが、出所が出所だけあつて上品なことはこの上なく、我々が一緒に勤めた頃はもう晩年でしたが、どこまでも旦那然として居られました。ドツシリと格幅のある、耳垂の大きい方でした。聞くところによるとかの名人三代目の長門太夫さんも天王寺の料亭の旦那だつたさうですから、その風格は丁度柳適さんのやうであつたゞらうと思ひます。柳適さんはもと豊竹巴太夫といつて京都の建仁寺町の友治郎(五代目)さんが弾いて居られたさうですが、この時代は私は知りません。その後暫らく休んで居られたのが、彦六座が出来て再び出座せられたので、お家の屋号が柳店といつてゐましたから、それから柳適と名乗られたのです。彦六座のお仕打は例の灘安さんで、これも同じく酒醸業で、柳適さんはお主筋でしたから、自分の小屋へ出て頂いてお給金で傭ふといふのは勿体ないといふので、賄をすべて灘安さんが受持つといふことで芝居へ出て居られました。その頃の三味線ほ稲垣(初代新左衛門)さんや清水町の師匠も弾いて居られましたが、だいたいの合三味線は松屋町(六代目広助――当時広作)でした。私がはじめて彦六座へ入つたのは、柳適さんの「橋供養」の琴を弾くためには入つたのです。
こんな風でお得意の語り物は「橋供養庵室」、「日向島」(「嬢景清八島日記三段目」)、「菅原道明寺」、「忠臣蔵九段目」、それから「良弁杉二月堂」はこの方が書卸しでとても結構でしたし、すべて品のよいもの許りで、世話物はあんまり語られませんでした。勿論床の行儀もよく、「日向島」のお稽古など頭の上へ湯呑を載せて、体の動かぬやうに稽古されたさうで、力が入つて来て耳垂が震へて来るのまで気にされたさうです。
いつでしたか神戸の大国座(今の八千代座)へ柳適さんに松屋町がシンで夜席がかゝつたとき、嘉納一統の御連中は総出で桟敷を切り通してきゝに見え、楽屋へ御挨拶に来られました。大国座の楽屋は格別に汚なかつたのですが、御主人はじめ一統は塵だらけの廊下に座つて挨拶をされると、柳適さんは「あゝ治郎はんようこそ、まあこつちへお入り、誰某も来てますか」といふやうな調子で大変な格式でした。さて舞台へ出られて、当夜の語り物がお得意の「日向島」で「松門独り閉ぢ――」と語り出されたのですが、何しろ夜席で一杯機嫌で浄瑠璃でも聞かうかといふお客が大分いましたから、結構な「松門」がわからないのです。「――春や昔の春ならん」のあたりになると「アー」と大きな欠伸をするものや「おもろないな」などいふものも出て来ました。当の柳適さんはそんなことは一向平気で語つて居られるのですが、桟敷の嘉納家の方々が気を揉み出しました。その中に吉井といふ番頭が退屈してゐるお客のところへ行つて「私は今語つて居ります柳適太夫の番頭で御座りますが、定めし御退屈様でござりませうがしばら[+く]の御辛抱を」といつて有り合はせのお菓子やお寿司を配つて歩いたりしました。しかし元々結構な「日向島」ですから、ぢつと聞いてゐれば面白いので、奥へ行くにつれて静かになりました。
柳適さんはだいたい「間」のよいお方で、彦六座時代は塩町の御堂筋西入の東側の一間露地構へのお家に住んで居られましたが、芝居からお家へ帰られるとき、お家の敷居を跨ぐのがよい「間」でないと中へ入られなかつたさうで、足数が悪くて門口で「半間」になると「吉井はいれんがな」と番頭にいはれます。吉井が「もう一ぺん廻つといなはれ」といふと町内を一廻りして足数をよくしてよい「間」で家へ入られたといふことです。
奥さんもごく堅気で、髪はいつも両輪に結い、木綿の着物をきつちりと合はせて着て居られました。私共が伺つても丁寧に挨拶をされ、奥へ通ると柳適さんが床の間の前に座つて居られ、その床の間には花生に柏が生けてあり、その葉の中に柏餅が仕込んであつて、お客が来ると鋏で切つてそれを出されるといふ風でした。
明治の初めから中頃にかけての文楽の有名な道具方で、カラクリ式の道具の名人でした。都踊の道具のよいのもこの人が指図をしてゐたからです。先年亡くなつた吉田玉蔵(もと三代目吉田玉造)の兄で、早くから文楽の棟梁をしてゐて俗に「ゲンマ」と呼んでゐました。今でも文楽でやります「伊賀越の沼津」の松林を歩かせるのや、「壷阪」で、『沢市内』から『山』への道具の変りを屏風式にしたのも皆この人の発案です。彦六座が出来てから弟の玉蔵(当時玉松)とともにずつと彦六にゐましたが、「大文字屋」の端場の『清水』で桟敷の欄間の駒提灯が割れると一杯の桜の満開になつたり、殆んど興行毎に目新らしい工夫をしてゐました。また明治十八年東京猿若町の文楽座で「廿四孝」が出たとき、三段目の『筍掘り』の藪を太い孟荘竹を釣道具にして降ろしお客様を驚かせました。その前に文楽座にゐた時代でも中々盛んで、初代の玉造さんが景事物で自由自在に宙吊り、早替りをして喝采を博してゐたのも、源松が道具を工夫したればこそ出来たのです。明治何年の頃でしたか、松島の文楽座で、「浦島太郎」の「景事物」があつて、場面は龍宮城で、客席のかぶりつきの一角をそのまゝ舞台の舟底へ引くとその下から大きな蛤のセリ上りで、口が開くと中から大玉造が乙姫様の出遣ひで現れ、蛤が閉ぢると客席が元へ戻るといふ仕掛けでしたが、ある日蛤の口が開いたなりで閉らなかつたのです。源松が大狼狽して修繕に出ましたが、赤光りのした禿頭でしたから、それが蛤の中に見え、丁度蛤に入れてある赤まん膏薬のやうだつたので、お客は「赤まんが出た/\」と大笑ひでした。
源松は私の母の前からの知り合ひで、家も近所でした。私を勝七さんのところへ世話してくれたのも源松でしたから、特に懇意にしてゐました。今申す赤光りのやかん頭でしたが、小柄で、綺麗な感じのする人でした。酒は呑まず、やつし男(めかし男)で、なり道楽でした。羽二重の半被に、甲斐絹のパッチを穿いて、切り立ての博多帯を締めたりして中々気の利いたなりをしてゐました。
明治十八年九月、東京浅草猿若町三丁目の猿若座の焼跡に人形浄瑠璃の専用小屋としての東京文楽座が新築されました。お仕打は、後には歌舞伎座の水場に落ちぶれましたが、当時は東京興行界きつての大顔で旭日の昇る勢であつた中村善四郎でした。その柿葺落しに大阪から我々が招かれ、一行は越路太夫(後の摂津大掾)、住太夫(四代目)、長尾太夫(二代目)、津太夫(法善寺)、呂太夫(初代)、南部太夫(二代目)――この方はしはがれた声でしたが浄瑠璃はよく語りました――織太夫(三代目)、路太夫、谷太夫(後の九代目染太夫)などに頭取の浪太夫(五代目)も行き、三味線は吉兵衛(五代目)、勝七(二代目)、広助(五代目)、叶(二代目)、才治(三代目)その外田中の清六(三代目)はまだ福太郎時代で、私などと一緒の下廻りでありました。人形は玉造(初代)、紋十郎(二代目)、玉助(初代)その他文楽座の人形遣ひの主な者全部で、先年亡くなりました文三が幸三郎時代、今の文五郎がまだ己[巳]之助時代で参加してゐました。勿論東海道線はまだ出来て居らず。神戸から西京丸といふ横車のついた船で、熊野灘遠州灘で思ふ存分揺られて横浜へ上り、それから汽車で新橋まで行つて東京へ乗り込んだのです。さてこのやうな文楽大一座の上京はほんとうにこの時が初めですから東京の鳶をはじめ、魚河岸、大根河岸、米屋町、兜町の顔役は総出で、それぞれ高張りを掲げて出迎へ、新橋から猿若町の文楽座まで行列を揃へててくれたのですが、越路さんと吉兵衛さんは船に酔つたといふ理由で、途中からぬけて宿へ行つてしまつたのです。さて新築の文楽座へ入り、手打も無事すんで、お開きにならうとしたとき、お仕打の中村善四郎がそれに気がつき、「一寸お待ち下さい、本日は皆様お疲れのところをわざわざお揃ひ下さいまして誠に有難うございました。しかしこのお席に櫓下の越路太夫、吉兵衛のお二人のお顔が見えませんのはどういふ訳でございませうか、折角この開場の手打に際して肝腎のお二人が見えませんことは甚だ心外なことで、中村善四郎腹を切つてもお顔役の方々に申訳が立ちません――。」と文楽座の手代の弥七に向つて談判を持ちかけて来ました。面喰つたのは弥七で、「実は船酔で静養して居られますので――」と一応は言訳をしたものゝ、二人の外は全部顔を揃へてゐるのに、それで先方が承知する筈はなし、それ以上の弁解は出来ず、たゞおろ/\するだけで、忽ちにして満場は唯ならぬ空気に蔽はれました。この時我々文楽の芸人側は舞台にならび、客席には新橋へ出迎へてくれた連中や特別のお客でぎつしりつまつてゐて、皆々どうなるかと片唾を呑んでゐました。その中から住太夫さんがつかつかと前へ進まれ、中村善四郎に対し一礼の後、傍に青くなつて蹲つてゐる弥七に向ひ、「これはこちらのお仕打さんに対しては申されんことだすが、只今聞いとりますと越路さんと吉兵衛はんの二人がいはらんので承知が出けんと仰つしやりますが、さうするとその二人さえゐたらえゝので残りの呂太夫、津太夫、私、広助、勝七、それから玉造も紋十郎も要らんのでござりませう。ですよつてに私はこれからすぐまた大阪へ帰らせてもらほうと存じますさかい、どうかそのお積りで、なあ松葉屋(広助)はんさうしようやおまへんか」と申されましたので広助さんも玉造さんも「そら住さんのいひはるのに間違ひはない、一緒にいにまひう/\」と賛成されたので、場内の空気はますます険悪になり、誰一人口を開くものもなく、満場静まり返つてしまひました。この住さんの挨拶は、表面は弥七にいはれたのですが、その実中村善四郎への反撥であることは申すまでもありません。
かうした重くるしい空気が何時間位でせう、舞台の蝋燭を何度も替えてゐましたから随分長い間だつたと思ひます。そして何時、どう解決するとも見当がつかず、さりとて遅くなつたからといつてそのまゝ開く訳に行かず、一同はどうなることかと心配をしてゐました。そのとき客席の中から「真平御免ねえ」と幡随長兵衛張りで出て来たのが有名な茅場町の宮松亭の持主で、東京切つての大規分の宮松三吉でした。宮松三吉さんは住さんに挨拶をした後、「さて今日の仕儀、中村善四郎さんのいはれるのも尤も、また住太夫さんの申されるのもまた尤も、両方共御尤といつて、かうしてゐてもいつ解決するかわからねえ。こいつは一つこのまゝあつしに預けて下さいませんか」と出たのです。住さんも「私は盲でどなた様がどなた様やらよう存じませんが、お顔役がさう仰言るのでしたら、私も強いて帰らうとは申しません、どうぞよろしう」と万事を托され、はじめて解決の糸口が見えて来ました。中村善四郎も初めは自分がいひ出したことですが住さんに逆ねじを喰はされて困り切つてゐたところですから、諾応なしに宮松三吉に一任して、やつとのことでその日がお開きになりましたが、この時の住さんの度胸といひ、賢明さといひ、しつかりして居られるのにはびつくりしてしまひました。前から住さんは浄瑠璃だけでなし、頭もよいし、人間もしつかりして居られることはよく承知してゐましたが、この時許りは一同が盲に引張られた形で、全く住さん一人のお蔭で面目が立つたといふもので、すつかり感心してしまひました。
その翌日改めて越路さんと吉兵衛さんの新橋からの乗込から手打のやり直ほしをすることになつたのですが、勿論上位の方々は新橋へ出迎ふ筈はなく、弟子共だけが出迎ひ、手打式も越路さんと吉兵衛さんの二人だけで行はれました。
このことをいつぞや文五郎さんに咄しましたら、「さうそ、あのときは怖うおましたな。あんたよう憶えてなはる」といつてゐました。
さてめでたく初日があいて、何様東京としては非常に珍らしいことでしたからあらゆる種類のお客で連日大入満員でした。華族の殿様方も随分お見えになり、中でも伊達様の御前様(伊達宗城侯)は毎日お見えでした。大きな特長のあるお顔でしたからよく憶えて居ります。
この引越興行に際し、住太夫さんに取つてもう一つ事件がありました。それは越路さんが昔修行時代に東京に居られたとき、一時住太夫を名乗つて居られたことがあつて、越路さん側として住太夫の名で東京で出られることは一寸都合が悪かつたのです。そこでお高(越路太夫の妻)さんから太郎助橋へ、今度に限り外の名で出てくれるやう注文があつたのですが、太郎助橋としても住太夫を名乗られてから廿年余にもなるのに、今更元の田喜太夫になることも出来ず、このときはもう二代目の田喜太夫が出来てゐて、これとてもかなりの古顔で、別の名もなく遂にこの注文には応ぜられませんでしたが、これはだいたい無理な話でした。
この上京に際して初代の玉造さんと住さんの二人がちよん髷を切られました。玉造さんは東京へ着いてから、たしか興行中であつたと思ひます。落された髷を見て、「これがわしの髷か」といつて涙をポロ/\こぼして泣かれました。住さんは出達前大阪で切られました。
この興行は旅興行でしたが私に忘れられないのは、はじめて役らしい役場を弾いたことでした。太夫連はかなりの顔ぶれが揃つてゐましたが、三味線の方は割合に少人数でしたので、私は田喜太夫(二代目)さんを弾きました。外題は三の替りまでゞ、お目見得のときは「神霊矢口渡」『頓兵衛住家』の中、二の替りは「廿四孝四段目の次」、三の替りは「白石噺」の『逆井村』の中と、「阿古屋琴責」の三曲でした。田喜さんは住さんのお弟子で、「道行」だとか、サラツとした端場などよく語られました。
この滞在中に東京亭へ名人円朝さんの人情噺をきゝに行きました。東京亭は大和太夫の席でしたから我々は特別の関係で一座の者殆んど全部行きました。丁度お得意の「牡丹灯籠」を読んで居られましたが、実に結構なものでした。住さんなど特に喜んで居られ、悲しいところなどは涙を流して泣いて居られました。円朝さんの芸は全部義太夫に応用出来ます。私が円朝さんを拝聴したのはこの時一回限りで、実に尊い経験だと思つてゐます。
猿若町文楽座興行は六十日程打ち、そのあとは越路さんの組と住さんの組とに二手に分れて、睦の席を百日廻りました。越路さんの方は、越路さん、路さんに黒鶴といつた鶴太郎(二代目)さん、南部さん(二代目)、常子大夫(後の三代目越路太夫)に後の田中の清六さんが福太郎時代の頃、外に競太夫などもゐたと思つてゐます。そして越路さんのお目見得狂言は「先代萩御殿」であつたのに対し、住さんの方は、新柳亭で「大文字屋」がお目見得狂言でした。東京では非常に珍らしい語り物でしたから、「助六揚巻の義太夫て何だらう」などと江戸ツ児はいつてゐました。この外に住さんは「酒屋」、「湊町」、「沼津」、「重の井」、「寺子屋」、「白石の二階」、「堀川」などを出して居られました。一座は住さんに勝七師匠、二枚目は谷(後の九代目染太夫)さんに玉助(後の四代目勝七)、三枚目が田喜太夫さんに私で座組は越路さんの方より劣つてゐました。谷さんは「融通大念仏」、「姫小松の洞ケ岳」など、田喜さんは「三日の本能寺」、「彦山六ッ目(お菊殺し)」、「朝顔日記浜松」、「合邦」などを出して居られました。そして一座は皆揃つて富沢町に和合連(東京の素義の連中)のドツサリの孝玉さんがやつて居られた「桜井」といふ商人宿に泊つてゐました。猿若町に出てゐた間は前茶屋でした。
お話が前後になりましたが、この東京行は私に取つてはじめての上京でしたので、行く前からうれしくてうれしくて堪らず、丁度生意気盛りの年頃で、神戸から船に乗る前、船着場からもう江戸弁を真似てゐました。そして横浜へ着いて泊つた宿のお風呂が狭かつたので銭湯へ行きましたら、そこの十位の小僧がペラペラと江戸弁を喋舌つたので、私は思はず「アツこんな子供まで江戸ツ児や」といつてしまつて皆に笑はれたことがありました。
この外にもまだいろいろ失敗談がありました。これは田喜太夫さんですが、この方は前に綾瀬太夫(初代)さんなどの座で東京へ来たことがあつて今度は二度目なのでだいたい様子はよくわかつてゐる、「蕎麦屋へ連れていつたろ」、「連れて行つとくなはれ」とお伴したのです。そばやへは入ると小僧が色種をペラペラといひならべたのですが、それが流暢な江戸弁だからきゝ取れないのです。田喜さんは慌てゝ「こないして(かき込む手真似をして)喰ふそばくれ」といつてしまつて皆大笑ひをしました。
寄席から帰りに、住さんは車で帰られますが我々は皆歩くので、その途中でいろいろ道草を喰ふのがまた非常な楽しみで、すし、てんぷらなどの屋台店の立喰ひをしました。当時てんぷらはよかつたのですが、すしの屋台店はとてもたちが悪く、中々貪つたのです。いつかも皆で立喰ひをしてゐたとき、谷さんが大きい海老をつまんでから値段をきくと、「一両だい」といつたので乞[吃]驚して手を引いたのですが、その前に我々は逃げ出してゐたので、谷さん一人おすしやに怒鳴られて、いだてん走りで逃げて来たことがありました。
谷さんは讃岐の産で、もと宮角力の一人だつたさうです。住さんが讃岐へ旅に行かれたとき弟子入りされたのです。その頃九平といふ号でしたので、丸平々々で通つてゐました。その丸平さんが、滞京中一人女が出来たのです。相方は霊岸島――当時霊岸島はまだ盛でした――のいゝ顔の芸者で、お正月にその芸者から斜子の竹仙染の小紋の三ツ[衣+重unicord8909]、に羽織から帯から煙草入まですつかり揃へて拵へてもらつて、大自慢でふんぞり返つて歩いて居らまれしたが、何様三ツ[衣+重unicord8909]など生れてはじめて着たらしく、少しも身についてなく皆がよつて冷やかしました。この外江戸堀の吉兵衛さんは鳥森のおいくさんとの仲が大評判でした。
彦六座は全く私達の芸道修行の道場だつたのですから、その名をきくだけでも実に懐しい気持がします。
お仕打は寺井安四郎さんといふ、長堀中橋南詰に「灘屋」といふ駄売酒屋の旦那で、通称を灘安さんといつた方でした。お仕打時代は号を「十八」といつて、最初は松葉屋(五代目豊沢広助)さんの連中で、後に松屋町(後の名庭絃阿弥)がお稽古をして居られました。また富助(四代目)さんも始終出入をして居られました。この富助さんといふ方は、松葉屋さんのお弟子で三味線の古実に通じた方でした。十八さんは彦六座の晩年から十八太夫と名乗つて太夫になられ、後二代目柳適太夫を継ぎ、彦六座の後身になる稲荷座にずつと出て居られました。灘安さんが人形芝居の興行に手をつけられた最初は、詳しくは知りませんが日本橋北詰の「沢の席」はこの方がお仕打であつたさうです。これが明治十六年で、翌年の一月から彦六座へ移られたのです。その彦六座の小屋は、その以前から博労町稲荷境内にあつた「いなり北門の席」を買収されたもので、十七年の夏中に改築されて、それが二十一年の二月に焼けたのです。位置は稲荷神社の北門(久宝寺町通)から入つてすぐ東側に西向いてありました。前茶屋は「梅屋」と「菱万」の二軒があつて、「梅屋」は本名を菱田といひ、灘安さんのお妾さんが居られ、おとらさんといつて当時三十位の方でした。また「菱万」はその南隣で人形遣ひの吉田三吾(四代目)さんの家でした。この両茶屋の隣に「玉水」といふ小料理屋があつて、腰掛式で安く、うまいものを食べさせました。これが今の新町の「玉水」の前身になるのです。
私は前にも申した通り十七年の二月に彦六座へ入つたのですが、当時の興行は毎月大入満員続きでした。といふのが灘安さんの方針といふのがよく、芸の為には勿論のこと、お客の待遇その他万事興行の為になら、損とわかつてゐても用捨なく金を掛けるといふ風でした。柿葺落しのときは、今日でいはゞ一つの新しい劇団が生れたやうなものでしたから、人形の衣裳、小道具は全部新調であつたことは勿論ですが、月々の大道具にとても金を掛けられたもので、一例を申しますと、「紙子仕立の清水坂」で舞台から客席一面桜を飾つたり、「大塔宮の三段目」の奥では、客席に大きい切子灯籠を一間置き位に下げ、舞台は小さいのを三段位飾つた道具で、それはそれは見事なものでした。これらは皆大道具師の中野源松の趣向でした。またお客への待遇では、それまではたいていござを敷いてあつた桟敷を畳敷きに改め、更に後に冬は毛氈、夏は籐莚を敷き、暑中になるとところどころに盥を置いて氷柱を立てたり、雨の日はお客様の下駄を拭いてお帰りまでに綺麗にしてあるといふやうな調子で、皆灘安さんの案でした。この下駄を拭ふのは後に東京で鳥熊が本郷の春木座でやつたさうです。
こんな風ですから芝居は満員でも欠損になるのは当り前で、終ひには行くところまで行つてしまつたのです。そして灘安さんは、今も残つてゐます長堀中橋南詰の土蔵の中で逼塞して居られたことがありました。それに何といつても廿一年二月の火事が彦六座の運の尽きであつたのです。これはつけ火であつたといふことですが、犯人は遂にあらが[がら]ず終ひでした。
芸の方は多少の例外はあつても実によく統一が取れてゐました。これは遍に清水町の師匠のお蔭で、十七年の盆替りに入つて見えてからは名実ともに一座の総帥で、総稽古の日に前でおきゝになつてゐて、太夫でも三味線でも、かけ出しであらうが、古参であらうが、悪いところはていねいに直して頂けました。そして師匠が「それは違ふ、かうや」と仰つしやつたら、前のが外の誰の稽古であらうが、所謂鶴の一声で、喜んで師匠に直して頂いたのですから、よい舞台が出来る筈です。そして清水町の師匠御自身をはじめ見習に到るまで銘々凝つたのです。
楽屋は今の文楽のやうな広いものでなく、太夫三味線全部が三つの部屋に入つてゐました。一番よい部屋――といつても別に綺麗にしてあるわけではありません――に清水町の師匠、その向ひに太郎助橋の住太夫さん、柳適(初代)さん、新左衛門(初代)さんが居られ、そのつゞきに組さん、大隅さん、勝七師匠が居られ、後にその仕切りを取つて一つの部屋になりました。後は全部大部屋で、その大将が松屋町で、一番隅に一段高く結界を拵へて、若い者が下手なことを弾いたりしたら「こらツ」と叱り役になつてゐました。これは前に申した灘安さんとの関係もあり、第一その資格があつたからで、役前ぎりぎりには入つて来たりしたら、いきなり「こらツ」とやられました。その外行儀作法などやかましく、普通に心掛けて居ればよいのですが、桁を外すと叱られました。尤も当時は「序切」を勤めるまでは羽織は着られず、履物も表附ははけませんでした。
松屋町は殊の外厳格な方で、一かどの芸人に対しても面と向つて「お前下手やな」と遠慮もなくいひ放たれました。彦六座で柳適(初代)さんを弾いて居られる間でさえ、柳適さんが出来の悪いときは、掛声もせずぶつぶついつて居られました。こんな方は足腰が立たなくとも口だけ達者でよろしいから、斯道のために何時までも生かせて置きたいものでした。
今はもう全くその面影が消えてしまひましたが、昔の名古屋は実に芸のやかましい土地で、我々は名古屋で芸をするのを怖ろしがりました。やかましいといふのは、つまり芸評の善悪が極端なのです。一箇所よいところがあれば、満場が湧き立つて終りまで賞讃の連発ですが、面白くないと怖ろしく弥次られます。入りもその通りで、初日の景気がよいと興行中ずつと物凄い大入です。昔から「名古屋の大入」などゝいひますが、逆に不入の時は実にひどいものです。
彦六座が出来て間もなく、一座揃つて名古屋の桑名町の千歳座へ出演したことがありました。主なる顔ぶれは、朝太夫さんに仙治郎さん、組さんに松太郎さん、柳適(初代)さんに広作(後の六代目広助)さん、次に○附きで大隅さんに源吉さん、それから住(四代目)さんに勝七師匠でしたが、この興行は大変な大入りでした。といつても全部が全部好評ではなかつたのですが、まず朝太夫さんなど「鈴ケ森」を語つてゐましたが、枕の郡[群]集の詞で「あんまり待つて寒なつた」のワザでお客がわあーツと喜んでしまつて、奥は少々悪くても何でもその惰力で行つてしまひました。それから組さんと松太郎さんが出てお得意の「十人斬(伊勢音頭)」を語られましたが、清水町の師匠の節付の新しいのですから、珍らしくて、面白いから場内はすつかり煮え返へつてしまつて、終つてからも暫らくはそのいきりが静まりませんでした。その後へ柳適さんが出て「太十」を語られましたが、例の如く行儀よく枕を語り出して、「母様にも祖母様にも」になりましたが、お客が一向喜びません。それどころか、場内のあちこちにパシヤ/\、パシヤ/\とざわめきが起つて来ました。これが怖いので、高じて来ると「面白ない、止めんか」といふ者が一人二人と出て来て、それでも続けてゐると、終ひには舞台へ上つて来て御簾を下してしまつて、やれなくしてしまふのです。その前兆がパシヤ/\なのですが、それが柳適さんの時に出かけたのです。さあ一座の者の心配は申すに及ばず、座方も、真打の太夫さんに不都合なことがあつては大変だが、お客は致し方ないから、はら/\し出ました。舞台では松屋町(広作)が一生懸命弾いて居られましたが、その内に「二世も三世も」になつて音を遣つて語り出されたら、場内は急転直下、ワアーツと来てしまひました。それから後はお定りで、ぞ[そ]のまゝ好評の波に乗つて段切となつたのですが、実に名古屋のお客は不思議なものでした。始めに一寸よければ後はかましでも、くすぐりでも何でもよいのですから、ほんとうに解つてゐないのだらうと思ふと、最初のつかみどころは本格ですから、やはり解つてゐるのでせう。その代り反対に不評となると、実に目も当てられぬ惨さで、今申したパシヤ/\から始つて、お客が舞台へ上つて来て見台を奪つてしまつて、語れぬやうにしてしまひます。現にこの興行でも、ある下廻りの太夫がそれを喰つて、見台を花道まで移されてしまひました。
次に大隅さんと源吉さんでしたが、「寿司屋」か何かで、これは何事もなかつたかして一向印象に残つて居りません。そしてお次がドツサリの住さんは十八番物の「大文字屋」でしたが、お松の出る前、手代のサラ/\とした詞でもうワアーツと喜んでしまひ、「お松といへど色かはる」では尚更、奥のお得意の題号は勿論のことで、場内割れん許りの喝采でした。
今は時勢が変つて、芸の勉強といふことがとてもしにくゝなりました。第一に生活のことを考へねばならぬ時代になりましたが、それではほんとうの勉強は出来ません。多少は境遇にもよるでせうが、三度の食事も目当てなく、着物は垢染みたものを着て、他人から「臭い/\」といはれる位、魂をそれに打込んでしまはぬと勉強出来ません。今の人にさうせよ、といつたら、「そんなことをしたら道も歩けません」といひますが、人交りがならぬのは昔でも同じことです。表面はそれでも、そのとき芸は光つてゐるのです。そこまでして到らぬときは、神の御加護に頼るより外致し方ないのです。そこで芸人には信心がなければいけないのですが、碌々勉強もせずに、神様にお願ひしても駄目なことはわかつてゐます。清水町の師匠も到つて信仰心の厚いお方で、中でも金毘羅様が特に御信仰で、朝夕二時間の御礼拝がありましたが、拵らへ物(節付)なんかされるときは、その御礼拝も中止で、芸の方へ一心を集注して居られました。そして出来上つてから初めて、神前で御無沙汰のお詫びをされるのです。
私達の若い時代でも、年寄連中から「今の者は勉強せん、凝らん」といはれましたが、今日のやうなことはありませんでした。今日の芸人は勉強せん過ぎます。今のやうなことでやつて行けたら結構ですが、芸といふものはそんなことで出来るものではないのです。
いつたい昔と今とでは稽古のしようが違ひました。今日では下廻りでも何でも来さえすれば心よく教えますが、昔は中々さうは行きませんでした。立者衆にお稽古して頂くにはまづその方の御機嫌を取らねばならず、――こ[か]ういふ稽古が目的のおべつかは大いにやるべしでした。――それが出来てからが下廻りでは忙しくて中々時間がなく、かりに私の修行時代にしますと、朝彦六座で「大序」を勤めて、それから法善寺の勝七師匠のところへお迎へに行つて芝居までお伴をし、師匠の役が終つて後片附をしてから時間があれば清水町の師匠のお宅へまたお迎へに行く(これは師匠のお役によつて順が逆になります)といふやうな風でしたが、それが松島の文楽座時代ですと一層遠く、松島から法善寺まで随分道のりがあり、勿論電車などなく歩くので、おまけに当時千代崎橋は開閉橋になつてゐましたから悪くすると通行止めになつてしまつて松島橋へ廻れば大廻りになるし、このために舞台をトチルこともありました。こんな忙しい中の少しの隙を見出してお稽古を願ふのですが、自分の都合だけでも行かず、殊に新左衛門(初代)さんなどは大変な朝寝坊でしたから、折角隙を拵へて伺つたらまだこれから御手水といふやうなこともあつて、お稽古の時間もなく、師匠の楽屋入りの時間が来てしまふやうな仕末でした。尤も興行の合間には時間がありますが、このときはたいてい次の興行の役の稽古で、芝居中は所謂平素のお稽古、常の鍛錬をするわけで、これを怠つたらもう駄日です。さてやつとのことで「何々のお稽古を」といつて本をもつて師匠の前へ出るまで漕ぎつけたにしてからが、そのときその外題を全然知らないやうなことでは駄目なのです。師匠の前へ座つたときに、師匠はもつて来た本と私なら私の顔をじつと見較べて御覧になります。そこで私の方に予備のお稽古がしてなかつた場合それが私の顔へ出てゐるもので、すると師匠は「お前まだこれを一ぺんも稽古したことがないな、もつと外で稽古して来い、それからうちへ来い」と、ポンと本を返へされてしまつて万事休してしまひます。つまり立者衆のお稽古は仕上げなのです。これに関して次のやうな話があります。大隅(先代)さんがある上位の太夫さんのところへ、たしか「沼津」でしたか、お稽古に行かれ、一段聞かせてもらつて師匠の宅を出られたのですが、そのとき大隅さんは「アノ『沼津』やつたらもう知つてるわ、俺の方がえゝ」といつて居られたさうです。大隅さんのやうな勉強家にはありさうなことです。またもう一つ、清水町の師匠の古いお弟子が本をもつて師匠の前へ出てお稽古を願はれました。すると師匠はその本を手に取つて御覧になつて「『日向島』やないか、これお前の稽古か、猫に小判や」と仰言つたのでそのまゝ引退つて終り、といふ話もあります。それから大立者衆のところへお稽古に伺ふと一かどの立者衆がお稽古に来て居られますから、そんな場合下廻りは先着でも後廻しは勿論です。清水町などは吉三郎(二代目)さん、新三郎さん、松太郎さんなどはじめ、時には松葉屋(五代目広助)さんもお稽古に来て居られ、その辺で勝手に順番をつけて稽古をされますから中々我々のところへ順番が廻つて来ず、気を揉みながらその日は遂に駄目になつてしまふことが度々ありました。しかしこの先輩方のお稽古を聞かせて頂くのがまた大変な勉強になることは申すに及ばぬことで、下廻りの間の勉強は直接のお稽古より、師匠のお宅の雑用を手伝つて使用人のやうになつて先輩のお稽古を聞かせて頂くのが大部分で、それが第一の勉強にもなつたのです。中堅程度になると少しはお稽古の機会が出来て来ます。とにかく昔の稽古はやりにくかつたもので、だからといつて稽古せずにはいられませんからとても苦しいものでした。しかしこれは昔の方、清水町の師匠や松葉屋さんでもやつて来られたに違ひありません。お二人とも西宮の勝七さんのところへ夜越しでお稽古に行かれたさうで、夜明けに着いて師匠のお家の戸のあくのを待つて中へは入られたさうです。また清水町の師匠は昔「すみこた」といふ素人の名人のところへお稽古に行かれたとき、簑を着て行かれ、やはり戸があくまで庭で焚火をして待つて居られたといふことを聞いて居りますが、実に勿体ないことです。
三味線の方では明治になつてからは何といつても清水町の師匠か松葉屋さんのお二人で、このどつちかにお稽古を受けてゐなければ稽古をしてゐない、と断言してもよいのです。
また太夫さんの方でも昔は外題によつて稽古の場所が定つてゐたものです。例えば「先代御殿」、「廿四孝四段目」、「中将姫」などは申すに及ばず越路(後の摂津大掾)さん、「忠臣講釈の喜内住家」や「伊勢物語の春日村」などは古靱(初代)さん、「大文字屋」、「白石の七ツ目」などは太郎助橋の住さんといふ風でした。そしてお門違ひへ稽古に行くと、勿論御存じない筈はないのですが、「それやつたら誰某のところ行け、その代り何々を教へてやる」といはれました。
また当時は稽古となつたら上も下もなく、何処へでも行つたものです。明楽座で「菅原」が出たとき、『配所』を住(五代目)さんが小団二さんと一緒に私のところへ稽古に来られました。住さんはもと越太夫(三代目)さんのお弟子で、後に太郎介[助]橋の住(四代目)さんのお弟子になられた古い太夫で、浄瑠璃もシツカリ中々よく語つた方です。また小団二さんは清水町の師匠のお弟子の中では古顔で(団平の「平」の字を「小」と「二」との二つに割つて一つ宛を上下ヘつけて出来た名前です)、二人共私等とは比べものにならぬ位の古顔だつたのです。いつたい昔は皆表面は呑気にして隠れて稽古に走り廻るのが流行してゐましたから、私が前に「配所」を勤めたとき、清水町の師匠にお稽古して頂いたことを知つてゐて来られたのでせう。今お話した住さん、朝さん、源(先々代)さん、新靱さん、生島(後の大島太夫)さんなどでも皆よくやつてゐました。
先年亡くなつた長子太夫の弥太夫(六代目)も大酒呑みで、表面は何時も酔払つてゐましたが、随分稽古もしてゐました。その稽古で一つ笑ひ話があります。私のところへ稽古に来てゐたとき、「もつと下腹へ力を入れて、もつと、もつと」といつてやつてゐましたら、稽古がすんでも立上りません。「どないしなはつた」ときくと、「えらい粗忽をしました」といつてもぢもぢしてゐます。酒呑みで始終下剤をかけてゐたゝめ、腹へ力が入つた拍子に大便が出てしまつたので、大騒動をしたことがありました。長子太夫は上手な浄瑠璃で、小手先が利き「地色」などでも上手にいひましたが、何様極く非力でした。しかし力を入れよ、といつたら肩へ入れてきばつてしまうやうな太夫ではなく、ちやんと下腹へは入りました。さすればこそ右の粗忽があつたのです。長子太夫の大きいのが丁度住(五代目)さんです。
今日では義太夫界は申すに及ばず、他の芸もさうではないでせうか。上べのことばかりで、みつちり土台の勉強をして置くといふことが殆んどないやうです。それに何か一寸よいことがあるとすぐ新開に出て、それが宣伝になる。やれ何処へやら実地見学に行つたとか、何か変つたことをしたとか、宣伝も結構ですが考へものです。そんなことは知れなくてもよいことで、出来上りの芸さえよければそれでよいのです。
もつとも歌舞伎の方では昔でも宣伝はしたらしく、その方法が実に面白く、五代目が猿若町の芝居で「四谷怪談」を出してゐたとき、「蛇山の庵室」で提灯ぬけに使ふ提灯の張り替く[え]を近所でさせず、わざわざ芝の神明の提灯屋まで持つて行つて張らせ、それを乾かしながら銀座通りを通つて芝居まで持つて帰つたので、何しろ大きいものですから人目につき、途中の人は「あれが音羽屋が今使つてゐる提灯ださうだ」と皆目を見はつたさうです。この話は五代目から聞いた話です。
私が清水町の師匠の三味線をきかせて頂いたのは、明治十五年六月松島の文楽座へはじめて出たときで、師匠は越路(後の摂津大掾)さんの「一の谷陣屋」を弾いて居られました。それから次が「中将姫」、「宿屋」、「紙治」などで、師匠の芸が他の方に抜出て烈しいのにすつかり感心してしまひ、それから後は「何でもこの日本一の師匠に取り入つて、特別の教へを授りたいものだ」と一筋に思ひつめてゐました。しかし何をいふもこちらは大序かけ出しで、雑用に忙しいばかりで碌に役もつかず、お稽古を願ひ出る隙もなく、お宅へ伺つてもお歴々が朝からお稽古につめかけて居られ、直接師匠にお目にかゝつて物をいふことさえ到底出来ませんでした。師匠の方でも、友松といふ三味線弾がゐること位は御存じだつたかも知れませんが、それがどんな気持でゐるのやら、そんなことまで知つて頂ける筈がありませんでした。さうかうする中、明治十七年二月に彦六座へ出ることになりました。それはその時の彦六座の興行に柳適(初代)さんが「橋供養」の『衣川庵室』を語つて居られ、その琴を弾ずよる適当なものが彦六座にゐなかつたとかで、合三味線の松屋町(後の名庭絃阿弥)の名指しで私が選ばれ、彦六座の床頭取をしてゐた町太夫が迎ひに来てくれましたので、彦六座へ出ました。ところがそのときはまだ文楽の方に名前が出てゐましたので、文楽の表方が[か]ら「文楽の者か、彦六の者かどつちや、はつきりしとくなはれ」と小言を喰ひましたので、勝七師匠も彦六の方に出て居られましたから翌月から彦六座へ出ることにしました。
ところが私の芸運が強かつたと申しませうか、清水町の師匠はその年の七月限りで越路さんと別れ、九月から彦六座の三味線紋下としては入られることになり、座の改築祝の「三番叟」を弾かれ、新左衛門(初代)さんはじめ皆お歴々の連弾きに、私と松吉(後の二代目新左衛門)も豆喰ひに出して頂きました。このときのうれしかつたことは今に忘れません。そしてこの「三番叟」は引抜いて七段がへしになる長いものでした。
だいたい彦六座は、櫓下の住さんをはじめ文楽座に対抗しようといふ気持の者がより集つて出来たやうなもので、そこへこれも越路さんと離縁になつて、決して円満に文楽を退かれたのではなかつた清水町の師匠を鵜飼(万鳳)さんなどのお世話で迎へたのですから、その結策は愈々固く、総て清水町の師匠の采配の下に、皆が銘々凝つて、芸道に励まうとの気風が濃厚でした。私も今度こそは親しく清水町の師匠に教へを乞ふことが出来ると思つて勇んでゐましたが、松島の文楽座時代よりは師匠に近づくことが出来、総稽古のときなどには直接直ほして頂けましたが、私より上に松太郎さん、源吉さん、仙治郎さんなどが居られる以上、さうあつさりと私の望み通りには行きませんでした。お宅へ何つても同じことで、いくらこつちが早く行つても、師匠の御用意が出来る頃には皆お歴々が見え「お先きに」と順番を取られてしまひ、その間に楽屋入りの時間になつてしまひます。挨拶のあるのはまだよい方で、松葉屋さん位になると、後から来て何もいはず先に稽古をすませて帰られます。
こゝで一寸私の母のことについて申さねばなりません。それは、私が松島の文楽座の大序ヘ入つて、はじめて座から包金二十銭を頂いて帰つたときは、神棚へ供へて非常に喜んでくれたのですが、性来勝気の、厳格な人でしたから、彦六座へ入つてとにかく役がつき、薄給ながらお給金を頂くやうになつたとき、「芸人の修行といふもんは、自分で苦労して、自分の力で立つて行かないかんもんだす。かならず親がゐると思ふたらあきまへんで」との詞を残して、家を畳んでふいと神戸へ行つてしまひました。後に残されて宿なしになつた私は、しようことなしに知合ひの家を転々とあちこちに居候生活を続けねばなりませんでした。これから数年の間が私の一生の中で一番苦しかつた時代で、彦六座がはねてから、心済[斎]橋の欄干に肱をついて考え込んだことは一度や二度でなく、そんなとき私は勿体なくも、酷い親と母を恨みました。これは後で知つたことですが、母は私が立寄りさうな先へ「楠之助が御無心にまゐりましたらどうか一時立替へてやつて下さい。私からお返し致しますから」といひに廻つてくれたさうです。申訳ないことには、当時私はそんなことゝは夢にも知らなかつたのです。しかし後になつて考へて見ますと、母が私を残してたち退いてしまつたことが、結局先で非常に私の幸になつたのです。
といふのは、丁度この当時清水町の師匠のお宅の露路内の長屋が一軒空いてゐるといふことを、師匠のお宅にゐるおくみといふ古い女中から聞いたのです。詳しく位置を申しますと、師匠のお宅は表通りが露路口で、勝手口を出たところに長屋の総井戸と雪隠があつて、そのとつつきの、師匠のお宅の丁度うしろ横になる家でした。かねて知り合の家を居候に歩いてゐた間のことゝて、別にどうするといふ目当もなかつたのですが、何とかせねばと思つてゐたところへの話でもあり、第一師匠のお宅にくつついた家といふのが師匠に近づく何よりの手段だと思ひましたので、早速詳しい様子をきいてみると、空いてゐるのも道理、もとその家に住んでゐたといふのがやもめの女髪結で、それが浮世の男を拵らへて子供が生まれると男は逃げてしまひました。もとより狭い長屋中のことゝて忽ち噂が広がり、女は悲感の揚句その家で首を吊つて死んでしまひ、残つた子供は屋根松屋の支配人などが計つて里子にやりましたが、子供に想が残つてか、その女の幽霊が出るとか、人玉が出るとかの噂のため借手がつかなかつたらしいのです。といつていつまでも空けて置くのは用心が悪く、家主の方では誰か入つてくれないかと探してゐた位だつたさうで、早速師匠のお家に口次ぎをして頂いて、いざ入る段になると家賃が五円だとのことです。当時の私には五円の家などにはとても住めませんでしたが、師匠のお宅の隣といふことが思ひ切れず、その家の因縁や家主の肚につけ込んで破格に二円にまけてもらひ、その代り必要なときはいつでも出るといふ条件をつけました。当時私の彦六座のお給金は二円だつたので、家賃だけはやつと払へるとしても後の生活費はどこからも出る目当はなかつたのですが、まあ何とかなるだらうと遂にその家には入つてしまひました。
さては入つたところが、その家には表の戸締りの外畳も建具も附いてゐなかつたのです。もとより自分で工面出来る筈はなく、思案の末、南地「平辰」の小六といふ名妓から犬を一匹もらつて来て、夜は押入の中に莚を敷いて一緒に寝ることにしました。この頃の私の生活ぶりは実に惨めなもので、着物といへば年中垢染みた袷一枚、それにすつた下駄といふ風体でしたから、芝居の中でも私の傍を避けるものが少くありませんでした。また肝腎の商売道具の撥は、普通稽古用の撥先だけ象牙の木撥に、紙を張つて丸象牙に見えるやうにし――この撥は後年まで自分の記念として残して置きましたが、花隈から今の家に引越したときに何処へしまい込んだか見当りません――三味線の張替は「桝東」の温情に縋つて前借ばかりでした。そして懐中は常に無一物同様、家での食物はお洗米のお粥、なんぼなんでもそれだけではお腹が堪りませんから、おくみさんの機嫌を取つて師匠のお家のお残りをよく頂き、唯一の家族の犬には拾ひ喰ひをしてもらはねばなりませんでした。この犬はすい犬(ぬく犬)で、名前だけは一人前にポチとつけてやりましたが、私のような主人で犬も可愛想でした。
ところである朝、ポチがしきりと吠えるのに眼を醒ましますと、「友はんお師匠はん来やしたで」とおくみさんの声がします。私は「しもたツ、えらいとこ見られた」と思ひましたがもう遅く、「そこ友のうちか、まだ寝てんのか」と師匠のお声も聞えて来ました。師匠は朝お手水を使はれた後、はしりに水をお撒きになるのが習慣て[で]、これは餓鬼に水を遣るお積りだつたさうです。その序にふとお見えになつたので、私はどうしようかと、思ひましたが、出ぬわけに行かず、戸口に控へてゐますと、師匠は家の中へ入つてみえて、「えらい暗いやないか、畳ひいてないのか」と仰つしやつて、しばらく辺りを見て居られましたがそのまゝまた出て行かれました。このときに何か独り言をぶつぶついふて居られましたが、向ふをむいて居られたので私には何かきゝ取れませんでした。
が、それから間もなくして、師匠の私に対する態度が変り、師匠の方から「稽古してやる」と仰せ出され、こつちは、長い間それを待つてゐました、と飛びついて節匠の前に座る。そこまではすらすらと進むのですが、それから先が大変で、今までとは打つて変つてのお稽古の厳しさ、急に殖えたお小言、一所が出来ぬために行詰つてしまつて、持ちも提げもならぬやうなことが度々ありました。しかしこれは、何とかして師匠に特別の教へを乞いたいといふ私の凝り固つた一心が遂に師匠に届いて、かほどの難儀をしてまでもわしの芸を学びたいのか、うい奴じや、と潜越ながら師匠に見込まれたのだと私は思つてゐます。
その後私は右の家に相当長い間住んでゐましたが、追々と建具なども入れられるやうになりました。また後には靱(油掛町)に、更に後に高麗橋(浮世小路)に稽古場を拵へました。これは稲荷座の晩年のことです。
が[か]うなると万事都合よく行くもので、おくみさんはおくみさんで私を可愛がつてくれ、「お腹がでけへえへなんだらお稽古もでけしまへん、今のうちによばれなはれ」と師匠のお宅のお台所の片隅で御飯を振舞つてくれ、私は十分お腹を拵らへて師匠の前へ出る、お稽古は今申す通りの厳しき[さ]ですが、こつちは命懸げ[け]で学ばうとかゝつてゐますから、師匠の仰つしやることも早晩は納得行く、次第に師匠も楽しまれ、源吉さん同様、撥遣ひ、指遣ひ、足取、息の一つ一つ、そして語る方のことも音遣ひ、詞もていねいにいつて下され、その一一が成程々々と感じ入ることばかりで、生活には苦しい時代でしたが、六十年間あとにもさきにもこの時代ぐらひ張合ひのある気持で稽古に励んだことはありませんでした。
と申すものゝ、お稽古で一箇所かゝつて、それを通して頂くまでの難しさ、苦しさは大ていのことではなく、「違ふ」と一言仰つしやつて、私の顔をじつと御覧になるときのお顔はとても怖しいものに見えました。
一例を申しますと、「一の谷熊谷陣屋」の枕で、「ヲクリ」がすんで「シヤン、相模は――」となるその「シヤン」の撥が問題で、普通の「シヤン」や「トテン」ではいけないのです。師匠は「そこは『チヤン』や」と仰つしやるのですが、師匠のいはれるやうな音が中々出ません。 何しろ師匠のは撥遣ひが根本から違ひ、従つて仕事も多く、さうなると撥の拵らへからして師匠と同じものにせなければ学ぶことが出来ません。私も次第にそのことに気がついて撥屋に削つてもらひましたが、かうなつて来ないといけないと思ひます。
清水町の師匠の連弾きを勤めさせて頂くのは私の最後の望みでした。それは師匠の芸を学ぶのにこれ以上の方法はなかつたからです。毎日「舞台で死ぬ」覚悟でして居られる芸に直接ぶつかつて行くのですから。師匠の連弾きはたいてい源吉さんでしたが、彦六座の終り頃からお蔭で私も連弾きをさせて頂くやうになり、初めの中は「阿古屋琴責」などで源吉さんと私の二人が連弾きに出たりしましたが、後には「堀川」、「狐火」、「吃又」など度々勤めさせて頂きました。その代り油断も隙もあつたものではなく、それこそ命懸けで勤めねばなりません。まづ連弾きの憲法として、撥から指から息、間[+、]全部師匠と揃はねばならず、これは理窟[+か]らいへば師匠と私とでは力が違ひますから同じことが弾けるわけはないのですが、「わしと揃はないかて[ん]」といふ師匠の命令ですから、出た以上は出来ても出来なくてもやらねばなりません。そして「揃ふ」といふことが、たゞほゞ同じやうに弾くといふことでなく、隅から隅までぴつたり一致せねば及第でないのですから、連弾きの役だけ稽古をしたのでは駄目で、師匠の芸の真髄を掴んでゐなければ出来ないことです。ですからいろいろな方が連弾きをして居られるのをきゝましたが、師匠と芸の違ふ方は出てゐて困つて居られました。また師匠直門の中にも師匠の連弾きが出来ない方も少くありませんでした。そして一ヶ所息を外したら最後、何様師匠の方は運びがきまつてゐますから、こつちが立直るところが中々なく、悪くすると終りまで揃はず終ひになることがあります。勿論こちらが立直なのを師匠の方で待つやうな容赦は絶対されませんから、丁度真剣勝負です。油断して外したら最後、そこで斬られたのと同じことです。
一例をいひますと、「吃又」の連弾きで、「土佐の又平光起が――」の前の「シヤン」、この最初の「シヤン」の撥が完全に揃はねばならないのです。これは私が師匠に随分やかましくいはれたことです。その上、この前に調子が上りますが、その上げ方が師匠のは三本の糸巻きを順にキユツ、キユツ、キユツ、とひねられるだけで、「テン」とも「トン」とも弾いてみられませんから、こちらも弾くことが出来ず――つまり合はすことが出来ず、調子の上げ方からして師匠と同じことをせねばなりません。この外「狐火」では源吉さんと二人で大分苦労しました。 こんな風ですから勉強になることは此上ないのですが、随分気を遣ひます。これは大分後のことですが、どうか師匠の連弾きを無事勤め了せられるやうに、とかねて信心してゐた伏見の稲荷さんへ日参し、お山の七本の滝に打たれに行つたことがありました。これがたしか「阿古屋」のときで、それから間もなく「堀川」を勤めさせて頂きま一[し]た。
たしか明治廿一二年の頃と思ひます。大隅さん、清水町の師匠、源さん、寛三郎(後の五代目仲助)さん、春子さん、助三郎、それから今の新左衛門も一緒で、下へ旅興行に出て居られました。その旅先の長崎で清水町の師匠がインフルエンザで容体がむづかしいといふ報らせが十二月の廿八日に我々の所へ来ました。そこで何としても看病に出掛けねばならず、万一の場合は死際にもお目にかゝつて置かねばと思ひ、源吉さんと二人で急に旅立つことにしました。当時源吉さんは神戸で稽古をして居り、私も時々神戸へ来てゐましたが、私は年末で旅費もなく、取り敢へず源吉さんに一足先に立つてもらふことにして、源吉さんは廿九日に神戸を立ち、大晦日に長埼に着きました。私も着物や何かを質に入れて三十日にやつと旅費八円を作りました。ところが昔から大晦日に舟出すると縁起が悪いときいてゐましたが、そんなこと構つて居られず、大晦日に立つて正月の二日に長崎へ着きました。芝居は勿論とやで、一座のものは二階借りをしたりして惨めな生活をしてゐました。清水町の師匠は、榎津町の旅館で養生して居られましたが、皆々一生懸命看病した甲斐あつて、私が着いたときはもう熱も下つてゐました。そしてそのとき喜ばれて、「元日にほんぶくせしうれしさのあまり口合長崎のつるのみなとに命をばつなぎとめたる御代の初春」と一首詠まれました。この短冊は今古靱さんが持つてゐます。それからまもなくてすつかり全快されましたので、一まづ大阪へ帰られることゝなり、源吉さんがお伴をして行きすぐまた引返へして大隅さんを弾くことになりました。
源吉さんの帰りを待つて、二月一日に榎津座で返り初日をあけましたが、少しも見物は来ませんでした。この時土佐太夫がまだ馬太夫といつて、大隅さんのところへ弟子入りしたてゞ、浄瑠璃も語らず、附人で来てゐましたが、声もよいので、急に出すことになつて、大隅さんは私に、「友やん、うちの馬公弾いてくれるか」といはれ、承知して伊達太夫として弾いて出ることになりましたが、これが伊達太夫と私との縁のはじめであります。この興行は不入のまゝ無理に十日間程打ちましたが、到底お仕打からの借りを捌けるどころではありませんでした。その時のお仕打は、同地の顔役の江口源太郎といふお年寄をはじめ、大壷市太郎、外にもう一二人あつたと思ひます。そして、大隅さんはこの間、贔負[屓]先の高野平の永見家に寄寓して居られました。またこの間に長崎の節分に会ひましたが、実に賑やかなものでした。
それからこのまゝでは到底いかず、協議の上熊本で打たうといふことになり、こんな談判の上手な伊達太夫が三角を廻つて熊本へ売込みに行きましたところ、同地米屋町の中島茂七といつて、「東雲」といふ女郎屋をしてゐる大成金の旦那と話が纏つて、「ハナシデキタ○ウケトツタアンシンセヨ」との電報が来ましたので、一座の者は皆いきり立ちました。
やがて伊達太夫は手金百円を持つて戻つて来ましたので、長崎でのお仕打の江口さんが改めて太夫元となつて熊本へついて来てくれました。江日さんはお金持ではなかつたのですが、看板がよかつたので、一座に取つては頼もしい後盾でした。そこで熊本へ乗込んで東雲座で開場しましたら大当りで、三十日間打ちつゞけました。勿論みどりですが、毎晩芸題が替つたのは大隅さん一人で、後はさうさう種がなく、掛合などにしてお茶を濁してゐました。伊達太夫は勿論種などなく、私と二人で昼夜兼行で烈しい稽古をして、大至急で語り物を拵らへましたがこれが伊達太夫の出世の糸口で、声はよし、男前はよし、忽ちにして人気が出て、御贔負[屓]も沢山出来、終ひにはお仕打の中島さんが「伊達が人気がよいから春子との順を変へたら」と大隅さんのところへいつて来られましたが、大隅さんが「さうはいきまへん」といふのを春子太夫が譲つたので順番が変りました。後年死ぬまで伊達太夫が得意にしてゐた語り物はたいていこの時に出来たものです。この時の伊達太夫の御贔負[屓]の中の一人にお仕打の中島さんの御家内の親の下川亀吉さんがあり、伊達太夫と私とは「東雲」の店で泊つてゐました。
熊本を打上げてから一行は、佐賀で打ち、それから人力車で久留米へ行き、博多へ着き、博多では共楽座で興行をしました。次に小倉を経て下関を打つて、大阪へ帰りました。
明治廿五年に清水町の師匠は大隅さんを連れて東京へ巡業に出掛けられ、それより廿六年にかけて東海道の各地から伊勢路、四国、九州まで廻られ、私も伊達さんを弾ひてずつとお伴をしました。
清水町の師匠の東京の御出勤は以前は何回もあつたことゝ思ひますが、私がお伴したのはこのときが初めで、同時に師匠の東京御出勤の最後でした。もう木挽町の歌舞伎座も出来てゐましたが、当時は「睦」を廻りましたから、師匠は歌舞伎座を御存じないじまひでした。その頃の寄席は十五日間で、木戸は十銭位でした。この後私が井上竹次郎時代に歌舞伎座へ出たり、また最近今の歌舞伎座や他の大劇場へ出て、時勢とはいひながら高い観覧料を取つてゐるのは、その度毎にいつも勿体ないことだと思つてゐます。一座の顔触れは、大隅(先代)さんに清水町の師匠、伊達太夫に私、春子太夫に団吉(後の団左衛門)、一太夫に寛之助(後の三代目寛三郎)、隅治太夫(初め四代目住太夫の門人にて住治太夫と書き後大隅太夫へ入門隅治と改む、後絹太夫更に筆太夫と改む)に力松(後の伝平)、勇太夫(元豊沢団勇)に団右、福太夫(伊達太夫の門人)に団友などで、東海道の旅から津ばめ太夫、今の古靱さんが加わりました。この中で今残つてゐるものは古靱さんと団友と私だけです。東京の宿は浅草新福井町の「福清」で、ここは大阪の「南一」のやうな温泉宿式で座敷も沢山ありました。滞在中に先々代片市(片岡市蔵)さんが三日にあげず訪ねて来られて、清水町の師匠にいろいろお話をきいて居られました。
また私はさる御ひいきの御紹介で梅若実さんのお舞台の寒稽古を見学させて頂きましたが、若いお弟子は皆素足でお稽古をして居られるのを中央に実さんが怖い顔をして見張つて居られ舞台の端へ来たお弟子を順々に突落されるのですが、大ていは白洲へ落ち、私の拝見したときは一人だけ残りましたが、お稽古ぶりの厳格なのに感心しました。それから滞在中にお能を拝見し、宝生新作[朔]さんの「勧進帳」のワキにすつかり感服しました。名乗りだけで全曲のすがたが出てゐました。
東京を立つて東海道の各地を打ちながら下つて来ましたが、静岡へ来ましたとき、一日大隅さんの語り物が「忠臣蔵九段目」で、そのとき土地の顔役で、先の清六さんの一番上の兄さん(今の大隅太夫の伯父)が楽屋へ見えて、清水町の師匠に「今夜は師匠の『九段目』をゆつくりきかせていたゞきましたが、大変面白うございました。殊に枕の雪景色、中々あゝ迄は弾けんものと存じます。真に迫つて実に結構でございました。有難う存じました」と御礼を述べられて、次いで傍の大隅さんに向つて、「師匠に較べる大隅さん、あんたはまだ/\ですわい」と評されたので、大隅さん急に顔をふくらし、傍に座つてゐた我々は笑ふに笑はれず、困つたことがありました。しかしこのときに限らず、師匠の「九段目」の枕は実際結構でした。「チンテンチンテン、ツツントンツン」の弾出しの間、太夫が「人の心の――」を語り出すまでにもうすつかり山科の雪景色を弾き表さねばならないので、一つ一つに寂しいウナリが必要で、左の指遣ひの修錬によるものです。
それから一度大阪へ帰つて、すぐまた中国四国から九州へ行きました。たしかこの旅に立つときだつたと思ひます。大阪駅で皆が待合はせてゐましたとき、師匠は縮緬の頭巾を耳から頭ヘかけてお高僧頭巾にし、その上から山高帽子をかぶられ、真正面に三等の赤切符をはさんで待つて居られました。皆は二等で行く積りをしてゐたのに師匠が三等切符を持つて居られるのを見て、誰か師匠に二等に乗られるようにすゝめようといふことになつて、私がその役を仰せ付かり、師匠のところへ行き
「お師匠はん三等より二等の方がよろしまつせ」
と申上げますと、師匠は真面目な顔付きで
「二等の方が先に着くのか」
と仰つしやつたのには困りました。まさか「さよです」ともいはれず、「同じことです」ともいへず、二の句がつげず引下りました。
この巡業中伊達太夫は「酒屋」をずつと持つて廻つてゐて私が弾いてゐましたが、一日我々のやつてゐるのを師匠がお聞きになつて、役をすませて御挨拶に出ましたとき「おい友、あのチン(今頃は半七さん、チン)はいかんで」とお小言を頂戴しました。しかしどういけないのかは御説明がありません。これは清水町の師匠に限らず昔の方は全部この式でした。さあその夜から「チン」一撥が気になつて気になつて仕方がありませんでしたが、別にどう弾くといふ見当もつかず、唯伊達さんが「今頃は半七さん」といふのを「チン」と一撥うけるだけですから、心にかゝりながらも舞台でそこへ来るとそのまゝ弾いてしまひ、役をすませて「有難うございました」をいにひ[ひに]行くとその日から師匠の御返事はなく、その都度「あゝまだいかんのやな」と思ひ、師匠の夜のお酒のお酌で(巡業中のお酒はお宅のときよりずつと長い時間でした[+)]、御機嫌のよいときを計つて遠廻しに探り出さうとしましたが中々仰つしや[+い]ません。思案にあぐみ果たまゝ次々と旅を続けてゐましたが、忘れもしません、一月の末か二月の初め頃でした、四国の丸亀ヘ来たときのことです。或晩師匠のお酒のお酌を終つて、自分の部屋に帰つたのが一時頃、寝床ヘ入つてからも寝つかれぬまゝに例の「チン」のことを考へてゐましたが、時刻にすればかれこれ丑満時、二時頃でせう、深夜の静けさを破つて突然「チョピーン」といふ音が聞えて来ました。それは宿の庭の釣瓶から井の中へ落ちる雫の音なのですが、時刻といひ、場所といひ、蒲団の中で瞑想してゐる私の耳へは此上もなく寂しく、且鋭く聞え、思はず身震いをしましたが、と同時に「これや、『酒屋』の『チン』はこの気持や、」と気がつき、それからはすつかり興奮してしまつて、明日の舞台の段取などを考へて見ましたが、あの「チン」は出来るだけ寂しい気持で弾かねばお園のやるせない気持は弾き表せないと気がつきました。師匠にお小言を頂戴してからもう数ケ月、その間考へに考へ通したがわからず、それが偶然の雫の音からヒントを得る事が出来たが、これこそ神のお恵みに違ひないと思ひました。遂にその夜は「酒屋」で明かしてしまひ、翌朝になつて早速伊達さんに訳を話して「今頃は半七さん」を出来るだけ締めて寂しくいつてくれと注文し、私も前夜の寂しい気持を一心に撥と指に込めて「チン」を弾き、無事役を終つて、「今日はどう仰つしやるやろ、ほめて頂けるかしら」と師匠の前へ「有難うございました」と御挨拶に出ましたら、「チン」に関しては何も仰つしやいませんでしたが、私の挨拶に対して久々御返事がありました。「今日の『チン』でよいのや」との御言葉がありませんでしたからこれで及第してしまつたとは申切れませんが、お返事の様子から見て、「酒屋」のチンは多分これでよいのだらう、と今だに思つてゐます。
年月をはつきり記憶しませんが、稲荷座が出来て間もない頃と思ひます。神戸の長狭通に「はり半座」といふ寄席程度の芝居があつて、その頃大隅さんは年に一度出て居られました。ある時清水町の師匠がお千賀さんの買ふて来られた上草履を部屋用に持つて行つて履いて居られました。それが花魁の草履のやうなぶ厚いもので、裏につるつるの皮がついてゐましたのでよくすべり、他から見て危かしく、殊に楽屋が二階でしたから私は一度、危いから外のをおはきになつたら、と申上げやうと思つてゐましたが、師匠は喜んで履いて居られたので遂そのまゝになつてゐました。すると案のじやうある日役の前のお手水に行かれるとき仰向けにすべりこけて、右手を怪我されました。
お身体には別状はありませんでしたが、右手のお怪我ですから舞台へは出られず、源吉(後の三代目団平)さんは一座に居ず、止むなく私が代り役をさせて頂くことになりました。その晩の大隅さんの出し物が「合邦」で、ほんとうの今いふて今の代役ですから、弾合せる隙もなく舞台へ上りましたが、大隅さんはさぞ頼りなかつたことゝ思ひました。その翌晩は「太十」で次は何か忘れましたが、やはり大物でしたので、急に「帯屋」と「新口」につき替えて、三日間師匠の代役を勤めさせて頂きました。
稲荷座時代だつたと思ひます。井上侯爵、後藤、土方伯爵などの間に天聴義太夫の御計画がもち上りました。それはさきに歌舞伎では団十郎菊五郎など、相撲では梅ケ谷常陸山などの天覧がありましたので、義太夫もお聴きに達したら、といふことになつたのです。さて光栄の演奏者と外題ですが、越路太夫一人で長い時間は御迷惑であるから、掛合で何か華やかなもので団平の三味線をお聴きに入れなければ、と、越路太夫の阿古屋、大隅太夫の重忠に団平の三味線と内定し、連弾きは越路さんから吉兵衛をとの注文でしたが、清水町の師匠は、源吉をといはれ、こゝで一悶着ありましたが、結局両人とも出るといふことで納まり、私は清水町の師匠にくつついて琴と胡弓に出して頂かうと一生懸命になつてゐましたが、後藤の御前でしたかゞ「義太夫はよいが、大隅のアノ芋づらと、吉兵衛の黒づらが御目に入るのは畏れ多い」と仰つしやつてゐました。その中井上様か後藤様かゞ御病気になられて、折角のお話が立消えてしまひました。これは斯道に取つて実に残念なことで、このとき実行されてゐたら我義太夫史の上に一光栄を残すことが出来たのです。私も一生の大自□[慢]が出来るところでしたのに。尤も大昔は天聴義太夫は度々あつたさうで、当時は御簾を垂げて語り、その御簾を頂戴し、受領されて退下されたのです。誰方のか知りませんが、頂いて帰られた御簾が、氏太夫(元養老太夫)が因講の頭取をしてゐた頃まで残つてゐましたが、惜しいかな船場の火事で焼けました。
明治三十五年の一月に東京の歌舞伎座で「廿四孝の御殿」が出て、「狐火」で伊達太夫を私が弾いて出語りを勤めました。これは最初は五代目が八重垣姫を勤める筈であつ[+た]のが、十二月中に中風が起つて出られなくなつたので、栄三郎(後の梅幸)さんが代ることになり、我々も新富町の五代目のお宅へ伺つて急に稽古を始めました。勿論人形振りですから、我々の方から変へて行く必要はなく、普通にやるのですが、役者衆の方は平常使つてゐるチョボの「間」と大分違ふものに乗つて行かねばならず、そこが稽古のしどころで、栄三郎さんもその点大分てこずつて居られましたので、少し位は我々の方から譲歩してもよいと思つてゐましたが、隣の部屋の病床の上で見物してゐる五代目が中々許さず、いろいろとダメを出すのですが、中気で舌が廻らす[ず]何をいつて居られるのか全然きゝ取れず、栄三郎さんがおろおろするので余計に癇が立つて来て、終ひには栄三郎さんを呼びつけて襟首をつかんで顔を畳にすりつけて怒られました。お稽古とはいひながら栄三郎さんにあんまり気の毒でもあり、第一病人の為によくないといふので、翌日からは別の場所で稽古をし、やつと初日まで漕ぎつけました。幕切れは何かよい趣向はないかといろいろ考へましたが名案もなく、丁度清水町のお千賀さんの筆で師匠が節付された一節があるのをやつて、立方は兜を持つて「枕瑞[獅]子」のやうな引込みにして幕にしましたが、お蔭で好評を博しました。このときは皆顔を揃へるのだといつて市村(当時家橘)さんは出遣ひの人形遣を勤め、八百蔵(後の中車)さんは口上を述べてゐました。
その年十一月の歌舞伎座は団菊の顔合せで、中幕に九代目の重太郎、五代目の喜内といふ配役で「講釈」の七ツ目が出て、私も度々見物しましたが、肝腎の「重太郎出かした」の条の五代目が今一息のやうに思つてゐました。すると或る日五代目から使ひが来て行つて見ると、五代目は二番目の「弁天小僧」の顔をしてゐるところで、私に、
「友さん見てくれたかね」
「拝見しました」
「何処か悪いところはないかね、気が付いたところがあつたら言つてくんねえ」
といはれるので、例のところと、はつきりいはず、それとなく不満をほのめかしましたら、五代目は、
「何処だい、『破れ扇』かい、『疱瘡子』かい」
と一生懸命です。そこで「重太郎出かした」が今一息だと思つた、と率直にいひましたら、五代目は、ではどうすればいゝんだ、といはれますから、それは天下の五代目に友松風情の者が教へるといふやうなことは出来ない、と申しますと、それならば一つ工風をするからまた見てくれ、とその日は引下りました。翌日になると男衆が私を迎へに来ましたので行つてみると、前日とは変へてやつて居られるが感心はしませんでした。楽屋へ行くと五代目は、
「どうだい今日のは」
とたづねられるので、思つた通りを遠慮なく
「まだいきまへんな」
と答へますと
「さうかい、また見てくれ」
とのことで、それから数日間毎日「喜内」の時間になると男衆が呼びに来て毎日見に行きましたが、流石は五代目で、毎日型が変つてゐました。しかしどうもこつちの思ふ壷へ嵌りませんでした。五代目の方でも気に掛けて、或る日私を家へ招いて
「いつたいどうすりやいゝんだ、おねげえだから教へてくんね」
と頼まれましたが、いくら何でも五代目に教へるなど、少し心臓が強すぎると思ひましたから、再び辞退しましたが、五代目は懸命に、
「いゝよ、この部屋には誰もいねえよ、ちよつといつてくれよ」
と立つての頼みでしたので、私も遂に折れて、
「そないいひなはるのなら申上げまひよ、しかしこれは勿論私の考へた型やおまん。以前ある人形遣ひがやつてたのを私がおぼえてゝ、あんたにはなしゝた、といふのならあんたのお顔も立ち、また事実それに違ひおまへんのやさかい。
これまで拝見してますと、重太郎が子供を殺す前、『口に称名手に小柄――』あたりであんたの喜内が屏風の陰で様子をうかゞうてゝ、そこで延び上つて『重太郎出かした』をいふてなはるが、その恰好がこつちから見ると幽霊かなんぞのやうに見えますのや。ましてあんたとこのお家芸に幽霊もんが多いよつてよけいさう思はれます。前に私が見て、えゝな、と思ふたんは『重太郎出かした』で屏風と一緒に喜内も前へ倒れる型で、とても烈しうてよろしおました。丁度幸ひ歌舞伎やと喜内が二重にゐまつさかい、屏風を倒して平舞台へ橋になるやうにしてその上を転ろがつて平舞台で『出かした』をやりはつたらえゝやろと思ひまんが、どうでつしやろ」
と申しましたら、五代目はしばらく考へてゐましたが「いやどうも有難う、一つやつてみよう」と早速小道具方に屏風を特別に誂へて準備をされました。翌日は先方から迎ひが来るまでもなく、早目にこつちから出向いて見物しましたが、「重太郎出かした」の条は大当りでした。幕が切れてから重太郎の九代目も
「おい寺島、今日のはとてもいゝじやねえか」
とほめて居られました。
この当時伊達太夫と私は、柳適(二代目)さんや鍛[錣]太夫その他で一座を作つてゐて、方々の寄席や、歌舞伎座の名人会のやうなものにも出たり、また東京を中心に各地へ巡業に出、北海道までも行つたりしました。東京では築地二丁目に家を一軒借りて、一座の谷路太夫の女房が台所をしてくれ、皆一緒に住んでゐました。今の清六は政治郎といつてこのときに私のところへ来て、大阪へ連れて帰つたのです。もう一人友太郎といふのも一緒に連れて帰りましたが、これは芸はよく、教へなくても具合など勝手に弾ける質でしたが、途中で辛抱出来ず、横須賀へ行つて稽古屋になり其後死にました。政治郎の方は手が強張つて中々弾けませんでしたが、私の家のいろいろな用事をさせてゐる中でも朱の本など見て勉強を怠らなかつた甲斐あつて今日までになつたのです。
また私が長年弾いて来た伊達太夫と別れようと決心したのもこの頃でした。勿論それを口外したり、亳も素振りに出さなかつた積りでしたが、有名な横浜の富貴楼のお倉が私の心中を見破つてしまひました。そして、今別れては両方の為に悪いから、と懇々と諭されましたが、私は間もなく大阪へ帰り、伊達太夫とも別れ、一身上の都合で舞台もやめ、神戸へ引込んでしまひました。富貴楼のお倉ともそれつきり会ひません。
その年の七月(明治三十五年)、伊達(後の土佐)太夫に私がシンに柳適(二代目)太夫などで東京の寄席廻りをし、夏になつてから一座を横浜へ持つて行つて、鉄橋の「富竹」といふ横浜では名題の寄席で興行してゐました。そこへひよつこり大阪から人形の紋十郎(先代)さんが訪ねて来て、話をきくと、夏場で文楽が休みなので暇にまかせて東京へ来たら、我々が横浜で興行してゐることを知つて、我々の床で東京の旧知の人形遣ひを集めて(紋十郎は四代目西川伊三郎の門人)一つ人形入りで一芝居拵らへたい、といふのです。しかし何様無人でこのまゝでは何ともならないので、どうすればよからうと思案をした揚句、我々の一座の頭取が七五三太夫(先代)の親の高久で、これが東京の明治座のお仕打に縁故があるので、一つ明治座へ話し込んでみようといふことになつてかけ合つて見ると、明治座も夏で入れものに困つてゐたところなので、早速引受けてくれました。紋十郎さんも明治座で打つのなら無人では恥しいからと、大阪から玉助(二代目)、助太郎、玉六(現玉七)、紋太郎(後の三左衛門)などを呼んで一座を拵へ、その上最初は誰の案か知りませんが、常盤津林中(初代)さん(三味線は文字兵衛さん)が一座に加はることになり、八月三日に初日を開けましたが、義太夫と常盤津の合同といふ珍らしい試みが市中の人気を呼び大変な大入りでした。我々の方の一座の顔触れは、伊達太夫、柳適太夫(二代目)、相生太夫(二代目で後の二代目綾瀬太夫、今の相生太夫の祖父)、錣太夫(先年歿)、和佐太夫(今の米翁)、谷路太夫に、三味線は私、卯三郎(今の紋左衛門)、弥七(元竹沢小弥七といひ、大三味線弥七の養子)、語左衛門(語息斎の門人)[+、]寛三郎(三代目先年歿)、卯之助(三代目清六の門人)で、私は「三番叟」と「先代御殿」、二の替りに「宿屋」を勤め、林中さんの語り物は初めが「吉田屋」、二の替りが「乗合船」で実に結構なものでした。それもその筈で、今から考へてみれば一座の中で、当時ほんとうの芸人といふのは林中さんだけでした。
最近では文楽座でも度々出ますし、四五年前に京都の顔見世興行で猿之助さんが踊つて私が弾きましたのが大変当つて、それ以来毎年出るやうになりました。
この曲で一番大切なことは、翁、千歳、三番叟の三つの位取です。我田引水のやうですが、その点で、能の「翁」は別として、各流の「三番叟」の中で義太夫の「三番叟」が一番結構に出来てゐるやうに思ひます。これ程位取の鮮かなのを外に知りません。私がいつも知りたいと思つてゐますのは、これを節付された方のお名前です。これ程結構な曲が残つてゐるのに未だに不明なのです。
文章は中々難しいもので、よくその意味を研究しませんと飛んでもない間違ひをします。かの「とうとうたらり――」は蒙古か西蔵あたりの言葉ださうで、以前ある博士が解説されたのが新聞に出て、切抜いて置きましたが、要するに位取が最も肝腎で、それによつて夫々「音遣ひ」、「足取」、「間」、「模様」のやり方が違ふのです。
翁は宇宙の支配者の格で、殊に面をつけてからは畏れ多くも天照皇太神宮様の位ですから、雄大無比でなければいけません。「万代の池の亀は甲に三曲を戴いたり。滝の水麗々と落て夜の月あざやかにうかんだり渚の砂さくさくとして旦の日の色をらうず」有様を御覧になつて、「天下がよく治まつてゐる、悦ばしいことだ」と舞を舞ふて御座るのです。といつてこれを殊更に勿体振つてやりますと陰気になつてしまひます。翁を語つて陰気になつたら恥です。私が聞かせて頂いた翁の中で最も結構でしたのはやはり大掾(二代目竹本越路太夫)さんでした。明治十八年東京猿若町の文楽座開場祝のときで、その音遣ひは子供ながらに神々しく感じました。その前に彦六座の改築祝のときに柳適さん(初代)が語られましたが、これも結構でした。この時は清水町の師匠が弾かれ、三味線ではこの方の右に出るものはないことは申すまでもないことです。千歳は武士ですから、何物にも拉がぬ勢がその「間」になければなりません。
三番叟は農民で、世界中の悦びを我身一つに受けて悦んでゐる、といふ心でなければいけません。それにこれは狂言ですから、詞は狂言風にいはねばならず、今日の文楽座でこれが出来てゐるのを聞いたことがありません。それから「御田」の条で、早乙女と神主さまのやりとりの語り分け、弾き分けが曖味になりやすいもので、よく気をつけねばなりません。
後藤象次郎、猛太郎両伯爵御親子の間のことは我々がお話しするよりもつと詳しく御存じの方や記したものも勿論あるでせうが、伊達(後の土佐)太夫と私がこのお二方の間に関係したことがありますので、そのときのお話しを致します。
もつとも伊達太夫は伯爵と同じ土佐の出でもあり、伯爵の奥様の舎弟がもとの歌舞伎座の社長の井上竹次郎で、その奥さんがおうたさんといつて伊達太夫の妹といふ関係がありましたので、初めは伯爵家の書生をしてゐたのですが、声がよいから太夫になつたら、といふことになつて、越路(後の摂津大掾)さんか大隅さんのどちらかへ弟子入りしようと考へてゐたところへ大隅さんが上京されたので大隅さんへ入門して、さしづめ本名の馬太郎の一字を取つて馬太夫と名乗つたやうなわけですから、後藤家の御贔屓で、続いて合三味線の私も何かと御贔屓にして頂いてゐたのが話の始りです。
明治三十五年に伊達太夫と私が東京に滞在してゐました頃、猛太郎さんはあることで象次郎伯爵の勘気を蒙り、越後の新潟の方に行つて居られ、同地で何かの会社に関係しておいで[+に]なりましたが、その御勘当も半ばゆりて(許されて)ゐました。象次郎伯としては新潟に於ける御子息の謹慎ぶりを今一度調べてからすつかり御勘当を許さうと思つて居られたので、その偵察を伊達太夫と私にお命じになつたのです。普通のものをやると猛太郎さんが感づくから我々を派遣するといふことになつたのですが、それも唯行つてはよくないと、象次郎伯がお口きゝで越後路の旅興行といふことにして出掛けたのです。つまり後藤の御前様のお仕打といふわけです。
当時信越線は直江津が終点で、新潟へ行くには直江津から船で行つたのです。ところが我々が直江津へ着きますと日本海が荒れてゐて船が欠航してゐるのです。致し方なく船待ちをしてゐますと、もう我々の来てゐることが新潟の猛太郎さんのところへ聞えたかして、猛太郎さんの方から直江津まで出むいて来られました。そしてこんなところにゐても仕方がないからこれから山越しで新潟まで行かう、と仰言つて五人曳きの車を仕立て米山越へをして、新潟へ向ひました。猛太郎さんと申すお方は、性来頭が敏く、いはゞその時代の尖端を行くお方で、従つてなさることはとても大きく、中々の事業家でいらつしやるのですが、何様周囲のものがそれについて行けず時折失敗のやうなことになつて、御親父さんや御親戚の方々の御不興を蒙られるのですが、事柄は小さいにもせよこの五人曳きなどもその一つの表れで、猛太郎さんと我々二人、合計三人に十五人の車夫がかゝるといふ豪勢さです。五人曳きとは梶棒が一人にその前に二人綱をつけて引張り、後押しが二人といふもので、速いことは普通の人力の比でなく、その代りお尻が痛くて乗つて居られぬ位でした。そして当時は電話はもう通じてゐましたから、宿場宿場へ、電話をかけて車夫を十五人誂へて置き、一つの宿場へ着いてお茶を呑んだり、小用をしたりするだけ休んでまた次へ向ふのでした。
そして米山の嶮所へさしかゝると車を担いで行くので、お駕籠と違つて背が高く、片方は崖で下は日本海の荒浪ですからその怖ろしさといつたらありませんでした。かうして信濃川の沿岸の与板といふところまで行つて、そこから側面に車のついた船で川を横断するのですが、信濃川は日々瀬が変るとかいつて船はあつちへ行つたりこつちへ行つたり随分長い間かゝりました。そして新潟へ入つたのですが、新潟での猛太郎さんの勢力は実に大したもので、会津屋といふ妓楼に入りびたりで、花魁は総揚げといふ大尽ぶりでした。我々もお相伴役で結構は結構でしたが、肝腎の象次郎伯からの内命に報告せねばならぬのには困りました。有りの儘を知らせば御勘当は許されぬに定つてゐるし、丸きり嘘をいふわけにも行かず、もとより敏い猛太郎さんですから我々が偵察に来たこと位初めから御存じで、最初からすつかり買収されてしまつてゐるわけで、その辺は伊達さんと相談して程よく申上げて逃れましたが、遂に御勘当は許されました。これは一つはお孫さんが出来て居られたためもありました。このとき私達は新潟に丁度二ケ月程居ました。
杉山其日庵茂丸さんには随分長い間御贔屓になりました。道八の名も旦那や小美田さんなどにつけて頂いたのです。旦那ほど義太夫に精通して居られた方はないと思ひます。私が伊達太夫(後の土佐)を弾いて東京に滞在してゐる間も始終お目にかゝつてゐましたが、引退してからも旦那が大阪へお越しになるときによくお呼び出しに預り、中の島の銀水などで、松屋町の広助さんと三人で何度も夜通しでお話をしたことがありました。私が神戸から出て来てお座致へ伺ひますと、松屋町からいきなり「なにしてんねん、出んか」と怒鳴られたことがありました。その後古靱さんも一緒のことがあり、やはり夜明しで、次の間に寛三郎や素女が控えてゐて、眠くて弱つてゐました。その中夜が明けて来て、雀が啼き出しましたので、素女が「旦那もう雀が啼いとります」と申しましたら、「雀が啼くのは当り前じや」といつて居られました。旦那は存外早くお逝くなりになりましたが、もつと長生きをして頂いて斯道の為に尽して頂きたかつた、と返へらぬことながら常に残念に思つてゐます。
私が明治三十五年ぎりで引退して、一身上の都合で神戸へ住ひ、大正十三年御霊文楽座へ再び出るまでの間神戸でした仕事について申上ませう。
私の家内は梅吉と申し、神戸の花隈で矢島といつて芸妓屋をして居りましたが、その頃の神戸の花柳界の有様は実にだらしがなく、芸者は南京芸者とか、淫売芸者だとかの異名をもらつて居り、事実専らその通りで、芸のことなど眼中になく、従つて演舞場など勿論なく、芸の歴史といふものが全然ありませんでした。大阪の花柳界と出会のときなどでも、芸ごとが始まると神戸の芸妓は隅の方へ退いて、お尻をもぢ/\させてゐるやうな有様でした。
私も丁度引退してから、何とか有意義に月日を送りたいと考へてゐました折柄家内の稼業を幸に、一つ神戸の花街の建直しに尽力してみようと決心をしました。何にせよ早く稽古を始めることが第一で、それには所属の中検(中の検番)の許しを得なければならないので、二人の主任に事情を話して口説きにかゝりましたが、こちらに信用がなかつたのか、中々困難でした。やつと許しを得ましたので、まず師匠を定めにかゝりましたが、長唄が当時日露戦争から凱旋して来た杵屋佐吉さん、常盤津はその頃京都に居られた林中さん、鳴物は福原鶴三郎さんに頼み、踊は大阪から楳茂都扇性(今の陸平さんの先代)さんが、汽車賃向ふ持ちで来て頂くことになりました。そこで、花隈に一軒家を借りて二階は踊、階下は地方の稽古場と定め、まず家内の妹分九人をはじめ、他所からも来て三十人程連中を集め鶯集会と名づけ、稽古場では一切膝を崩すことならん、といふことをはじめに、時間のことやら、その他厳重な規則を定め、猛練習を始めました。この間私は表面へ出ず、万事陰で指図をしてゐましたが、芸妓の負担を出来るだけ軽くしてやるのにとても骨が折れました。かうしてしばらく続けてゐる中に総てが段々とよくなり、成果が外へ現れるやうになつて来ましたので、検番でも黙つて見て居られぬやうになり、手伝ひに出て来ました。
そこで、何とかしてこれを世間に問ふて見なければならず、普通のことでは面白くなく、色々考へた揚句、服部兵庫県知事を間接に動かして神戸在住の各国の領事に案内を出して、見てもらふことにしました。たしか五月頃で、会場は三宮警察から少し浜寄りの、旧居留地の名前を忘れましたが、何とかクラブとかいふダンスホールで、外人相手ですから午後八時の案内で番組は「五条橋」、「螢狩」、「小鍛治」、「元禄花見踊」の四つを選びました。当夜になつて、我々は六時頃から会場へ出向いて色々準備をしてゐましたが、七時すぎになつても一人のお客も来ないどころか、場内の瓦斯もつけてくれません。刻々時間が迫つて来るので、こつちはそろそろ心配をしはじめましたら、その中に七時五十分になると、灯火が一勢につきましたが、その明るいことは不夜城の如く驚きました。そして、七時五十五分になると俄に車の音がして来て馬車と人力で、一時に五六十人お客さんが見えました。見ると男は皆燕尾服、女はドレスで、玄関へ入ると一勢に帽子と外套を脱いで、傍の帽子掛に銘々かけてゐましたが、それが少しも混雑せず、実に順序よく運んで行くのに感心しました。それから次々と場席へついたのですがその静粛なことに二度びつくりしました。お客さんが揃つたので、ではすぐ開幕しませうと告げると、監督が来て「まだ一分早い」といひますので、命令通り一分待つて、正八時に開演しました。この時思ひ出したのですが、私がこの会場へ来て、はじめて監督に会つたとき、監督が「時計を合はせて置きます」といひました。その時私は「なんでやいなあ」と思つてゐましたが、これ程時刻を厳格にやるとは思つてゐませんでした。
かくして当夜の催しは大成功のうちに終り、その後間もなく各国から礼状が来ましたが、これは今中検に紀念として残してあると思ひます。また私は御礼に上等の萄萄酒をもらひました。とに角、私の力の及ぶ範囲での国際的な仕事でしたから、これを見た柳原や福原の花街でもじつとして居られなくなりました。
それから、中検では年二回春秋に大温習会を催すことになり、奉は着流しで会場は神港倶楽部、秋は衣裳付で大国座を借りることにしました。
その他東京の真似をして元禄芸者を十人拵へ、その衣裳を大阪の丸亀屋に飾つたら、大阪にはまだなかつたのでびつくりしたさうです。
一昨年(昭和十六年)の春、木村富子さんの作で、私が節付した「酔奴」を猿之助さんが東劇で出したとき、持物に竹馬を使ふことを私もいひ出しました。その稽古のとき振附師の花柳寿輔さんにお目にかゝりましたが、当代のお父さんに当る名人の先代花柳寿輔さんに私はよくお目にかゝつたことがあることを話しましたら、今の寿輔さんはまだ小さくてよく憶えて居られないさうで、非常に懐しがつて居られました、そのときの話しで「酔奴」の節付の中に「仙台浄瑠璃」の一節を取入れた話から、かの常盤津の「蜘珠の糸」の座頭の物語の踊の中で「金だぞよ銀だぞよ」といふところを振付されたときのお話をしました。それはいろいろ結構な振りを残して居られる名人の寿輔さんですが、何様相手が盲人で、それが金だ銀だといふのですから流石に行き詰られてしばらくそのまゝになつてゐたさうです。その中さる旅先の宿で按摩を取つて居られるとき、ふつと思ひついて「按摩さん、お前さん方は金と銀との区別はわかるかな」とたずねてみられました。すると按摩は「そりやすぐわかりますよ」といひます、「どうして区別するんだ」ときかれると「嘗めますよ」と答へたのです。寿輔さんは、はたと膝をたゝいて「成程ツ」と感心し、それにヒントを得て考へられた末、嘗めるのは振りとしてよくないから、頬に触れてみるといふ振りを案出されたのです。そして、「金だぞや銀だぞよ」は今だに手で頬をするやうな振りが伝はつてゐるといふのです。このいはれは今の寿輔さんはまだ御存じなかつたので、お話しましたとき、大変喜んで居られました。
昨年の六月に猿之助さん一座の「三番叟」を弾きに九州を巡業しましたとき、熊本の芝居で流石にまだ地方らしく、小屋の裏にはなれがあつて、そこに厠があり、その奥が小使部屋になつてゐました。私は用達に行つて何気なく見ると小使部屋に何かしら小さい動物が動いてゐます。大かしらと思つたのですが、少し様子が違ふのでよく眺めて見ると小狐が飼つてあるのです。それが小犬と同じやうに下駄にぢやれてゐるのですが、ぢやれ方は犬と亦全然違ひます。じつと見てゐると実に面白く、その中に忠信や八重垣姫の狐の振りが思ひ出されて、誰方が付けられたのか知りませんが、実によく付けられたものとつくづく感心しました。手の恰好などそのまゝで、下駄と鼓とを替えれば四段目の忠信そつくりです。それから一人で見るのは勿体ないから、猿之助さんにも参考のため見せて置くとよいと思つて「一寸よいものを見せてあげますさかいおいなはれ」といつて呼んで来ましたら、段四郎も一緒に来て感心して見てゐました。狐がぢやれてゐるところなど動物園でも一寸見られず、ほんとうによい勉強をしました。
我々が毎日舞台で鳴らしてゐます三味線は、三味線屋から皮が張れて来て、それに棹を突込んで絃を掛けた[-だ]ゞけで鳴つてゐるのではありません。舞台で使へるやうにするまでには、三味線弾の手に入つてからなかなかの一仕事があるのです。それを三味線の拵へといつて居りますが、一度拵へた三味線は皮が破れるか、さもなくば興行が終るまでそのまゝでいゝかといふと決してさうでなく、殆んど毎日調べなければなりません、まして天候の不順なときなどは格別です。ですから我々は舞台へ上る少くとも二時間、ときによつては三時間位前に楽屋入りをして準備をせねばなりません。これは一般のお客様にはわかつて頂けぬことですが、歌舞伎役者が荒事などの役で隈の多い面倒な顔を造つて、たいさうな衣裳をつける以上の時間を要します。
さて、三味線の拵へと申すのは、一口に申せば絃張り――絃の高さ(皮と絃、棹と絃との距離)と駒を調べることなのですが、それが皮によつて悉く違ふのですから、そこに厄介な問題が生れて来るのです。早い話が同じ猫でも夫々体質が違ふ筈で、達者なのもあればか弱いのもあるわけで、こゝでもう皮の質(厚さ)がはつきり別れて来ると思ひます。これを皮の肉と申して、三味線の皮として最初にやかましく吟味する点であります。すべて少し薄い目の皮がよいとしてありますが、どういふわけですか、三味線屋がこれなれば皮の性質もよし、肉もよしと見て、湿して胴へ張つてから急に肉がついて来るのがあつて、そんなのは駄目です。その外死際の悪かつた猫などもいけないでせう。それから皮の晒し具合――昔は木灰汁で晒しましたから皮の色は茶色がゝつてゐましたが、今は薬品を使ひますから皮の色は真白で綺麗ですが皮の為にはやはり木灰汁がよろしい――も大関係しますが、三味線屋の手に入つてからの皮の仕立、つまり三味線屋の仕事の領分ですが、これが第一肝腎です。
そこでかりに非常によい皮が一枚三味線屋の手に入つたとします。三味線屋はそれを一且[旦]、水の中に漬けて上から重しをしてしばらく湿し、それを出して布でくるんで水気を取つて胴へのせるのですが、この仕事は一流の三味線屋でないとようしません。太棹の方では大阪の「半助」だけでせう。胴の上へのせた皮はもぢり竹、もぢり紐、くさびにかけてそれを槌で打つて皮を締めて行くのですが、その打つ槌が真所で、初めに真中のくさびを打ち、次に両脇を打つので「トン」と打てばそれだけ皮が緊張して行き、構はず打つて行けば終ひには皮は裂けてしまひます。その裂ける一歩手前まで槌が打ち込んであるのが最もよいのです。すべて縦はある程度十分に打てますが、横が大事です。もう一つ打つて置かう、と思つて打つとバンと裂けてしまつて皮一枚丸損で、折角のそれまでの仕事もほんとうに水の泡になつてしまひます。それと反対に「破れるかも知れんが、一枚損をしてもよい、もう一つ打つて置かう」と、「トン」と一つ打つて破れなかつたらしめたもので、最上に張れたことになるのですが、この一瞬間が実に危機一発[髪]のところです。ところが「もう一つ打つたらよいのだが、破れたら損だからもうこの辺で止めておかう」といふのも間々あつて、そんなのは不十分です。つまり思ひ切つた仕事でなければいけないのです。それから槌の「間」と打つときの息が大切なことは申すまでもありません。
現今は堀江に「半助」といふ三味線屋が一軒だけ残つてゐて主人はよい腕ですが、以前のやうなよい材料もなく、時勢の関係で昔ほどのよい仕事が出来ません。私共の修行時代には「桝東」、「桝善」、「若村屋」、「勝助」などゝいふ中々権式のあるよい三味線屋がありました。この中でも「桝東」、「桝善」が筆頭で、清水町の師匠へ出入してゐたのもこの二つの店でした。この二軒は本家と分家の関係だつたと思ひますが、どつちが本家であつたかは忘れました。今の「半助」は「桝東」の弟子です。
「桝東」は三休橋安堂寺町南入東側二軒目にあつて、私達の知つてゐる頃の親爺はもう仕事をやめて「雨夕」といつて俳諧師になつてゐました。そして伊助といふ弟子を娘の養子にして、東助を名乗らせてこれが仕事をしてゐましたが、これが中々よく張りました。酒が好きで、清水町の師匠からの注文などの大事の三味線を張る時は一杯引かけてよい気持になつたところで槌を持つて、息をつめて暫らく伺つて、息の積んだところでよい「間」で「トン、トン/\――」と打つてゐました。惜しいことには割合に早死にで、その息子――これは実子で――がまたよく張りましたが、これも若死しました。半助はこの人の弟子に当るわけです。
「桝善」は博労町心斎橋東入、学校の隣にありました、話が脇へ入りますが、その頃は学校で時の大鼓を打つたものです。初め捨太鼓といつて合図の大鼓が「ドン/\/\/\――」と鳴[-権]つて、次に一時になら一ツ、五時なれば五ツ鳴ります。「桝善」の主人は善助といつて中々権式を持つてゐて、「桝善」で張つた三味線を拵へても鳴らなくて、張り替へてくれ、と持つて行くと、皮をポン/\とはじいて見て、「これで鳴らん筈はない、これでよう鳴らさんやうなら手を張り替へて来い」といひ放ちました。それも一かどの立物衆に向つてずけ/\いつたのですから大したものでしたが、また鳴らないやうな仕事は決してしませんでしたから結局勉強しない三味線弾は泣寝入りで致し方なかつたのです。
「若村屋」も古い店で、主人はよく張り、西横堀筋新町橋西詰、南寄りにありました。
「勝助」は「桝東」の別家で、新町塀の側西寄北側にあり、これもよく張りました。
これらの三味線屋が揃つてあつた時代は皆一等の仕事で、皮が破れる一歩前まで打ち込んでありましたからよく鳴りましたし、皮のくるいも少く、強いのになると一年位も持ちました。しかしそれはずつと舞台で使つてゐてのことで、抛つておくとすぐ破れます。最近のは逆で、この間東京へ出勤しましたとき、三味線を四挺用意して行き中日頃に調べてみましたらどれも破れてゐませんでした。つまり昔のは弾き込めたのです。かう申すと今の三味線屋(「半助」)を排斥するやうですが、前にも申す通り材料や何やかの関係で致し方ないのです。三挺張れて来て三挺とも使へない場合もあります。我々としても辛抱して拵への方で出来るだけ補はねばなりません。ところで一概によく張れたのがよいといふものゝ、無法に張れすぎたのはいけません。昔は田舎の三味線屋などによくこの式のがあつて――今でもあるでせうが[+――]、大阪の「桝東」、「桝善」など一流所の張つた皮を叩いてみて、「こんな張れ方でよいのですか」といつて、国へ帰つてから「大阪で一流などゝいつてゐるが大したことはない」などゝいつてゐるものがあつたやうです。この無法に張れすぎてゐるのは小さくて甲(カン)ばつた音がします。それも時が経つて皮がヘたるに従つて次第によくなりますが、その頃には打つ撥が利かなくなつて結局いけません。つまりよくは張れてゐなければなりませんが、張り立てから皮の伸縮の余裕といひますか、よい具合がなければいけません。そこに口では申されぬ、また他人に教へようとて教へられぬ妙があるのです。
話が前後になりましたが、我々が三味線を張りにやるときは、舞台で弾く外題、太夫の声柄によつて皮を注文します。例へば二匁八分(駒の目方)で六本(調子)、といふ風に誂へて、張れて来た三味線に二匁八分の駒をかけて六本の調子にするとピツタリ合ふわけで、それに三匁の駒をかけるとよい音が出ないのです。これを駒が合はんといつてゐます。これは皮の張り方の技巧で、「半助」に注文すると殆んど完全に合つた皮を張つて来ます。外題では「廿四孝の御殿」などは高調子で、音の重みよりも派手な音を出さねばなりませんから厚い目の皮を注文してそれに軽い駒をかけて弾きます。それと反対に大時代の三段目物などは低調子で、重味のある雄大な音でなければいけませんから薄い皮で、重い駒をかけます。「鰻谷」などもその曲風からいつて重味のある音がよくうつります。「景事物」はまた格別です。それから相手の太夫の声柄によつて三味線の調子が違ひます。普通一番よいところで五本半から六本少し出る位ですが、それで上がつかえる太夫を弾く場合などやはり皮を考へねばなりません。はらはら屋の呂太夫(初代)さんの調子は二分位でこんなのは特別ですが、彦六では住さん、柳適さんがだいたい五本、大隅さん組さんが五本半から時によつて六本そこそこ、千駒さん朝さんは六本しつかりあり、低い方では弥太夫(五代目)さんが四分足らずでした。
この外に三味線弾によつて皮の好みがあります。これは長年の間誂へてゐる三味線屋との以心伝心で、三味線屋が「この皮は誰某によからう」と、張つてくれます。こんなときだとか、特別に注文を出したときなど、三味線屋は自分が苦心して張つた皮でどんな音が出るだらうかと芝居へよくきゝに来ます。今でも「半助」はよく文楽へきゝに来てゐます。「桝東」や「桝善」など清水町の師匠が三味線を拵へられるところからきゝに来てゐました。こゝらが三味線屋の楽しみなところでせう。
結局おしなべてどういふ皮がよいかといひますと、乳の締つた、多少薄目で張れ上つた、特に撥下駒下のよく張れてあるのをよいとしてゐます。そして張れて来た皮を指でポン/\とはじいてその音をきくとよしあしはほゞわかります。
畢竟義太夫の三味線屋の仕事は一つの立派な芸術で、商売づくでは決してよい仕事は出来ません。金儲けが目的なら細棹の三味線屋になるがよく、琴屋は一番よい儲けでせう。
以上がだいたい三味線屋の仕事で、これから先、舞台で弾けるやうにするまでが三味線弾の仕事、三味線の拵へであります。
三味線の拵へといふものは、要は皮を上台として絃張り、サワリ、駒の調節――使ひこなしなのですが、その定つた法則といふものがなく――ないことはありませんが、総て感がもとで、それに今までお話した通り、材料も仕事も機械といふものを一切使つてなく、全部人手ですからその出来上りも似よりはあつても二つと同じものはないので、それを皆ある程度まで美しい音が出るやうに調節するのですから、その方法は三味線一つ一つによつて皆違ふわけです。ですからこゝにお話し申すのはほんの特別の場合と、拵への苦心の一端だけです。
そこで誂へておいた三味線が張れて来ますと、第一はそれの鑑定です。勿論三味線屋が届けて来るまでには今まで申したやうな苦心はしてゐますが、一応は使へるものか使へないものかを試して見なければなりません。まして近頃は材料なり仕事なりが一般に下つてゐますから、折角張れて来ても使へない場合が間々あります。尤もそんなことは昔でもありましたが、今ほどではありませんでした。この鑑定は皮の急所を指でポン/\とはじいて見るとだいたいの見当はつきますが、何といつても拵への技術が問題で、折角よく張れてあるのに、三味線弾の方でそれを拵へる技術を持ち合はさないために鑑定を誤り、張り直してほしいと持つて行く場合もあります。前にお話した昔の「桝善」の主人に怒鳴られるのはこんな場合で、今の「半助」は「手を張り替へて来い」などと酷いことはいひませんが、三味線弾の方が誤つてゐて、「半助」の方で不服なときは今日でも屡々あると思ひます。こんな場合もありますから、三味線弾が皮も張れると一番よいのですが、さうも行きません。私の知つてゐる限りでは松屋町だけが、三味線屋をして居られましたから、よく自分で好きなやうに張つて居られ、よい音がしてゐました。
それはさておき、仮りに張れて来た三味線の鑑定が無事すんで、これなら使へると定つたら、まづ絃張りの調節にかゝるのですか[が]、これが最初の難関で、どんな皮のときにはどれ位の高さといふことが定つてゐませんから物さしを使ふことは出来ず、初めに目分量でよい加減の高さに拵へて弾いて見て、その音で見当をつけて高さを変へて行くのですが、これが二三回で出来上ることもありますが、十数回、数十回、一日かゝることもあります。そんなときは耳が麻痺してしまつて一番よいところへ来てゐながら聞き逃して、また変へることがあります。ですから拵へるときには聞手が一人ゐるのが一番よく、私も清水町の師匠の聞き役を度々しましたが、殆んどこの間に拵へ方を勉強させて頂きました。師匠の命令ですぐ前で聞いたり、次の間へ行つて聞いたりして、「前のと今のとどつちがえゝ」とのおたづねに対し、「三は前の方がよろしおましたが、二は今度の方がよろしおます」などお答へするのです。この間に師匠の三味線の扱ひ方を見、音を聞いて拵へを憶えるので、拵への伝授法はこの外にはありません。
この絃張りについて起つて来る問題がサワリで、これは三味線の音色、殊に弾く役場に最も重大な関係のあるものです。尤も絃張りがちやんと調へば自然よいサわリがつくのが定式で、つまり皮の絃張りと棹の絃張りとサワリ(一の絃と棹の山との触れ加減)との三つは釣合ふものなのですが、度々申すやうに数字で割り出すことゝ違ひますから中々さううまく行きませんので、いろ/\加工せねばなりません。しかしこれがまた加減もので、サワリがつきすぎるとジャブ/\と音がして、蝉の鳴く声のやうだといつて元祖から厭つてゐます。それに調子も合ひにくゝなります。外題の方からいひますと、「廿四孝御殿」、「盛衰記神崎揚屋」のやうなものは幾分サワリが余計にある方が映りがよろしい。私の口からいひにくいことですが、今文楽では清六のサワリがほんとうの切場のサワリです。
次に駒ですが、これは駒そのものの善悪もありますが、その扱ひ方が大切です。今は駒屋がなくなりましたが、前は「吉金」――俗に「吉キン」と[+い]つて三代前の主人が名人でした。駒の地は水牛で昔は鉛も何も籠めてなく一手でしたが――その時代の駒を私が子供のとき師匠の吉左衛門さんから頂いて一つ持つてゐます。中古から鉛を籠めて種々の目方のものが沢山出来ました。これは非常な便利なものですが、水牛の生地によつて乾いて来る程締つて鉛が浮くことがあり、さうなると音はビゞつて台なしになりますから、鉛は舞台へ上る前によく調べて槌で打ち込んでおかねばならず、どうかしたはづみで舞台で浮いて来る場合もあります。駒は穴のくり具合によつて鳴るので、どんな名人の駒師でも全く同じ駒は二つと出来ません。そのくり具合がまた皮によつて合ふのと合はないのとありますから、同じ目方の駒を沢山持つてゐなければなりません。私が三味線を一つ拵へるときは持つてゐるだけの駒を全部前にならべます。
それから駒の扱ひ方ですが、これは中々むづかしいもので、絃張りよりもこの方が重要な位です。現在は軽重六通りの駒が出来てゐて、皮と調子によつて扱ひこなすのですが、清水町の師匠はその上尚調節する為、鎮(しづ)をつけて拵へて居られました。これは地唄の方でやつたことで、師匠はそれからヒントを得られたのだと思ひますが、駒の扱ひの中で最もむづかしい高級なもので、余程勉強せねば出来ぬ拵へです。この場合は薄目の皮を誂へて、駒を鎮(しづ)で重めにして合はすのですから、下手をするととんでもない音になつてしまひますが、成功すると実に雄大な結構な音が出来ます。それが清水町の師匠の音なのです。尤も高調子のときは厚皮ですから鎮(しづ)は殆んど用ひられませんが、六本以下位の調子のときはたいてい鎮(しづ)で拵へて居られました。濳越な話ですが、先年映画の「浪花女」のトーキーの方で清水町の師匠の真似をせねばならぬことになりましたとき、映画のことですから日本全国までいき渡るわけで、まだ清水町の師匠を御存じの方も居られる筈で、万一そんな方がお聞きになつたとき、一寸影法師のやうなものがあるな、と思つて頂きたかつたので、鎮(しづ)で拵へた三味線を使ひました。清水町の師匠の足許へも及ばぬことは勿論ですが、普通のときの私の音とは変つてゐた筈です。この鎮(しづ)の拵へのとき駒をニジラせて据えることが必要になつて来るので、鎮も用ひないのに定式だと思つてニジラせて据えてゐるのをよく見かけますが、実に笑止です。鎮のつけどころもその場合によつて違ひ、駒の上、下、時にはくりの内側からつけることもあります。それがどんなときにどうするといふことは口では申されません。その場その場に当つて研究するのです。近頃文楽の楽屋で、清六が弾いてゐるのをきいて鎮の扱ひ方を伝授してゐます。もう櫓下を弾いてゐるのですから、鎮で拵へねばいかん、といつてゐます。
次に絃、これは新しいのがよいことは申すに及ばぬことですが、絃も昔は手で縒りましたから今の紡績のものより質は上でした。中でも一の絃の縒りはサワリに大関係しますから大切です。絃は何よりも湿りを厭ひまして、糊がシヤリ/\してゐるものでないと音が出ません。ですから梅雨時が一番にが手で、缶に入れるのは勿論、燥実を焚いて乾かします。巡業のときも持つて行つた方が安全で田舎へ行くと売つてゐないことがあつて困つたりします。こんなにしておいても湿りのひどいときは舞台で弾いてゐる間に縒りが戻つてベト/\して来ることがあり、殊に一の絃がくるふと「サワリ」がくるつて来て仕末におへません。丁度鼓と正反対になるわけです。清水町の師匠が絃の扱ひに深い注意をされたのは全く右の点で、その日の天候を非常に気にして居られました。それからよく絃が風を引くといふことをいひますが、風を引くことはないので、結局湿るのが一番いけないのです。といつて直接日に当てるのは悪く、かげ干しがよいのです。
天候との関係のことで感心しましたのは平家琵琶のカミ駒です。あれは三味線と違つて檜に限り、膠でつけず、御飯粒でつけてあります。それはその日の天候によつて場所を変へたり、斜につけかえたりして加減するので、すぐとれるやうにしてあるのです。今はもう平家琵琶を弾く方が殆んどなくなつたやうです。以前京都のお医者で北川といふ方が平家琵琶を弾ぜられるといふことを知つてゐましたので、私も参考の為一通り教はつて置かうと思ひながら遂にそのまゝになつてしまひました。
平家琵琶の楽器そのものも以前引退してゐる間に、神戸元町の太田に出てゐましたので求めましたが、これは楳茂都扇性さんに贈り、その後東京で何かの入札に出たといふことをきゝましたので、是非欲しいと思ひ、道具屋に任せて置き、手に入ることゝ袋の地まで用意してゐましたら、少しのことで他所へ取られてしまひました。その後は一向に見つかりません。
またこれも私が引退してゐる間のことですが、大阪千日前の竹林寺で、平家琵琶を使ふ「頓写」といふ仏事が営まれたとき、早速見学に出かけましたが、坊さんが二列に並んで前列の方がお経を写し、その後で琵琶を弾ずるといふ仏事で、実に荘厳なものでした。
三味線の拵への根本は以上のやうなことですが、一つの三味線を一度拵へ上げたら皮が破れるまでそのまゝでよいかといふと、決してさうでなく、厳格にすれば毎日工夫しなければいけません。私は舞台で弾いてゐる間に、「明日は絃張りを変へならんな」と感じることがよくあります。ところで皮がどれだけへたつたらどれ位拵へを変へて行かねばならぬ、といふ定式がないのですから厄介です。まず絃張りで工夫して見る、駒の重さを変へて見る。据えどこをニジラす、いろいろ研究せねばなりません。この間文楽で清六が一の絃を数日間毎日変へてゐました。一の絃は四五日もつものですが、これは絃のためでなく、皮の調子のため、サワリに影響して来て一を続けて変へたのです。
結局三味線はいらひ通しでないといけません。そして二挺も三挺も壊はして来ないと出来ません。
三味線の音色は、皮の張れ方、拵へも勿論大事ですが、棹と胴との質、細工に根本の問題があります。それは絃から出た音は、胴の木目にひゞき、棹の木目を伝つて初めて三味線の音になるからです。これについて大分以前お名前を忘れましたが、音を研究して居られる博士の方が古靱さんの紹介で私のところへ見え、三味線の音はどうして出るのか、とおたづねになりましたので右のお返事をしましたら、博士も学の方から研究されてさう信じて居られたらしくお話が非常によく合ひました。
棹の材料は紅木や紫檀の埋れ木がよく、樫でもよろしいが、要するに木目が大切で、葡萄の房や、虎の背中のやうな木目のが一番よいのです。そして古くて堅いのは押へた音がよく、樫棹の上へ紅木をはつてよい仕事をしますと、これまた結構な音が出ます。それから一本木の棹がまたよいのですが、品がなく、その代り天柱の木が落ちます。また延棹はくるはなくてよいといひますが、長年の間にはくるふだらうと思ひ、随分薦められましたが私はよう買ひませんでした。我々三味線弾は棹に随分お金をかけますが、決して贅沢ではなく、少しでも音をよくするためなのです。
棹の重さ、太さは材料により、また三味線弾によつて好みが違ひますが、棹の拵へ、つまり「ちぶくろ」から上の仕事が大切です。昔は「ちぶくろ」の形が違つてゐて、指の股がぴつたり添ふやうに出来てゐたのです。これは「三上」殊に「二の上」の譜が押えよく、非常によいのですが、この形は今はありません。私の家にあります胡弓でこの「ちぶくろ」の形のが一つあります。それでも「二の上」は昔から押さえにくいものとしてあつて、「二の上」が減つたら赤飯を炊いてお祝をした位です。私は幸にして若い頃から「二の上」は押さえられてゐましたが、自分でそれを知らず、あるとき清水町の師匠に、「二の上の絃道がへつてどんなりまへんが、なんでゞおまつしやろ」と伺ひましたら、師匠は「見せてみ」と御覧になり、「こら結構やがな、まともに押さえられてるさかい減るのや、これでえゝのや」と教へて頂き、「あゝ左様ですか」と引下つたことがありました。「三上」でも押さえにくいもので、定式は「山」の一寸ニジツタところなのですが、えてしてそこへ指が行かず、そのも一つ下へ行きやす[+い]のです。今文楽の三味線弾でも、ほんとうの「三上」が押さえられてゐるものは少いやうです。
それから「ちぶくろ」の表の渓は出来るだけ深く、山までの間は長い方がよい音がします。今の三味線はたいてい「ちぶくろ」の角に山が拵へてありますが、私は半助に注文して、角より一分位下に山を拵へさせたものがあります。
絃巻は、義太夫の三味線は黒炭[檀]に限りますが、その篏げ方――殊に一と三との篏げ具合、それに穴の場所などは注意して欲しいところです。そして座金の拵へは是非斜でないと、絃巻の納まりが悪く、調子がくるつて来ます。
天柱も音に大関係するもので、天柱袋は舞台では脱がさねばなりません。かぶせてあるとでは音は大分違ひます。それどころか、かぶせたまゝで手厚い撥を打ち込むとポンと飛んで脱げてしまふことがあります。近頃では皆天柱袋をかぶせたまゝ舞台へ出てゐるやうで、中には脱げぬやうに紙を狭んだりしてあるのを見かけますが、実に笑止千万です。
胴は木瓜が一等よく、やはり木目が大切で、度々皮を剥いだ跡形の少いなるべく新しいのがよろしい。それに中のくりをやかましくいひ、本ぐりといふのが一番上等で、これも今日出来ないやうです。
最後に、棹もよく、胴もよいものでも、その仕込み(填込み)がよくなくては何にもなりません。仕込みの悪いのは、いくら他のところが全部がよくても、音が出ず、たまたま無法な拵へをすると音が出ることがあります。
撥は三味線弾によつて大小夫々好みがあり、我々の子供の頃は大きい重い撥を使ふのを自慢にしてゐて、百五十匁、八十匁、中には三百匁位のものを使つて腕が強いといつて誇つてゐましたが、中で清水町の師匠が小さい百二三十匁の撥を使ひ始められ、それで手厚いところは他人一倍手厚く、またあしらひのところなどは全く軽妙に、自由自在にすがたを弾き表して居られましたので、師匠の側近にゐましたものは皆師匠にならつて小さい撥を使ひました。先年亡くなられた東京の松太郎さんも極めて小さい薄い撥でした。弟子の新左衛門も小さいのを使つてゐました。また源吉(後の三代目団平)さんなどは清水町の師匠の撥そつくりのを誂へてゐました。私のも小さいものですが、清水町の師匠の芸風を学ぶのにどうして[+も]小さい撥でないと弾けぬところがあります。
いづれにしても撥は、撥先、握り、さい尻(撥尻)の三つの釣合が整つたものでないといけません。
撥屋は以前は鍛治屋町御池橋東へ入つた北側に「大儀」といふ古い店があつて、沢山の中の一等店で主人は名人でした。この店は早く絶えて、今は下寺町北に「小森」といふのがあり、私の引退してゐる間に出来たらしく、どこの弟子か知りませんが、今の主人は名工で、殊に耳入れの仕上げはこの人が完成して、我々業者に大変な便宜を与へてくれました。耳入れは昔もやりましたが、細工が悪くて、形が変り、弾いてゐる間に離れるおそれがあり、稽吉[古]撥位にしか使はなかつたのが、小森の主人が綺麗に仕上げを完成しました。これはヤスリのよいのを使ふとのことで、そのヤスリを作るヤスリ師は大阪に一人よりゐないさうです。勿論ヤスリだけでなく、よい腕と、長年の研究の贈物でせう。そして絶体に離れません、それでゐて主人が取ると簡単に離れるのが不思議です。何か秘伝があるのだと思ひます。
この耳入れは申すまでもなく、絃と撥の摩擦によつて撥先が減つた部分の補足の修繕で、その減り方が人によつて皆異つてゐますが、減り方を見ればその三味線弾のよしわるしがだいたいわかるものです。つまり撥遣ひのよしあしが形になつて表れてくるのです。勿論清水町の師匠のやうに耳入れの形の通りに減るのが本道です。
三味線の調子は、御承知の通り笙から出たもので、従つて調子笛は昔は笙の笛師が作つたもので、随分よいのがありました。私も清水町の師匠や、勝七師匠から頂戴した変つたのを二、三持つてゐますが、今の出来合ひのは、間には合ひますが、よいのはありません。
二代目新左衛門の思ひ出 [この項原載浄瑠璃雑誌419号(1943.5)30-33]
新左衛門は私にとつてはたつた一人の六十年間の友達でした。
松吉といつて、松太郎さんのところへ弟子入したのは私が三味線弾になつたのより一年程後だつたと思ひます。年はあつちの方が二つ上ですが、若い頃に「おなえ年や/\」といつてゐましたので、後年になつて「あいつ若い時おなえ年やちたのにいつの間にやら二つ下になつてしまひよつた」といつてゐました。
最初は因講の寄合で顔を合せてゐる筈ですが、そのときの記憶はなく、二人がはじめて親しくなつたのは明治十三年の頃でせう姫路へ旅興行に行つたときからです。この興行は太郎助橋の住太夫さんに勝七師匠がシンで、二枚目は仮名太夫さんに松太郎さんで、二人ともに師匠のお伴をして行つたのです、大阪を朝一番の汽車で立つて神戸まで行き、それから入力車に乗り丁度明石が昼で、夕方遅く姫路へ着きました。このときに姫路で二人一緒に撮つた写真が宅にありますが、今思ふとどんな気持で写したのか、おかしいやら懐しい思ひ出です。
この旅の後大阪へ帰つてから、私は師匠とゝもに松島の文楽座に出勤し、松吉は松太郎さんがずつと外の芝居(文楽座以外の人形芝居)に出て居られました関係上師匠について出勤してゐましたから松島の文楽座へは出たことがないでせう。その後彦六座の前身になる日本橋北詰の沢の席が出来たときたしか出てゐたと思ひます。彦六座へ入つたのは私の方が先で、松吉は彦六座の改築が出来た明治十七年九月、松太郎さんが駒太夫(五代目)さんの合三味線で入つて来られたとき師匠について来たのです。このときは清水町の師匠も三番叟の三味線で初めて出られたときで、松吉も私もその豆喰ひに出して頂きました。これが二人が同じ床に出た初めで、この後は一緒に出たことは割合に少なかつたのですが、彦六座では私達二人をお互に競争相手にして励むやうに、役もそのやうにしむけ、番付なども常に同じ位置の筆上と筆下と隔月交代に座りました。こんな例は最近は珍らしくありませんが、当時として全く珍らしいことで、私達二人の外には例がありませんでした。
年月をはつきり記憶しませんが、やはり彦六座のごく初期のことで、船場のどこかのお座敷で三味線会のやうにして「妹背山三段目」を、松屋町が大判事、松太郎さんが定高、仙次郎さんか富助さんかゞ久我之助、兵三(後の六代目吉兵衛)さんがひな鳥の役割で勤められたとき、私達二人が特に選ばれて、私が染太夫の方を、松吉が春太夫の方を弾きました。このときは大変なきゝ手で、中々の盛会でした。これが明治十七八年の頃のことでせう。そして五十年後の昭和八年の暮に東京の歌舞伎座で「山の段」を二人がたま[また]同じ配役で勤めました。この時は松太郎さんが二度もきゝに来て下され、三人で昔のことを語り合ひました。
これも彦六座時代のことですが、当時楽屋で「ハリキリ角力」といふのをよくやりました。これはおもちやの土俵をこしらへてその両側に三味線が調子を合せて置いてあつて、一二三でその前へ座るなり「テヽン」と「ハリキリ」を打ち、それを審査員がきいて勝負を定めて番付を作るのですが、三味線は自分のものを使はれず、座ると同時ですから調子を合すことも許されず、撥だけは自分のを使ひました。審査員は大隅さん、組さん、松屋町などで、今の誰某のは後の撥が死んだとか、息がまぬるかつたとかで軍配を定めるのですが、時によつては審査員同士がモメることもありました。この「ハリキリ角力」に、松吉は小松山、私は友綱、時によつて友千鳥と名乗つて盛んに戦ひましたが、大ていの時私達二人が両方の大関でした。いくら三味線をよく弾いてもこれは「ハリキリ」一度だけのことですから、外せばそれきり負けで、源吉さんや仙次郎さんなどは小結になつたり、時には前頭に下つてゐたこともありました。これはお互の修行時代の思出で、それから松吉は芳太夫や生島太夫や時には七五三太夫を弾き、松三郎と改めて春子太夫を弾くやうになり、清水町の師匠の最後の舞台の興行で新左衛門になつたのです。一方私は隅栄太夫や七五三太夫、生島太夫を弾き、この当時に松吉と一日替りの役があつたりして、その後伊達太夫(後の土佐)を弾き、明治卅五年ぎりて[で]一時引退してしまつたのです。
新左衛門は新町の出で、お父さんを私は知りませんが、おぢいさんは大工で、越後町辺の露路に住んでゐました。お母さんはおじゆ(寿)さんといつてもとは出てゐた人ださうですが、私が知つてからは今の新町演舞場の横手の辺で、たしか「林」といつたと憶えてゐますが小茶屋をしてゐて、新左衛門はこの家で大きくなつたのです。兄弟はなし、大切な一人子で、商売柄でもあり、私と違つてお小遣には不自由をしてゐませんでした。ずつと後に新左衛門が京都の木屋町(後に東山)で「寿」といふ旅館をしてゐましたのはお母さんの名前から取つたのだと思ひます。
芸は御存じの通りの天性綺麗な音の、マクレぬ、よい芸で、死ぬまでボロを出さず終ひでした。そして用ひ方によつてとてもよいところがありました。春子太夫があそこまで語れてゐたのも全く新左衛門が弾いてゐたからです。
近年は大分年を取つてゐました。それもその筈で、家へ帰れば二人も孫があつて「おぢいちやん/\」と呼ばれてゐたからで、私はよく「おぢいちやんなんていはすな、お兄ちやんていふてもらへ」といつてやりました。この間も何処かのお葬式か何かで出会つたとき、息子が後からついて、杖をつきながら歩いてゐましたから、「お前なんや、その杖」と声をかけましたら「ステツキやがな」と痩我慢をいつてゐました。それにつけても可愛さうで堪らぬのは晩年の舞台の待遇でした。何といつても長い間よいのもきゝ、叩き込んだ腕ですから、老いたりと難も床へ上つて三味線を弾けば、若い者の五人や十人かゝつても叶ふ筈はありません。この一月に弾いた「茶屋場」でも太夫は若い者許りで、それを新左衛門が弾いたればこそ「茶屋場」になつたのです。外のものではとてもあれだけ太夫を引張つて行けません。あらが皆出てしまひます。また二月は「石屋の宝引」の掛合で、一月興行の終り頃に楽屋で誰かゞ「お稽古を」と頼んだとき、新左衛門が「お前憶えた通りどないでも語り、わしどないでも弾くよつて、しかし聞えるやうにいふてや」といつてゐたのを傍で聞いたときはほんとうに可愛さうに思ひました。死んだ鍛太夫を弾いてゐる間でさえブツブツいつてゐて、よく私が「そない贅沢いふたかてあかへん、昔と違ふて今は総体が悪なつてんねんさかい」となだめてゐたのですから「宝引」の連中に対してそんなにいふのは無理はないのです。いつかも[+「]この頃は幼稚園の先生や、鳩ポツポと手をたゝいて子供を連れて歩かしてんねん、しかし此頃の子供は中々手強うて先生のいふこときゝよらん」といつてゐました。聞けばこの秋には引退するといつたさうで、近頃のやうに虐待されてゐたら、引退するといひ出すでせう。その時は役によつてツレ弾きにでも出て、花を添えてやらうと思つてゐましたのに。
丁度私が東京の歌舞伎座に出てゐる留守中に死んだので、電報が来たときは役前でしたから私にかくしてあつたらしく、役を終つて相生太夫が披露しましたが、あんまり悲しかつたので声をあげて泣きました。宿へ帰つてからも懐しい思ひ出が次から次と頭に浮んで来て、新左衛門の顔が幻から遁かず、その夜は一睡も出来ませんでした。親子でも六十年一緒に居ることは殆んどありませんから、親身の者に死別するより悲しい思ひでした。実際娘を亡くしたときでもそんなに泣きませんでした。
お正月に会つたとき、「お前とこ今年は喜の字のお祝やな、お祝くれよ」といひましたら、「うんお祝しようと思てるねん、お前とこへもやるさかいお返しくれよ」といつてゐましたのに、香奠を供へねばならぬことになつてしまひました。
| 年月 | 彼[役]場 | 共演者 | ||
| 明治十五年(十四歳) | ||||
| ○ | 六月 | 松島文楽座 | 見習として入座 | |
| ○ | 九月 | 同 | 見習として出勤 | |
| ○ | 十一月 | 同 | 同右 | |
| 明治十六年(十五歳) | ||||
| ○ | 一月 | 京都四条北側演劇 | 忠臣蔵の大序 | 四世長登太夫 |
| ○ | 一月 | 松島文楽座 | 信仰記の大序 | |
| 爪先鼠の琴 | 四世住太夫 | |||
| 三世勝七 | ||||
| ○ | 四月 | 同 | 大江山の大序 | |
| ○ | 六月 | 同 | 彦山の大序 | |
| このときは新左衛門さんが重太夫さんの「嫗山姥」を弾いて居られました。 | ||||
| ○ | 九月 | 同 | 播磨潟の大序 | |
| ○ | 十一月 | 同 | 鬼一の大序 | |
| 同五条橋の連弾 | 六世時太夫外 | |||
| このとき太郎助橋の住さんは病気で休んで居られ、勝七師匠は「大倉卿館」の堀江弥太夫さんを弾いて居られました。 | ||||
| 明治十七年(十六歳) | ||||
| ○ | 一月 | 旅 | ||
| ○ | 二月 | 彦六座 | 橋供養庵室の琴 | 初代柳適太夫 |
| 三世広作 | ||||
| ○ | 三月 | 松島文楽座 | 玉藻前の大序 | |
| ○ | 同月 | 彦六座 | 白石噺浅草の口 | 若靱太夫 |
| ○ | 五月 | 同座 | 岸姫飯原館の中 | 隅栄太夫 |
| 法界坊庵室の口 | 若靱太夫 | |||
| ○ | 六月 | 同座 | 朝顔日記宇治川 | 信太夫 |
| 重太夫 | ||||
| 同宿屋の琴 | 四世重太夫 | |||
| 五世広助 | ||||
| ○ | 七月 | 同座 | 加賀見山の兵法の奥 | 歳太夫 |
| 同又助内の中 | 隅栄太夫 | |||
| 信太夫は住さんの門人で盲人でした。歳太夫も同じく太郎助橋の門人で、元楠太夫といひました。 | ||||
| ○ | 九月 | 同座 | 三番叟の連弾 | 五世駒太夫 |
| 初代柳適太夫 | ||||
| 四世住太夫 | ||||
| 六世組太夫 | ||||
| 三世大隅太夫 | ||||
| 二世団平 | ||||
| 初代新左衛門 | ||||
| 三世広作 | ||||
| 三世源吉外 | ||||
| 大塔宮三の切の胡弓 | 初代柳適太夫 | |||
| 三世広作 | ||||
| 卅三間堂平太郎内の中 | 駒子太夫 | |||
| この興行は彦六座改築落成記念興行で、団平師匠がはじめて彦六座へ出られ、「三番叟」だけを弾かれました。その「三番叟」は引抜いて七段返しなつた長い「三番叟」でした。 | ||||
| ○ | 十一月 | 同座 | 伊賀越の般若坂の口 | 隅栄太夫 |
| ことき団平師匠がはじめて大隅さんを弾かれました。役場は「国姓爺三段目切」で大隅さんは稽古から声をいためて芝居はずつと源(先々代)さん代つてゐました。切狂言の「桂川」の道行のシンの新左衛門(初代)さんがとても結構でした。このとき先日死んだ新左衛門は松吉時代で「新関」の口、芳太夫場を弾いてゐました。 | ||||
| ○ | 十一月 | 同座 | 盛衰記辻法印の口 | 隅栄太夫 |
| 団平師匠は「盛衰記三段目切、逆艪」の柳適さんを弾いて居られました。 | ||||
| 明治十八年(十七歳) | ||||
| ○ | 一月 | 彦六座 | 廿四孝力石 | 若靱太夫 |
| 同桔梗ヶ原口 | 隅栄太夫 | |||
| 団平師匠は「出世太平記九ッ目」、柳適さんを弾いて居られました。 | ||||
| ○ | 二月 | 同座 | 妹脊山序切の口 | 生島太夫 |
| 三段目掛合の琴 | 四世住太夫 | |||
| 初代新左衛門 | ||||
| 団平師匠は「妹背山三段目」の染太夫の方と、附け物の「鳴戸」を弾いて居られました。大隅さんは「杉酒屋」新左衛門さんが弾いて居られましたが実に結構なものでした。我々の知る限りではこれ以上の「杉酒屋」はありません。又「井戸替」は田喜太夫さんで、吉三郎(三代目、後の六代目吉兵衛)さんが抜擢されて弾きました。 | ||||
| ○ | 三月 | 同座 | 千本櫻の尻馬 | 生島太夫 |
| 同川連館の連弾 | 四世住太夫 | |||
| ○ | 四月 | 同座 | 太功記瀬川求女内の中 | 隅栄太夫 |
| 団平師匠は「太功記十段目」、柳適さんを弾いて居られました。 | ||||
| ○ | 五月 | 同座 | 五天竺広野 | 歳太夫 |
| 同桃園 | 隅栄太夫 | |||
| ○ | 六月 | 同座 | 信仰記割普請の中 | 生島太夫 |
| 団平師匠のお役は附け物の「封印切」柳適さんの場でした。 | ||||
| ○ | 七月 | 同座 | 朝顔日記船別れ | 若靱太夫 |
| はじめての昼夜二部興行で「船別れ」は夜の部の大序でした。このとき昼の部に「夏祭」が立つて『泥仕合』が住さんの団七に組さんの義平次の掛合で「舅殺し」の間のメリヤスを清水町の師匠が作曲されました 、いかにも向ふに祭礼の行列行くやうな実に結構な手がついてゐました。これを打揚げてから住さん勝七師匠のお伴をして東京猿若町の文楽へ出たのです。 | ||||
| ○ | 九月 | 東京猿若町文楽座 | 矢口渡頓兵衛内の中 | 二世田喜太夫 |
| ○ | 十月 | 同座 | 廿四孝謙信館の次 | 同 |
| ○ | 十一月 | 同座 | 白石噺逆井村の中 | 同 |
| 阿古屋琴責の三曲 | 二世織太夫 | |||
| 初代呂太夫 | ||||
| 四世住太夫 | ||||
| 五世広助 | ||||
| 二世鶴太郎 | ||||
| 明治十九年(十八歳) | ||||
| この年は上半期は東京で寄席を廻り(四代目住太夫鶴澤勝七の一座にて、二枚目の田喜太夫を弾く)、大阪は夏からコレラが流行して芝居は休んでゐました。 | ||||
| ○ | 九月 | 彦六座競進会 | 振袖始序切 | 袖太夫 |
| ○ | 十月 | 同座競進会 | 合邦下の巻 | 同 |
| 同 | 朝顔日記浜松 | 同 | ||
| この競進会では団平師匠は組さんを弾いて居られました。 | ||||
| ○ | 十一月 | 休 | ||
| ○ | 十二月 | 同座競進会 | 伊賀越円覚寺 | 生島太夫 |
| 嫗山姥足柄山 | 富司太夫 | |||
| 寛三郎外 | ||||
| 明治廿年(十九歳) | ||||
| ○ | 一月 | 同座 | 先代萩の鶴ヶ岡 | 七五三太夫 |
| 景事雪月花の連弾 | 十世若太夫外 | |||
| ○ | 二月 | 同座 | 卅三所桜の宮の連弾 | 十世若太夫 |
| 二世団平 | ||||
| 三世広作 | ||||
| 二世源吉外 | ||||
| 同 東大寺 | 七五三太夫 | |||
| 団平師匠は「桜の宮」と、大隅さんの「壺坂寺」とを弾いて居られました。 | ||||
| ○ | 四月 | 同座 | 玉藻前二の中 | 七五三太夫 |
| ○ | 五月 | 同座 | 菅原大内天変 | 同 |
| 団平師匠は「道明寺」の大隅さんを弾いて居られました。 | ||||
| ○ | 六月 | 同座 | 太功記七ッ目 中 | 生島太夫 |
| 団平師匠のお役は大隅さんの「水責」で、端場の「ちんぷんかんろく」七五三太夫場を松吉の新左衛門が弾いてゐました。 | ||||
| ○ | 七月 | 同座 | 白石噺田植の口 | 七五三太夫 |
| ○ | 九月 | 同座 | 卅三所江州左衛門館の中 | 同 |
| この場は江戸ッ児の浄瑠璃でした。 | ||||
| ○ | 十月 | 同座 | 加賀見山又助内の中 | 田喜太夫 |
| 「又助内」の切は大隅さんと団平師匠、「奥庭」はお千賀さんの加筆に団平師匠の節付で、七五三太夫が語り松吉が弾いてゐました。 | ||||
| ○ | 十一月 | 同座 | 彦山毛谷村の中 | 七五三太夫 |
| ○ | 十二月 | 同座 | 苅萱桑門狐川 | 田喜太夫 |
| 明治廿一年(廿歳) | ||||
| ○ | 一月 | 同座 | 休 | |
| ○ | 二月 | 同座 | 忠臣講釈喜内住家の中 | 同 |
| この興行中に彦六座の火事があり、小屋は全焼、すぐ新築にかゝり六月に落成しました。 | ||||
| ○ | 六月 | 同座 | 休 | |
| ○ | 八月 | 同座 | 朝顔日記船別れ | 芳太夫 |
| ○ | 九月 | 同座 | 伊賀越相合傘 | 七五三太夫 |
| ○ | 十月 | 同座 | 逆巻浪夢夜嵐岩崎谷 | 同 |
| ○ | 十一月 | 同座 | 廿四孝桔梗ヶ原 | 七五三太夫 |
| 芦屋道満信田森 | 生島太夫 | |||
| 右の二役を七五三、生島両太夫一日替り、三味線は松三郎(二世新左衛門)と私の一日替りで勤めました。 | ||||
| 明治廿二年(廿一歳) | ||||
| ○ | 一月 | 同座 | 妹背姫戻り | 七五三太夫 |
| ○ | 二月 | 同座 | 菅原天拝山 | 同 |
| ○ | 三月 | 同座 | 太功記夕顔棚 | 同 |
| ○ | 四月 | 同座 | 信仰記上かん屋 | 同 |
| ○ | 五月 | 同座 | 先代萩竹の間 | 同 |
| 阿古屋琴責の三曲 | 朝太夫 | |||
| 大隅太夫 | ||||
| 組太夫 | ||||
| 源太夫 | ||||
| 二世団平 | ||||
| ○ | 六月 | 同座 | 三代記米洗ひ | 七五三太夫 |
| ○ | 九月 | 同座 | 大塔宮切子渡し | 同 |
| ○ | 十月 | 同座 | 加賀見山廊下 | 同 |
| ○ | 十一月 | 同座 | 日蓮記子売り | 同 |
| 日蓮記爪そき血絞り | 同 | |||
| この場はお千賀さんの作で、老の阪で日親聖人が二人の盗賊に会はれ「先の世でかりたるものを今なすか、おかし申して先で取るのか」詠はれて襟の中の小判を出されるので盗賊が改心するといふ場でした。 | ||||
| ○ | 十二月 | 同座 | 休 | |
| 明治廿三年(廿二歳) | ||||
| ○ | 一月 | 同座 | 合邦住家の中 | 生島太夫 |
| このときの端場はお千賀さんの添作に、団平師匠の節付で講中のお齋よばれの条でした。 | ||||
| ○ | 二月 | 同座 | 伊賀越相合傘 | 生島太夫 |
| ○ | 三月 | 同座 | 忠臣蔵道行 | 田喜太夫外 |
| ○ | 四月 | 同座 | 玉藻前二の中 | 生島太夫 |
| 同三の中 | 七五三太夫 | |||
| ○ | 五月 | 同座 | 卅三所志賀の里 | 同 |
| ○ | 六月 | 同座 | 大江山松太夫内の中 | 同 |
| 千本桜小金吾討死 | 同 | |||
| ○ | 七月 | 同座 | 彦山権現あやめふく | 同 |
| 白石噺田植 | 同 | |||
| ○ | 九月 | 同座 | 布引瀧紅葉山 | 同 |
| ○ | 十月 | 同座 | 五天竺太子難行 | 同 |
| ○ | 十一月 | 同座 | 休 | |
| 明治廿四年(廿三歳) | ||||
| ○ | 一月 | 同座 | 廿四孝于売り | 七五三太夫 |
| 同 鉄砲渡し | 田喜太夫 | |||
| 同 十種香の連弾 | 大隅太夫 | |||
| 二世団平 | ||||
| ○ | 二月 | 巡業 | ||
| 引続き秋まで巡業 | ||||
| ○ | 十月 | 同座 | 一の谷石屋内 | 七五三太夫 |
| 合邦住家の中 | 伊達太夫 | |||
| ○ | 十一月 | 同座 | 日蓮記子売り | 生島太夫 |
| 同座 | 日親記戸陀林 | 伊達太夫 | ||
| 明治廿五年(廿四歳) | ||||
| 明治廿六年(廿五歳) | ||||
| 二年間巡業 | ||||
| 明治廿七年(廿六歳) | ||||
| ○ | 三月 | 稲荷座 | 菅原の茶筌酒 | 伊達太夫 |
| 三番叟の連弾 | 五世弥太夫 | |||
| 三世大隅太夫 | ||||
| 四世越太夫外 | ||||
| 二世団平 | ||||
| 五世源吉外 | ||||
| 廿六年に彦六座が瓦解して、このときが稲荷座の開場式でした。 | ||||
| ○ | 五月 | 休 | ||
| ○ | 六月 | 休 | ||
| ○ | 七月 | 同座 | 白石噺の田植 | 伊達太夫 |
| ○ | 九月 | 同座 | 伊賀越相合傘 | 七五三太夫 |
| 四谷怪談一ッ家 | 同 | |||
| ○ | 十月 | 同座 | 太功記夕顔棚 | 伊達太夫 |
| ○ | 十一月 | 同座 | 野崎村あいたし小助 | 同 |
| 明治廿八年(廿九[七]歳) | ||||
| ○ | 一月 | 千本桜の中 | 七五三太夫 | |
| 阿古屋琴責の三曲 | 三世大隅太夫 | |||
| 伊達太夫外 | ||||
| 二世団平 | ||||
| 五世源吉 | ||||
| ○ | 二月 | 同座 | 加賀見山草履打 | 伊達太夫 |
| 安宅新関の道行 | 二世春子太夫 | |||
| 同 勧進帳の連弾 | 生島太夫 | |||
| 三世大隅太夫 | ||||
| 伊達太夫 | ||||
| 二世団平 | ||||
| 龍助 | ||||
| 源吉外 | ||||
| 「勧進帳」の書卸しで、道行は歌舞伎の「鞍馬獅子」のやうなもので、次の「新関所」(新靱太夫役場)はチヤリ場で「三国関所」のやうな場でした。「勧進帳」の段は只今文楽で演るものですが、この書卸しのときのは随分長く、今演つてゐるのはその三分の二位です。弁慶は生島太夫が抜擢されて語りました。今やらぬところで奥の義経と弁慶のやりとりなど結構な節が付いてゐますから、一度全部やるとよいと思ひます。生島太夫は声もあり、音も遣へたので中々よく語りましたが、師匠の大隅さんが富樫で「ヤアレ暫く、富樫之助正広それへ参つて糺さん」と一言語られたら居並んでゐた太夫連は皆スツ飛んでしまひました。因みにこの作者はお千賀さんではありません。 | ||||
| ○ | 三月 | 同座 | 恋女房坂の下 | 伊達太夫 |
| 嫗山姥御殿 | 生島太夫 | |||
| 伊達太夫外 | ||||
| ○ | 四月 | 同座 | 廿四孝四段目の連弾 | 伊達太夫 |
| 二世春子太夫 | ||||
| 三世大隅太夫外 | ||||
| 二世団平 | ||||
| ○ | 五月 | 同座 | 休 | |
| ○ | 六月 | 同座 | 休 | |
| ○ | 十月 | 同座 | 休 | |
| ○ | 十一月 | 同座 | 植木屋 | 伊達太夫 |
| 二世春子太夫外 | ||||
| 明治廿九年(廿八歳) | ||||
| ○ | 一月 | 同座 | 明烏山名屋 | 伊達太夫 |
| ○ | 二月 | 同座 | 休 | |
| ○ | 三月 | 同座 | 五天竺難行 | 同 |
| ○ | 四月 | 同座 | 一の谷組打 | 生島太夫 |
| このときの「組打」は勿論団平師匠にお稽古していたゞいたものですが、生島太夫は中々よく語りました。 | ||||
| ○ | 五月 | 同座 | 合邦住家の中 | 伊達太夫 |
| ○ | 六月 | 同座 | 菅原の配所 | 同 |
| ○ | 十一月 | 同座 | 三番叟の連弾 | 生島太夫 |
| 新靱太夫 | ||||
| 源太夫外 | ||||
| ○ | 十二月 | 同座 | 盛衰記笹引 | 伊達太夫 |
| 明治卅年(廿九歳) | ||||
| ○ | 一月 | 同座 | 彦山権現六ッ目 | 同 |
| ○ | 三月 | 同座 | お駒歳三鈴ヶ森 | 同 |
| ○ | 四月 | 同座 | 妹背山三段目の琴 | 三世大隅太夫 |
| 二世団平 | ||||
| 同 姫戻り | 伊達太夫 | |||
| ○ | 五月 | 同座 | 加賀見山草履打 | 同 |
| ○ | 六月 | 同座 | 粂仙人吉野山 | 伊達太夫 |
| 生島太夫 | ||||
| ○ | 九月 | 同座 | 休 | |
| ○ | 十月 | 同座 | 布引瀧竹生島 | 伊達太夫 |
| ○ | 十一月 | 同座 | 休 | |
| 明治卅一年(卅歳) | ||||
| ○ | 一月 | 同座 | 三勝半七 | 同 |
| ○ | 二月 | 同座 | 同右 | 同 |
| ○ | 三月 | 同座 | 忠臣蔵雪転し | 新靱太夫 |
| ○ | 四月 | 同座 | 恋女房坂の下 | 伊達太夫 |
| 同座 | 志渡寺の中 | 同 | ||
| 団平師匠最後の舞台 | ||||
| ○ | 五月 | 同座 | 休 | |
| ○ | 六月 | 同座 | 伊勢音頭油屋 | 同 |
| これで稲荷座は瓦解しました。 | ||||
| 明治卅二年(卅一歳) | ||||
| ○ | 一月 | 堀江明楽座 | 紙治炬燵 | 同 |
| ○ | 二月 | 同座 | 加賀見山廊下 | 同 |
| ○ | 三月 | 同座 | 太功記妙心寺 | 同 |
| ○ | 四月 | 同座 | 阿古屋琴責 | 伊達太夫 |
| 五世住太夫 | ||||
| 新靱太夫 | ||||
| 長子太夫 | ||||
| ○ | 五月 | 同座 | 中将姫雪責 | 伊達太夫 |
| このとき文楽座でも越路(摂津大掾)さんが「雪責」を出して居られ、計らずも競争になりました。 | ||||
| ○ | 六月 | 同座 | 休演 | |
| この夏に大隅さんの一座で東京歌舞伎座へ行き、この年中ずつと東京に滞在してゐました。 | ||||
| 明治卅三年(卅二歳) | ||||
| ○ | 一月 | 同座 | 信仰記爪先鼠 | 組太夫 |
| 大隅太夫 | ||||
| 伊達太夫外 | ||||
| 前年の暮に東京から帰つて色々の都合で私がこの掛合場を弾くことになりましたが、お稽古のとき組さんの音遣ひの上手のに感心してしまひました。役は大膳でしたが、組さんにはこんな駒太夫風の場などどうかと思つてゐたらお稽古になつてうまいことはいはれるのにびつくりしてしまひました。 | ||||
| ○ | 二月 | 同座 | 休 | |
| ○ | 三月 | 同座 | 大江山保昌邸の切 | 新靱太夫 |
| 同戻り橋の大薩摩 | 伊達太夫 | |||
| 生島太夫 | ||||
| 錣太夫 | ||||
| 三世仙左衛門外 | ||||
| 同人身御供の切半分 | 伊達太夫 | |||
| このとき「戻り橋」の書卸しで、節付は植畑(仙左衛門)さん、私は植畑さんの注文で大薩摩を弾きましたら、義太夫の三味線が細棹を弾いてはいかん、と因講で問題になりましたが、すぐ解決しました。この芝居で私は三段目のえらい場を勤めてすぐ大薩摩に出、また「松太夫」の三段で「えらい/\」といひながら勤めました。 | ||||
| ○ | 五月 | 同座 | 先代萩竹の間 | 同 |
| ○ | 六月 | 同座 | 朝顔日記浜松 | 同 |
| ○ | 七月 | 同座 | 廿四孝四段目切 | 同 |
| これよりまた伊達太夫と東京へ行き、翌年の夏まで滞在してゐました。 | ||||
| 明治卅四年(卅三歳) | ||||
| ○ | 九月 | 同座 | 加賀見山廊下 | 同 |
| ○ | 十月 | 同座 | 日親記題目飴 | 同 |
| 布引瀧音羽山 | 同 | |||
| ○ | 十一月 | 同座 | お駒際三鈴ヶ森 | 同 |
| 明治卅五年(卅四歳) | ||||
| この年はずつと東京にゐて、東京から近郊やら北海道などへも巡業に行きました。 | ||||
| ○ | 八月 | 明治座 | 三番叟 | 伊達太夫外 |
| 先代萩御殿 | 伊達太夫 | |||
| 同二の替り | 同座 | 廿四孝四段目切 | 同 | |
| これぎり一時退座してしまひました。 | ||||
| 大正十三年(五十六歳) | ||||
| ○ | 十一月 | 御霊文楽座 | 布引瀧鳥羽離宮 | 津太夫 |
| ○ | 十二月 | 同座 | 盛衰記三の切 | 同 |
| 大正十四年(五十七歳) | ||||
| ○ | 一月 | 同座 | 堀川猿廻し | 同 |
| ○ | 二月 | 同座 | 嬢景清日向島 | 同 |
| ○ | 三月 | 同座 | 千本桜すし屋 | 同 |
| ○ | 四月 | 同座 | 桂川帯屋 | 同 |
| ○ | 五月 | 同座 | 国姓爺三段目切 | 同 |
| ○ | 六月 | 同座 | 忠臣講釈七ッ目 | 同 |
| ○ | 十月 | 中座 | 伊賀越沼津 | 同 |
| 阿古屋琴責 | 土佐太夫 | |||
| 津太夫 | ||||
| 静太夫 | ||||
| 古靱太夫 | ||||
| 四世清六 | ||||
| ○ | 十一月 | 文楽座 | 太功記十段目 | 津太夫 |
| 大正十五年(五十八歳) | ||||
| ○ | 一月 | 同座 | 弥作鎌腹 | 同 |
| ○ | 二月 | 同座 | 新薄雪蔭腹 | 同 |
| ○ | 三月 | 同座 | 忠臣蔵九段目 | 同 |
| ○ | 四月 | 同座 | 紙子仕立大文字屋 | 同 |
| このとき津太夫病気休演、駒太夫代役を勤め好評。 | ||||
| ○ | 五月 | 同座 | 千本桜道行のシン | 駒太夫 |
| 静太夫外 | ||||
| ○ | 六月 | 同座 | 妹背山三段目妹山 | 源太夫 |
| ○ | 九月 | 同座 | 伊賀越岡崎 | 津太夫 |
| ○ | 十月 | 同座 | 阿漕平次住家 | 同 |
| ○ | 十一月 | 同座 | 法然上人御流罪 | 同 |
| 新作浄瑠璃にて「御流罪の段」は津太夫道八の節付、一日京都知恩院へ奉納。この興行打揚げの翌日文楽座全焼。 | ||||
| 昭和二年(五十九歳) | ||||
| ○ | 一月 | 弁天座 | 合邦住家 | 津太夫 |
| ○ | 二月 | 同座 | 盛衰記三の切 | 同 |
| ○ | 三月 | 同座 | 御所桜三の切 | 静太夫改メ四世大隅太夫 |
| ○ | 四月 | 同座 | 菅原二の切 | 同 |
| ○ | 五月 | 同座 | 千本桜二の切 | 同 |
| ○ | 六月 | 同座 | 一の谷組打 | 同 |
| ○ | 十月 | 同座 | 河原達引四条河原 | 同 |
| ○ | 十一月 | 同座 | 本蔵下屋敷 | 同 |
| 昭和三年(六十歳) | ||||
| ○ | 一月 | 京都南座に出勤 | ||
| ○ | 二月 | 同座 | 伊賀越円覚寺 | 同 |
| ○ | 三月 | 弁天座 | 卅三所壺坂寺 | 同 |
| ○ | 六月 | 同座 | 忠臣蔵四段目 | 同 |
| ○ | 十月 | 同座 | 合邦住家 | 同 |
| 昭和四年(六十一歳) | ||||
| ○ | 一月 | 神戸名古屋その他巡業 | ||
| ○ | 三月 | 弁天座 | 休演 | |
| ○ | 四月 | 天満 八千代座 | 忠臣蔵四段目 | 同 |
| ○ | 五月 | 弁天座 | 一の谷組打 | 同 |
| 昭和五年(六十二歳) | ||||
| ○ | 一月 | 四つ橋文楽座 | 三番叟のシン | 津太夫 |
| 古靱太夫 | ||||
| 錣太夫 | ||||
| 大隅太夫 | ||||
| この外清六病気休演の為古靱太夫の「平家女護島二段目切」を一週間代役にて弾く。この時四ッ橋文楽座柿葺落し。 | ||||
| ○ | 二月 | 同座 | 勧進帳のシン | 大隅太夫外 |
| 清水町団平師匠節付の「勧進帳」久々復活上演大好評。 | ||||
| ○ | 三月 | 同座 | 野崎村 | 大隅太夫 |
| ○ | 四月 | 同座 | 千本桜道行のシン、二枚目新左衛門と一日替り村 | 錣太夫 |
| 大隅太夫 | ||||
| 新左衛門外 | ||||
| ○ | 五月 | 同座 | 恋女房道中双六 | 大隅太夫外 |
| ○ | 六月 | 同座 | 廿四孝三段目切後半 | 大隅太夫 |
| ○ | 七月 | 同座 | 伊勢音頭油屋 | 大隅太夫外 |
| ○ | 八月 | 同座 | 菅原四段目切 | 大隅太夫 |
| ○ | 九月 | 同座 | 八陣八ッ目切 | 同 |
| ○ | 十月 | 同座 | 伊勢物語はつたい茶 | 同 |
| ○ | 十一月 | 同座 | 忠臣蔵茶屋場前半新左衛門と一日替 | 土佐太夫 |
| 大隅太夫外 | ||||
| ○ | 十二月 | 同座 | 安達ヶ原矢の根 | 大隅太夫 |
| 昭和六年(六十三歳) | ||||
| ○ | 一月 | 同座 | 三番叟のシン | 大隅太夫外 |
| ○ | 二月 | 同座 | 一の谷組打 | 大隅太夫 |
| ○ | 三月 | 同座 | 伊賀越饅頭娘 | 同 |
| ○ | 四月 | 同座 | 日蓮記土牢 | 同 |
| ○ | 五月 | 同座 | 菅原東天紅 | 同 |
| ○ | 六月 | 同座 | 赤垣出立 | 同 |
| ○ | 九月 | 同座 | 盛衰記三段目切 | 同 |
| ○ | 十一月 | 同座 | 伊賀越相合傘 | 同 |
| 昭和七年(六十四歳) | ||||
| ○ | 一月 | 同座 | 阿古屋琴責 | 大隅太夫 |
| 南部太夫 | ||||
| 小春太夫 | ||||
| 文字太夫 | ||||
| ツレ吉弥外 | ||||
| ○ | 二月 | 同座 | 菅原茶筌酒と桜丸切腹新左衛門と一日替 | 大隅太夫(錣太夫) |
| ○ | 三月 | 同座 | 妹背山鱶七上使 | 大隅太夫 |
| ○ | 四月 | 同座 | 忠臣蔵殿中匆々刃場 | 同 |
| ○ | 九月 | 同座 | 勧進帳のシン | 大隅太夫外 |
| ○ | 十月 | 同座 | 宵庚申上田村 | 大隅太夫 |
| ○ | 十一月 | 同座 | 太功記夕顔棚 | 同 |
| 昭和八年(六十五歳) | ||||
| ○ | 一月 | 同座 | 忠臣蔵二ッ玉 | 同 |
| ○ | 二月 | 同座 | 河原達引四条河原 | 同 |
| ○ | 四月 | 同座 | 千本桜三の口 | 同 |
| ○ | 五月 | 同座 | 本蔵下屋敷 | 同 |
| ○ | 六月 | 同座 | 苅萱桑門高野山 | 同 |
| ○ | 十月 | 同座 | 卅三間堂平太郎内後半 | 同 |
| ◎ | 十二月 | 木挽町歌舞伎座 | 勧進帳 | 大隅太夫外 |
| ◎ | 十二月 | 同座 | 三番叟 | 和泉太夫外 |
| ◎ | 十二月 | 同座 | 訴訟 | 大隅太夫 |
| ◎ | 十二月 | 同座 | 背山 | 大隅太夫 |
| ◎ | 十二月 | 同座 | 勧進帳 | 大隅太夫外 |
| 昭和九年(六十六歳) | ||||
| ○ | 一月 | 同座[四ツ橋文楽座] | 勧進帳のシン | 大隅太夫外 |
| ○ | 三月 | 同座 | 太功記妙心寺 | 大隅太夫 |
| ◎ | 四月 | 同座 | 増補大江山 戻橋 | 大隅太夫外 |
| ○ | 五月 | 同座 | 休演 | |
| ◎ | 七月 | 木挽町歌舞伎座 | 鱶七上使 | 大隅太夫 |
| ◎ | 七月 | 同座 | 戻橋 | 大隅太夫外 |
| ◎ | 八月 | 同座 | 十種香 | 大隅太夫外 |
| ○ | 十月 | (竹本座アト)道頓堀浪花座 | 世継曾我 | 大隅太夫外 |
| ○ | 十一月 | 文楽座 | 忠臣蔵四段目 | 大隅太夫 |
| ◎ | 十二月 | 木挽町歌舞伎座 | 小金吾討死 | 大隅太夫 |
| 昭和十年(六十七歳) | ||||
| ○ | 一月 | 同座 | 天拝山 | 大隅太夫 |
| ○ | 三月 | 同座 | 三番叟のシン | 大隅太夫外 |
| ○ | 五月 | 同座 | 一の谷熊谷桜 | 大隅太夫 |
| ◎ | 七月 | 浜町明治座 | 勧進帳 | 大隅太夫外 |
| ◎ | 七月 | 同座 | 茶筌酒 | 大隅太夫 |
| ◎ | 七月 | 同座 | 渡海屋 | 大隅太夫 |
| ◎ | 七月 | 同座 | 組打 | 大隅太夫 |
| ◎ | 七月 | 同座 | 沢市内 | 大隅太夫 |
| ○ | 十月 | 同座[文楽座] | 合邦住家切後半 | 同 |
| ○ | 十一月 | 同座 | 忠臣蔵茶屋場前半 | 大隅太夫外 |
| 以下省略、今日に至る。 | ||||
| [原本本文は以上。] | ||||
| [『出勤のおぼえ』昭和八年以降の◎の項、及び昭和十一年以降の記事はぺりかん社版によった] | ||||
| 昭和十一年(六十八歳) | ||||
| ◎ | 一月 | 四ツ橋文楽座 | 寿式三番叟 | 大隅太夫 |
| 文字太夫外 | ||||
| ◎ | 三月 | 文楽座 | 大森彦七 | 大隅太夫外 |
| ◎ | 六月 | 同座 | 道八作曲 連獅子 | 相生太夫外 |
| ◎ | 六月 | 同座 | 国姓爺合戦 | 大隅太夫 |
| ◎ | 九月 | 同座 | 鷹野こしえ おつる 錣 | 大隅太夫外 |
| ◎ | 十月 | 同座 | 道八作曲 釣女 | 相生太夫外 |
| 昭和十二年(六十九歳) | ||||
| ◎ | 一月 | 文楽座 | 道八作曲 三人片輪 | 相生太夫外 |
| ◎ | 二月 | 同座 | 一谷嫩軍記 組打 | 相生太夫 |
| ◎ | 二月 | 同座 | 寿式三番叟 | 呂太夫 |
| 大隅太夫外 | ||||
| ◎ | 四月 | 文楽座 | ひらかな盛衰記 | 相生太夫 |
| ◎ | 五月 | 同座 | 鬼一法眼三略巻 | 相生太夫外 |
| ◎ | 六月 | 明治座 | 本藤[蔵]下邸 | 相生太夫 |
| ◎ | 六月 | 同座 | 明石舟別 | 相生太夫 |
| ◎ | 六月 | 同座 | 五条橋 | 相生太夫外 |
| ◎ | 六月 | 同座 | 釣女 | 相生太夫外 |
| ◎ | 七月 | 文楽座 | 生写朝顔日記宿屋 | 相生太夫 |
| ◎ | 七月 | 同座 | 菅原伝授手習鑑 | 相生太夫 |
| ◎ | 十月 | 北新地 北陽演舞場 | 摂州合邦辻 | 相生太夫 |
| ◎ | 十一月 | 新町演舞場 | 冥途の飛脚 | 相生太夫外 |
| 昭和十三年(七十歳) | ||||
| ◎ | 一月 | 東京劇場 | 市川猿之助 道行初音ノ旅路 | 相生太夫外 |
| ◎ | 一月 | 同座 | 寺子屋 合邦 堀川(素浄瑠璃) | 相生太夫 |
| ◎ | 二月 | 新町演舞場 | 桂川連理柵 帯屋 | 相生太夫 |
| ◎ | 三月 | 同座 | 妹背山婦女庭訓 | 相生太夫 |
| ◎ | 四月 | 北陽演舞場 | 釣女 | 相生太夫外 |
| ◎ | 四月 | 新町演舞場 | 一谷嫩軍記 | 相生太夫 |
| 呂太夫 | ||||
| ◎ | 五月 | 文楽座 | 連獅子 | 相生太夫外 |
| ◎ | 七月 | 新橋演舞場 | 団子売 | 相生太夫外 |
| ◎ | 七月 | 同座 | 連獅子 | 相生太夫外 |
| ◎ | 七月 | 同座 | 小牧山 草履打 | 相生太夫 |
| ◎ | 八月 | 京都 南座 | 勧進帳 舟別れと連判 | 相生太夫外 |
| ◎ | 九月 | 明治座 | 吃又 | 相生太夫 |
| ◎ | 九月 | 同座 | 阿古屋 | 伊達太夫 |
| 相生太夫 | ||||
| ◎ | 九月 | 同座 | 妹背山 | 相生太夫 |
| ◎ | 九月 | 同座 | 新口村 | 相生太夫 |
| ◎ | 十月 | 文楽座 | 蝶の道行 | 相生太夫外 |
| ◎ | 十月 | 大阪 歌舞伎座 | 梅玉他 旅路の道行 | 相生太夫外 |
| ◎ | 十一月 | 文楽座 | 鎌倉三代記 | 相生太夫 |
| 織太夫 | ||||
| ◎ | 十二月 | 同座 | 伊賀越道中双六 | 相生太夫 |
| 織太夫 | ||||
| 昭和十四年(七十一歳) | ||||
| ◎ | 一月 | 文楽座 | 勧進帳 | 相生太夫外 |
| ◎ | 二月 | 大阪 歌舞伎座 | 梅玉外 道八作曲 偲月俤曾我 | 相生太夫外 |
| ◎ | 四月 | 文楽座 | 天網島時雨炬燵紙屋内 | 相生太夫 |
| ◎ | 五月 | 同座 | 東海道膝栗毛 | 相生太夫 |
| 織太夫 | ||||
| ◎ | 五月 | 名古屋 御園座 | 勧進帳 | 相生太夫外 |
| ◎ | 六月 | 文楽座 | 彦山権現誓助剣 | 相生太夫外 |
| ◎ | 六月 | 同座 | 傾城阿波の鳴戸 | 相生太夫外 |
| ◎ | 七月 | 京都 南座 | 桜の宮 | 休みました |
| ◎ | 八月 | 明治座 | 茶筌酒 | 相生太夫 |
| ◎ | 八月 | 同座 | 釣女 | 相生太夫外 |
| ◎ | 十月 | 文楽座 | 恩讐の彼方に | 相生太夫外 |
| 昭和十五年(七十二歳) | ||||
| ◎ | 一月 | 文楽座 | 三人片輪 | 相生太夫外 |
| ◎ | 二月 | 大阪 歌舞伎座 | 道八作曲 猿之助一座 小鍛冶 | 相生太夫夫外 |
| ◎ | 三月 | 文楽座 | 摂州合邦辻 | 相生太夫 |
| 伊達娘恋緋鹿子 | 織太夫 | |||
| 源太夫外 | ||||
| ◎ | 六月 | 文楽座 | 契情和倭荘子 | 相生太夫夫外 |
| ◎ | 六月 | 神戸松竹劇場 | 初音の旅路道行 | 雛太夫外 |
| ◎ | 七月・八月 | 浪花女 劇中劇 千本道行撮影 | ||
| ◎ | 十月 | 文楽座 | 勧進帳 | 大隅太夫外 |
| 昭和十六年(七十三歳) | ||||
| ◎ | 一月 | 東京劇場 | 遠[猿]之助一座 寿式三番叟 | 織太夫外 |
| ◎ | 二月 | 大阪 歌舞伎座 | 遠[猿]之助一座 小鍛冶 | 相生太夫外 |
| ◎ | 三月 | 文楽座 | 戦陣訓 | 相生太夫外 |
| ◎ | 四月 | 東京劇場 | 道八作 酔奴 | 織太夫外 |
| ◎ | 五月 | 文楽座 | 海国日本魂 | 相生太夫外 |
| ◎ | 五月 | 角座 | 遠[猿]之助 寿式三番叟 | 南部太夫外 |
| ◎ | 六月 | 文楽座 | 小鍛冶 | 相生太夫外 |
| ◎ | 九月 | 文楽座 | 本朝廿四孝 | つばめ太夫外 |
| 昭和十七年(七十四歳) | ||||
| ◎ | 四月 | 文楽座 | 連獅子 | 相生太夫外 |
| ◎ | 十月 | 文楽座 | 出陣 | 織太夫外 |
| 昭和十八年(七十五歳) | ||||
| ◎ | 六月 | 文楽座 | 壺阪観音霊験記 | 松太夫外 |
| ◎ | 十月 | 文楽座 | 釣女 | 相生太夫外 |
| ◎ | 十二月 | 南座 | 顔見世 小鍛冶 寿式三番叟 | 相生太夫外 |
| 昭和十九年(七十六歳) | ||||
| ◎ | 一月 | 文楽座 | 勝舞竜 | 相生太夫外 |